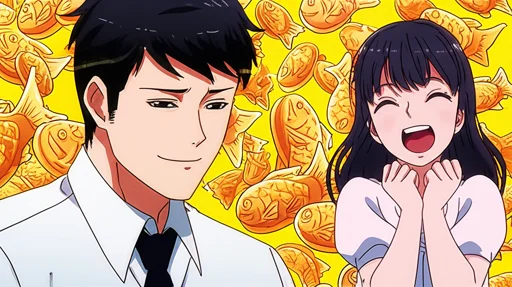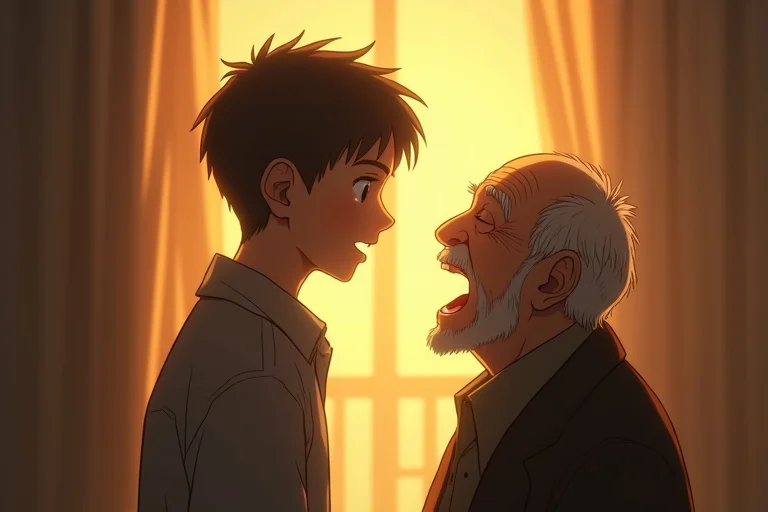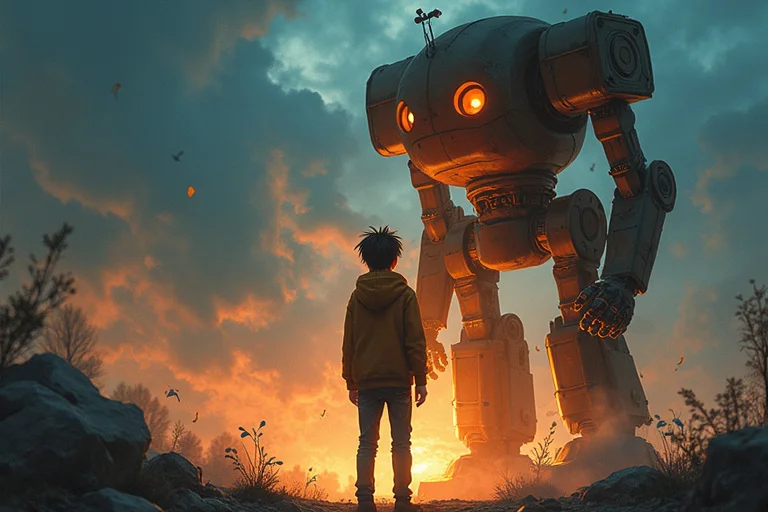第一章 膨張都市の片隅で
僕、レオの体は、一種の楽器のようなものだ。ただし、演奏者は僕自身じゃない。心の奥底で眠る、僕にも制御できない何者かだ。極度の感動や興奮がその指揮棒を振るうと、僕の体は勝手に歌い、踊り出す。まるで三流ミュージカルの主役みたいに。
この「喝采都市」では、あらゆるものが賞賛の言葉を浴びて物理的に膨張する。パン屋の店先では、「なんて素晴らしい焼き色!」という一言で、パンが釜から溢れんばかりに膨らみ、花屋の店先では、「息をのむような美しさ!」という囁きで、薔薇の蕾が破裂寸前まで膨らむ。人々は、対象を破裂させない絶妙な塩梅で褒め称える技術を「賞賛術」と呼び、それを磨くことに人生を捧げていた。
そんな世界で、僕の体質は厄介者以外の何物でもなかった。先日もそうだ。広場の噴水に架かった七色の虹を見て、僕の心臓が不意に高鳴った。次の瞬間、僕の意思とは裏腹に、両腕は天を仰ぎ、高らかな歌声が喉から飛び出していた。
「おお、愛! それは世界を照らす光! 勇気の翼で、さあ飛び立とう!」
虹とは全く、一ミリも関係のない陳腐な歌詞。道行く人々は足を止め、膨らみかけた街路樹を心配そうに見ながら、僕の唐突なパフォーマンスに苦笑いを浮かべていた。僕は顔から火が出る思いで歌い踊り続け、最後のポーズを決めた瞬間、地面に突っ伏して逃げ出したくなった。感動が僕を支配するたび、僕は孤独の穴に突き落とされるのだ。
第二章 王城からの招待状
この都市で最も偉大な「賞賛術」の使い手は、国王アルベリヒその人だった。彼の言葉にかかれば、萎れた苗木は一夜にして大樹となり、ただの鉄塊は荘厳な彫像へと姿を変えるという。しかし、そんな国王には一つの奇妙な噂があった。彼が決して褒めない、そして絶対に膨らまない国宝、「沈黙の壺」の存在だ。
ある朝、僕のもとに一通の分厚い手紙が届いた。蝋で封をされたその紋章は、紛れもなく王家のものだった。恐る恐る中を開くと、そこにはこう記されていた。
「街角の吟遊詩人、レオ殿。君の心を揺さぶる歌声が、我が耳に届いた。王城にて、その稀有な才能を披露されたし。目的は一つ、国宝『沈黙の壺』を君の感動で膨らませてみせること」
招待状というよりは、挑戦状に近い文面だった。僕のこの忌々しい体質が、まさか国王の耳にまで届いていたなんて。厄介者扱いされることには慣れていたが、王城にまで呼び出されるのは初めてだった。断れば不敬罪に問われるかもしれない。僕は深くため息をつくと、震える手で招待状を握りしめ、王城へと向かう覚悟を決めた。僕のミュージカルが、一体何の役に立つというのだろう。
第三章 沈黙の謁見
王城の中は、賞賛で満ち溢れていた。磨き上げられた大理石の床は、人々の感嘆のため息を吸って、雲のように柔らかく波打っている。天井から下がる巨大なシャンデリアは、「星々の煌めきのごとし!」という賛辞を受け、今にも天井を突き破りそうなほどに膨らんでいた。この城の全てが、美しく、そして危うい緊張感の上で成り立っていた。
謁見の間で待っていた国王アルベリヒは、噂に聞く「褒め言葉の達人」の姿とはかけ離れていた。その瞳は深く窪み、輝きを失っている。まるで、世界中のあらゆる音を聞き続けた末に、疲れ果ててしまったかのような静かな絶望が漂っていた。
「来たか、街角の吟遊詩人」
彼の声は、乾いた砂がこすれるような音だった。
やがて、侍従が厳かに運んできたのは、一台のビロードの台座。その上に鎮座していたのが、国宝「沈黙の壺」だった。それは、驚くほどに地味で、何の装飾もない、ただの素焼きの壺だった。人々の熱狂的な賞賛が飛び交うこの世界で、その壺だけが、まるで音のない空間にいるかのように、ただ静かにそこにあった。その存在感は、異様としか言いようがなかった。
第四章 届かぬ賛歌
「さあ、歌うがいい。君の感動のすべてを、その壺にぶつけてみよ」
国王に促され、僕は壺の前に立った。だが、心が動かない。この地味な壺のどこに感動すればいいのか、皆目見当もつかなかった。無理に感動を絞り出そうとすればするほど、心は乾いていく。歌は、出てこなかった。
沈黙が謁見の間を支配する。やがて、国王が諦めたように小さく息を吐いた。
「……やはり、無駄か」
そう呟くと、国王は自ら壺の前に進み出た。そして、その唇から、今まで僕が聞いたこともないような、完璧で、流麗な褒め言葉が紡がれ始めた。
「おお、静寂の器よ。おまえの肌は、夜明け前の空の色を宿し、その形は、万物の始まりと終わりを内包する。おまえの沈黙こそが、この世で最も美しい音楽なのだ……」
それは、言葉の芸術だった。謁見の間の柱や絨毯が、その声の余波だけで微かに膨張するほどに。しかし、当の壺は、相変わらずピクリともしない。まるで、王の言葉を嘲笑うかのように。
国王は深く、長い息を吐き、疲労を隠しもせずに玉座へ戻った。そして、虚ろな目で僕を見つめて言った。
「この世界は……賞賛という名の、騒音に満ちているのだよ」
その声には、王としての威厳ではなく、一人の人間の、魂からの叫びが滲んでいた。
第五章 心が奏でるメロディ
その瞬間だった。
国王の孤独な横顔、賞賛の重圧に何十年も耐え続けてきたその魂の疲弊。それを見た僕の胸の奥で、今まで感じたことのない種類の感情が、熱い奔流となって込み上げてきた。
それは、美しいものを見た時の興奮ではなかった。「素晴らしい!」と叫びたくなるような熱狂でもない。ただひたすらに、目の前の孤独な魂に対する、深い、深い共感と慈しみだった。
僕の体が、勝手に動き出す。
だが、それはいつもの大げさなミュージカルではなかった。天を仰ぐ腕も、高らかな愛の歌もない。
僕の唇から漏れ出たのは、歌詞にもなっていない、静かなハミングだった。それは、傷ついた小鳥を慰めるような、嵐の夜に赤子をあやすような、切なく、優しいメロディ。僕の魂が、初めて本当に歌った歌だった。
その歌声が、謁見の間に響き渡る。すると、信じられないことが起きた。今まで、王の完璧な賛辞にさえ何の反応も示さなかった「沈黙の壺」が、僕の拙いハミングに呼応するように、微かに震え始めたのだ。キィン、と高く澄んだ共鳴音が、壺から発せられた。
第六章 沈黙の解放
共鳴音は次第に大きくなり、壺はカタカタと激しく振動し始めた。謁見の間にいる誰もが息をのむ。そして、次の瞬間、ポンッ、と乾いた音を立てて壺の蓋が宙に舞った。
中から溢れ出してきたのは、金銀財宝ではなかった。伝説の秘薬でもない。羊毛や柔らかな粘土で丁寧に作られた、無数の、小さな塊。それは……耳栓だった。大量の、手作りの耳栓が、まるで祝福の吹雪のように床に散らばった。
国王は、その光景に目を見開いた。驚き、困惑、そしてやがて、その表情は深い安堵へと変わっていった。彼はふらふらと壺に歩み寄ると、床に落ちた一つの耳栓を拾い上げた。そして、まるで祈りを捧げるかのように、そっと、自らの耳にはめ込んだ。
途端に、国王の顔からすべての力が抜けていった。
世界から、音が消えたのだ。絶え間なく聞こえてくる人々の賞賛の声、膨張を促す熱狂的な囁き、期待に満ちた喝采……そのすべてが、完全に遮断された。国王の瞳から、一筋の涙が静かに流れ落ちた。それは、数十年ぶりに訪れた、完全なる静寂への感謝の涙だった。
沈黙の壺は、褒め言葉を拒絶していたのではない。むしろ、その「音」を吸収し、遮断するために存在していたのだ。それは、この騒がしい世界で唯一、王に安らぎを与えるための、古代の知恵の結晶だった。
第七章 新しい世界の響き
「ありがとう、街角の吟遊詩人よ」
耳栓を片方だけ外し、国王は僕に言った。その声は、驚くほど穏やかだった。
「君の歌は……物を膨らませるための賛辞ではなかった。初めて私に届いた、『静寂』そのものだったのだ」
それから、国王は褒めることをやめたわけではなかった。ただ、無闇に賞賛を振りまくことをやめたのだ。彼は耳栓を使い、本当に心が動いたものだけを、誰にも聞こえない声で、静かに愛でるようになった。
僕もまた、自分の忌まわしい体質を、少しだけ受け入れることができた。僕の歌は、物を膨らませるための厄介な発作なんかじゃない。時には、誰かの心を震わせ、騒がしい世界に一瞬の静寂をもたらすことさえできるのだと知ったから。
喝采都市は、今も変わらず賞賛の言葉で溢れ、様々なものが膨らんでは、その形を危うく保っている。けれど、王城の一角だけは、穏やかな静けさを取り戻していた。僕は時々、王に招かれて、謁見の間を訪れる。何かを膨らませるためではない。ただ、疲れ果てた一人の王のために、静かな、静かな歌を歌うために。
賞賛とは、果たして祝福なのだろうか。それとも呪いなのだろうか。答えはまだ見つからない。けれど、僕たちは知っている。本当の感動は、熱狂的な喝采の中ではなく、時に、深く、穏やかな沈黙の中にこそ響くのだということを。