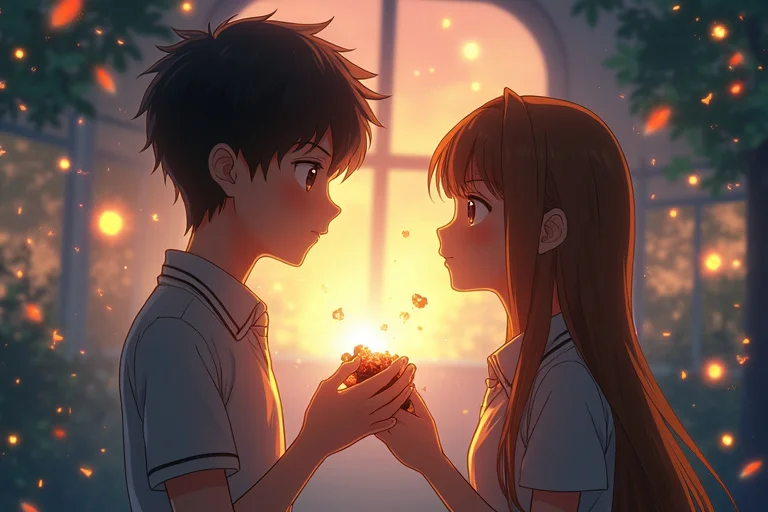第一章 微光の輪郭
僕、高槻アキトの右手には、時折、奇妙なものが宿る。
それは誰かの『一番大切な記憶』に触れたときにだけ、淡い光を帯びて現れる小さな結晶だ。この常葉(とこは)学園は『時間の歪み』と呼ばれる現象に包まれていて、生徒たちの強い感情が『時間の残響』として、あちこちに染み付いている。例えば、放課後の旧音楽室。誰もいないはずのその場所で、僕は鍵盤に触れた。ひんやりとした象牙の感触と共に、指先から柔らかな光が溢れ出す。
目の前には、夕陽に照らされた少女の幻影が、楽しげにショパンを弾いていた。彼女の長い髪が、旋律に合わせて揺れる。その残響にそっと手を伸ばすと、幻影は霧散し、僕の手のひらには、夕焼けを閉じ込めたような小さな結晶が残されていた。それは微かに温かく、ドロップのように甘い光を放っていたが、数分も経てば空気の中に溶けるように透明になり、跡形もなく消えてしまう。
「また見つけたの、アキト?」
背後からの声に振り返ると、快活な笑顔を浮かべたユイナが立っていた。彼女の瞳は、いつも学園の謎を追いかける好奇心で輝いている。
「……うん。ピアノの記憶だった」
「へぇ、どんな音だった?」
ユイナは僕の手のひらを覗き込む。もう消えかけた結晶を見て、彼女は少しだけ寂しそうに眉を寄せた。この学園で、僕がこの能力を持つ理由を知る者はいない。僕自身でさえも。そして、この歪みが近年、なぜか急速に拡大していることも、僕たちを不安にさせていた。
第二章 忘れ物の砂時計
「学園の七不思議、その八つ目、って感じよね。この『時間の残響』って」
ユイナはそう言って、僕を引っ張るように図書館の奥へと進んだ。埃っぽい紙の匂いが満ちる書架の隙間で、僕らは学園の古い記録を漁っていた。歪みの拡大。頻発する残響。そして、誰もがその存在すら知らない、あるはずの『失われたイベント』。手掛かりは何も見つからない。
諦めかけたその時、ユイナが「見て!」と声を上げた。彼女が指差したのは、書架の最上段に打ち捨てられたように置かれた、奇妙なオブジェだった。それは、様々な生徒の忘れ物――割れた万年筆のペン先、色褪せたリボン、片方だけのイヤリング――を寄せ集めて作られた、歪な砂時計だった。
僕がそれに手を伸ばした瞬間、砂時計が鈍い光を放つ。ガラスの中には、星屑のような銀色の砂が詰まっていたが、なぜか決してすべてが落ちきることがない。最後の一粒が、何度ひっくり返しても、くびれの部分で頑なに留まり続けるのだ。
「何だろう、これ……」
僕が呟きながら、好奇心で砂時計を逆さにした。その瞬間、図書館の空気がぐにゃりと歪む。窓から差し込む光が屈折し、僕たちの周りに、無数の生徒たちの囁き声や笑い声が、過去からの残響となって溢れ出した。
「すごい……この砂時計、残響を増幅させるんだ!」
ユイナが目を輝かせる。だが僕は、その異常な力の奔流に、言い知れぬ寒気を感じていた。そして気づいた。落ちきらない最後の一粒こそが、この学園の『失われた何か』の象徴なのではないかと。
第三章 残響のステンドグラス
寄せ集めの砂時計を手に入れてから、僕たちは学園中の残響を巡った。砂時計を逆さにするたびに、過去の光景はステンドグラスのように色鮮やかになり、僕は次々と『微光の結晶』を採取していった。
体育館の床に触れれば、最後の試合に勝ったバスケ部員の歓喜の結晶が。理科室の机からは、実験を失敗させた生徒の悔し涙の結晶が。夕暮れの屋上、そのフェンスからは、告白が叶った少女の、震えるような喜びの結晶が生まれた。
僕の手のひらに集まった結晶たちは、それぞれが異なる光と温度を持ちながら、互いに微かな共鳴を起こしているようだった。まるで、一つの大きな絵を完成させるための、失われたピースのように。
しかし、奇妙なことが起こり始めた。残響が鮮明になるほど、隣にいるはずのユイナの輪郭が、時折、陽炎のように揺らぐのだ。
「ユイナ……?」
「ん? どうかした?」
彼女は不思議そうに首を傾げるが、その笑顔が一瞬だけ、ノイズの走った映像のように乱れたのを、僕は見逃さなかった。僕が結晶を集めれば集めるほど、この世界から何かが失われていく。そんな予感が、胸の奥を冷たく締め付けた。
第四章 罅割れたフーガ
集めた十数個の結晶が、僕の手のひらの上で同時に、強い光を放った。光は僕の意識に直接流れ込み、一つの鮮明なビジョンを映し出す。
それは、学園祭のステージで、グランドピアノに向かう一人の少女の姿だった。彼女が弾き始めたのは、誰も知らない、けれど聴く者の心を締め付けるような、悲しくも美しいピアノソナタ。その演奏会こそが、学園の記録から消された『失われたイベント』だった。
そして僕は息を呑んだ。ピアノを弾く少女の横顔が、ユイナと瓜二つだったからだ。
「……思い、出したんだね」
隣から、か細い声が聞こえた。ユイナだった。しかし、彼女の体は半ば透け、光の粒子がはらりはらりと剥がれ落ちていた。その姿は、僕が何度も見てきた残響そのものだった。
「ユイナ、君は……」
「思い出さないで、アキト。お願いだから」
彼女は悲しげに微笑む。その瞬間、学園全体が大きく軋み、窓ガラスに罅が入った。時間の歪みが暴走を始める。足元が崩れるような感覚の中、僕は見た。今まで頑なに落ちなかった寄せ集めの砂時計の、最後の一粒が、ゆっくりと、しかし確実にくびれを通り抜けていくのを。
第五章 君がいたセカイ
最後の一粒が落ちきった瞬間、奔流のような記憶が僕を呑み込んだ。それは僕の記憶ではなかった。いや、正確に言えば、遥か未来の『僕』の記憶だった。
この学園は、現実の世界などではなかった。
未来の僕が、病で夭折した恋人――ユイナとの果たせなかった約束を、永遠に再現し続けるために創り出した、巨大な『記憶の箱庭』。彼女は学園祭で、僕のためにピアノを弾いてくれるはずだった。だが、その日を迎えることなく、彼女はこの世を去ったのだ。
後悔に苛まれた未来の僕は、自らの記憶と時間を歪める力で、この箱庭を創り上げた。ここにいる生徒も教師も、全てはユイナとの幸せな日々を彩るために生み出された『思念の投影』。そして、この箱庭にいる僕自身もまた、あの頃の自分を追体験するための、過去の自分の投影に過ぎなかった。
僕が持つ能力は、散らばった記憶の欠片を『微光の結晶』として集めるためのもの。全ての結晶を集めることは、この箱庭の再現を完成させ、その役目を終わらせることを意味していた。
ユイナの輪郭が揺らいだのは、僕が真実に近づき、この偽りの世界が終わりを迎えようとしていたからだ。全ては、未来の僕の、痛切な願いが生み出した、美しくも残酷な幻だった。
第六章 解放のソナタ
僕は、光の粒子となって消えかけているユイナを探し、旧音楽室へと走った。夕陽が差し込むその場所で、彼女はあの日の幻影のように、ピアノの前に静かに座っていた。
「……ごめんね。あなたを、こんな場所に閉じ込めて」
それは、未来の僕への言葉であり、今の僕への言葉でもあった。
「もういいんだよ、アキト」ユイナは僕を見上げ、微笑んだ。「あなたの未来には、この思い出だけじゃない。もっとたくさんの、眩しい光があるはずだから。過去に囚われないで」
彼女の言葉で、僕は全てを悟った。未来の自分は、もうこの箱庭を必要としていない。前に進むべきなのだ。悲しみを乗り越え、新しい記憶を紡いでいくべきなのだ。
僕はユイナの隣に座り、静かに鍵盤に指を置いた。そして、集めた全ての結晶を胸に抱きながら、あの日ユイナが弾くはずだった、そして未来の僕がずっと聴きたかった『失われたソナタ』を弾き始めた。それは、過去への追悼であり、未来への解放を願う、鎮魂の旋律だった。
第七章 はじまりの結晶
僕の指が最後の和音を奏で終えた瞬間、音楽室の窓から溢れた光が世界を包み込んだ。学園が、校舎が、グラウンドが、出会った全ての生徒たちが、美しい光の粒子となって空へと昇っていく。誰もが穏やかな笑みを浮かべていた。まるで、長い夢から覚めるかのように。
「ありがとう、アキト。最高の演奏会だったよ」
ユイナはそう言うと、僕の頬にそっと触れた。その指先から光に溶けていき、温かい感謝の気持ちだけを残して、完全に消えていった。
僕自身の体もまた、足元からゆっくりと透明になっていく。この追憶の役者としての、僕の役目も終わったのだ。これでいい。そう思った。
しかし、その消滅の直前、僕の胸の中心から、これまで集めたどの結晶よりも暖かく、力強い輝きを放つ、一つの新しい結晶が生まれた。
それは、未来の僕が創り出した過去の記憶ではない。この箱庭の中で、偽物のユイナと過ごした、かけがえのない時間から生まれた、僕だけの『新しい一番大切な記憶』の結晶だった。
その結晶は、崩壊する世界からふわりと浮かび上がると、時空の彼方へと吸い込まれるように消えていった。
それはきっと、未来のどこかで、孤独に凍える誰かの心を温める、新たな小さな箱庭の、はじまりの種となるのだろう。