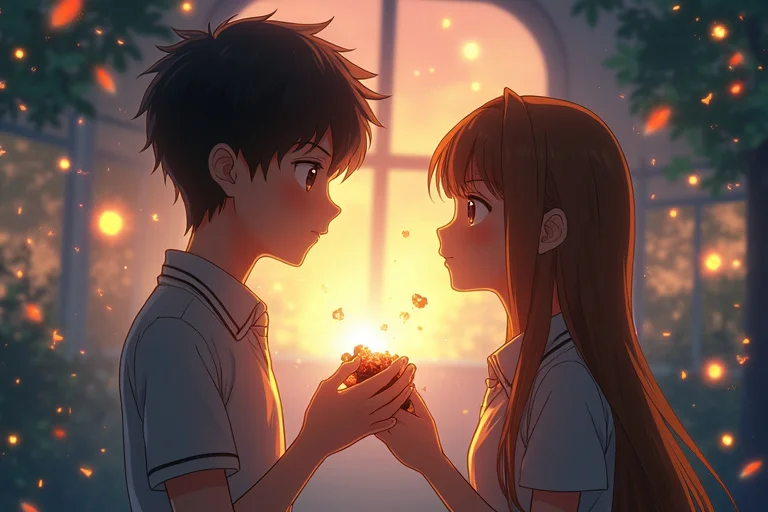僕にとって、世界はあまりにもうるさく、そして色彩に溢れすぎていた。
人の声、風の音、遠くで鳴るチャイム。そのすべてが僕の網膜に、固有の色と形を伴って映し出される。共感覚、と医者は言った。珍しいが、病気ではない、と。しかし、幼い僕にとってそれは呪いと変わらなかった。特に、たくさんの声が混じり合う合唱や教室の喧騒は、まるで泥水をぶちまけられたパレットのようで、吐き気すら覚えるほどだった。
だから高校に入った僕は、誰とも深く関わらず、放課後はいつも美術室の隅でキャンバスに向かうことに決めていた。静寂だけが、僕に唯一の平穏を与えてくれる。絵具の匂いと、画布を滑る筆の乾いた音。それだけが、僕の世界のすべてだった。
あの日までは。
旧音楽室の前を通りかかった時、ふと、澄み切った歌声が聞こえてきた。それは、まるで一点の曇りもないサファイアのような、深く、静かな青色をしていた。これまで僕が見てきたどんな音とも違う、純粋な祈りのような響き。僕は吸い寄せられるように、錆びついたドアノブに手をかけた。
埃っぽい部屋の中、夕陽のスポットライトを浴びて歌っていたのは、一人の男子生徒だった。天野響。クラスは違うが、その名前は知っていた。彼が、部員が一人しかおらず廃部寸前だという合唱部の、最後の部員らしかった。
僕の気配に気づいた彼が歌うのをやめ、振り返る。その瞳は、彼の歌声と同じ、真っ直ぐな青色をしていた。
「聴いてくれたんだ。ありがとう。君、美術部の水瀬くんだよね?」
彼の声は、柔らかな水彩の青として僕の目に映った。僕はただ、こくりと頷くことしかできなかった。
「よかったら、一緒に歌わないか? 合唱部、部員を探してるんだ」
その誘いを、断るべきだった。僕の世界は、誰かと交わるようにはできていないのだから。しかし、彼の声が描くあまりに美しい青に魅せられて、僕は曖昧に微笑んでその場を立ち去ることしかできなかった。
翌日から、響は昼休みや放課後になると美術室に顔を出すようになった。彼は僕の描く絵を褒め、そして飽きもせずに合唱部に誘ってきた。僕が頑なに首を横に振っても、彼は気にした様子もなく、ただ楽しそうに歌の話をした。
「二人なら、デュエットができる。きっと、すごい化学反応が起きると思うんだ」
化学反応、と彼は言った。僕にとっては、それはただ色が濁り、汚い混沌が生まれるだけの行為だ。それでも、日に日に彼の声の「青」は僕の心に深く染み込んでいった。断りきれなくなった僕は、ついに一度だけ、という条件で旧音楽室に足を踏み入れた。
響がピアノで簡単な音階を弾く。彼の指から生まれる音は、きらきらと輝く金の粒子となって舞い上がった。
「じゃあ、この音で、『あー』って伸ばしてみて」
僕は恐る恐る、息を吸い込んだ。そして声を出す。僕自身の声は、少しオレンジがかった、情熱的な赤色をしていた。自分でも持て余すような、強い色。
「いいね、すごくいい声だ。じゃあ、一緒に」
響の声が重なった瞬間、世界がぐにゃりと歪んだ。彼の純粋な青と、僕の激しい赤が混ざり合う。しかし、それは美しい紫にはならなかった。お互いの色が反発しあい、せめぎ合い、どす黒く濁ったインクのような染みとなって空間に広がっていく。頭が割れるように痛い。僕は思わず耳を塞ぎ、その場にうずくまった。
「ごめん……僕には、無理だ」
僕の感覚では、これは不協和音そのものだった。僕の存在が、彼の完璧な青を汚している。その事実に、絶望的な気持ちになった。
それから僕は響を避けるようになった。しかし、彼は諦めなかった。ある雨の日の放課後、美術室で一人、真っ黒に塗りつぶしたキャンバスを前に座り込んでいた僕の元へ、響はやってきた。
「逃げるなよ、水瀬」
いつもと違う、少し硬い声。それは深い藍色をしていた。
「君が何に苦しんでいるのか、僕には分からない。でも、君が音に対して、僕なんかよりずっと正直だってことは分かる」
彼は僕の隣に座ると、静かに続けた。
「僕は、君と歌いたい。君の見てる世界を、僕も見てみたいんだ。汚い色だって? いいじゃないか。それも、僕と君が一緒にいるから生まれる色なんだろ。世界でたった一つの、僕たちの色だ」
そう言って、彼は一枚の楽譜を差し出した。タイトルには、拙い文字でこう書かれていた。
『君と僕の色彩のために』
「君の声と僕の声が、一番きれいに響くように、僕なりに編曲してみたんだ」
楽譜に並ぶ音符たちは、まるで色とりどりの宝石のように、僕の目には見えた。藍色の声で語りかける彼の真摯な瞳を見ているうちに、僕の胸を覆っていた灰色の霧が、少しだけ晴れていくような気がした。
地域の小さな音楽祭の日がやってきた。ステージの袖で、僕は照明の熱に汗ばむ手でマイクを握りしめていた。隣に立つ響が、僕の肩をぽんと叩く。
「楽しもう。僕たちの色を、聴かせてやろうぜ」
その声は、自信に満ちた、力強い群青色だった。
ステージに足を踏み出す。客席のざわめきが、様々な色の煙となって渦巻いていた。ピアノの伴奏が始まる。きらめく金の粒子。僕は一度、ぎゅっと目を閉じた。響の言葉を思い出す。『世界でたった一つの、僕たちの色だ』。
響の、あのサファイアの歌声がホールに響き渡る。僕はそっと目を開け、息を吸い込んだ。恐怖を乗り越え、僕の赤い声を、彼の青い世界へと解き放った。
その瞬間、奇跡が起きた。
僕の目に映ったのは、もはや濁ったインクではなかった。響の青と僕の赤は、互いを否定することなく、溶け合い、螺旋を描きながら天へと昇っていく。そして、これまで見たこともないほどに深く、気高く、そして光り輝く「ロイヤルパープル」の光となって、ステージを満たしたのだ。それは、完璧な調和が生み出した、祝福の色彩だった。
歌い終えた瞬間、ホールは一瞬の静寂に包まれた。そして次の瞬間、割れんばかりの拍手が嵐のように僕たちを襲った。その一つ一つの拍手は、温かい金色の光の雨となって、僕の全身に降り注いでいた。
結果なんて、どうでもよかった。僕はもう、一人ではなかった。自分の呪いだと思っていた感覚が、誰かと世界を繋ぐための、かけがえのない祝福だったと知った。
ステージの袖で、僕たちは顔を見合わせて笑った。彼の瞳は、達成感に満ちた、どこまでも澄んだ青色に輝いていた。僕の世界は、相変わらずうるさくて色彩に溢れている。けれど、それはもう、僕を孤独にする色ではなかった。響と出会って、僕は初めて、この世界を美しいと思えたのだ。