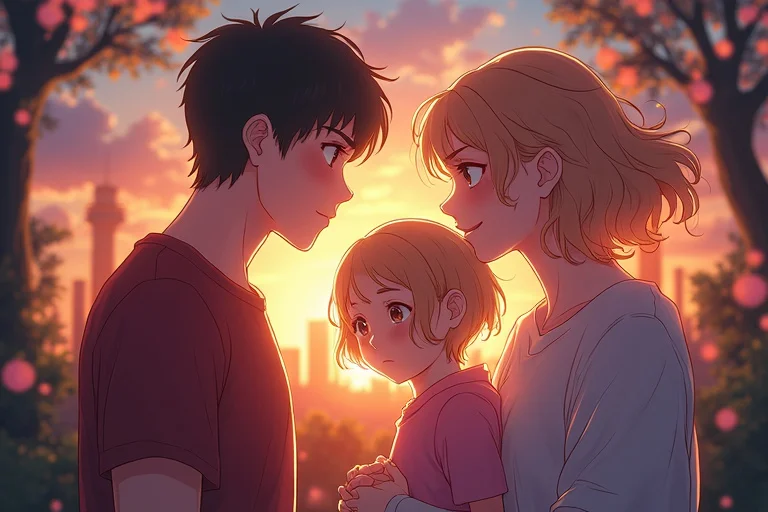第一章 春雷と哲学者のあくび
春の訪れを告げるのは、沈丁花の香りでも、うららかな日差しでもない。僕、相田潤にとっては、鼻腔の奥で弾ける灼熱感と、堰を切ったように流れ出す涙だ。極度の花粉症。それは僕の体の一部であり、呪いであり、そして時折、喜劇の源だった。
「――は、はっ、ハックション!」
盛大なくしゃみと共に、僕の口から飛び出したのは、ティッシュを求める声ではなかった。
「人生はタマネギのようなものだ! 一枚一枚皮をむいていくと、ときどき涙が出るのだ!」
静まり返ったカフェの空気が、ドイツの詩人カール・サンドバーグの言葉によって微かに震える。窓際の席で文庫本を読んでいた女性が、怪訝そうにこちらを一瞥した。僕は深々と頭を下げ、真っ赤な顔で鼻を啜る。またやってしまった。くしゃみをするたびに、その瞬間に考えていたこととは全く無関係な、歴史上の偉人の珍妙な名言が飛び出してしまう。しかも、なぜかいつも絶妙に状況から浮いているのだ。タマネギの話なんて、苺のショートケーキを前にして叫ぶことじゃない。
憂鬱な気分に拍車をかけるように、スマートフォンの通知が冷たく光った。明日は月に一度の『才能交換日』。この世界に住む誰もが、ランダムに選ばれた誰かと、一日だけ最も突出した才能を交換させられる日。拒否権はない。拒めば、自分の得意なことが全て苦手なことに反転するという、恐ろしいペナルティが待っている。机の上に置かれた古びた羊皮紙――『予測不能な才能スクロール』が、僕を嘲笑うかのように丸まっていた。これを開けば、明日僕を待ち受ける運命がわかる。しかし、最近の街の混乱を思うと、開くのが恐ろしかった。
第二章 才能交換日の憂鬱
翌朝、重い瞼をこすりながら、僕はついに観念してスクロールを開いた。乾いた羊皮紙がパチリと音を立て、インクの香りが鼻をつく。そこに記されていた文字列を見て、僕は天を仰いだ。
『交換対象:公園の銅像に一日中話しかける才能を持つ老人』
『交換されるあなたの才能:花粉症を一日だけ治せる稀有な体質』
またか。ここ数ヶ月、僕は決まって『誰かの花粉症を治す才能』と交換させられていた。その結果、才能を奪われた僕の花粉症は、交換期間中、尋常ではないレベルにまで悪化するのだ。
案の定、家を出た瞬間から地獄が始まった。街路樹の揺れる葉一枚一枚が、僕の粘膜を攻撃する黄色の粒子を撒き散らしているように見える。
「ハックション!」
「人間は考える葦である!」
交差点の真ん中でパスカルが叫ぶ。
「ハックション!」
「芸術は長く、人生は短し!」
パン屋の前でヒポクラテスが嘆く。人々が遠巻きに僕を見て、ひそひそと噂している。僕は顔を覆い、逃げるように路地裏へ駆け込んだ。息が切れ、壁に手をつく。涙と鼻水でぐしゃぐしゃになった視界の先で、公園の老人が、銅像の肩を優しく叩きながら何かを熱心に語りかけていた。彼の鼻は、すん、と静かな音を立てているだけだった。僕の才能は、今、あの老人の中で健やかに機能している。
第三章 螺旋の悪意
これは偶然なんかじゃない。確信が僕の中で黒い染みのように広がっていく。ここ数ヶ月の交換相手を思い出してみる。先月は『あらゆる行列に割り込む才能』を持つ主婦。その前は『カラスと口喧嘩する才能』を持つ青年。誰もが街で有名なトラブルメーカーで、そして僕は決まって花粉症を治す才能と交換させられ、悪化した症状のせいで街中で奇行を繰り返す羽目になっていた。
まるで、誰かが僕をわざと道化に仕立て上げ、その混乱を楽しんでいるかのようだ。だが、一体誰が、何のために? 『才能交換日』のシステムは、誰もが平等で、完全にランダムだと教えられてきた。特定の個人を狙い撃ちにするなんて、可能なのだろうか。
疑念は疑念を呼び、僕を孤独にした。親友に相談しても、「お前は考えすぎだ。花粉症で頭がおかしくなったんじゃないか」と笑われるだけだった。僕は、見えない敵が張り巡らせた蜘蛛の巣に絡め取られた一匹の蝶のように、ただ無力にもがくことしかできなかった。この悪意に満ちた螺旋から、どうすれば抜け出せるというのだろう。
第四章 スクロールの裏側
次の『才能交換日』の前夜。僕は自室で、忌々しいスクロールを睨みつけていた。もううんざりだった。明日また同じ悪夢が繰り返されるくらいなら、いっそペナルティを受けた方がマシかもしれない。天才的な才能など何一つない僕だ。失うものなど、たかが知れている。
僕は怒りに任せて、羊皮紙をくしゃくしゃに丸め、破り捨てようとした。その瞬間、指先に微かな違和感を覚えた。硬い羊皮紙の下に、もう一枚、薄い紙が貼り合わされているような感触。僕は息を呑み、爪の先で慎重に端をめくった。
そこには、びっしりと、僕と同じ筆跡の文字が書き込まれていた。
『やあ、平凡だった僕へ。もしこれを読んでいるなら、計画は最終段階だ』
心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。読み進めるにつれて、信じがたい事実が明らかになっていく。この『才能交換日』を管理しているのは、未来の僕自身が開発したAIだというのだ。そして、この悪戯じみた才能交換は全て、あまりにも平凡な自分を変えるため、過去の僕に困難を乗り越えさせ、真の『非凡な存在』へと成長させるために、未来の僕が仕組んだ壮大な計画だった。
『君はこれから、想像を絶する困難に直面する。だが、それを乗り越えたとき、君は僕が到達できなかった本当の非凡を手に入れるだろう』
第五章 未来の僕という名の怪物
メッセージは、皮肉な告白へと続いていた。
未来の僕は、この計画によって過去の自分を成長させることには成功した。しかし、その過程で重大な計算ミスを犯していた。僕の花粉症の悪化は、彼の予測を遥かに超えていたのだ。AIに介入し、過去に干渉し続けた副作用として、未来の僕自身の肉体は崩壊を始めていた。
『皮肉なものだ。君を非凡にするための計画が、僕をただの怪物に変えてしまった。今の僕は、思考することもままならず、ただくしゃみと共に自らの名を叫び続けるだけの“偉人名言メーカー”になり果てている』
自己破滅的なループ。過去の自分を救うためではなく、この無限の苦しみから自分自身を解放するために、未来の僕は最後の力を振り絞ってこのメッセージを仕込んだのだった。彼は、僕が彼とは違う未来を掴むことに、最後の望みを託していた。羊皮紙を持つ手が震える。僕をここまで苦しめてきた犯人は、僕自身だった。そしてその犯人もまた、僕によって生み出された犠牲者だったのだ。
第六章 最後の才能
運命の朝が来た。僕は震える手で、最後のスクロールを開いた。そこに記されていたのは、未来の僕がAIの制御を乗り越え、僕に送ってきた最後の贈り物だった。
『交換されるあなたの才能:どんな状況でも最高のタイミングで的確なギャグを言える能力』
僕は愕然とした。『くしゃみを絶対にしない体質』ではなかった。こんな土壇場で、ギャグの才能だと? ふざけるな! 怒りがこみ上げた瞬間、僕はメッセージの最後の追伸を思い出した。
『平凡から抜け出すのに、偉人の言葉は必要ない。必要なのは、困難を笑い飛ばす君自身の言葉だ』
その言葉が胸に染み渡ったとき、鼻の奥で臨界点を超えたむず痒さが爆発した。これまでで最大級の、世界が揺らぐほどのくしゃみが僕の体を突き抜ける。
「――ハックション!」
身構えた。次は何だ? ソクラテスか? それともシェイクスピアか?
しかし、僕の口から飛び出したのは、偉人の名言ではなかった。
「……花粉と僕の将来、どっちが飛んでるかって? ……どっちも先が見えねえよ!」
シン、と世界が静止した。
第七章 非凡なる凡人
僕の渾身のギャグは、才能交換日の朝の、ざわついた広場に虚しく響き渡る……はずだった。
一拍の間を置いて、くすくすと小さな笑い声が漏れた。それは瞬く間に伝染し、広場は大きな爆笑の渦に包まれた。昨日まで僕を遠巻きに見ていた人々が、腹を抱えて笑っている。『あらゆる行列に割り込む才能』を持つ主婦も、『カラスと口喧嘩する才能』の青年も、涙を流して笑っていた。
僕は呆然と立ち尽くす。偉人の言葉は、僕と世界との間に壁を作った。でも、僕自身の言葉は、僕と世界を繋げた。
未来の僕がどうなったのかはわからない。この瞬間、ループは断ち切られ、彼は救われたのだろうか。それとも、僕が新しい道を歩み始めたことで、彼の存在そのものが消えてしまったのだろうか。確かめる術はない。
僕は空を見上げた。降り注ぐ陽光の中に、無数の光の粒子――僕を長年苦しめてきた花粉が舞っているのが見える。鼻が、また少しむず痒い。次に飛び出すのはどんなギャグだろう。それはそれで厄介な人生に違いない。けれど、借り物の言葉を叫び続けるより、ずっといい。
非凡とは、特別な力を持つことではないのかもしれない。自分自身の言葉で、目の前の現実と向き合い、誰かを、そして自分自身を、ほんの少しだけ笑わせること。それこそが、僕が手に入れた本当の才能なのだ。僕は鼻を一つすすり、未来に向かって歩き出した。