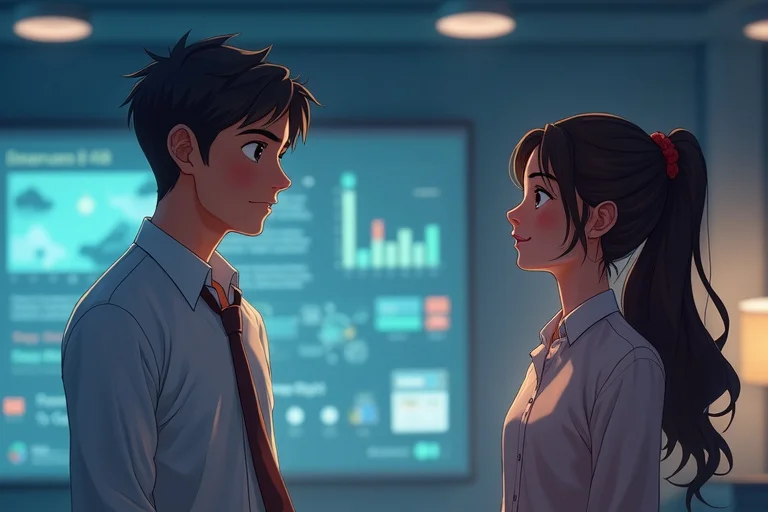第一章 逆さまの朝食と不協和音
吐き気がした。
二日酔いではない。内臓そのものが、喉元までせり上がってくるような強烈な浮遊感だ。
目の前で、納豆が浮いている。
箸先から伸びたネバネバの糸が、まるで重力を無視した蜘蛛の巣のように、天井へ向かって垂直に立ち昇っていた。
茶碗の中の米粒が、スノードームの中身みたいにキラキラと舞い上がり、蛍光灯の周りに集まっていく。
「……またかよ」
僕、天野慎重(あまの しんちょう)は、浮き上がりそうになる身体をテーブルの脚にしがみついて固定した。
ドオンッ!
壁の向こうから、何かが爆発したような衝撃音が響く。
隣室の権田さんだ。
「ふざけんじゃねえぞ、この野郎ッ!」
野太い怒号とともに、部屋の空間が歪む。
空気がキシキシと悲鳴を上げ、僕の胃袋がさらにねじり上げられる。
権田さんの『怒り』だ。
彼の激情は物理法則を無視して空間に作用し、局所的な重力反転を引き起こす。
ガシャアン!
テーブルの上に置いてあったマグカップが、天井に向かって「落下」した。
砕け散った陶器の破片が、頭上——いや、天井という名の地面に散らばる。
その瞬間、こめかみに鋭い痛みが走った。
視界がホワイトアウトする。
来た。
『予知』だ。
僕の脳味噌に、これから起こる未来の映像が無理やりねじ込まれる。
——ギギギ、バキィッ!
鉄骨が飴細工のようにねじ切れる音。
アパート『ハイツ・ヒヤヒヤ』の外壁が内側へ向かって急速に収縮していく。
逃げ遅れた住人たちが、圧縮された建材の隙間で手足をばたつかせ、断末魔の悲鳴を上げる。
そして最後には、アパートがあった場所が巨大なクレーターとなり、土煙だけが虚しく舞う——。
「う、ぐぁ……ッ!」
あまりに鮮明な『崩壊』のビジョンに、僕は口元を押さえた。
いつもの「階段でスネを打つ」とか「コンビニでお釣りを落とす」といった可愛い予知じゃない。
これは、死だ。
全滅だ。
「は、吐きそうだ……でも、逃げなきゃ……」
震える手で、枕元に常備している防災ヘルメットを掴み取る。
ベルトを顎に食い込むほどきつく締めた。
「権田さんの怒りを……いや、この異常な『エコー』の元凶を止めないと、僕たちはミンチになる!」
僕は意を決して、床——今は天井となっている面——を蹴った。
逆さまの世界で手足をばたつかせ、ドアノブにしがみつく。
ガチャリ。
ドアを開けた瞬間、平衡感覚が暴力的にシェイクされた。
廊下は重力が正常らしい。
僕は天地が逆転する感覚に翻弄されながら、無様に廊下の床へ叩きつけられた。
「痛っ……!」
全身を打撲した痛みに呻く間もなく、僕は顔を上げた。
一刻の猶予もない。
あのアパート圧壊の未来図が、現実になるまでのカウントダウンは始まっている。
しかし、立ち上がろうとした僕の視界から、急速に「色彩」が失われ始めた。
第二章 灰色の廊下とスルメの回避
廊下の突き当たり、203号室から冷たい風が吹き抜けてきた。
物理的な風ではない。
肌にまとわりつくような、湿った陰鬱な気配だ。
壁のシミも、錆びついた手すりも、僕が着ている派手なピンクのTシャツさえも。
すべてが彩度を失い、古いモノクロ映画のような灰色に染まっていく。
「うう……私のサボテンが……また枯れちゃった……」
203号室から漏れ聞こえる、細川さんの啜り泣く声。
彼女の『悲しみ』は、周囲の事象から活力を奪い、色あせさせる。
「寒い……」
歯の根が合わない。
気温は下がっていないはずなのに、骨の髄から凍えるような寒気がする。
足が鉛のように重い。一歩踏み出すだけで、泥沼に腰まで浸かっているような抵抗を感じる。
このままでは動けなくなる。
僕は震える手で、ポケットに入れていた非常食の『激辛スルメ』を取り出した。
「これを食べてカプサイシンパワーで……いや、細川さんに投げ渡して元気づければ……」
スルメを振りかぶった、その瞬間。
脳裏に再び閃光が走る。
——ピシャッ。
投げたスルメが美しい放物線を描き、廊下の角から現れた大家さんの顔面に張り付く映像。
激怒した大家さんが「ワシの顔は珍味置き場か!」と叫び、その『興奮』で衝撃波が発生。
ただでさえ不安定なアパートの構造が致命的なダメージを受け、崩壊が早まる——。
「っ……危ない!」
僕は寸前で投球動作を止め、スルメを口にくわえたまま、咄嗟に横の物置スペースへ飛び込んだ。
直後、廊下の角から白衣姿の老人が現れた。
大家さんだ。
「ふむ、数値が安定せんのう……」
彼はブツブツと呟きながら、僕が隠れた物置の前を通り過ぎていく。
セーフだ。
スルメ顔面事件は回避された。
しかし、安堵したのも束の間、僕は異変に気づいた。
大家さんが去ってきた方向——廊下の天井にある点検口が、半開きになっている。
そこから、禍々しい紫色の光が漏れ出していた。
そして、耳障りな重低音が響いている。
ヴゥゥゥン……ヴゥゥゥン……
腹の底に響くような、不快な振動音。
権田さんの怒りでも、細川さんの悲しみでもない。
もっと異質で、人工的な『歪み』の発生源。
僕の予知能力が、けたたましく警鐘を鳴らした。
あの天井裏だ。
あそこにあらゆる災厄の根源がある。
「……あそこに行けば、確実に『何か』ある」
足がすくむ。
僕は慎重だ。石橋を叩いて、ヒビがないか確認してから、結局渡らないタイプの人間だ。
あんなお化け屋敷みたいな天井裏に飛び込むなんて、正気の沙汰じゃない。
でも。
脳裏に焼き付いた、アパートがクレーターになる映像が消えない。
「くそっ……僕の部屋には、まだ読み終わってない漫画が山ほどあるんだよ!」
僕は恐怖を怒りでねじ伏せ、スルメを噛みちぎると、天井裏へと続くハシゴに手をかけた。
第三章 屋根裏の咆哮と臆病者の突撃
屋根裏部屋は、サウナのような熱気と、電子レンジの中に入ったような不快な波動に満ちていた。
「うっ……」
目の前の光景に、僕は息を呑んだ。
部屋の中央に鎮座する、巨大な機械。
複数のスピーカーを溶接して固めたような歪な形状。
そこから伸びる無数のケーブルが、脈打つ血管のように床を這っている。
機械の中心部には、紫色のクリスタルが埋め込まれており、それが不規則に明滅するたびに、空間がビリビリと震えた。
これが、原因か。
「素晴らしい数値じゃ! これなら住民全員の感情をブーストできる!」
戻ってきた大家さんが、機械の前で狂喜乱舞していた。
白衣を翻し、両手を広げている。
「大家さん! 何やってるんですか!」
僕が叫ぶと、大家さんはギョッとして振り返った。
「おお、天野くん。見ろ、ワシの発明『エモ・ホーン』じゃ! 最近のアパートは活気がないからな、感情を増幅させる電波を出しておるんじゃよ!」
「活気ってレベルじゃないですよ! 外はめちゃくちゃだ!」
「ふふふ、多少の副作用はあるが、データは順調じゃ!」
バチチチッ!
その時、エモ・ホーンから火花が散った。
紫色のクリスタルに亀裂が走り、今までとは桁違いの轟音が響き渡る。
ギャアアアアアアアッ!
機械が断末魔を上げているようだ。
直後、僕の視界が真っ赤に染まった。
本日最大級の予知ビジョン。
——クリスタルが砕ける。
放出されたエネルギーが、権田さんの怒りと細川さんの悲しみを限界突破させる。
重力係数が無限大になり、アパートが一瞬でブラックホールのように収縮。
僕も、大家さんも、一瞬で素粒子レベルまで分解される——。
「ひいぃッ! 確定する! 未来が確定しちまう!」
膝がガクガクと震える。
逃げたい。今すぐここから逃げ出して、遠くへ行きたい。
でも、間に合わない。
今ここで止めなければ、僕の慎重な人生はここでジ・エンドだ。
「スイッチは! 停止スイッチはどこだ!」
「スイッチ? そんなもの、つけるわけなかろう! 男は一度走り出したら止まらんのじゃ!」
「このマッドサイエンティストがァッ!」
あと数秒。
あと数秒で、限界を超える。
機械の周囲には、衝撃波のバリアのようなものが渦巻いている。
近づけばただでは済まない。
骨の一本や二本、いや、内臓破裂もあり得る。
僕は天野慎重だ。
リスクを冒さない男だ。
でも、最大のリスク(死)を回避するためには、中程度のリスク(重傷)を取るしかない。
「……うおおおおおおッ!」
僕は叫んだ。
恐怖で動かない足を、無理やり前へと叩き出す。
心臓が破裂しそうだ。
怖い、痛い、死にたくない。
衝撃波が全身を殴りつける。
皮膚が裂けるような痛み。
それでも、僕は止まらない。
狙うは一点、あの亀裂の入ったクリスタル。
「僕の平穏を……返せェェェェッ!」
僕はヘルメットを被った頭から、弾丸のように突っ込んだ。
不格好なロケットダイブ。
大家さんの制止する声がスローモーションに聞こえる。
ガッ、シャアアアアアンッ!!
ヘルメットの硬質な先端が、クリスタルを粉砕した。
閃光。
そして、鼓膜をつんざくような高周波音。
世界が白く染まり、僕の意識はそこでプツリと途切れた。
最終章 退屈な極彩色
小鳥のさえずりで目が覚めた。
「……生きてる?」
身体を起こすと、激痛が走った。
全身打撲に、首のむち打ち。
でも、手足はついているし、アパートもブラックホールにはなっていなかった。
廊下に出ると、窓から差し込む朝日が眩しい。
なんて鮮やかな色彩だろう。
重力はちゃんと下に向かって働いている。
「おはようございます……」
向こうから、権田さんが歩いてきた。
いつものような殺気がない。
まるで僧侶のように穏やかな顔で、僕に会釈をして通り過ぎていく。
続いて細川さん。
彼女もまた、能面のような無表情で、植木鉢に水をやっている。
「……水、やらないとね」
感情の籠っていない、事務的な声。
「……副作用か」
背後から、包帯だらけの大家さんが現れた。
エモ・ホーンの爆発に巻き込まれたはずだが、しぶとく生きているらしい。
「感情増幅の反動で、みんな『感情枯渇状態』になってしもうた。しばらくは、このアパートは静寂に包まれるじゃろうな」
大家さんは寂しそうに言った。
僕は廊下の手すりにもたれかかり、眼下を見下ろした。
静かだ。
怒号も飛ばない。壁も震えない。色もあせない。
完璧で、平穏で、安全な日常。
僕が求めていた「慎重な生活」そのものだ。
……なのに。
なんでこんなに、胸が詰まるような虚しさを感じるんだろう。
ふと、脳裏に新しい予知が浮かんだ。
数日後。
大家さんが懲りずに新しい装置『エモ・スタビライザー』を起動させる映像。
今度はアパート全体が虹色に発光し、住人たちがミュージカルスターのように歌いながら、商店街へ踊り出ていく未来。
権田さんがタップダンスを踊り、細川さんがソプラノで愛を歌い、僕自身も満面の笑みでタンバリンを叩いている。
「……ぶっ」
僕は思わず吹き出した。
首の痛みが走ったが、笑いは止まらなかった。
「どうしたかね、天野くん」
「いえ……大家さん、次の発明、手伝いますよ」
「ほう?」
「ただし、今度は安全装置を三重につけますからね。僕が設計します」
「ふむ、慎重な君らしい。交渉成立じゃ!」
大家さんの瞳に、怪しげな光が戻る。
灰色の静寂の中に、少しだけ色が戻った気がした。
僕はこのトラブルだらけの『ハイツ・ヒヤヒヤ』が、どうしようもなく好きなのだ。
首のコルセットをさすりながら、僕は空を見上げる。
さあ、覚悟を決めよう。
嵐のような、最高に騒がしい日常を取り戻すために。