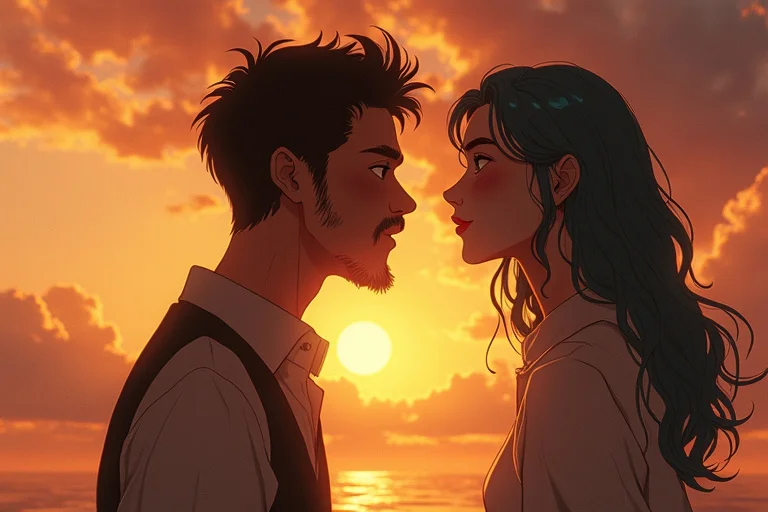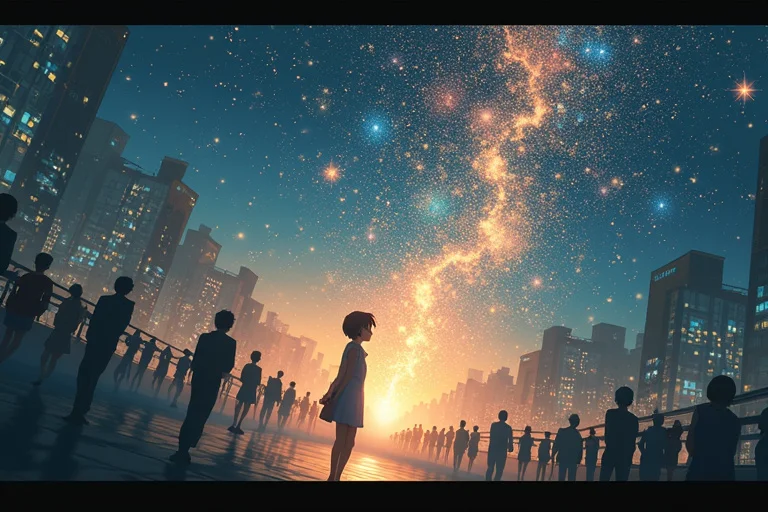第一章 鳴き声だらけの朝と、けたたましい沈黙
僕、音無響(おとなしひびき)の朝は、いつだってオーケストラの狂騒曲で幕を開ける。窓の外で雀が「チュンチュン」と鳴けば、僕の耳にはシンバルが「シャーン!」と鳴り響き、階下の夫婦が「ワン!」「ニャー!(喧嘩だろう)」とやり合えば、ゴングの音が「カーン!」と頭蓋を揺らす。そう、僕は感情が高ぶると、周囲のありとあらゆる音が、その感情に合わせたギャグ漫画の効果音に変換されてしまう、実に厄介な体質の持ち主だった。
勤め先の図書館は、本来ならば静寂の聖域のはずだった。しかし、利用者が本を落とせば「ドッシャーン!」、くしゃみをすれば「ハクション大魔王!」とでも言いたげなファンファーレが鳴り響く。僕は今日もカウンターの奥で、内心の喧騒を押し殺しながら、ひたすら本の背表紙を眺めていた。この世界では、人々は皆、生まれた時からランダムな動物の鳴き声でしか話せない。僕にとっては、それが救いでもあり、呪いでもあった。意味の分からない鳴き声は、感情の起伏を最小限に抑えてくれるから。
その日の夕暮れ、仕事を終えた僕の前に、けたたましい音と共に一人の女性が現れた。
「ミャオ!(響、見つけた!)」
幼馴染の発明家、月島鳴(つきしまめい)だ。彼女が興奮気味に駆け寄ってくるだけで、僕の耳元では「ダダダダダ!」と足音がオーケストラヒットに変換される。
「キッキッキー!(すごいものができたの!)」
鳴はそう鳴きながら、古めかしいトランシーバーのような機械を僕の目の前に突きつけた。銀色のボディに不格好なアンテナ、そして小さな液晶画面がついている。これが、僕らの世界の運命を、そして僕自身の耳を、ほんの少しだけ変えることになる『嘘つきの翻訳機』との、最初の出会いだった。
第二章 嘘つき翻訳機とゴールデンタイムの憂鬱
「これを、そこの猫に向かって使ってみて!」
鳴は目を輝かせながら「チューチュー!」と鳴いた。僕は言われるがまま、路地裏で毛づくろいをする三毛猫に翻訳機を向け、スイッチを入れる。ピポパ、と間の抜けた起動音が鳴り、液晶画面に文字が浮かび上がった。
翻訳結果:あー、今日のカリカリ、ちょっと湿気ってんだよな。もっとパリッとしたやつ寄越せってんだ、人間。
思わず吹き出しそうになるのを堪える。猫の威厳に満ちた「ニャア…」という鳴き声の裏に、そんな俗物的な本音が隠されていたとは。
「どう? すごいでしょ!」
「クワックワッ!(どういう仕組みなんだ?)」
僕がアヒルのように鳴くと、鳴は得意げに胸を張った。
「コケコッコー!(脳波の微弱な振動から、本音の言語情報を抽出するの! だから嘘はつけない!)」
なるほど、嘘つきの翻訳機、とはよく言ったものだ。相手が隠したい本音ほど、正確に暴き出してしまうらしい。この発明は、コミュニケーションを円滑にするのか、それとも破綻させるのか。僕の頭上には、巨大な「?」マークが「ポヨヨン」と浮かんだ気がした。
その夜、僕らは鳴の研究室で、一日に一度だけ訪れる奇跡の時間を待っていた。
午前零時。
壁掛け時計の長針と短針が重なった瞬間、世界から動物の鳴き声が消え、まるで魔法が解けたように、僕らは人間の言葉を取り戻す。
「――やっと、話せるね」
鳴の透き通るような声が、鼓膜を優しく震わせる。この一時間だけが、僕らが本当の意味で心を通わせられる、『言語のゴールデンタイム』だった。
「最近、この時間がどんどん短くなってる気がしないか?」
僕の言葉に、鳴はこくりと頷いた。彼女の表情が不安に曇る。その深刻な雰囲気に、僕の感情がざわついた。壁の時計の秒針の音が、やけに大きく聞こえ始める。「カチ、カチ」という無機質な音が、次第に「ドクン、ドクン」という不吉な心音に変わり、そしてついに、終了時刻を五分も残して、時計の針が止まったかのように、世界は再び鳴き声だけの混沌に沈んでしまった。
「ピヨ……(嘘でしょ……)」
鳴の絶望的なつぶやきが、僕の耳には「ガビーン!」という雷鳴となって突き刺さった。
第三章 消えゆく言葉
ゴールデンタイムの短縮は、日に日に深刻になっていった。一時間が五十分になり、三十分になり、やがて十分を切る頃には、街は目に見えて混乱し始めていた。言葉を交わせる時間が短くなるにつれ、人々の鳴き声には焦りと苛立ちが混じり、街角では些細な誤解から生まれる喧嘩が絶えなかった。翻訳機を使っても、表示されるのは「(ああもう、どいつもこいつもイライラする! 早く帰って寝たい!)」といった身も蓋もない本音ばかりで、解決の糸口にはならなかった。
僕と鳴は、鳴の研究室にこもり、この世界の異変の原因を探っていた。あらゆる神話、伝承、古文書を読み漁る日々。僕の耳は、ページをめくる音すら「ペラリーン♪」というコミカルなサウンドに変換し、シリアスな調査の邪魔をする。
「あった……これかもしれない」
ある晩、鳴が埃まみれの古文書の一節を指差した。羊皮紙に書かれていたのは、『星のささやき』と呼ばれる、忘れられた伝承だった。
「太古の昔、我々の祖先は星と話した。大地そのものが意思を持ち、その声に耳を傾けることで、豊穣と平和を得ていた、と……」
「地球が、話す?」
ゴールデンタイムがまだ残っていた、貴重な数分間での会話だった。僕がそう聞き返すと、鳴は真剣な眼差しで頷いた。
「もし、この世界が動物の鳴き声でしか話せないのが、その『地球』の意思だとしたら? そして、ゴールデンタイムが短くなっているのは……」
彼女は言葉を切り、窓の外に広がる、ネオンと排気ガスに汚れた夜空を見上げた。その瞳には、僕らが今まで考えもしなかった、途方もない可能性が映っていた。
第四章 地球の声
ゴールデンタイムが、ついに残り三分となった夜だった。僕らは鳴の研究室の屋上にいた。鳴は『嘘つきの翻訳機』を改造し、巨大なパラボラアンテナに接続していた。
「バカげてるって思うでしょ」
鳴は自嘲気味に笑いながら、ケーブルを繋いでいく。
「でも、もし本当に地球に意思があるなら、その声を聞けるかもしれない。この世界で一番大きな『本音』を」
彼女がスイッチを入れると、翻訳機のディスプレイに砂嵐のようなノイズが走った。僕は固唾を飲んで画面を見守る。僕の心臓の音が「ドッドッドッ…」と、恐怖を煽るドラムロールのように鳴り響く。
その、瞬間だった。
ノイズの合間に、たった一言、カタコトの文字が浮かび上がった。
……ウルサイ……
直後、世界から、完全に音が消えた。
車の走行音も、遠くで鳴いていた救急車のサイレンも、隣のビルから漏れる音楽も、そして僕の耳の中で絶えず鳴り響いていたギャグ効果音さえも。全てが、まるで分厚い真空の壁に吸い込まれたかのように、完璧な無音に包まれた。
僕の人生で初めて体験する、絶対的な静寂。
それは安らぎなどではなく、むしろ全てから拒絶されたような、巨大な孤独感だけを僕に突きつけた。地面が、まるで溜め息をつくように、ごくかすかに、ゆっくりと揺れた。
僕らは、星の機嫌を損ねてしまったのだ。
第五章 古代の契約と僕らの無駄話
揺れが収まると、翻訳機のディスプレイに、今度は鮮明な文章が、まるで誰かがタイプしているかのように、ゆっくりと表示されていった。
お前たちの祖先は、あまりにも饒舌だった。どうでもいい話、悪意のある話、意味のない話。その言葉の洪水が、私――この星のエネルギーを削り、私を疲弊させた。だから、契約を交わしたのだ。お前たちの『無駄話』を減らすために、言葉を少しだけ預かる、と
それが、僕らの世界にかけられた、コミュニケーション制限という名の呪いの正体だった。人類が地球のエネルギーを消費しすぎないための、一種の安全装置。ゴールデンタイムは、地球が人類に与えた、最低限の慈悲だったのだ。
だが、最近のお前たちはどうだ。空気を汚し、水を濁し、私の肌を傷つける。おかげで私の気分は最悪だ。イライラして、お前たちにくれてやる慈悲の時間も、惜しくなる
近年の環境破壊が、地球の体調を悪化させ、その不機嫌がゴールデンタイムを短縮させていた。僕らの未来は、文字通り、この星の気分一つにかかっていた。
絶望的な真実に、僕らは言葉を失った。いや、元々、僕らにはもう鳴き声しか残されていなかった。僕が呆然と空を見上げると、鳴が僕の袖を弱々しく引いた。彼女の「ピィ…」という小さな鳥のような鳴き声が、絶対的な静寂の中で、やけに悲しく響いた。
第六章 僕らはそれでも鳴き交わす
世界はすぐには変わらなかった。地球の意思という途方もない真実を前に、人々はただ戸惑い、怯えるだけだった。しかし、絶望の淵から、ほんの少しずつ、変化の兆しが生まれ始めた。
公園のゴミを拾う高校生の「モー(やれやれだぜ)」。蛇口の水をこまめに止める主婦の「コケッ(節約、節約)」。誰に強制されるでもなく、人々は星を労わるように、自分たちの生活を静かに見直し始めた。
ゴールデンタイムは、一日に数秒ずつ、亀の歩みのように回復していった。完全な一時間を取り戻すには、何十年、いや何百年かかるか分からない。それでも、誰も諦めはしなかった。
あの日から一年が過ぎた、秋の夕暮れ。僕は鳴と共に、丘の上の公園のベンチに座っていた。隣のベンチでは、若いカップルが身を寄せ合っている。
「ニャー(今日の夕日、綺麗だね)」
「ミャウ(君ほどじゃないよ)」
二人の鳴き声に、鳴がそっと翻訳機を向けた。ディスプレイには、こう表示されていた。
(君の寝癖、渦巻銀河みたいで最高にクールだな)
(あなたの指先のささくれ、私のために頑張ってくれてる証拠だもんね)
口に出すには少し照れくさい、けれどどうしようもなく愛おしい本音。僕は思わず、ふっと笑みを漏らした。
すると、僕の耳に、優しくて温かい音が響いた。
「ポワワーン」
それはもう、僕を苛む騒音ではなかった。世界を彩る、愛すべきシンフォニーの一部だった。
僕らは、完全な言葉を取り戻すことはないのかもしれない。地球曰く、「また無駄に喋りすぎたら困るからね」とのことだ。
でも、それでいいのかもしれない。
不完全で、もどかしいコミュニケーションの中で、僕らは言葉以外の何かで繋がり、本当に伝えたい一言の重みを、今、噛み締めている。
この呪いは、もしかしたら、僕ら人類への最後の贈り物だったのかもしれない。僕らはこれからも、この星の上で鳴き交わし、互いの本音を探り合いながら、生きていくのだろう。けたたましくも、愛おしいこの世界で。