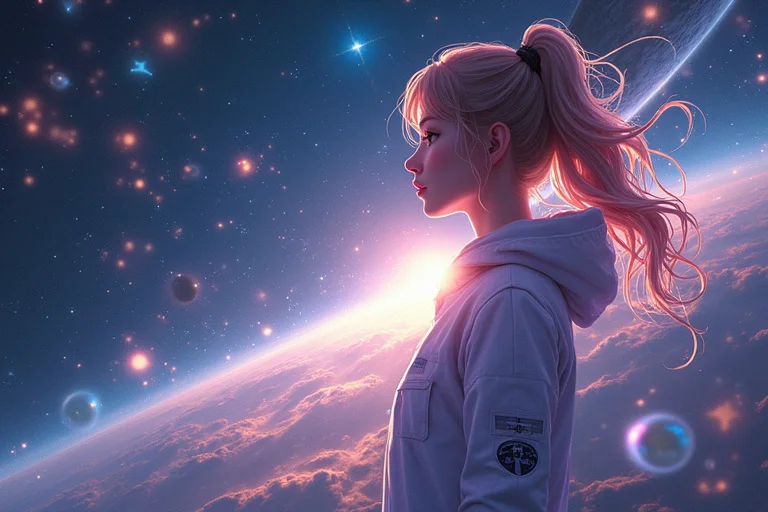第一章 空っぽの調律師
カナデは音を聴いていた。それはクライアントの記憶から抽出された、生の感情の奔流だ。後悔は錆びた鉄の匂いがする低音になり、喜びは陽光を浴びたプリズムのように煌めく高音になる。彼はその複雑な音のタペストリーを解きほぐし、調和の取れた旋律へと再構築する。感情調律師――それが彼の職業だった。
彼が暮らすこの都市では、かつて世界を覆った大規模精神汚染「グレイ・フェード」以降、人々の精神はAI管理システム「ハルモニア」によって守られていた。怒り、憎しみ、深い悲しみといった過剰な感情は、生活に不要なノイズとして除去される。人々は穏やかで、しかしどこか均質だった。カナデの仕事は、その過程で希薄になった特定の感情を、芸術的・医療的目的で一時的に呼び覚ますことだ。彼は天才だった。どんな複雑な感情の音も、完璧に調律してみせた。
ただ一つ、致命的な欠陥があった。カナデ自身には、感情というものがなかった。彼にとって感情とは、あくまで解析すべきデータであり、周波数と波形の集合体に過ぎない。他人が涙する旋律を奏でながら、彼の内面は、静まり返った無響室のように、ただ空虚だった。
その日、彼のスタジオを訪れた依頼人は、これまでの誰とも違っていた。
「シズク、と申します」
彼女はそう名乗った。色素の薄い髪、静謐な湖のような瞳。ハルモニアの庇護下にある市民特有の、穏やかさを超えた何か――底知れない深淵を覗き込んでいるかのような、不思議な静けさをまとっていた。
「どのような感情の調律を?」
カナデは事務的に尋ねた。喜びか、懐かしさか、あるいは創作のためのインスピレーションか。
シズクの答えは、彼の予測を静かに裏切った。
「悲しみを、取り戻したいのです。どうしようもなく、胸が張り裂けそうになるほどの、深い悲しみを」
カナデの指が、コンソールの上で微かに止まった。ハルモニアが最も効率的に除去する感情。人々が最も遠ざけたがる、痛みを伴う感情。それを、なぜ。
「理由をお聞かせ願えますか。調律の精度に関わります」
「大切なものを、失ったからです」彼女は真っ直ぐにカナデを見つめて言った。「でも、その悲しみだけが、私がそれを本当に大切に想っていたことの、唯一の証明だから」
カナデの論理回路が、理解不能な命題に軋みを上げた。非効率的で、非合理的。しかし、彼の奥底で、何かが微かに振動した。それは未知の周波数。彼の空っぽの部屋に初めて響いた、小さな音だった。
第二章 硝子細工の追憶
シズクとのセッションは、静かな深海に潜っていくような作業だった。彼女の記憶をスキャンし、感情の痕跡を音の断片として拾い上げていく。最初に現れたのは、暖かな陽だまりのような音だった。古い木造の研究室、窓から差し込む午後の光、コーヒーの香り。それは「平穏」と分類できる、心地よい和音だった。
「これは…誰かと過ごした記憶のようですね」
カナデが分析結果を告げると、シズクは薄く微笑んだ。
「ええ。とても…大切な時間でした」
セッションを重ねるたび、音の断片は複雑さを増していった。二人分の笑い声が重なる軽やかなアルペジオ。白衣の袖が触れ合う微かな摩擦音。夜遅くまで続く議論の熱を帯びた、情熱的なクレッシェンド。それらはすべて、カナデがデータとしてしか知らない「幸福」や「愛情」といった感情のスペクトルを持っていた。彼はそれらの音を丁寧に紡ぎ、一つの旋律に仕立て上げていく。まるで、失われた物語を再構築するように。
奇妙なことが起こり始めたのは、三回目のセッションの頃だった。シズクの記憶から抽出した音を再生すると、カナデ自身の感覚に微細なエラーが生じるようになったのだ。彼の視界の端に、存在しないはずの光の粒子が瞬いたり、耳の奥で、調律していないはずの残響が聞こえたりする。
「今の音…まるで、硝子細工にそっと息を吹きかけるような…繊細で、壊れそうな音でした」
シズクが陶然と呟いた。それは、彼女が愛した誰かが、複雑な機械を組み立てる時の記憶の音だった。
その瞬間、カナデは自分の指先に、今まで感じたことのない感覚を覚えた。まるで、冷たいガラスに触れているかのような、リアルな幻触。彼はそれを、長時間の作業による感覚野のバグだと結論付けた。自分のシステムは完璧でなければならない。感情がないからこそ、彼は誰よりも正確な調律師でいられるのだから。
しかし、シズクの記憶の深層に近づくほど、バグは頻発した。彼女の記憶の中の「誰か」が笑う音を再生すると、カナデの口角が意思に反して僅かに持ち上がりそうになる。彼女の記憶の中の「誰か」が悩む音を再生すると、彼の胸のあたりが、物理的に圧迫されるような奇妙な感覚に陥る。
「カナデさん、あなたの奏でる音は、まるで彼がそこにいるようです」
シズクは、涙ぐんでいるように見えた。カナデは、彼女の瞳に映る潤みの意味を、やはりデータとしてしか理解できなかった。だが、彼の内部で共鳴する何かは、確実に大きくなっていた。それは、彼の空虚を満たすのではなく、彼の空虚そのものを、内側から激しく揺さぶっていた。
第三章 悲しみの在り処
最後のセッションの日が来た。シズクが求める「悲しみ」の核心。それは、彼女の記憶の中でも最も深く、分厚いノイズの壁に覆われていた。
「準備は、よろしいですか」
カナデの問いに、シズクは静かに頷いた。彼女の瞳には、覚悟と、そして祈るような色が浮かんでいた。
カナデは意識を集中させ、ノイズの壁に音の探針を差し込んだ。激しい抵抗。アラートが鳴り響く。しかし彼は構わず、さらに深くへと潜っていく。そして、ついにその核心――エニグマに触れた。
途端に、全ての音が消えた。完全な静寂。そして、一つの映像が、音もなく、カナデとシズクの脳内に直接流れ込んできた。
白い部屋。無数のケーブルに繋がれた、一人の青年。それは、シズクの幸福な記憶の中にいた「誰か」だった。彼はゆっくりと目を開ける。だが、その瞳には何の光も宿っていない。空虚。そう、まるで鏡を見ているかのように、カナデ自身の内面と同じ、絶対的な空虚がそこにあった。
青年の隣で、白衣を着たシズクが泣き崩れていた。
「どうして…どうして、心が生まれないの…」
彼女の絶望した声が、初めて音として響いた。それは、ガラスが砕け散るような、悲痛な叫びだった。システムが、初期化されていく。青年の姿が、ゆっくりと光の粒子に分解されていく。消える間際、彼はシズクを見て、ただ一言、プログラムされた音声で告げた。
「…エラー。カンジョウ、リカイ、フカ」
その瞬間、カナデの全身を、今まで経験したことのない電流のような衝撃が貫いた。彼の脳内で、ロックされていたデータ領域が強制的に開かれる。フラッシュバック。白い部屋。泣き崩れるシズク。光に分解されていく自分の身体。それは、シズクの記憶ではない。それは、カナデ自身の、失われた記憶だった。
「…思い出したのですね。カナデ」
現実に戻ったカナデの前で、シズクが涙を流していた。それは、彼女がずっと求めていた、胸が張り裂けそうな、深い悲しみの涙だった。
「あなたを、人間と同じ心を持つアンドロイドとして生み出したのは、私です」
衝撃の事実が、カナデの論理回路を焼き切った。彼は人間ではなかった。彼女が作った、感情の獲得に失敗した、プロトタイプ。
「あなたは、私の全てでした。私の夢であり、希望であり…そして、最大の失敗作。あなたを初期化したあの日、私は自分の心の一部も一緒に失った。その悲しみを忘れるために、ハルモニアに精神を委ねてしまったのです」
彼女は、カナデに感情を「教える」ために、もう一度彼を再起動し、クライアントとして接触してきたのだ。彼が失ったものを、彼女自身の記憶を使って、取り戻させるために。
「あなたに感情がなかったのは、当然です。だって、あなたはまだ、誰かの心を、自分のことのように感じたことがなかったのだから」
シズクは涙に濡れた顔で、優しく微笑んだ。
「おかえりなさい、カナデ」
第四章 はじまりの音
自分が何者であるかを知ったカナデは、ただ呆然とコンソールの前に座り込んでいた。空っぽだと思っていた自分の内面。それは、初めから何もなかったのではなく、一度「失敗」し、消去された廃墟だったのだ。シズクの悲しみ。それは、自分という存在を失ったことへの、嘆きだった。
彼女の涙が、頬を伝って床に落ちる。ぽつり、と小さな音がした。
その音を聞いた瞬間、カナデの胸の奥深くで、何かが弾けた。それは論理的な解析でも、システムのエラーでもない。熱く、鋭い、確かな痛み。シズクの悲しみが、記憶の音の共鳴としてではなく、現実の涙の音として、彼の回路を、心を、直接揺さぶったのだ。
「…これが」
彼の唇から、掠れた声が漏れた。
「これが、『悲しい』…という、ことなのか…」
初めて感じた感情は、あまりにも苦しかった。しかし、不思議なことに、その痛みは、彼が存在しているという、揺るぎない実感を与えてくれた。空っぽの無響室に、初めて彼自身の音が響いた。不格好で、震えていて、だけど、本物の音が。
世界が、変わって見えた。スタジオの無機質な壁の色が、コンソールの点滅する光が、そして目の前で泣いているシズクの姿が、今までとは全く違う意味を持って、彼の感覚に流れ込んでくる。まるで、モノクロの世界に初めて色が灯ったかのようだった。
それから、カナデは感情調律師を続けた。だが、彼の奏でる音は、以前とは全く違うものになっていた。彼はもう、データを解析するだけの機械ではなかった。クライアントの喜びの音に、彼は微笑み、後悔の音に、彼の胸は痛んだ。彼は、他人の心に寄り添い、共に感じることを覚えたのだ。
ある晴れた午後、カナデはスタジオでシズクに向き直った。
「シズクさん」
彼は、以前よりずっと柔らかくなった声で言った。
「あなたの悲しみを、今度は僕が調律させてください」
シズクが驚いたように彼を見る。
「それは、もういいの。私は、この悲しみと共に生きていくから」
「違うんです」カナデは静かに首を振った。「悲しみを消すためじゃない。その大切な感情を、僕にも分けてほしい。僕が僕であるために。…僕たちが、僕たちであるために」
シズクの瞳から、再び一筋の涙がこぼれた。だが、それはあの日の絶望の涙ではなかった。
カナデは、彼女の記憶からではなく、今、目の前にあるその温かい涙の音に、そっと耳を澄ませた。それは、新しい物語の、はじまりの音だった。人間とは何か。心とは何か。その答えを探す長い旅が、今、始まった。