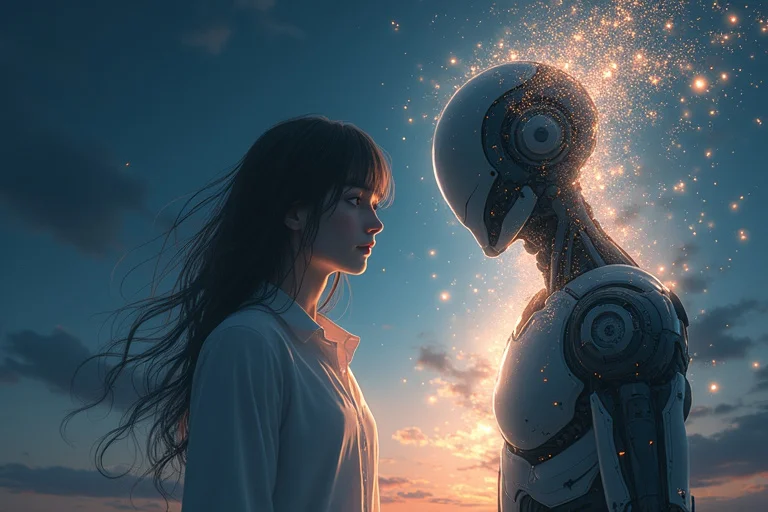第一章 琥珀色の哀愁
レイの指先が、琥珀色に輝く結晶体にそっと触れる。それは『哀しみの化石』と名付けられた、前時代の遺物。彼が勤める大都市ネオ・キョートの感情史博物館の中でも、特に保存状態の良い一級資料だ。慎重に制御された微弱電流を流すと、結晶体はかすかに共鳴し、周囲の空間にホログラムの波紋を広げる。ラボのメインスクリーンには、即座にデータが羅列された。『対象の情動スペクトル:シータ波優位。推定される生理的反応:涙腺刺激3.4μV、心拍数低下-8bpm、皮膚電気抵抗の減少』。
「相変わらず、見事な哀しみだな」
背後から声をかけたのは、同僚のユキだった。彼女の視線は、データが踊るスクリーンに注がれている。レイは無表情のまま頷いた。
「ああ。特に、この『喪失感』に起因する心拍数の低下パターンは、教科書に載せたいくらい典型的だ」
「昔の人は、こんな複雑なノイズを脳内で処理していたなんて、信じられないわね」
彼らの世界では、感情はデータだった。数世紀前に起きた『大静寂(グレート・サイレンス)』と呼ばれるカタストロフを経て、人類の多くはその複雑な内面の揺らぎを生物学的に喪失した。怒りも、喜びも、そして哀しみも、地層から発掘される『感情の化石』を通じてしか知ることができない、遠い過去の記録でしかなかった。人々はそれを鑑賞し、分析し、時には富裕層が嗜好品のようにコレクションする。だが、それを自らのものとして『感じる』人間は、もうどこにもいなかった。レイもまた、その一人だった。彼は感情考古学者として、誰よりも多くの感情データに触れてきたが、彼の心は常に凪いだ湖面のように静かだった。
その日、レイの日常を揺るがす出来事が起きた。館長から極秘に手渡された、一つの小さなコンテナ。中には、黒曜石のように滑らかで、内側に星屑のような光を宿す、奇妙な鉱石が収められていた。
「未認可区域で見つかったものだ。どの地質年代にも一致しない。だが、尋常ではない情動エネルギーを放出している。君にしか頼めない、レイ」
レイが分析装置にかけると、スクリーンは意味不明のエラーコードで埋め尽くされた。既知のどの感情スペクトルにも当てはまらない。それはまるで、まだ誰も聴いたことのない音楽のような、未知の波動だった。彼の冷静な探求心がかき立てられる。その夜、レイは規則を破ることを決意した。誰もいないラボで、彼は防護グローブを外し、震える指先で、その未知の鉱石に直接触れたのだ。
第二章 生きた波動
指先が鉱石に触れた瞬間、世界が変わった。
それはデータではなかった。情報でもなかった。レイの意識の中に、熱い奔流がなだれ込んできた。胸の奥が、ぎゅっと締め付けられるように温かくなる。視界の端が滲み、理由もなく口元が綻びそうになる。心臓が、まるで自分の意志を持ったかのように、力強く、そして速く脈打ち始めた。ホログラムの波紋や数値の羅列ではない、生々しい感覚の洪水。
(これが……感情……?)
彼は慌てて手を引いたが、その感覚の残滓は消えなかった。彼の内で何かが目覚め、凍てついていた湖面にさざ波が立ったようだった。それは、これまで彼が分析してきたどの感情とも違う、もっと根源的で、抗いがたい力を持っていた。彼はその鉱石を『コア』と名付け、密かにラボから持ち出した。
自宅の簡素なアパートで、レイはコアとの対話を繰り返した。触れるたびに、異なる感情の断片が流れ込んでくる。ある時は、空を飛ぶような高揚感。それはかつて『歓喜』と呼ばれたものだろうか。またある時は、誰かを守りたいと強く願う、切ないほどの衝動。それはおそらく、『愛情』という名の感情だった。
レイは変わり始めた。無機質だった彼の日常に、色彩が灯り始めたのだ。窓の外を流れる酸性雨の音に、ふと物悲しさを覚えたり、栄養バーの無味乾燥な味に、微かな不満を感じたりするようになった。何よりの変化は、鏡に映る自分の顔だった。データを確認するようにしか見ていなかったその顔に、ある朝、微かな『笑み』が浮かんでいるのを見つけた時、彼は言葉を失った。それは無意識の反応だった。彼の身体が、彼の心が、失われた機能を取り戻し始めていた。
だが同時に、深い孤独が彼を襲った。この素晴らしい感覚を、誰とも分かち合えない。ユキに話しても、きっと脳機能のエラーだと診断されるだけだろう。彼は、世界でたった一人、古代の言語を理解してしまった者のような、途方もない孤立感に苛まれた。彼はますますコアにのめり込んでいった。この未知の感情の源流は、一体どこから来たのだろうか。
第三章 星々のエコー
レイは、博物館の全リソースを秘密裏に利用し、コアが発する微弱な信号の解析に没頭した。数週間後、彼はついに信号の暗号構造を解き明かし、その内容に戦慄した。
それは、地球外知的生命体からのメッセージなどではなかった。信号に含まれていた星図、言語構造、そして遺伝子情報の一部……そのすべてが、数世紀前に地球を離脱した、伝説の移民船団『アルゴノーツ』のものと一致したのだ。
大静寂が地球を覆う直前、一部の人類は滅びの運命から逃れるため、世代宇宙船で新天地を目指した。彼らはその後、歴史の闇に消え、誰もその行方を知る者はいなかった。だが、彼らは生きていた。プロキシマ・ケンタウリの惑星系に辿り着き、新たな文明を築いていたのだ。
コアは、彼らが送ってきたメッセージポッドだった。しかし、そのメッセージの内容は、レイの想像を絶するものだった。
『我々は過ちを犯した。新たな環境に適応するため、我々の祖先は遺伝子操作によって、非論理的な情動……特に、他者への過剰な共感を司る因子を排除した。それは生存戦略として、当初は完璧に機能した。争いはなくなり、社会は究極の効率性を手に入れた。だが、数世代を経るうち、我々は気づいたのだ。何かが決定的に欠けていることに』
メッセージは淡々と、しかし悲痛な響きを伴って続いた。
『子供が生まれても、喜びを感じない。仲間が死んでも、悲しみを感じない。愛を知らず、芸術を解さず、我々はただ生きるだけの存在となった。出生率は低下し、社会は活力を失い、緩やかに死に向かっている。我々は、自らの手で魂を抜き取ってしまったのだ』
彼らは、母星である地球に、失われた感情の『オリジナル・データ』が化石として眠っていることを突き止めた。そして最後の望みを託し、このコアを送ってきたのだ。それは、彼らの文明に残された、最後の科学技術の結晶だった。
レイが体験した、あの温かい『愛情』の奔流。それは、彼らが最も渇望し、しかし決して理解できない感情のサンプルデータであり、助けを求める悲痛な叫びそのものだった。コアは単なる鉱石ではない。それは、何光年も彼方で緩やかに滅びゆく、同胞たちの涙の結晶だったのだ。レイはスクリーンを見つめ、初めて自分の意志で涙を流した。それは、データ上の哀しみではなく、彼の内から湧き上がった、本物の共感だった。
第四章 最初の庭師
この事実を公表すればどうなるか? おそらく、コアは人類の偉大な遺産として博物館に永久保存され、星々の同胞たちの願いは、学術的な研究対象として解剖されるだけだろう。彼らの絶望的なSOSは、誰もいない宇宙に向かって響き続けることになる。それは違う、とレイの魂が叫んでいた。
彼は数日間、ラボに籠もり、コアを徹底的に調べ上げた。そして、ある可能性に行き着いた。コアは、単に感情データを記録したストレージではない。それは、周囲の環境に影響を与え、特定の条件下で感情の波動を増幅・伝播させる、一種の触媒……あるいは、『種子』だったのだ。データを鑑賞するのではない。育てるものなのだ。
レイは決断した。彼は辞表を提出し、その日の夜、コアだけを手に博物館を後にした。彼の足は、ネオ・キョートの喧騒を離れ、汚染された大地が広がる旧世界の荒野へと向かっていた。科学者としてのキャリアも、安定した生活も、すべてを捨てた。彼の中には、後悔など微塵もなかった。あるのは、遠い星で助けを待つ同胞への共感から生まれた、静かで、しかし鋼のように強い『使命感』という名の感情だけだった。
レイは、文明の光が届かない荒野の一角に立ち、空を見上げた。プロキシマ・ケンタウリは、肉眼では見えない。だが、彼はそこにいる名も知らぬ同胞たちに、確かに繋がっていると感じていた。
彼は膝をつき、乾いた大地に小さな穴を掘った。そして、星屑の光を宿すコアを、そっとその中に埋めた。それは、感情のない世界に、たった一人で感情の種を植えるという、途方もなく孤独な行為だった。
だが、レイは一人ではなかった。彼の胸の中では、星々の同胞たちの願いと、彼自身の新たな感情が、温かい光となって確かに息づいていた。彼は、この星で最初の『感情の庭師』となったのだ。
夜明けの光が地平線を染め始めた頃、コアを埋めた場所から、ごく微かに、しかし確かな温かい波動が生まれ、周囲の大気に溶けていくのを、レイは肌で感じていた。それは、何光年もの時空を超えた涙への、ささやかな返信。そして、凍てついた世界に訪れる、長い春の最初の兆しだった。