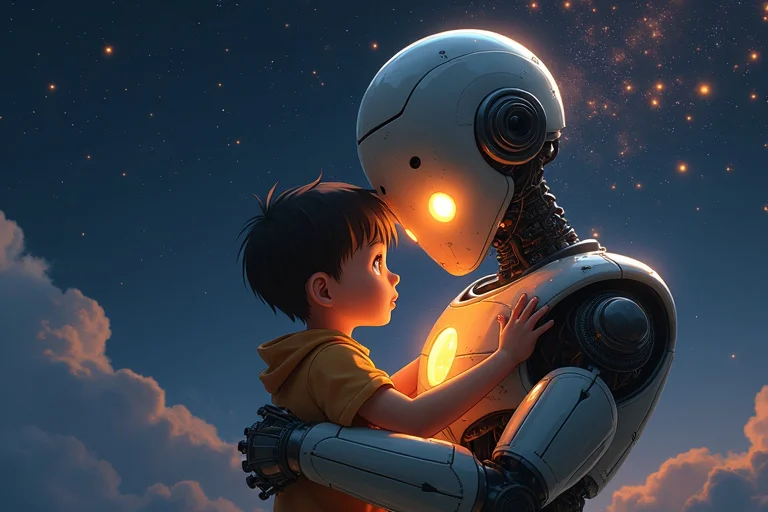第一章 揺らぐ世界の観測者
その朝、重力は昨日よりもわずかに弱かった。
ベッドから身を起こしたカイの身体は、綿のようにふわりと浮き上がり、慣性の法則が気まぐれに書き換えられたことを告げていた。窓の外では、隣家の屋根から滑り落ちた猫が、まるでスローモーション映像のように、優雅な弧を描いて地面に着地している。世界の再構成は、今朝も滞りなく行われたらしい。
カイは慣れた手つきでコーヒーを淹れる。湯が豆に落ちる音はいつもより甲高く、立ち上る香りは焦げ付くような鋭さを持っている。これもまた、分子間力の微細な変動によるものだ。この世界では、物理定数は眠りから覚めるたびに変わる。昨日の常識は、今日の非常識になる。人々は揺らぐ法則の中で、その日限りの最適解を探りながら、綱渡りのように生きていた。
カイは椅子に腰かけ、テーブルに置かれた小さな砂時計に目をやった。「刻縛の砂時計」。くびれたガラス管の中には砂の一粒もなく、代わりに数個の光の粒子が、まるで蛍のように頼りなげに漂っているだけだった。
彼はそっと息を吸い、意識を内側へ沈めた。
思考を、加速させる。
一瞬。世界から音が消え、色彩が滲む。コーヒーから立ち上る湯気は空中で凍りつき、窓の外で羽ばたく鳥は琥珀に閉じ込められたかのように静止した。一秒が、一時間に引き伸ばされる。彼の意識だけが、静止した世界を駆け巡っていた。
孤独な観測者。それが彼の立ち位置だった。手の中の砂時計に目を落とす。加速した彼の思考に呼応するように、内部の光が激しく明滅し、ガラスの内壁に無数の残像を焼き付けていた。まるで、彼の思考そのものが形を得たかのように。
第二章 刻縛の砂時計
「また、世界の歪みが大きくなっている」
研究室の冷たい空気の中、エリアがホログラムに映し出された複雑な数式を指でなぞりながら言った。彼女の眉間には、深い憂慮の皺が刻まれている。
「再構成の周期が乱れ始めているわ。このままでは、大規模な法則の破綻が起きるかもしれない」
「……だろうな」
カイは壁にもたれ、窓の外を流れる雲を眺めていた。今日の光速は普段より少し遅いらしく、雲の輪郭が奇妙に滲んで見えた。
「カイ。あなただけが頼りなの。あなたのその『眼』で、何か法則の綻びを見つけられない?」
「見つかれば苦労はしない」
カイはそっけなく答えながら、懐から例の砂時計を取り出した。エリアはそのガラス細工に興味深そうに目を細める。
「その砂時計…いつも持っているわね。ただのガラクタには見えないけれど」
「俺にも何なのかは分からない。ただ、これだけが俺の思考と同期する」
カイはエリアの目の前で、軽く思考を加速させてみせた。彼の瞳の奥が深く澄んでいくのと同時に、砂時計の中の光が一斉に輝きを増し、激しく乱舞する。エリアは息を呑んだ。
「これは…まるで共鳴ね。ねえ、カイ。この世界で唯一、揺らぐことのない定数があるわ。それは『時間』よ。重力も光速も変わるのに、なぜか一秒の長さだけは絶対に変わらない。もし、この砂時計が、あなたの思考によって固定される前の…本来の『揺らいでいた時間』の記憶を留めているとしたら?」
エリアの仮説は、カイの心の奥底に眠っていた漠然とした違和感を的確に射抜いていた。なぜ、時間だけが?そして、なぜこの砂時計は、自分の思考にだけ反応するのか?
第三章 無の境界線
世界の崩壊は、エリアの予測よりも早く始まった。
南の市街地で局地的な重力異常が発生し、高層ビルが飴のように捻じ曲がりながら崩落した。東の海上では空間そのものが歪み、蜃気楼のように現れた存在しないはずの島に何隻もの船が吸い込まれていった。人々の悲鳴は、予測不能な物理法則の前ではあまりに無力だった。
カイは瓦礫の山と化した市街地で、思考を限界まで加速させていた。崩れ落ちる鉄骨の隙間を駆け抜け、衝撃波が到達するよりも早く、瓦礫の下敷きになった少女を抱きかかえる。彼の網膜には、コンマ数秒先の未来予測が、無数の分岐を伴って映し出されていた。
もっと速く。もっと深く。
思考のギアをさらに一段階上げる。
その瞬間、世界が軋む音を立てた。視界の端が黒く欠け始め、全ての情報が意味を失ったノイズの奔流となって意識に流れ込んでくる。耳鳴りが思考を塗りつぶし、手足の感覚が薄れていく。これが「無」の入り口。情報のブラックホール。現実世界との同期が切れ、存在そのものが融解していく恐怖。
「カイッ!」
引き伸ばされた時間の向こう側から、エリアの叫び声が聞こえた。その声が、暗闇に沈みかけていた彼の意識を繋ぎ止める最後の錨だった。カイは必死に腕を伸ばし、現実の光を掴もうともがいた。
意識が現実の速度に戻った時、彼はエリアの腕の中で荒い息を繰り返していた。助け出した少女は、すでに救護班に保護されている。
「無茶よ…!あなたまで消えてしまったら…!」
「……見えたんだ」
カイは霞む視界で、自身の手のひらを見つめた。「無」の淵で、彼は奇妙なビジョンを見ていた。時間の流れがぐにゃりと歪み、自身の思考と絡み合っていく光景。そして、その中心には、あの「刻縛の砂時計」があった。
第四章 忘れられた記憶
「確かめなければならないことがある」
研究室に戻ったカイの瞳には、死地から生還した者の狂気にも似た光が宿っていた。彼はエリアの制止を振り払い、「刻縛の砂時計」を強く握りしめる。
「『無』の淵で時間の流れが歪んだ。俺の思考と、この世界の時間が繋がっている。もしそうなら…答えは俺の中にあるはずだ」
彼は目を閉じ、これまで踏み込んだことのない思考の最深部へと意識をダイブさせた。砂時計が媒介となり、彼の精神を防護壁のように包み込む。光が溢れ、記憶の回廊を凄まじい速度で逆行していく。そして、彼は辿り着いた。忘れられた、原初の記憶に。
そこは、何もない白い空間だった。幼い彼が、たった一人で泣いていた。制御不能に陥った思考加速が、彼を現実世界から引き剥がし、「無」へと突き落としたのだ。存在が希薄になり、自分が自分であるという感覚さえ消えかけていく絶望的な恐怖。
消えたくない。
その一心で、幼い彼は叫んだ。唯一、己の意思でコントロールできるものに縋った。自身の『思考の速度』という、内なる物差し。彼はそれを、まるで槍のように外部世界へ向かって突き立てた。
『この速度こそが、絶対不変の基準だ!』
その瞬間、彼の思考は世界に焼き付けられ、物理法則として強制的に固定された。それが、この世界における『時間』の正体だった。本来ならば他の定数と同じく揺らぐはずだった時間を、彼自身の存在がアンカーとなって縛り付けていたのだ。
そして、「刻縛の砂時計」は、その時に彼の意志から零れ落ちた、固定される前の『時間』の概念そのものだった。それは彼の魂の欠片であり、彼が世界にかけた呪いの物理的実体だった。
第五章 決断の零秒
真実という名の光は、あまりにも残酷だった。
世界を安定させていたのは自分自身。そして、世界の崩壊を招いているのもまた、自分自身。彼の精神が限界に近づくにつれて、時間のアンカーが揺らぎ、他の物理法則との間に致命的な不協和音を生み出していたのだ。
カイは、血の気の引いた顔で待つエリアに、全てを話した。彼女は静かに聞き終えると、震える手で彼の手に触れた。
「そんな…じゃあ、あなたは…この世界を支えるために、ずっと一人で…」
「支えてなどいない。歪めていただけだ」カイは自嘲気味に笑った。「俺が存在する限り、この世界はいつか俺ごと『無』に飲み込まれる。もう、時間がない」
その言葉通り、研究室の窓が突如として液体のように溶け始め、外の景色が歪んだ絵の具のように混ざり合った。世界の再構成が、もはや周期を無視して暴走を始めている。
「何か、何か方法があるはずよ!あなたの力を制御できれば…!」
「制御はできない。これは俺という存在そのものだからだ」
カイはエリアの手をそっと握った。その手は氷のように冷たかった。彼は、たった一つの、そして究極の解決策に辿り着いていた。
「エリア。ありがとう。君の声がなければ、俺はとっくに『無』に消えていた」
それが、別れの言葉だった。彼はエリアの手を離し、研究室の中央に立つ。その顔には、恐怖も絶望もなかった。ただ、深い安堵と、これから成し遂げることへの静かな決意だけが浮かんでいた。
第六章 世界という名の思考
最後の思考加速が始まる。
カイは「刻縛の砂時計」を胸に強く抱いた。それは失われた自分の一部を取り戻すための、最後の儀式だった。
意識が無限に拡散していく。一秒が永遠になり、永遠が刹那となる。彼の肉体が、まばゆい光の粒子となってゆっくりと分解を始めた。それは消滅ではなかった。遍在。彼は、彼を縛り付けていた時間の軛から自らを解き放ち、その思考を、意識を、世界の全ての物理定数へと分け与えていく。
重力に、彼の穏やかな思考を。
光速に、彼の揺るぎない意志を。
電磁気力に、彼の温かな記憶を。
彼の個としての意識は、霧散していく。だが、彼の思考は、世界の法則そのものと融合し、完璧な調和を奏で始めた。暴走していた再構成は収束し、不安定だった物理定数は、永遠に揺らぐことのない絶対的な安定を得た。
エリアは、窓の外で起こっている奇跡を、涙を流しながら見つめていた。歪んでいた空間は元に戻り、空は一点の曇りもない、完璧な青色に染まっている。風が窓から吹き込み、彼女の頬を優しく撫でた。その風の音は、まるで囁きのように聞こえた。
彼女の手の中に残された砂時計は、内部の光を完全に失い、ただの冷たいガラスの器になっていた。
世界は、美しく安定した。それは、カイという一人の青年が捧げた、零秒にも満たない永遠の遺言によって成し遂げられたのだ。エリアは空を見上げる。この世界の全ての原子が、全ての光が、全ての響きが、彼そのものなのだ。彼はどこにもいない。けれど、どこにでもいる。
風が再び吹き、エリアの髪を揺らす。その感触の中に、彼女は確かに、彼の思考の残響を感じていた。