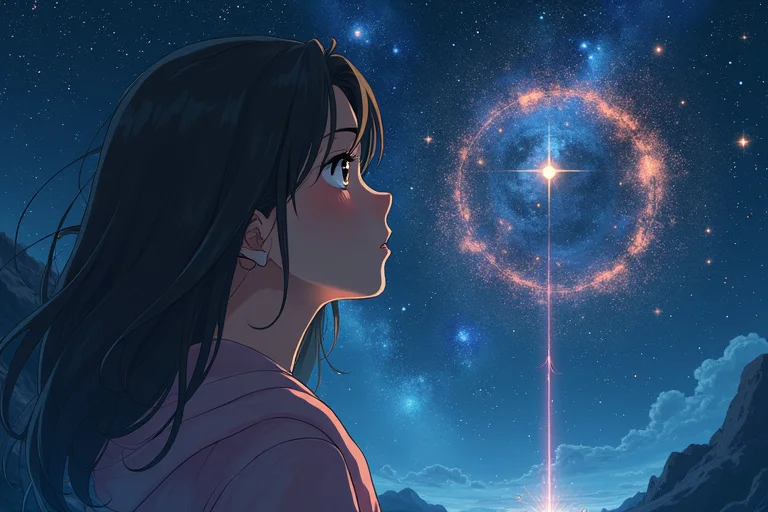第一章 砕けた感謝
リクトの世界は、言葉でできていた。人々が紡ぐ想いは、空気中で瞬く間に結晶化し、「言晶(げんしょう)」となる。朝の食卓に交わされる「おはよう」は、部屋を暖める柔らかな光の粒となり、「愛してる」という囁きは、掌で温かな熱を放つ宝玉に変わる。この世界で、リクトは「言霊師(ことだまし)」だった。人々の言葉から生まれた言晶を育て、その力を社会のために調律する、庭師のような存在だ。
彼が管理する第十七言晶庭園は、都市の中心にありながら、静寂に包まれていた。ガラス張りのドーム内に整然と並べられた台座の上で、無数の言晶がそれぞれの光を放っている。「希望」の言晶は青白い光を明滅させ、「勇気」の言晶は燃えるような真紅に輝く。リクトは、その一つ一つに触れ、埃を払い、囁きかけるようにして力を引き出す。それが彼の日常であり、すべてだった。
中でも、彼が最も心を注いでいるのは、庭園の最奥に安置された琥珀色の言晶だった。十年前に亡くなった祖母が、最後に彼に残した「ありがとう」という言葉の結晶だ。それは他のどんな言晶よりも温かく、優しい光を放ち、過去に囚われがちなリクトの心を慰めてくれる唯一の錨だった。
その日、異変は静かに訪れた。
いつものように庭園の巡回をしていたリクトは、祖母の言晶に近づき、その輝きが僅かに揺らいでいることに気づいた。心臓が嫌な音を立てる。彼は台座に駆け寄り、言晶をそっと両手で包み込んだ。いつもなら、じんわりと広がるはずの温もりが、今日は妙に冷たい。目を凝らすと、信じられないものが映っていた。滑らかだったはずの琥珀色の表面に、髪の毛ほどの細さの、しかし明確な亀裂が走っている。
「……嘘だ」
声が漏れた。言晶は、込められた想いが純粋で強固なほど、永続的な輝きを保つ。特に、死にゆく者が遺した感謝の言葉は、半永久的にその形を留めると教えられてきた。それが、なぜ。
リクトはすぐさま中央管理局に連絡を入れたが、返ってきた答えは彼をさらに絶望させた。彼の庭園だけでなく、世界中の言晶、特に「感謝」や「愛情」といったポジティブな言晶に、同様の亀裂や輝きの減衰が報告されているというのだ。世界から、言葉の力が失われつつある。人々はそれを「言葉の枯渇」と呼び、静かなパニックが広がり始めていた。
リクトは砕け散りそうな祖母の言晶を握りしめた。このままでは、祖母との唯一の繋がりが消えてしまう。なぜ、こんなことが起きるのか。彼の脳裏に、幼い頃に聞かされた古い伝説が蘇った。世界には、人々が意図的に忘れてしまった「失われた言葉」が存在するという。その言葉の欠如が、世界の言葉の循環を歪ませ、やがては枯渇を招くのだ、と。
ほとんどの言霊師は、そんなものは迷信だと一笑に付した。だが、リクトは藁にもすがる思いでその伝説を信じた。そして、彼には心当たりがあった。十数年前、事故で両親を同時に失った時の記憶。それは曖昧な霧に包まれ、どうしても思い出せない。だが、両親が最後に何かを言いかけた、その唇の動きだけが、悪夢のように彼を苛むのだ。もしかしたら、あの言葉こそが……。
リクトは決意した。この世界の謎と、自分自身の過去の謎を解き明かすために。「失われた言葉」を探し出さなければならない。砕けかけた祖母の「ありがとう」が、彼の背中を静かに押していた。
第二章 沈黙の図書館
「失われた言葉」の手がかりを求め、リクトが向かったのは、都市の地下深くに存在する「沈黙の図書館」だった。そこは、現代では使われなくなった古語や、危険思想と見なされて封印された言葉の言晶が眠る、禁断の書庫だ。埃と時間の匂いが混じり合った空気が、彼の肺を満たした。
図書館の入り口で彼を迎えたのは、トキと名乗る老婆だった。深く刻まれた皺の一つ一つが、一つの物語を秘めているような顔をしている。彼女はここの番人だという。
「言葉を探しに来たのかい、若いの」
トキのしゃがれた声が、静寂に響いた。
「ただの言葉じゃない。忘れられた言葉を」
リクトの真剣な眼差しに、トキは興味深そうに目を細めた。
「言葉はね、与え、創造し、勇気づけるだけじゃない。何かを終わらせるためにも、存在するんだよ」
謎めいた言葉を残し、トキは「好きにしな」とだけ言って、奥の闇に消えていった。
リクトは一人、広大な書庫を進んだ。棚には、今では誰も発音できない古代の言晶が、弱々しい光を放っている。壁には、かつて革命を扇動した「闘争」の言晶が、その鋭い輝きを鎖で封じられていた。ここは、言葉の墓場だ。
彼は、両親の事故に関する記録を探した。当時の社会では、人々の心を乱すネガティブな言葉は極力使わないようにという風潮が強かった。記録は淡々と事実を述べるだけで、両親が最後に何を思ったか、何を言おうとしたかについては一切触れられていなかった。
手詰まりかと諦めかけたその時、彼は図書館の最下層で奇妙な空間を発見した。そこには、棚も台座もなかった。ただ、広大な空間に、無数の霧のような光が漂っているだけだった。それらは、形を結ぶことなく、生まれかけては消えていく、不完全な言晶の群れだった。
リクトがそっと手を伸ばすと、一つの光の霧が彼の指先に触れた。瞬間、彼の脳裏に誰かの記憶が流れ込む。
『ごめん……。本当は、あの時、そう言うべきだった』
別の霧に触れる。
『好きだ。どうして、この一言が言えなかったんだろう』
それは、人々が心に秘めたまま、遂に口に出すことのできなかった「後悔」や「未練」の言葉たちだった。言霊になれなかった想いの残骸が、この場所に吹き溜まっていたのだ。リクトは胸が締め付けられるのを感じた。世界は、美しい言葉だけで成り立っているわけではない。言えなかった言葉、言わなかった言葉の重みが、この沈黙の図書館の礎となっているのだ。
彼はふと、自分の両親もまた、何かを言えないまま逝ってしまったのではないか、という思いに駆られた。だとしたら、彼らが遺したかった言葉は、一体……。リクトは、後悔の霧が渦巻く空間の、さらに奥へと足を踏み入れた。そこから、か細く、しかし確かな引力を感じたからだ。
第三章 終わりの始まり
空間の最深部に、それはあった。
巨大な球体だった。何層にも重なった水晶のようで、かつては計り知れないほどの光を放っていたであろうことが窺える。だが今、その輝きはほとんど失われ、まるで眠っているかのように静まり返っていた。壁の銘板には、掠れた文字で『原初の言晶』と刻まれている。この世界の、すべての言葉の始まりとなったとされる伝説の言晶だ。
リクトは吸い寄せられるように、その冷たい表面に手を触れた。
その瞬間、世界が反転した。
閃光と共に、彼の脳を焼くような奔流が流れ込む。それは、彼自身が固く蓋をしていた、十数年前の記憶だった。
白い病室。機械の無機質な電子音。痩せた父と、微笑む母の顔。二人は、不治の病に侵されていた。当時の医療技術では、手の施しようのない未知の病。リクトはまだ幼く、事の深刻さを理解していなかった。ただ、大好きだった両親が日に日に弱っていくのを、不安な目で見つめることしかできなかった。
そして、最期の日。父が、か細い声で何かを言おうとした。母も、涙を堪えながら唇を動かした。リクトはずっと、その言葉が「愛してる」か「元気で」のような、彼を励ます言葉だと思い込もうとしてきた。
だが、流れ込んできた真実は違った。
『リクト……さようなら』
両親が言おうとしていたのは、その一言だったのだ。別れの言葉。終わりの言葉。
しかし、当時の社会は「終わり」を極端に恐れていた。永遠の繁栄と継続こそが善とされ、「死」「別れ」「終わり」を肯定する言葉は、世界の活力を削ぐ禁句として扱われていた。言霊師でさえ、その言葉を紡ぐことを躊躇うほどに。両親は、最愛の息子に別れを告げることすら許されず、ただ微笑んで、その手を握りしめることしかできなかったのだ。
「ああ……ああ……!」
リクトは膝から崩れ落ちた。彼がずっと探していた「失われた言葉」。それは、壮大な伝説の言葉などではなかった。誰もが知っているはずなのに、誰もが目を背けていた、ごく当たり前の、しかし決定的に重要な言葉だったのだ。
世界の「言葉の枯渇」の真の原因が、雷に打たれたように理解できた。
始まりがあるものには、必ず終わりがある。出会いがあれば、別れがある。生があれば、死がある。その自然な循環を、人々は恐れるあまり断ち切ってしまったのだ。「終わり」を認めない世界では、新しい「始まり」も生まれない。感謝も愛情も、いつか終わるかもしれないという切なさがあるからこそ、その一瞬が強く輝くのではないか。永遠を求めるあまり、人々は言葉の本当の力を、その輝きの源泉を、自ら枯渇させていたのだ。
祖母の「ありがとう」にヒビが入ったのも、リクトが祖母の死という「終わり」を本当の意味で受け入れず、言晶という形あるものに執着し続けていたからかもしれない。
彼は嗚咽した。両親に言えなかった言葉、両親から言ってもらえなかった言葉。言えなかった無念と、言ってもらえなかった寂しさが、今になって彼の全身を打ちのめした。彼は過去に囚われていたのではない。終わらせるべき過去を、終わらせることができずに、ただ立ち尽くしていただけだったのだ。
第四章 さようなら、そして、こんにちは
涙が枯れるまで泣き続けた後、リクトはゆっくりと立ち上がった。彼の表情には、もう迷いはなかった。彼は『原初の言晶』に向き直り、震える唇で、十数年間、心の奥底に封じ込めていた言葉を紡いだ。
「お父さん、お母さん……さようなら」
それは、諦めの言葉ではなかった。絶縁の言葉でもない。愛する二人との思い出を胸に、未来へ歩き出すための、決意の言葉だった。
「そして……ありがとう」
彼の両方の手のひらに、ぽつ、ぽつと、小さな光が灯った。一つは、澄み切った冬の空のような、静かで穏やかな青色の光を放つ言晶。もう一つは、これまで彼が育ててきたどんな感謝の言晶よりも、温かく力強い、黄金色の言晶だった。
「さようなら」と「ありがとう」。別れと感謝。終わりと始まり。二つの言葉は、対極にあるようで、実は分かちがたく結びついていたのだ。
リクトは、生まれたばかりの二つの言晶を、そっと『原初の言晶』に捧げた。
すると、奇跡が起きた。
死んだように沈黙していた巨大な言晶が、脈動を始めた。リクトが捧げた二つの光を核として、中心から柔らかな光の波紋が広がり、失われた輝きがみるみるうちに蘇っていく。やがて、その光は図書館の天井を突き抜け、一条の光の柱となって、地下深くから地上へと向かって伸びていった。
光は、世界中に降り注いだ。
都市の広場で、恋人との別れを悲しんでいた女性が、空を見上げて涙を流した。それは、ただ悲しいだけの涙ではなかった。共に過ごした時間への感謝が、心から込み上げてきたのだ。
病院のベッドで、人生の最期を迎えようとしていた老人が、窓から差し込む光に目を細め、そばにいる家族に穏やかに告げた。「みんな、ありがとう。もう行くよ」。彼の最後の言葉は、美しい光の言晶となって、家族の手に遺された。
ヒビが入っていた世界中の言晶が、その輝きを取り戻し、以前にも増して力強く光り始めた。「終わり」を受け入れた世界で、言葉の循環が、再び正常に流れ始めたのだ。
リクトは、光に満たされた図書館で、静かにその光景を感じていた。彼の後ろに、いつの間にかトキが立っていた。
「これで、分かったかい。終わりは、始まりの別名だということを」
リクトは、ただ静かに頷いた。彼はもう、過去の曖昧な記憶に苛まれることはないだろう。両親との別れを、喪失としてではなく、自分を形作るための、愛おしい記憶として受け入れることができたからだ。彼は、本当の意味で「言霊の庭師」として成長したのだ。
数日後、リクトは自分の庭園に戻っていた。砕けかけていた祖母の言晶は、その亀裂が嘘のように消え、以前よりも深く、優しい琥珀色に輝いている。
彼は、新しく生まれた小さな言晶の芽に、そっと指で触れた。それは、庭園を訪れた子供が、転んだ友達にかけた「大丈夫?」という言葉の結晶だった。
風がドームを吹き抜け、リクトの耳元で囁いた。
『始まりは、いつだって終わりのそばにある』
彼は空を見上げ、穏やかに微笑んだ。この世界は、喜びや希望だけでできているわけではない。悲しみも、切なさも、そして避けられない別れもある。だが、だからこそ、今この瞬間に交わされる言葉が、どうしようもなく愛おしく、尊く輝くのだ。
リクトは、その輝きを、これからも育て続けるだろう。