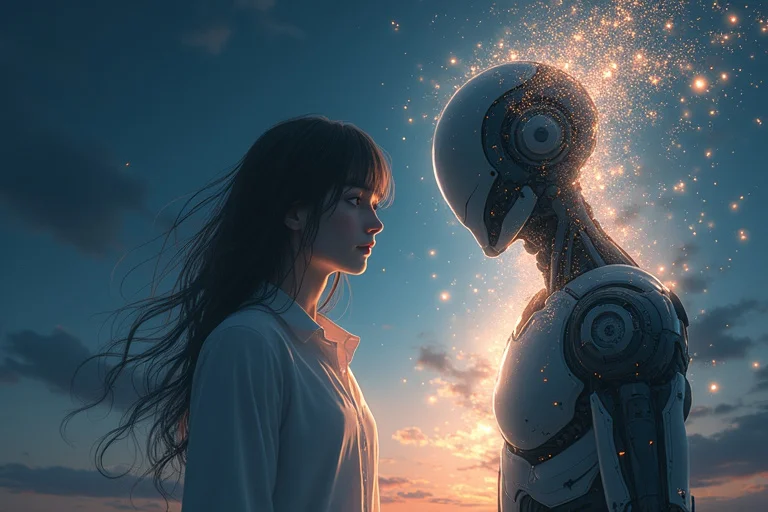第一章 錆びついた記憶の破片
リクの部屋は、時間の澱が溜まった海底のようだった。壁には陽に焼けて色褪せたポスター。棚には、今では誰も使わない紙の本や、フィルム式の古いカメラが埃をかぶって並んでいる。世間が記憶をクラウドサーバー『メモリア・バンク』に預け、忘却という名の呪いから解放されて久しいこの時代に、彼の部屋だけが意固地なまでに過去を抱え込んでいた。
リクはメモリアを使わない。脳に埋め込まれたナノマシン・インターフェースを起動すれば、昨日の夕食の味から十年前の雨の匂いまで、完璧な精度で再生できるというのに。彼は、曖昧で、不確かで、時に自分を裏切る生身の記憶こそが、人間である証だと信じていた。あるいは、そう信じようと足掻いていた。
すべては、十年前に死んだ姉、ミサキとの約束のせいだった。
『絶対に、私のことを忘れないでね』
遊園地の観覧車が頂点に達した瞬間、夕陽に照らされた姉の横顔は、リクの脳裏に焼き付いて離れない。その数週間後、彼女は唐突な事故でこの世を去った。以来、リクは忘れることを何よりも恐れた。姉の声を、仕草を、香りを、その不完全な記憶の中で必死に反芻し続けることが、彼の贖罪であり、存在意義だった。
そんなある日の午後、郵便受けに滑り込んできた小さなパッケージが、彼の停滞した時間に波紋を投げかけた。差出人の名はない。武骨な緩衝材に包まれていたのは、指先ほどの大きさの旧式データチップだった。リクの古いコンソールに接続すると、画面にノイズが走った。再生されたのは、断片的な映像だった。
風に揺れる名も知らぬ野草。ひび割れたアスファルト。遠くで聞こえるサイレンの微かな残響。そして、一瞬だけ映り込んだ、星屑を散りばめたような夜空の映像。
見覚えのない風景。しかし、胸の奥がざわりと冷たくなるような、奇妙な既視感があった。解析ソフトにかけると、撮影場所の座標が浮かび上がる。そこは、十年前、姉が命を落とした高速道路のすぐ近くだった。心臓が嫌な音を立てて脈打つ。これは一体、誰が、何のために? 姉の死は、単なる事故ではなかったというのか。錆びついていたはずの過去が、不意に生々しい手触りをもってリクに迫ってきた。
第二章 忘却の街
「また古物漁りか? リク」
サイバーラウンジの薄闇の中、友人のカイがヘッドマウントディスプレイをずらしながら言った。壁一面を埋め尽くすホログラム広告が、彼の顔に青や赤の光をまだらに落としている。カイは、デジタル世界の裏路地を知り尽くした腕利きの情報屋だ。
リクは無言でデータチップを差し出した。
「これを調べてほしい。暗号化されてるみたいで、俺の機材じゃここまでが限界だ」
カイはチップを受け取ると、手慣れた様子で解析を始めた。指先から伸びる光の糸が、仮想キーボードを叩いていく。
「古いプロトコルだな。意図的に痕跡を消してある。……これは、ただのデータじゃない。誰かの『記憶』の断片だ。それも、メモリア・バンクを介さずに、直接記録されたものらしい」
メモリア・バンクを介さない記憶の記録。それは、この社会では異端の行為だった。人々は、辛い記憶や不都合な事実をバンクから削除することで、精神の平穏を保っている。リクの両親も、ミサキの事故の記憶があまりに辛いからと、その一部を専門のカウンセラーに依頼して削除していた。彼らは今、穏やかに笑い、姉のいなかった人生を生きているかのように見える。その姿が、リクには時折、ひどく恐ろしく感じられた。
「リク、お前がメモリアを使わないのは勝手だが、過去を掘り返すのは感心しないぜ」
カイは忠告したが、リクの決意は揺らがなかった。これは、姉が遺した声なきメッセージかもしれない。そう思うと、止まることはできなかった。
数日後、カイからの連絡で、リクは街の再開発から取り残された旧市街の一角に足を運んだ。そこには、「忘却の権利」を掲げる人々の小さなコミュニティがあった。彼らは、政府が管理するメモリア・システムに異を唱え、人間が本来持っていた「忘れる」という営みを取り戻そうと活動していた。リーダーだという初老の女性、アヤメは、リクの持ってきたデータを見て静かに言った。
「これは『魂の欠片』ね。メモリアに魂を売り渡すことを拒んだ者が、最後に遺す記録。私たちはそう呼んでいるわ」
彼女の言葉は、リクの胸に深く突き刺さった。忘れることは、本当に悪なのだろうか。記憶に縛られ、未来ではなく過去を生きている自分は、本当に正しいのだろうか。初めて、彼の信念が微かに揺らいだ。カイとアヤメたちの協力で、データの復元は最終段階へと進んでいく。リクは、真実を知るのが怖いような、しかし知らずにはいられないような、引き裂かれる思いでその時を待った。
第三章 姉が遺した星空
解析の完了を知らせる電子音が、静寂な部屋に響き渡った。カイが頷き、リクは息を呑んでコンソールの前に座る。画面に、修復された映像が流れ始めた。
そこには、リクの知らない姉、ミサキの姿があった。病院の一室だろうか、窓の外には見慣れない街並みが広がっている。彼女の顔は少し痩せていたが、その瞳は驚くほど澄んでいた。彼女はカメラに向かって、静かに語りかける。それは、リクの記憶の中にいる快活な姉とは違う、穏やかで、どこか達観したような声だった。
『リクへ。この映像を見ているということは、あなたはまだ、私のことを覚えていてくれているのね。ごめんね、そして、ありがとう』
姉は、不治の神経性疾患に侵されていたことを告白した。その病は、徐々に記憶を蝕み、やがては人格そのものを崩壊させていくのだという。
『私は、私が私でなくなるのが怖かった。楽しい思い出も、リクと交わした約束も、全部忘れてしまうのが。パパやママが悲しむ顔も、あなたの辛そうな顔も、もう見たくなかった』
彼女の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
『だから、決めたの。一番綺麗な記憶のまま、消えようって。私が一番、私らしくいられるうちに、この世界からお別れしようって』
姉が選んだのは、「メモリア・ブレイク」という非合法な手段だった。自らのメモリア・データを物理的に破壊し、同時にバンクに登録された関連情報にも強力なウイルスを仕掛けることで、他者の記憶からも自分の存在を消去する。それは、デジタル社会における、完全な自殺だった。事故に見せかけたのは、家族に罪悪感を抱かせないための、彼女なりの最後の優しさだった。
『リク、遊園地の観覧車で言ったこと、覚えてる? 「私のこと忘れないで」って。あれは、私の我儘。本当はね、あなたに過去を背負ってほしくなんてなかった』
映像が切り替わる。それは、リクに送られてきたデータチップの風景だった。風にそよぐ草花、ひび割れたアスファルト。
『ここは、私が最後に見る場所。ねえ、綺麗でしょう? 何もないけど、空が広いの。星が、すごくよく見える』
カメラがゆっくりと夜空を映し出す。そこには、リクが今まで見たこともないような、満天の星が広がっていた。それは、街の光に邪魔されない場所でしか見ることのできない、本物の星空だった。
『リク、忘れていいんだよ。ううん、忘れて。忘れることは、前に進むための力だから。私のことなんか忘れて、あなたの時間を生きて。あなたの記憶には、これからもっと素敵なことでいっぱいになるべきなんだから』
最後に、姉はふわりと笑った。リクが一番好きだった、太陽のような笑顔で。
『さよなら、私の可愛い弟。夜空の星が、あなたを守ってくれますように』
映像が途切れ、部屋は再び静寂に包まれた。リクの頬を、熱いものが伝っていく。姉との約束は、彼女を守るためのものではなかった。彼女を忘れたくないという自分のエゴが作り出した、過去に自分を縛り付けるための呪縛だったのだ。姉は、忘れてほしくなかったんじゃない。忘れられてしまう前に、自ら消えることを選んだのだ。その孤独と絶望、そして深い愛情に、リクは声を上げて泣いた。
第四章 余白に描く未来
どれくらい泣き続けたのか、リクには分からなかった。涙が枯れ果てた頃、窓の外は白み始めていた。十年という歳月をかけて固く閉ざされていた心の扉が、姉の最後の言葉によって、ゆっくりと開かれていくのを感じた。
彼は立ち上がり、棚の奥から、一度も使ったことのない自分用のメモリア・デバイスを取り出した。冷たい金属の感触が、手のひらにずしりと重い。彼はそれを起動し、自らの脳内インターフェースと接続した。
検索窓に、ただ一言、『ミサキ』と打ち込む。
途端に、膨大な記憶の奔流が流れ込んできた。忘れていたはずの些細な思い出。一緒に食べたアイスの味、些細なことで喧嘩した日の気まずさ、病室で無理に微笑んでいた姉の顔。不完全だと思っていた自分の記憶が、メモリアのデータと結びつき、鮮やかな色彩を取り戻していく。
そして、最後にあの観覧車での記憶が再生された。夕陽に染まる姉の横顔。『絶対に、私のことを忘れないでね』。その言葉の奥に隠された、悲痛なほどの祈りが、今なら痛いほど分かる。
リクは、メモリアのメニューから『データ削除』の項目を選んだ。指が、震えた。本当に、消してしまうのか?
だが、彼は実行ボタンを押さなかった。代わりに、彼はそっと、デバイスの電源を落とした。
忘却は、削除ではない。
姉が教えてくれたのは、そういうことだ。大切な記憶を無理に消し去る必要はない。ただ、その記憶に縛られるのをやめる。心の奥にある宝箱にそっとしまい、鍵をかける。そして、前を向く。そうすれば、心には新しい記憶を刻むための「余白」が生まれるのだ。
リクは窓を開けた。夜明け前の冷たい空気が、部屋の停滞した空気を洗い流していく。東の空が、優しい光で白んでいく。これまで灰色にしか見えなかった世界が、少しだけ色鮮やかに感じられた。
いつか、姉が最後に見たあの場所へ行ってみよう。彼女が見上げた、あの満天の星を、この目で見に行こう。
それは、過去への訣別ではなかった。姉の想いを受け継ぎ、未来へと歩き出すための、新しい約束だった。リクの心に生まれた静かな余白に、これからどんな物語が描かれていくのだろう。彼は、昇り始めた太陽の光を浴びながら、静かに微笑んだ。