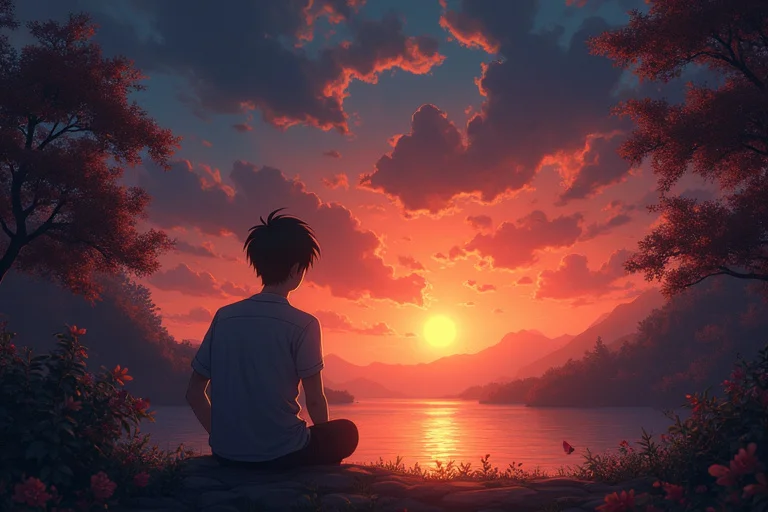第一章 色褪せた約束
神保町の古書店街の片隅に佇む『時雨堂』は、僕、永瀬奏(ながせ かなで)の城であり、同時に鳥籠でもあった。亡き祖父から受け継いだその店は、古い紙とインクの匂いが濃密に満ち、壁という壁が時間という名の埃を被った背表紙で埋め尽くされている。僕はここで、現実の騒がしさから逃れるように、物語の残骸と共に静かに息をしていた。
その日も、夕暮れの橙色の光が埃をきらきらと舞わせる中、僕はカウンターの奥で黙々と本の修繕をしていた。カウベルの乾いた音が鳴り、古びた扉が開く。入ってきたのは、背を丸めた小柄な老婆だった。上等だが着古された菫色の和服をまとい、その顔には深い皺が、まるで地図のように刻まれている。
「いらっしゃいませ」
僕のか細い声に、老婆はゆっくりと顔を上げた。その瞳は、曇りがかった玻璃のようで、どこか遠くを見ている。彼女はゆっくりとカウンターに近づくと、風呂敷に包まれた一冊の本を、そっと置いた。
「これを……預かっていただけないでしょうか」
掠れているが、芯のある声だった。差し出されたのは、革装の古びた本。タイトルはない。見覚えのある装丁に、僕は息を呑んだ。それは、小説家になる夢を抱きながらも、一冊も世に出すことのなかった祖父が、手製で仕上げた未発表の原稿だった。なぜ、見ず知らずの老婆がこれを。
「これは、祖父の……」
「存じております」
老婆は静かに頷いた。「そして、これをいつか、"本当の持ち主"に渡していただきたいのです」
本当の持ち主? 祖父の本の持ち主は、祖父自身か、あるいは相続した僕ではないのか。僕が問い返す前に、老婆は「では、お願いします」と深く頭を下げ、来た時と同じように静かに店を出ていった。
残されたのは、謎の言葉と、一冊の本。僕は恐る恐るそのページを繰った。インクで綴られた流麗な文字は、紛れもなく祖父のものだ。物語は、ある時計職人と、彼が愛した女性の悲恋を描いていた。そして、物語の中盤に、一枚の紙片が挟まっていた。そこには、祖父の筆跡で、こう書かれていた。
『最初の鐘は、記憶の味と共に。始まりの場所で、君を待つ』
意味不明な一文。しかしその瞬間、僕の退屈な日常のページは、音を立てて乱暴に捲られた。祖父が遺した、たった一つの物語。その奥に隠された謎を解き明かさなければならない。そんな強い衝動が、鳥籠の中にいた僕の心を、初めて外へと突き動かしたのだった。
第二章 インクの道標
『最初の鐘』『記憶の味』。その言葉は数日間、僕の頭の中で反響し続けた。祖父が遺した唯一の手がかり。僕は店の隅に積まれた祖父の遺品を、何かに憑かれたように漁り始めた。日記、手紙の束、古い写真。その中に、一枚のレシートを見つけた。日付は三十年以上前。店の名前は『喫茶 鐘楼』。
これだ。僕は錆びついた心の蝶番を軋ませながら、コートを羽織って店を出た。
『喫茶 鐘楼』は、時雨堂からほど近い路地裏で、今もひっそりと営業していた。店内に足を踏み入れると、焙煎された珈琲豆の香ばしい匂いと、微かな煙草の香りが僕を迎える。壁には古びた振り子時計がかかり、重々しい音で時を刻んでいた。最初の鐘、とはこの時計のことか。
カウンターに座る白髪のマスターに、祖父の写真を見せ、事情を話した。マスターは目を細め、懐かしそうに呟いた。
「ああ、永瀬先生。よくいらっしゃってましたよ。いつも窓際のあの席で、難しい顔をして何かを書いておられた」
マスターは「先生はいつも、うちのブレンドを『記憶の味だ』と言って飲んでいましたな」と続けた。記憶の味。謎が一つ解けた。僕は祖父と同じ席に座り、その珈琲を注文した。深い苦味と、後から追いかけてくる柔らかな酸味。この味を、祖父は何を想いながら味わっていたのだろう。
珈琲を飲み干したカップの底に、何かが見えた。ソーサーをずらすと、カップの裏に小さな紙が貼り付けられていた。店のロゴが入ったコースターの切れ端だ。そこには、次の暗号が記されていた。
『二つ目の影は、白鳥の眠る水面に』
マスターに尋ねると、彼は少し考えた後、「ああ、近くの公園の池のことじゃないかな。昔はよく、先生が女性と二人でボートに乗っているのを見かけましたよ」と教えてくれた。
公園の池は、夕暮れの光を浴びて鏡のように空を映していた。白鳥の形をしたボートが数隻、岸に繋がれている。僕は池のほとりを歩き、一つのベンチに目が留まった。座面の下に、小さなブリキの箱が隠されるように置かれていたのだ。
箱の中には、古びた万年筆と、もう一枚のメモが入っていた。
『最後の言葉は、星降る丘の上で。君がくれた光と共に』
星降る丘。祖父の日記を思い出す。そこには、若い頃に恋人と訪れたという天文台の記述があった。彼女から贈られたという星座早見盤の話も。君がくれた光、とはそのことだろうか。
祖父の足跡を辿るうちに、僕が知っていた物静かな祖父とは違う、情熱的で、誰かを深く愛した一人の男性の姿が浮かび上がってくる。それは、本の中に閉じこもっていた僕にとって、眩しすぎる光景だった。
第三章 偽りの最終章
最後のメモが示す天文台は、都心から電車を乗り継いだ先の、小高い丘の上にあった。古びたドーム型の建物は、まるで巨大なきのこのようだ。僕は錆びた扉を開け、螺旋階段を上った。
観測室には、巨大な天体望遠鏡が夜空を待っていた。そして、その傍らに、あの老婆が静かに立っていた。菫色の和服が、差し込む月光に淡く照らされている。
「…お待ちしておりました、奏さん」
老婆――千代(ちよ)さんは、僕の名前を知っていた。彼女は僕を真っ直ぐに見つめ、ゆっくりと語り始めた。彼女こそが、祖父が愛した女性だったのだ。
「あの方の物語は、読み解けましたか?」
「はい。でも、分かりません。なぜ、こんな回りくどいことを…」
僕の問いに、千代さんは悲しげに微笑んだ。「あの物語は、フィクションではありません。あれは、あの方が私を守るために作り上げた、偽りの供述書なのです」
彼女の言葉に、僕は凍りついた。
「三十数年前、私とあの方は、この丘で星を見ていました。その帰り道、車の運転を誤り、人を…轢いてしまったのです」。千代さんの声は震えていた。「運転していたのは、私でした。しかし、あの方は警察に、自分が運転していたと嘘をついた。作家になる夢も、何もかも捨てて、私の罪をすべて背負ってくれたのです」
祖父が、人殺し? 信じられなかった。だが、千代さんの瞳は、揺るぎない真実を語っていた。
「あの方は、あなたにだけは、いつか真実を伝えたかった。でも、自分の口からは言えなかった。だから、物語に託したのです。あなたなら、この謎を解き明かし、本当の意味を理解してくれると信じていました」
祖父の小説。それは悲恋の物語ではなかった。時計職人は、祖父自身。彼が愛した女性は、千代さん。物語の結末で、時計職人は愛する人を庇って罪を背負い、姿を消す。それは、現実に起こったことの、比喩的な記録だった。
「本当の持ち主とは、僕のことだったんですね」
「いいえ」と千代さんは首を振った。「あの物語の本当の持ち主は、あなたと、そして未来のあなたが出会う誰かです。あの方は、過去に縛られていた私と、本の中に閉じこもっていたあなたを、解き放ちたかった。だから、私にこの役目を託したのです」
彼女は、自分の命がもう長くないことを告げた。最後に、祖父の想いを僕に届けることが、彼女の最後の願いだった。
「あの本は、あの方からあなたへの、最後のラブレターなのですよ」
その言葉は、僕の心の最も深い場所に突き刺さった。祖父は、僕が生まれる前から、僕の未来を案じ、愛してくれていた。本のページに滲むインクは、祖父の涙だったのかもしれない。僕の頬を、熱いものが伝った。
第四章 夜明けのプロローグ
千代さんの話は、僕が知る世界の全てを塗り替えた。祖父は罪人などではなかった。彼は、愛する人を守るために、自らの人生を犠牲にした、誰よりも気高い騎士だったのだ。あの未発表の小説は、彼の罪の告白ではなく、彼の愛の証明だった。
僕がずっと感じていた、人との関わりを避ける心。それは、祖父が背負った孤独と罪悪感を、無意識のうちに受け継いでいたからなのかもしれない。祖父は、僕に同じ道を歩んでほしくなかった。だから、謎解きという形で、僕を外の世界へと導いたのだ。
千代さんと別れ、丘を下りる頃には、東の空が白み始めていた。夜明けの冷たい空気が、涙で濡れた頬に心地よかった。
時雨堂に戻った僕は、カウンターに祖父の小説を置いた。もう、それは単なる古書ではない。祖父の魂そのものだ。僕は、窓の外を眺めた。朝日が神保町の街並みを照らし始め、人々が動き出す気配がする。これまで僕が目を背けてきた、現実の世界だ。
祖父は、僕に一つの物語を遺してくれた。それは、過去の真実を明らかにするミステリーであり、未来へ進むための道標だった。
僕は、店の扉に掛けられた『準備中』の札を、そっと裏返して『営業中』にした。カウベルが、夜明けを告げる鐘のように軽やかに鳴った。
もう、僕は鳥籠の中の鳥ではない。祖父が遺した物語の最終章は、僕がこれから生きていくこの世界で、僕自身が紡いでいくのだ。それはきっと、悲劇ではない。祖父の愛を受け取った僕が始める、希望に満ちた、新しい物語のプロローグになるはずだ。
カウンターに差し込む朝陽の中で、僕は静かに微笑んだ。ありがとう、おじいちゃん。あなたのレクイエムは、確かに僕の心に届いた。