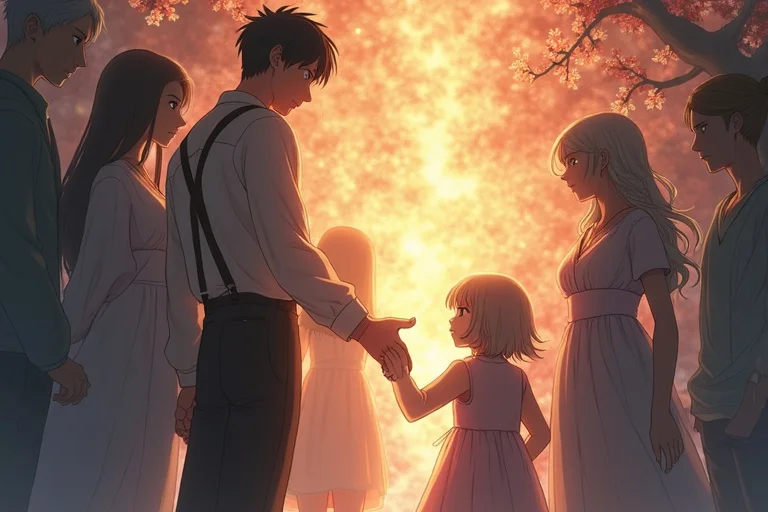第一章 錆びついた記憶の断片
東京のコンクリートジャングルで、僕は時間を切り売りして生きていた。柏木湊、二十八歳。グラフィックデザイナーという聞こえの良い肩書きも、連日の徹夜と修正依頼の前では色褪せる。実家とはもう五年も疎遠だった。父とも母とも、そして特に祖父とは、大学進学を機に上京して以来、まともに話した記憶がない。そんな僕のスマートフォンの画面に、母からの短いメッセージが表示されたのは、締め切りに追われる火曜日の深夜だった。「おじいちゃんが、亡くなりました」という、句読点だけの感情が添えられた文面。不思議と涙は出なかった。僕にとって祖父は、錆びついたアルバムの中の、気難しそうな顔をした老人でしかなかったからだ。
重い身体を引きずるようにして、僕は数年ぶりに故郷の土を踏んだ。潮の香りが混じる懐かしい風が、都会の排気ガスに慣れた肺をぎこちなく満たす。黒い礼服に身を包んだ親戚たちの囁き声と、鼻をつく線香の匂いが充満する座敷で、僕は所在なく壁に寄りかかっていた。遺影の中の祖父は、やはり僕の記憶にある通りの、眉間に深い皺を刻んだ厳しい顔をしていた。
その、異変が起きたのは、読経が終わり、静寂が部屋を支配した瞬間だった。ふと、祖父の遺影に目をやった僕の視界が、ぐにゃりと歪んだ。耳の奥でキーンという金属音が鳴り響き、線香の香りが一瞬にして硝煙と土埃の匂いに変わる。目の前の畳敷きの座敷が、赤黒い土くれと瓦礫の山へと変貌した。空は不気味な橙色に染まり、遠くで建物の燃える音がパチパチと聞こえる。見知らぬ軍服を着た男が、僕のすぐそばで血を流して倒れていた。「タカシ……」と掠れた声が聞こえた。それは僕の声ではなかった。低く、絶望に打ちひしがれた、若い男の声。僕の右手は、硬く冷たい何かを握りしめていた。小石ほどの大きさの、ざらついたお守りだった。
「湊?どうした、顔が真っ青だぞ」
父の心配そうな声で、僕は現実世界に引き戻された。目の前には再び見慣れた座敷が広がり、親戚たちのひそひそ話が耳に戻ってくる。しかし、先ほどの光景の生々しさは、網膜に焼き付いて消えなかった。汗でじっとりと濡れた右の手のひらを見つめる。もちろん、そこにお守りなどなかった。あれは幻覚だったのか。だが、あの土の匂いも、友の死を嘆く悲痛な感情も、まるで自分が体験したかのようにリアルだった。僕の中で、何かが静かに軋み始めた。
第二章 知らない祖父の肖像
通夜の夜から、奇妙な「追体験」は僕を断続的に襲うようになった。それは決まって、祖父の遺品に触れたり、祖父の話題が出たりした時だった。古い万年筆を手に取れば、インクの匂いと共に、白い原稿用紙に向かう若い男の真剣な横顔が見える。彼は絵描きになるのが夢だったらしい。僕が知っている、大工一筋で無口な祖父とは似ても似つかない姿だった。
混乱する僕を見かねてか、父が重い口を開いた。「うちの家系には、時々いるんだ。先祖の記憶の断片を、夢のように見てしまう人間が」父はそれを「記憶の継承」と呼んだ。科学では説明できない、血に刻まれた呪いか、あるいは祝福のようなものなのだと。父自身も、自分の祖父、つまり僕の曾祖父がシベリアの凍てつく大地を歩く光景を、子供の頃に一度だけ見たことがあるという。
「お前が見ているのは、親父の記憶だ。特に、感情が強く揺さぶられた瞬間の記憶が、遺伝子に悪戯書きみたいに残っちまうらしい」
父の話は、にわかには信じがたいものだった。だが、あの鮮明すぎる感覚を否定することもできない。僕はまるで、パズルのピースを拾い集めるように、祖父の人生を追体験していった。戦争で親友のタカシを失った絶望。絵描きの夢を諦め、家族を養うために大工になった日の、金槌の冷たい感触。そして何より僕を驚かせたのは、祖父に深く愛した女性がいたという記憶だった。
それは、夏祭りの夜の光景だった。浴衣姿の若い祖父が、綿菓子を手に、恥ずかしそうに笑う女性を見つめている。彼女の髪には、小さな桔梗の髪飾りが揺れていた。その笑顔は、夜店の灯りに照らされて、僕の胸が締め付けられるほどに輝いていた。祖母ではない、僕の知らない女性。祖父は彼女を「小夜子」と呼んでいた。厳格で、笑った顔などほとんど見たことのない祖父が、あんなにも優しい眼差しを誰かに向けていたという事実が、僕の胸をざわつかせた。僕が知っている祖父は、彼の人生のほんの一部分でしかなかったのだ。知らない祖父の肖像が、僕の中で少しずつ形作られていく。それは、僕が抱いていた「気難しい老人」という印象とは全く違う、情熱と優しさを秘めた一人の青年の姿だった。
第三章 スケッチブックの告白
祖父の遺品を整理していた僕は、桐の箪笥の奥深くから、一冊の古いスケッチブックを見つけ出した。表紙は色褪せ、角は擦り切れている。僕はごくりと唾を飲み込み、そのページをゆっくりとめくった。そこには、息を呑むほど美しい鉛筆のデッサンが、何枚も、何枚も描かれていた。風景画、静物画、そして、一人の女性の肖像画。
そこに描かれていたのは、記憶の中で見た、あの「小夜子」さんだった。桔梗の髪飾りをつけてはにかむ姿。縁側で本を読む横顔。そのどれもが、愛情に満ちた繊細なタッチで描かれている。僕はページをめくる手を止められなかった。祖父の秘められた想いが、紙の上から溢れ出してくるようだった。
そして、最後のページを開いた瞬間、僕は呼吸を忘れた。そこに描かれていたのは、これまでの肖像画とは少し違う、少し年を重ねた彼女の姿。その顔立ちは、驚くほどに、僕の母親に瓜二つだったのだ。混乱する頭で、僕は無意識に母の顔を思い浮かべる。優しい目元、ふっくらとした頬の輪郭。間違いない。
その時、これまでで最も鮮烈な記憶が、僕の脳裏に稲妻のように突き刺さった。
終戦から数年後。ざわめく闇市の雑踏の中を、若い祖父が必死の形相で歩いている。彼は一枚の写真を手に、人に尋ねて回っていた。そして、ついに人垣の向こうに、探し求めていた女性の姿を見つける。小夜子さんだ。しかし、彼女の隣には見知らぬ男が寄り添い、その腕には小さな赤ん坊が抱かれていた。祖父は凍りついたように立ち尽くす。再会の喜びと、全てを失った絶望が、彼の表情の上でせめぎ合っていた。小夜子さんは祖父に気づき、悲しそうに微笑むと、隣の男性に何かを囁き、そっと頭を下げた。それが、二人の永遠の別れだった。
僕はスケッチブックを落としそうになり、慌てて抱きしめた。頭の中で、バラバラだったピースが一つの残酷な絵を完成させる。あの赤ん坊は誰だ?なぜ、小夜子さんは母にそっくりなんだ?まさか……。
嫌な汗が背中を伝う。僕はスケッチブックを手に、父のいる部屋へ駆け込んだ。父は黙って僕からスケッチブックを受け取り、最後のページをじっと見つめた。その横顔は、僕の知らない深い哀しみを湛えていた。
「母さんに、似てるだろう」
父は静かに言った。
「小夜子さんは、俺の本当の母親なんだ」
第四章 血を超えた系譜
父の告白は、僕が築き上げてきた「家族」という概念を根底から破壊した。父の話によれば、小夜子さんは戦後の混乱期に夫を亡くし、赤ん坊だった父を抱えて途方に暮れていた。それを知った祖父は、自分の想いを胸の奥深くに封じ込め、小夜子さんとその息子を守ることを決意したのだという。
「親父は、小夜子さんの遠縁にあたる女性…つまり、俺たちが母さんと呼んでいる人と結婚した。そして、何も知らない赤ん坊だった俺を、自分の息子として引き取った。血の繋がりは、なかった」
厳格だった祖父。無口で、不器用で、愛情表現など一度もしてくれなかった祖父。その全ての行動の裏に、生涯を懸けた巨大な愛と自己犠牲があったことを、僕は初めて知った。祖父は、愛した女性の面影を持つ義理の母を妻とし、その女性が遺した息子を、実の子として育て上げた。その胸の内には、どれほどの葛藤と孤独があったのだろう。僕が煩わしいとさえ感じていた家族の食卓は、祖父が人生を賭して守り抜いた城だったのだ。
「親父は、俺が小夜子さんの息子だと知っていた。だからこそ、人一倍厳しく育てたのかもしれん。半端な人間になるな、と。……不器用な男だったからな」
父の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。
葬儀が終わり、僕は東京へ戻る準備をしていた。あのスケッチブックは、父が仏壇に供えていた。父は僕に「お前が持っていなさい」と言ったが、僕は首を横に振った。それは、祖父がこの家で守り抜いたものの証だから。
駅のホームで電車を待っていると、父が言った。
「湊。血だけが家族を作るんじゃない。親父が俺に注いでくれた時間と愛情が、俺たちを本当の家族にしたんだ。それは、お前にも繋がってる」
電車のドアが閉まる直前、僕は父に向かって、何年かぶりに、心の底から深く頭を下げた。
東京に戻った今も、時折、祖父の記憶の断片が蘇ることがある。だが、もはやそれは僕を混乱させない。トンカチを握るごつごつした手の感触も、夕暮れの縁側でタバコをふかす時の穏やかな吐息も、全てが僕の一部となって、温かく脈打っている。僕は、血の繋がりという単純な事実だけでなく、名前も知らない人々の想いや、誰かを守るために捧げられた巨大な愛情の連なりの、その最先端に立っている。
モニターに向かい、新しいデザインのラフを描き始める。僕の指先から生まれる線は、以前よりも少しだけ、力強く、そして優しくなった気がした。