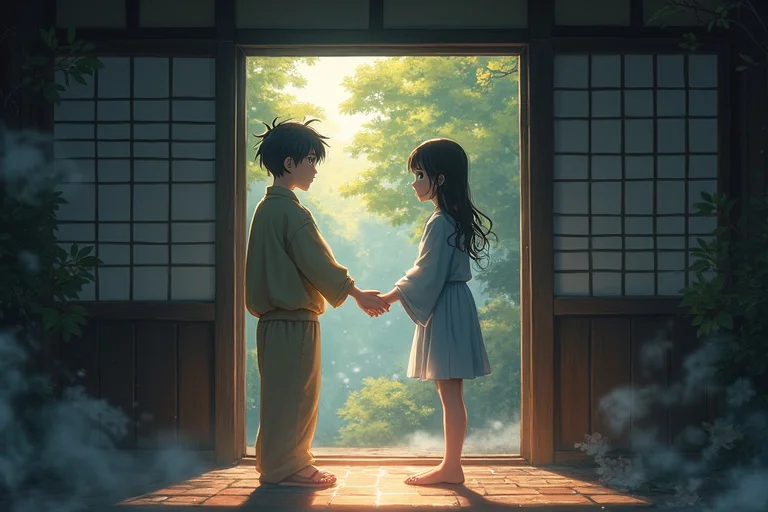第一章 開かれたパンドラ
父が死んで、もう五年になる。
三十歳になった俺、水野亮太は、梅雨入り前の湿った空気の中、実家の書斎で父の遺品を整理していた。母に「あなたももういい歳なんだから、お父さんの本くらい整理してちょうだい」と、半ば押し付けられた役目だった。
書斎は、父の匂いがまだ濃密に残っているようだった。古い紙とインク、微かに混じる煙草の香り。生前、厳格で仕事人間だった父とは、まともに話した記憶がほとんどない。俺が大学に入り家を出てからは、年に数回顔を合わせるだけ。その短い時間でさえ、交わす言葉はいつもぎこちなかった。父にとって俺は、期待に応えられない頼りない息子だっただろうし、俺にとって父は、理解しようのない、分厚い壁のような存在だった。
本棚の奥、父が愛用していた重厚なマホガニーのデスクの引き出しに、それはあった。鍵のかかった、古びた木箱。掌に載るほどの大きさだが、ずしりと重い。母に聞いても心当たりはないと言う。好奇心に負け、工具箱から細いドライバーを持ち出し、稚拙な錠前をこじ開けた。
カチリ、と乾いた音が響く。蓋を開けた瞬間、防虫剤の樟脳の匂いがふわりと鼻をかすめた。中には、クリーム色の封筒が隙間なく詰め込まれている。一番上の封筒の宛名書きを見て、俺は息を呑んだ。
『二十六歳の亮太へ』
それは、間違いなく父の、几帳で少し右肩上がりの癖のある字だった。俺が二十六歳だったのは、四年前。父が亡くなった翌年だ。震える手で封を開けると、万年筆で書かれた文字が目に飛び込んできた。
『亮太、誕生日おめでとう。お前がこれを読んでいる頃、俺はもうこの世にいないだろう。不思議な気分だ。未来のお前に手紙を書いている。二十六歳の誕生日、覚えているか。お前が就職して初めてのボーナスで、安物のウイスキーを一本、照れ臭そうに差し出した日だ。俺は「こんなもの」とぶっきらぼうに言ったが、実はずっと、あの日を待っていた。お前と酒を酌み交わす日を。あの夜、お前が寝た後、一人で書斎で飲んだウイスキーの味は、生涯忘れられないだろう。ありがとう』
脳裏に、忘れかけていた光景がフラッシュバックする。そうだ、確かにそんなことがあった。父の素っ気ない反応に傷つき、やはり俺たちは分かり合えないのだと、勝手に失望したあの日。だが、違ったのか。父は、あのウイスキーを一人で……。
胸の奥が、ぎゅっと締め付けられる。封筒の束をかき分けると、『二十七歳の亮太へ』『二十八歳の亮太へ』…と、未来の俺の年齢が記された手紙が、六十歳分まで、ぎっしりと詰まっていた。
時を超えて届いた父からの手紙。それは、俺の知らない父の姿を映し出す、パンドラの箱だった。俺はゴクリと唾を飲み込み、次の封筒へと手を伸ばした。知ってはいけないのかもしれない。それでも、知らずにはいられなかった。
第二章 インクに滲む過去
それから、奇妙な習慣が始まった。毎年、自分の誕生日が来ると、俺は実家へ向かい、あの木箱から一つだけ封筒を取り出す。そして、父の書斎で、父が座っていた革張りの椅子に身を沈め、手紙を読むのだ。
『二十七歳の亮太へ。仕事に慣れ、少し天狗になっていないか。だが、それも若さだ。俺もそうだった。大きな契約を取って有頂天になり、足元をすくわれたことがある。鼻をへし折られる経験は、早い方がいい。そこから何を学ぶかが、男の価値を決める』
『二十九歳の亮太へ。そろそろ、生涯を共にする相手のことを考える頃か。母さんと出会ったのは、駅前の小さな喫茶店だった。土砂降りの雨の日でな。彼女が忘れた傘を届けたのが始まりだ。ありきたりだろう? でも、人生を変える出会いなんて、案外そんなものだ』
手紙の中の父は、俺が知っている無口な父ではなかった。饒舌に、時にユーモラスに、時に厳しく、人生の先輩として語りかけてくる。俺の知らない父の青春、母との馴れ初め、仕事での失敗談。一枚、また一枚とページをめくるたびに、俺の中で凝り固まっていた父のイメージが、良質なインクが水に溶けるように、ゆっくりと輪郭を変えていった。
父と心の対話をしているような、不思議な感覚だった。生前、あれほど遠かった背中が、今はすぐ隣にあるように感じられる。三十三歳の誕生日、俺は初めて父の墓前に手紙を持っていき、声に出して読んだ。そこには、俺が子供の頃に熱中していた、プラモデルの戦闘機の話が書かれていた。
『あの零戦の模型、翼のデカールを貼るのにえらく苦労していたな。お前は癇癪を起こして投げ出しそうになった。俺は「それくらい自分でやれ」と突き放したが、お前が寝静まった後、こっそり書斎に持ち込んで、ピンセットで一枚一枚貼ってやったんだ。翌朝、完成した模型を見て目を丸くしていたお前の顔、今でもはっきりと思い出せる。不器用な父親で、すまなかった』
涙が、墓石にぽたぽたと落ちた。記憶の底に埋もれていた、朝の光に輝く零戦の姿。あの翼の完璧な仕上がりは、父の仕業だったのか。どうして、一言「手伝ってやったぞ」と言ってくれなかったんだ。どうして、こんな不器用な方法でしか、愛情を伝えられないんだ。
嬉しさと、どうしようもない切なさが胸に込み上げる。俺は父について、一体何を知っていたのだろう。この手紙は、父からの愛情の証だ。そう、信じて疑わなかった。三十五歳の誕生日が来るまでは。
第三章 共犯者の告白
三十五歳の誕生日は、よく晴れた日だった。係長への昇進も決まり、公私ともに順風満帆と言えた。いつものように実家へ向かい、書斎で手紙の封を切る。しかし、その手紙の書き出しは、いつもと明らかに違っていた。インクの文字が、どこか切迫しているように見える。
『亮太。三十五歳になったお前に、謝らなければならないことがある。そして、俺の人生最大の過ちを告白しなければならない。お前が、俺と同じ過ちを繰り返さないために』
心臓が嫌な音を立てて跳ねた。背筋を冷たい汗が伝う。
『俺は若い頃、ある罪を犯した。当時勤めていた会社で、上司の命令で、不正な会計処理に加担してしまったんだ。まだ若く、逆らえば自分の将来が断たれるという恐怖に負けた。その不正の責任を、俺のたった一人の親友が、すべて被ることになった。彼は会社を追われ、家族も離散し、その後の人生は苦難に満ちたものになったと聞いている。俺は、友を裏切った。自分の保身のために、他人の人生を犠牲にした卑劣な人間だ』
息が止まった。信じられなかった。俺が尊敬し始めていた父。不器用だが誠実で、愛情深いと思っていた父の姿が、音を立てて砕け散る。手紙を持つ手が、わなわなと震えた。
『俺は、この罪の意識から、生涯逃れることができなかった。お前に厳しく当たったのも、お前が真っ直ぐで強い人間に育ってほしいと願う一方、俺のような卑劣な人間の血が流れていることへの恐怖があったからだ。この手紙は、お前への愛情の証などという綺麗なものじゃない。これは、臆病者の俺が、たった一人で行った懺悔であり、時効のない罪の告白だ。親友の名は、榊(さかき)という。もし、いつかお前が道に迷い、不正の誘惑に駆られることがあったなら、この手紙を、そして榊さんのことを思い出してくれ。それが、俺にできる唯一の償いだ』
読み終えた手紙が、手から滑り落ちた。怒りか、失望か、悲しみか。分からない感情の渦が、俺を飲み込んでいく。裏切られた、と思った。父は英雄なんかじゃなかった。ただの臆病者で、共犯者じゃないか。俺がこれまで抱いてきた温かい感情は、すべて偽りの上に成り立っていたのか。
木箱に残された、未来への手紙の束が、急に呪わしいものに見えた。もう、読みたくない。父の罪から、目を背けたかった。
第四章 未来への返信
一年が経った。三十六歳の誕生日が、重苦しい沈黙とともにやってきた。俺は迷っていた。もう、あの書斎へは行かないと決めたはずだった。だが、足は自然と実家へ向かっていた。父の罪と向き合うことから逃げるのは、結局、父と同じではないか。
革張りの椅子は、ひんやりと冷たかった。深呼吸をして、封を切る。
『これを読んでいるということは、お前は俺を許さず、それでも俺の告白と向き合うことを選んだのだな。ありがとう。それだけで、俺は救われる』
その一行を読んだ瞬間、堰を切ったように涙が溢れた。
『亮太。俺は、お前に完璧な人間になってほしかったわけじゃない。人生は過ちの連続だ。大切なのは、過ちを犯さないことではなく、犯してしまった過ちとどう向き合うかだ。俺は逃げた。だが、お前にはそうなってほしくない。「正しい弱さ」を持ってほしいのだ。自分の過ちを認め、謝罪し、償う勇気。それこそが、本当の強さだと、この歳になってようやく気付いた。榊さんには、ついに謝罪できないままだった。それが俺の限界だ。だがお前は、俺の限界を超えていけ』
手紙は、父の不器用な謝罪であり、俺への祈りだった。完璧な父ではなく、過ちを犯し、悩み、苦しみ続けた一人の人間としての、魂の叫びだった。俺は、父の不完全さごと、父という人間を、ようやく心の底から受け入れることができた。父は、俺の理想の父親ではなかった。だが、唯一無二の、俺の父親だった。
木箱に残された手紙は、まだたくさんある。六十歳まで続く、父との対話。俺は一番奥にあった『六十歳の亮太へ』と書かれた封筒をそっと取り出し、その紙の感触を指先で確かめた。まだ、その封を切る時ではない。
俺はデスクの引き出しから、真新しい便箋と万年筆を取り出した。父が使っていたものだ。そして、インクを吸わせ、静かに文字を綴り始める。
『天国の父さんへ』
それは、時を超えて届いた父への、初めての返信だった。俺は、父が犯した罪のことも、教えてくれた愛情のことも、すべて書き記した。そして最後に、こう締めくくった。
『父さん、俺はあなたの息子で、幸せです。あなたの罪も、弱さも、すべて受け取ります。そして、あなたの限界を超えてみせる。だから、空の上から見ていてください』
書き終えた手紙を、木箱の一番手前に入れる。父が遺した時間と、これから俺が生きる時間。二つの時間が、この小さな箱の中で交差する。父はもういない。けれど、俺たちの対話は、これからも続いていく。その事実は、どうしようもない切なさと、一条の光のような温かさを、俺の胸に灯していた。
書斎の窓から差し込む西日が、埃をきらきらと輝かせている。俺は立ち上がり、未来へ向かって、新しい一歩を踏み出した。