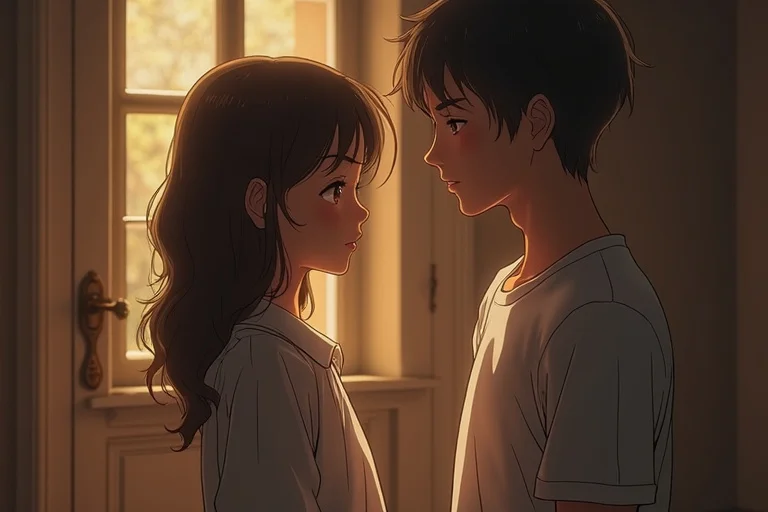第一章 知らない家族の写真
母からの電話は、いつも唐突だ。受話器の向こうで聞こえる声は、乾いた落ち葉が風にこすれるような音を立てていた。
「健太、お父さんが、倒れたの」
その言葉は、俺の鼓膜を通り過ぎ、心臓に冷たい杭を打ち込んだ。三十六年間、ほとんどまともに言葉を交わしたことのない男。俺にとって父とは、家という舞台に鎮座する、感情の読めない石像のような存在だった。
「意識は……?」
「まだ、戻らない」
覚悟はしていた。頑固で、医者嫌いで、酒と煙草を手放さなかった男の末路だ。だが、俺を本当に動揺させたのは、母が続けた言葉だった。
「それとね、健太。お父さんの部屋を片付けていたら……変なものが出てきて」
声が震えている。電話線を通して伝わってくる母の不安に、俺は眉をひそめた。
「変なものって何だよ」
「写真よ。知らない、家族の写真。たくさん……」
週末、俺は十年ぶりに実家の暖簾をくぐった。潮の香りと、古い木材の匂いが混じり合って鼻をつく。病院に詰めている母に代わって、俺は父の部屋に足を踏み入れた。万年床の脇にある桐箪笥。その一番下の引き出しを開けると、菓子箱が一つ、埃をかぶって鎮座していた。
蓋を開けた瞬間、息を呑んだ。
色褪せた写真の束。そこに写っていたのは、見知らぬ若い女と、幼い男の子だった。満開の桜の下で笑う二人。運動会で鉢巻きを締め、緊張した面持ちで駆ける男の子。その隣で、拳を握りしめて応援する女。どの写真にも、温かく、幸せそうな空気が満ちていた。まるで、俺が決して手に入れることのできなかった、理想の家族の縮図のようだ。
父は、どこにいる? 俺は目を皿のようにして写真の隅々まで探した。だが、父らしき姿は見当たらない。それでも、確信があった。これは父の秘密だ。俺たち家族に隠れて、もう一つの家族を持っていたのだ。
ふいに、腹の底から黒いマグマのような怒りがせり上がってきた。あの男は、俺たち家族を捨てて、別の場所で笑っていたのか。俺がどれだけ父親の温もりを求めても、あの分厚い背中が一度も振り返ることがなかった理由が、これだったのか。写真の中の、屈託なく笑う男の子の顔が、俺を嘲笑っているように見えた。俺は菓子箱を乱暴に閉じると、壁に叩きつけたい衝動を必死でこらえた。
第二章 父の日記
写真の束の下から、一冊の古びた大学ノートが見つかった。表紙には何も書かれていない。ページをめくると、そこには、俺の知らない、几帳で丁寧な男の文字が並んでいた。父の、あの無骨で乱暴な字とは似ても似つかない。
『四月八日。春の嵐。満開だった桜が、まるで涙のように散っていく。今日、由美子が無事に拓也を産んだ。三千グラムの、元気な男の子だ。俺の腕の中で、小さな手がか細い指を懸命に握ってくる。この温もりを、俺は一生かけて守り抜こうと誓った』
日記は、写真の家族の物語だった。拓也という男の子の成長、妻である由美子への愛情、ささやかな日常の喜び。その一つ一つが、まるで上質な短編映画のように、生き生きと綴られている。日記の主は、驚くほど饒舌で、愛情深い男だった。公園で拓也と泥だらけになって遊び、由美子の手料理を世界一だと褒めそやす。俺の知る、食卓で新聞を広げたまま一言も発しない父とは、まるで別人だった。
俺は憑かれたように日記を読み進めた。それは、父への憎しみを募らせる行為であると同時に、自分が得られなかった「父親」の姿を、嫉妬と羨望の入り混じった目で追体験する、奇妙な時間でもあった。
『拓也が初めて「パパ」と呼んでくれた。ただそれだけで、世界中のどんな宝物よりも価値があると感じた。由美子が隣で嬉しそうに笑っている。この二人こそが、俺の生きる意味だ』
読めば読むほど、胸が締め付けられた。この幸福な男は、いったい誰なんだ。父は、この男の日記を読みながら、何を思っていたのだろうか。この偽りの家族ごっこに、どんな満足を見出していたというのか。
苛立ちは最高潮に達していた。俺はノートを床に叩きつけようとして、ふと、最後のページに何か走り書きがされていることに気づいた。それは、これまで見てきた丁寧な文字とは違う、乱れた筆跡だった。まるで、絶望の縁で書き殴ったような。
『健一兄さんへ。もし俺に何かあったら、どうか由美子と拓也を頼む。俺の代わりに、あいつらを守ってやってくれ。不甲斐ない弟で、ごめん。でも、兄さんなら、きっと……』
健一。
その名は、俺の父の名前だった。
第三章 言葉にならない愛
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。全身の血が逆流し、耳鳴りが世界を支配する。俺は震える手で、もう一度、父の戸籍謄本を取りに役所へ走った記憶を呼び覚ました。そうだ。父の名前は、藤堂健一。そして、そこには確かに記されていたのだ。俺が生まれる五年前に、交通事故で死亡した、父の弟の名が。
藤堂、健二。
日記の主は、父ではなかった。父の、若くしてこの世を去った弟だったのだ。写真は、弟の家族。妻の由美子さんと、息子の拓也くん。
父は、もう一つの家族を持っていたわけではなかった。亡き弟との最後の約束を、ただ一人で、誰にも明かすことなく、三十年以上も守り続けていただけだったのだ。
脳裏に、断片的な記憶が蘇る。幼い頃、父が頻繁に「出張だ」と言って家を空けていたこと。母が「あんなに働いて、体を壊さなければいいけど」といつも心配そうに呟いていたこと。俺が欲しがった高価なグローブを、黙って買ってきてくれた日の、少しだけ疲れた父の横顔。あの無口も、不器用さも、俺に向けてくれなかった笑顔も、すべてがこの重い約束のためだった。自分の家族との時間を削り、必死に働いて得た金を、弟の家族に仕送りしていたのだ。運動会の写真の隅に、人混みに紛れるようにして立つ、見覚えのある背中が写っていることに、俺は今更ながら気づいた。顔を隠し、ただ遠くから、弟の息子の成長を見守っていたのだ。
父は、二つの家族を一人で背負っていた。弟の影を背負い、その家族の人生というワルツを、つまずかないように必死で支えながら踊り続けていた。俺に注がれるはずだったかもしれない愛情や時間は、その重すぎる責任の代償だった。
俺は泣いていた。声も出さず、ただ涙が頬を伝っていく。父への憎しみは、跡形もなく消え去っていた。そこにあったのは、あまりにも巨大で、あまりにも不器用な父の愛に対する、途方もない感謝と、気づけなかった自分への深い後悔だけだった。
病院の白いベッドで眠る父は、小さく、弱々しく見えた。酸素マスクが、か細い呼吸に合わせて白く曇る。俺は、その皺だらけの、節くれだった手を、生まれて初めて両手で包み込んだ。職人だった父の、硬く、分厚い手。この手で、父は二つの家族を守り抜いたのだ。
「親父……」
声が掠れた。
「ありがとう。ずっと、気づかなくて……ごめん」
言葉は、父に届いたのだろうか。その時、固く閉じられていた父の瞼が、ぴくりと動いたような気がした。
数日後、父は奇跡的に意識を取り戻した。まだ言葉はうまく話せない。けれど、俺が病室に入ると、その目は確かに俺を捉え、ほんの少しだけ、本当にほんの少しだけ、その口元が綻んだ。それは、俺が三十六年間、一度も見たことのない、父の笑顔だった。
週末、俺は地図を片手に、少し離れた町へ向かう電車に乗っていた。父の日記に記されていた住所。拓也くん――今はもう四十歳近い彼が住むはずの場所だ。何を話せばいいのか、まだ分からない。けれど、行かなければならないと思った。父が繋いだ縁を、父が守り抜いた約束を、今度は俺が受け継ぐ番なのだと、そう直感していた。
車窓から流れる景色を見つめながら、俺は思う。家族とは、血の繋がりや、一つ屋根の下で暮らすことだけを指すのではないのかもしれない。誰かを想い、その人生を背負うと決めた瞬間に生まれる、目には見えない絆。言葉にはならない、けれど確かに存在する、愛の形。
父がその無骨な背中で示し続けた、言葉にならない愛のワルツを、俺は確かに受け取った。空は、どこまでも青く澄み渡っていた。