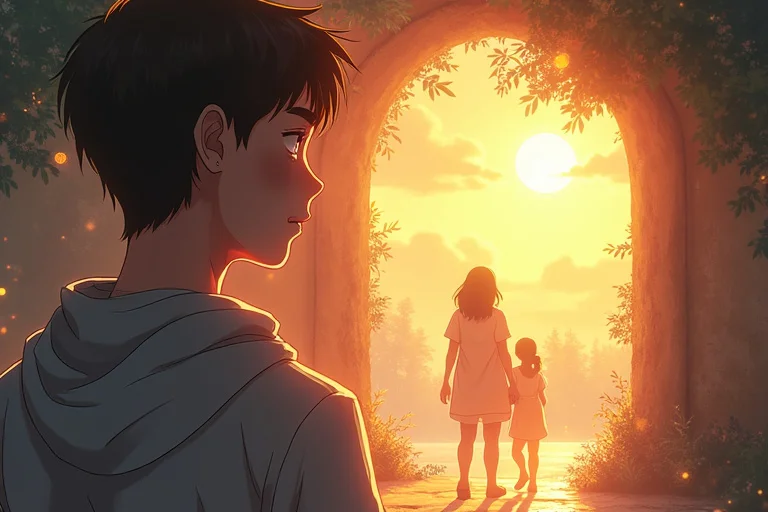第一章 疼く記憶
僕、水上湊(みなかみ みなと)の身体は、家族の記憶を収めた古い書庫のようなものだ。それは比喩ではない。例えば、祖母が窓辺で楽しげに編み物をしているのを見ると、僕の指先には決まって、凍傷になりそうなほどの鋭い痛みが走る。それは雪深い戦地で砲弾の破片を拾い集めたという、曾祖父の記憶の残響だ。母がキッチンで豆を挽く香ばしい匂いが漂うと、僕の心臓はまるで初恋の少年のような、甘く苦しい動悸を打つ。それは、父がこの家で母にプロポーズした瞬間の、高揚と不安が入り混じった感情の化石だった。
僕にとって、家族の歴史は物語ではなく、不意に訪れる肉体的な感覚だった。腹を満たすことのなかった祖父の飢えは、僕の胃をキリキリと締め付け、新しい命を宿した時の曾祖母の喜びは、僕の全身を春の陽だまりのような幸福感で満たした。
だが、その無数の記憶の断片の中に、ひとつだけ来歴のわからないものがあった。それは、燃える薪のはぜる音と、背中を優しく撫でる大きな手のひらの温もり。そして、僕のものではないはずなのに、どうしようもなく胸を締め付ける、強烈な『家族の絆』の感覚。我が家の家系図を何度遡っても、暖炉のある家に住んでいた者はおらず、その温もりをくれるはずの人物はどこにも存在しなかった。その記憶だけが、僕の中で寄る辺のない孤児のように彷徨っていた。
第二章 白紙のコーラス
我が家のリビングの隅には、奇妙な調度品がある。それは、決して閉じることのできない、分厚い革張りの家族アルバムだ。表紙には何も書かれておらず、中身は常に真っ白なページが続いている。しかし、このアルバムは死んではいない。世界のどこかで新しい家族が生まれるその瞬間に、カサリ、と乾いた音を立てて、ひとりでに新しいページが追加されるのだ。
ある夜、僕はそのアルバムの前に座っていた。遠くで産声のようなものが聞こえた気がした直後、アルバムはいつものようにページを増やした。白紙のページには、一瞬だけ、幸せそうに笑う夫婦と赤ん坊の姿が淡く浮かび上がる。しかし、それは陽炎のように揺らめくと、次の瞬間にはまったく別の家族――公園で遊ぶ親子――の絵へと、何事もなかったかのように入れ替わった。まるで、世界のどこかでひとつの家族の席が空き、すぐさま別の家族がその席を埋めたかのように。
その時だった。耳を澄ますと、白紙のページの中から、か細い声が聞こえてきた。囁き声のコーラス。
「…忘れないで…」
「…ここにいたことを…」
それは、忘れ去られた者たちの声なのだろうか。僕は、あの来歴不明の『暖炉の記憶』も、この声の持ち主たちと同じ場所から来ているのではないかと、漠然と感じ始めていた。
第三章 輪郭のない影
「謎の記憶」の正体を突き止めたい一心で、僕は市の図書館に通い詰めた。古い戸籍謄本、地域の歴史書、過去の新聞。しかし、僕の家系に繋がる手掛かりは何も見つからなかった。
「何かお探しですかな」
声をかけてきたのは、白髪の司書だった。埃と古い紙の匂いを纏ったその老人は、僕の手元にある戸籍の写しを覗き込み、静かに言った。
「家族とは、不思議なものですな。この街の家族の総数は、私が子供の頃から、なぜかほとんど変わらないのですよ。まるで、器の大きさが決まっているかのように」
その言葉は、僕の胸に小さな棘となって突き刺さった。
家に帰り、僕はもう一度、古い写真を探し始めた。埃っぽい木箱の底から出てきた一枚の写真。それは、まだ僕が生まれる前の、若い両親と祖父母が写ったものだった。しかし、その写真には奇妙な点があった。祖母の隣に、誰かが立っていたであろう空間が、まるで鋭い刃物で切り取られたかのように、不自然に空白になっているのだ。家族に尋ねても、誰もその場所に誰がいたのか覚えていない。「最初から、こうだったんじゃないか?」と首を傾げるだけだった。輪郭だけが残された、存在しないはずの家族の影。僕の心臓が、不安に脈打った。
第四章 隣人の消失
その日は、僕の家に新しい光が灯った日だった。姉が、元気な男の子を産んだのだ。家族全員が喜び、祝福の言葉を交わし合う。僕も、もちろん嬉しかった。だが、赤ん坊の誕生を知らせる電話が鳴った、その瞬間。
ドクン、と心臓が大きく跳ねた。
それは祝福の動悸ではなかった。胸にぽっかりと穴が空いたような、激しい喪失感。あの『暖炉の記憶』の温かさとは正反対の、すべてを奪われるような絶対的な孤独。僕はリビングへと駆け込んだ。
そこでは、例のアルバムが凄まじい勢いでページをめくり、白紙のページからは、これまで聞いたこともないような悲鳴が響き渡っていた。僕は窓の外に目をやった。いつも笑顔で挨拶を交わしていた、隣の鈴木さん一家の家の明かりが、ふっと消えた。
いや、違う。明かりが消えたのではない。鈴木さんの家そのものが、そこに建っていたという事実ごと、僕の認識から滑り落ちていく。リビングの壁に飾ってあった、鈴木さん一家と僕たち家族が一緒に写った写真。その写真の中から、鈴木さん一家の姿が、水彩絵の具が水に溶けるように、すぅ…と消えていった。
「湊、どうしたの? そんなに慌てて」
背後から母の声がした。僕は震える指で窓の外を指さす。
「鈴木さん一家が…消えたんだ…!」
しかし、母は怪訝な顔で僕を見た。
「鈴木さん? 隣の家は、もうずっと前から空き家じゃないの」
世界の法則。それが、冷酷な現実として僕の目の前に突きつけられた。僕の家族が一人増えた代償として、隣の家族が、世界から『忘れ去られた』のだ。
第五章 暖炉の誓い
僕は、まるで亡霊にでもなったかのように、アルバムの前に崩れ落ちた。母の言葉が、世界から拒絶されたかのような孤独感を僕に与える。僕以外の誰も、鈴木さん一家を覚えていない。
震える手で、悲鳴の止んだアルバムの白紙のページに触れた。その瞬間、僕の脳裏に、奔流のように記憶が流れ込んできた。それは、僕がずっと追い求めていた『暖炉の記憶』の、完全な姿だった。
燃え盛る暖炉を囲む、温かい家族の笑顔。そこにいるのは、若い頃の祖父母、そして僕の両親。そして…写真から切り取られていた、見知らぬ、しかし懐かしい顔をした曽祖父母たち。それは、紛れもなく僕の家族だった。しかし、彼らの表情は次第に悲しみと恐怖に歪んでいく。彼らの身体が、輪郭が、世界から薄れ始めていたのだ。世界の法則によって、彼らが『忘れ去られる』番が来たのだ。
消えゆく瞬間、彼らは最後の力を振り絞り、ひとつの願いを紡いだ。まだ生まれていなかった、僕の姉の中に宿る、新しい命に向かって。
『どうか、この絆だけは』
『私たちの記憶だけは、お前の中に』
『世界が私たちを忘れても、家族がここにいたという証だけは、残っておくれ』
その集合的な強い願いが、呪いのように、祈りのように、生まれてくるはずだった僕の魂に集約された。僕のこの特異な能力は、一度は世界から忘れ去られた僕自身の家族が、その存在の証を留めるために生み出した、最後の抵抗だったのだ。僕の家族は、別の家族が消えることで、再びこの世界に席を取り戻し、再構成されていたに過ぎなかった。
第六章 忘却の番人
真実を知った僕の目の前で、アルバムが眩い光を放った。白紙だったページに、忘れ去られていた家族の姿が、そして現在の家族の姿が、次々と鮮明に浮かび上がっていく。まるで、長い眠りから覚めたかのように。リビングに温かい空気が満ちる。僕の家族は、今この瞬間、完全に世界に再認識されたのだ。
だが、光は僕にあるものを突きつけた。光の中に、無数の見知らぬ家族の姿が、走馬灯のように映し出される。彼らの笑い声、泣き声、ささやかな日常。アルバムは、僕に選択を迫っていた。僕の家族が世界に存在し続けるための、次の代償を。次に『忘れ去られる』べき家族を、この僕が選ばなければならないのだと。
僕の能力は、家族の記憶を守るための灯火であると同時に、世界のどこかで別の家族の灯火を吹き消すための、冷たい儀式でもあった。
涙が頬を伝った。それは、家族を取り戻した歓喜の涙か、これから背負う途方もない罪の重さに震える涙か、自分でもわからなかった。
僕は、ゆっくりと立ち上がり、新たに追加された真っ白なページに、そっと指を置いた。
家族の記憶を守る『継承者』として。
そして、世界の均衡を保つ『忘却の番人』として。
「忘れないよ」
僕は、光の中に浮かぶ、名も知らぬ家族に向かって呟いた。
「君たちのことも。僕が、決して忘れない」
その声は誰に届くでもなく、ただ、家族の温もりが戻った静かな部屋に、小さく溶けて消えていった。