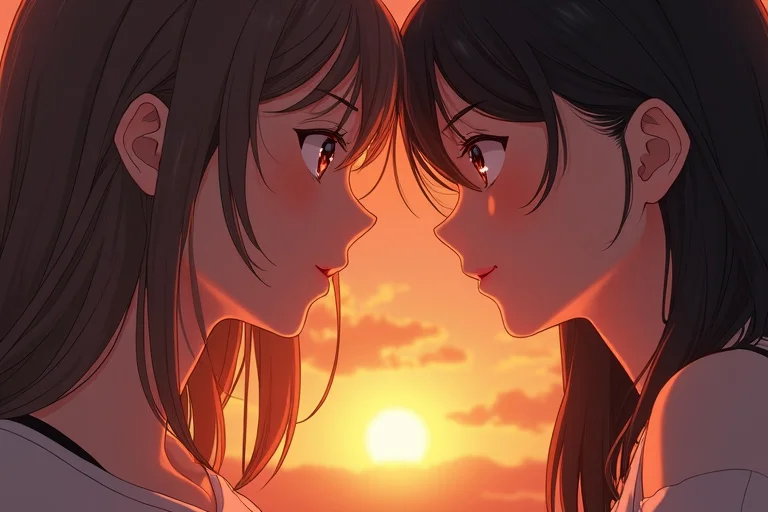タイトル: 共鳴家族
-----
第一章 ガラス細工の幸福
完璧な静寂が、磨き上げられたマホガニーのテーブルに満ちていた。カトラリーが皿に触れる微かな音だけが、まるで計算された和音のようにリビングに響く。今日は妹、遥の十七歳の誕生日。母の焼いたローストチキンは黄金色に輝き、父の選んだワインはルビーのように煌めいていた。そして、テーブルの中央には、遥の笑顔のように華やかなフルーツタルトが鎮座している。すべてが完璧だ。完璧すぎるほどに。
「凪、どうしたの? チキン、冷めちゃうわよ」
母が絹を張ったような声で僕、凪(なぎ)に微笑みかける。その顔には一点の曇りもない。僕は無理やり口角を引き上げ、曖昧に頷いた。視線を左手首に落とす。そこには、すべての国民が装着を義務付けられている銀色のブレスレット――『共鳴計』が冷たい光を放っていた。
ディスプレイには、僕たち家族の『幸福総量』を示す数値「98.6%」と、それに基づいて算出された『予測余命』がデジタル表示されている。僕たち水上家は、この地域でも指折りの高数値を維持していることで有名だった。父の会社の成功、母の献身、遥の学業優秀。そして、そんな家族の一員である僕。僕たちは、幸福の見本市のような家族だった。
「お兄ちゃん、プレゼントありがとう! この万年筆、すごく嬉しい!」
遥が子犬のようにはしゃぎながら、僕に笑いかける。その純粋な喜びが、共鳴計の数値をほんの少しだけ押し上げた。98.7%。父と母は満足げに頷き合う。
その時だった。僕の視界の端で、自分の共鳴計の予測余命の数字が、一瞬だけ激しく乱れた。まるでバグを起こしたかのように、現在からマイナス五年、十年、二十年と、目まぐるしく数字が暴落し、そしてすぐに元の穏やかな表示に戻った。一秒にも満たないノイズ。家族の誰も気づいた様子はない。
だが、僕の背筋を冷たいものが走り抜けた。
心臓が嫌な音を立てて脈打つ。この家は、まるで繊細なガラス細工だ。どこか一つにひびが入れば、次の瞬間にはすべてが粉々に砕け散ってしまうのではないか。僕たちの幸福は、一体何の上に成り立っているのだろう。完璧な笑顔を浮かべる家族の顔を見渡しながら、僕は、この幸福という名の薄氷の下に、深く冷たい、底なしの闇が広がっているような気がしてならなかった。
第二章 不協和音の源
あの日以来、僕は家の空気に含まれる微かな歪みを、以前よりも敏感に感じ取るようになっていた。それは、母が料理中にふと遠くを見つめる一瞬の虚ろさであり、父が新聞を読みながら無意識に共鳴計を撫でる癖であり、遥が時折見せる、年齢不相応な諦観を宿した瞳だった。
僕の疑念は、共鳴計のノイズという形で、日に日に確信へと変わっていった。家族が誰も見ていない瞬間、僕の余命だけが不規則に揺らぐ。まるで、僕だけが知ることを許された、家族の悲鳴のようだった。
「どうして、うちの家族はこんなに『幸せ』でいなくちゃいけないんだ?」
ある日の夕食後、僕はついに口火を切ってしまった。静まり返るリビング。父は読んでいた本から顔を上げ、母は編み物をしていた手を止めた。遥の肩が小さく跳ねる。
「何を言っているんだい、凪。幸せなのは良いことじゃないか」
父が穏やかに、しかし有無を言わせぬ口調で言った。その声には、話題を逸らしたいという明確な意志が滲んでいる。
「良いこと? これは呪いみたいだ! 少しでも不幸を感じたら、機嫌を損ねたら、この数字が下がる! まるで僕らは、この計器の奴隷じゃないか!」
僕は自分の共鳴計をテーブルに叩きつけるように見せた。その瞬間、リビングに甲高いアラーム音が鳴り響く。全員の共鳴計が、警告を示すように赤く点滅し始めた。幸福総量が、90%を割り込んでいる。
「凪! やめなさい!」
母が悲鳴のような声を上げた。その顔は恐怖に引きつっている。
「ごめんなさい、お父さん、お母さん。お兄ちゃんのせいじゃないの、私が今日、テストで悪い点を取っちゃったから……」
遥が震える声でそう言うと、堰を切ったように泣き出した。
違う。そうじゃない。遥のせいじゃない。僕が、僕たちが抱える根本的な何かが、この家を蝕んでいるんだ。だが、父と母は遥を慰めるのに必死で、僕の声は届かない。彼らは、問題の根本を見ようとせず、ただひたすらに幸福度を維持することに固執している。
僕は、この家にいるのが息苦しくてたまらなくなった。僕という存在が、この完璧な家族の不協和音の源なのだとしたら。
「もう、うんざりだ」
吐き捨てるようにそう言うと、僕は椅子を蹴立てて玄関へ向かった。背後で母が僕の名前を呼ぶ声がしたが、振り返らなかった。冷たい夜の空気が、燃えるように熱い頬を撫でる。僕は、この偽物の幸福から逃れるように、闇の中へと駆け出した。
第三章 共鳴の真実
当てどなく彷徨った末、僕の足は市街地から外れた丘の上に立つ、小さな家へと向かっていた。母方の祖母の家だ。祖母は、共鳴計が義務化される前の世代で、その腕には何も巻かれていない。ドアを開けると、樟脳と古い木の匂いが僕を包んだ。
「……おや、凪じゃないか。どうしたんだい、そんな顔をして」
祖母は驚いた様子もなく、僕を温かいココアで迎えてくれた。僕は、堰を切ったようにすべてを話した。家族の不自然なまでの幸福への執着、共鳴計のノイズ、そして今日の出来事。
祖母は黙って僕の話を聞いていたが、やがて重い口を開いた。
「凪。お前には、お兄さんがいたんだよ」
言葉の意味を理解するのに、数秒かかった。兄? 僕に兄が?
「お前の生まれる二年前に亡くなった。名前は、海(かい)……。あの子は、生まれつき共聞計の機能が不全でね。感情の振れ幅が極端に少なくて、ほとんどの時間を『幸福でも不幸でもない』状態で過ごしていた。あの子自身は、それで穏やかに生きていたんだが……」
祖母の言葉が、雷のように僕の頭を打ち抜いた。
「共鳴計は、『家族全員』の幸福を計測する。海の存在は、お前たち家族の幸福総量を、常に危険な水準まで引き下げていた。お前の両親は、それでも海を愛し、必死で幸福度を上げようと努力した。だが、ある日……海は、一枚の置き手紙を残して、いなくなったんだ」
祖母は、古びた文箱から一枚の便箋を取り出した。それは、子供の拙い字で書かれていた。
『ぼくがいると、みんなのじかんがへっちゃうから。ごめんなさい。みんなが、ずっとしあわせでいられますように』
「海は、家族のために自ら姿を消したんだよ。あの子は、崖から……。あの日以来、お前の両親は自分たちを責め続けた。海の死は自分たちのせいだと。だから、二度と誰も失わないように、残されたお前たちを『完璧な幸福』の中に閉じ込めて、守ろうとしたんだ。あの計器が示す数字だけを信じてね」
これが、真実。
僕が感じていた息苦しさの正体。両親の必死さの理由。ガラス細工の幸福の下に隠されていたのは、失われた息子への、あまりにも深く、痛ましい愛情と贖罪の念だった。
そして、僕はもう一つの事実に気付いて愕然とした。共鳴計の隠されたルール。家族が一人欠けたことで、僕たちの幸福度には永久に埋まらない『穴』が空いてしまったのだ。だから、残された僕たちが、文字通り命がけで幸福を演じ続けなければ、予測余命はあっという間に尽きてしまう。僕が見ていたノイズは、僕の心の奥底にあった、まだ見ぬ兄への無意識の問いかけが、この家のシステムの綻びを突いていたのかもしれない。
第四章 私の選択
祖母の家を出る頃には、東の空が白み始めていた。僕の心は、罪悪感と、知らなかった兄への愛しさと、そして両親への張り裂けそうなほどの想いでいっぱいだった。逃げ出した自分が恥ずかしかった。僕は、家族の元へ帰らなければならない。
家のドアを開けると、リビングの光景に息を呑んだ。父も、母も、遥も、ソファで寄り添うように座っていたが、その顔は土気色で、生気が完全に失われていた。テーブルの上の共鳴計は、僕が家を出てから一度も回復することなく、危険水域を示す赤い光を放ち続けている。僕という部品が欠けたことで、この脆い幸福は、いよいよ崩壊の瀬戸際にあった。
僕の姿を認めると、母がふらりと立ち上がった。
「凪……よかった、帰ってきてくれた……」
その声は掠れ、安堵と絶望が入り混じっていた。
僕は、ソファの前にゆっくりと膝をついた。そして、震える家族の顔を一人ひとり見つめて、言った。
「ごめんなさい。……もう、いいんだよ」
「え……?」
「もう、幸せなフリはしなくていい。僕、全部聞いた。お兄ちゃんのこと」
その言葉に、母の瞳から大粒の涙が溢れ落ちた。父は固く唇を結び、遥は息を呑んだ。家の空気が、張り詰めた糸が切れるように、ふっと緩んだ。
「辛かったよね。苦しかったよね。お兄ちゃんのことを忘れたフリをして、笑っているのは。悲しいなら、一緒に悲しもう。寂しいなら、一緒に寂しがろう。それが、家族だろ?」
僕の言葉が引き金になった。母は、子供のように声を上げて泣き崩れた。その肩を、父が震える手で抱きしめ、その父の背中に、遥がすがりついて泣いた。そして僕も、生まれて初めて会う兄を想い、声を殺して涙を流した。
それは、絶望の涙ではなかった。何十年という歳月を経て、ようやく流すことを許された、解放の涙だった。
その時、不思議なことが起きた。僕たちの手首で、警告音を鳴らし続けていた共鳴計が、ふっと静かになった。赤く点滅していた光が、穏やかな青色に変わる。そして、危険なほど低下していた予測余命の数字が、ゆっくりと、しかし、確実に上昇を始めたのだ。
僕たちは、泣きじゃくりながら顔を見合わせた。
共鳴計が本当に測りたかったのは、上辺だけの笑顔や、無理に作った明るさではなかった。悲しみも、痛みも、弱さも、すべてを隠さずに共有し、ありのままの感情で繋がり合うこと。それこそが、計器が定義する『真の幸福』だったのだ。
数年後。水上家のリビングには、一枚の写真が飾られている。少し気弱そうに、でも優しく笑う、僕の知らない兄、海の写真だ。
僕たちの共鳴計が示す数値は、以前のように98%を超えることはない。時には喧嘩をして、大きく下がる日もある。でも、もう誰もその数字に怯えたりはしない。手首の冷たい銀色の輪は、もはや僕たちを縛る鎖ではなかった。それは、言葉にしなくても互いの心の脈動を伝え、不完全な僕たちが、それでも確かに繋がっていることを証明してくれる、温かい絆の証となっていた。
僕は、窓から差し込む柔らかな光の中で、兄の写真にそっと微笑みかけた。家族とは、完璧な幸福を目指す終着点ではない。痛みや欠落を抱えながらも、互いを赦し、受け入れ、共に歩み続ける、終わりのない旅そのものなのだと。その静かな真実が、僕の胸を穏やかに満たしていた。