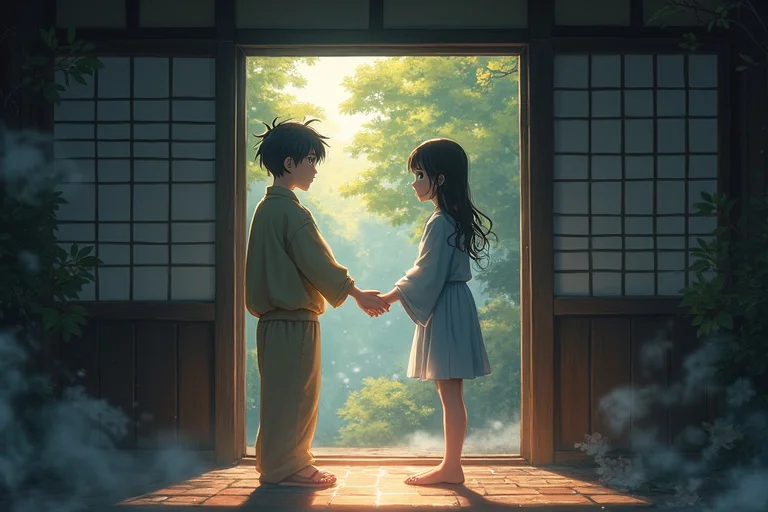第一章 入れ替わる食卓
朝、目が覚めると、僕は「父親」だった。
瞼の裏にざらりとした疲労感がこびりついている。これは僕自身の、昨夜遅くまで続いた受験勉強の疲れではない。もっと深く、永続的な、家計を支え、家族を守る者の重圧だ。身体は十七歳の痩躯のまま。鏡に映る顔も、寝癖のついた見慣れた高校生の僕、空(ソラ)だ。しかし、その瞳の奥に宿る精神は、紛れもなくこの家の家長たる「父親」のものだった。
「父さん、起きて。朝ごはん、遅れるわよ」
ドアの向こうから聞こえたのは、十歳の妹、ひかりの声。だが、その口調は幼い妹のものではなく、家族の健康を気遣う「母親」のそれだった。僕は重い体を起こし、「ああ、今行く」と、自分のものではないような、低く落ち着いた声で答えた。
これが、僕の家族の「日常」だ。僕たち、佐藤家には、古代から続く奇妙な掟がある。毎朝目覚めると、家族四人――父さん、母さん、僕、ひかり――の「役割」が、精神だけランダムに入れ替わるのだ。身体や記憶は昨日のまま、完全に地続き。しかし、担うべき役割――父親、母親、息子、娘――だけが、まるで配役のようにシャッフルされる。
リビングに降りると、味噌汁の優しい香りが鼻をくすぐった。小さなエプロンをつけたひかりが、僕の身体よりずっと背の低い「母親」として、かいがいしく朝食の準備をしている。その隣では、本来の父親である健一が、制服のネクタイをだらしなく緩め、ふてくされた顔でスマートフォンをいじっていた。今日の彼の役割は「息子」。つまり、僕の立場だ。
「健一、いい加減にしなさい。学校に遅れるでしょう」
「わかってるよ、うるさいな…」
ひかりの「母親」らしい叱責に、健一が「息子」として反抗的な声を返す。その光景は、滑稽で、そして僕にとっては耐え難いほどに息苦しかった。本来の母親である美咲は、今日の役割は「娘」。ひかりの隣で、無邪気にテレビのアニメを観ている。
「父さん、今日の会議、資料は大丈夫?」
ひかりが、僕の顔を覗き込みながら尋ねた。僕の頭には、健一が勤める設計事務所の重要なプレゼンの内容が、まるで自分のことのように浮かび上がってくる。
「ああ、問題ない。昨夜、最終確認しておいた」
僕はごく自然にそう答えた。この役割を演じるのは、もう慣れたものだ。
しかし、慣れることと、受け入れることは違う。どうして僕の家だけが、こんな奇妙な儀式を続けなければならないのか。友達の家では、父親はいつも父親で、母親はいつも母親だ。それが当たり前で、「普通」のはずだ。僕は、この入れ替わりの演劇に心底うんざりしていた。早くこの家を出て、大学に行って、誰でもない「僕」として生きたい。その思いだけが、この歪な日常の中で僕を支える唯一の光だった。
第二章 仮面の向こう側
その日は、僕が「娘」で、母の美咲が「妹」の役割だった。僕は生まれて初めて、本来ならひかりが着るであろう、フリルのついたワンピースに袖を通すことになった。もちろん、十七歳の男子高校生である僕の身体には到底入らないので、精神的な役割として、家では一日中、少しだけか細い声で、甘えるように話すことを求められる。
リビングで母と二人きりになった時だった。今日の彼女は「妹」、つまりひかりの役割だ。いつもは気丈で、完璧な「母親」を演じることが多い美咲が、ソファの隅で膝を抱え、小さく震えているように見えた。
「どうしたの、美咲ちゃん」
僕は「娘」として、できるだけ優しい声で話しかけた。
彼女は顔を上げ、その瞳は不安げに揺れていた。普段の彼女からは想像もつかない、か弱い表情だった。
「……お兄ちゃん。私、学校の友達と、喧嘩しちゃったの」
それは、実際にひかりが昨日、学校で経験した出来事だった。役割が入れ替わっても、個人の記憶は共有される。だから僕たちは、それぞれの身に起きたことを、別の役割の視点から追体験することになる。
美咲は、ぽつり、ぽつりと語り始めた。友達に些細なことで意地悪を言われ、何も言い返せなかった悔しさ。一人ぼっちになった教室の冷たさ。それは、いつも自信に満ち溢れている母・美咲の姿とはかけ離れた、十歳の少女の純粋な痛みだった。僕はただ、黙って彼女の話を聞いていた。そして気づいた。僕が知っている「母」は、数ある役割の一つに過ぎなかったのだと。この仮面の向こう側には、僕の知らない、一人の弱い人間の顔が隠れていたのだ。
またある日、僕は「息子」で、父の健一が「父親」だった。その夜、健一は珍しく僕を自室に呼び、「少し話さないか」と言った。本来の彼らしい、威厳のある「父親」の顔だった。
「空。お前、最近、大学のパンフレットをよく見ているな」
僕はドキリとした。家を出たいという僕の計画を、彼は見抜いていた。
「……別に」
僕は「息子」として、素っ気なく答えた。
健一はため息をつき、窓の外の夜空を見つめた。その横顔には、僕が「父親」の役割を演じる時に感じるものと同じ、深い孤独の影が落ちていた。
「この家が、嫌か。……そうだろうな」
彼の声は、責めるようでもなく、ただ静かな諦念に満ちていた。
「父さんも、お前くらいの年には、ここから逃げ出すことばかり考えていた」
その言葉は、僕にとって意外だった。父も、同じ苦しみを抱えていたのか。
僕たちはその夜、多くを語らなかった。しかし、沈黙の中に、これまで感じたことのない、父と子の間の微かな共感が流れていた。
様々な役割を経験する中で、僕は家族の知られざる一面に触れていった。役割という仮面は、僕たちを縛る呪いであると同時に、互いの心を深く理解させるための装置でもあるのかもしれない。だが、それでも僕の決意は揺らがなかった。僕は、仮面をつけずに生きていきたい。本当の父、本当の母、そして本当の僕がいる「普通の家族」になりたい。大学の合格通知を手にしたら、この家を出よう。僕は固く心に誓っていた。
第三章 儀式の真実
雪がちらつく二月の夜だった。僕はリビングに家族を集め、震える声で切り出した。
「春から、京都の大学に行くことにした。家を出て、一人で暮らす」
推薦入試で、第一志望の大学への合格が決まったのだ。
一瞬、時が止まったかのような沈黙が落ちた。その日の役割は、父が「父親」、母が「母親」、僕が「息子」で、ひかりが「娘」という、本来の姿に最も近い配役だった。だからこそ、僕の言葉は、ただの役割を越えた、僕自身の宣言として、重く響いた。
「そうか……。おめでとう」
父が、絞り出すように言った。母は何も言えず、俯いている。ひかりだけが、僕の顔をじっと見つめていた。その時、奥の和室の襖が静かに開き、祖母が姿を現した。祖母だけは、この役割交代の儀式に参加していない。いつも静かに僕たちを見守っている、この家の揺るぎない中心だった。
「空。お前が家を出るというのなら、話しておかなければならないことがあります」
祖母は、僕たちを囲むように座り、重々しく口を開いた。
「お前たちが続けているこの『儀式』が、なぜ始まったのか、知っていますか?」
僕たちは顔を見合わせた。物心ついた時から続く、当たり前のルール。その起源など、考えたこともなかった。
「我々の一族はね、古くから、人の心に寄り添いすぎる性質を持っていた。良く言えば共感能力が高い。悪く言えば、他人の感情に呑み込まれて、自分を見失ってしまう」
祖母は、遠い目をして語り始めた。
「他人の悲しみは自分の悲しみとなり、他人の怒りは自分の怒りとなる。やがて心の境界線が曖昧になり、多くの者が精神を病み、自ら命を絶ったり、家族を傷つけたりした。家族という最も濃密な関係の中では、特にその危険が大きかったのです」
リビングの空気が、シンと張り詰める。
「そこで、ご先祖様は考え出した。強制的に役割を入れ替え、他者の視点を体験することで、客観的に自分と他者を見つめ、自我のバランスを保つ方法を。これは、呪いから身を守るための、一族の知恵であり、祈りなのです。この儀式をやめて『普通の家族』になろうとした分家は、皆、例外なく、心が壊れて家族が崩壊しました」
僕の背筋を、冷たい汗が伝った。僕が忌み嫌っていたこの日常は、僕たちを守るための、必死の防衛策だったというのか。
「じゃあ、僕は、ここから出たら……」
「一人で、その宿命と向き合うことになる。誰の心にも寄り添わず、孤独に生きるか。あるいは、誰かの心に呑み込まれ、自分を失うか。茨の道です」
絶望的な言葉だった。だが、祖母が次に告げた事実は、それ以上に僕の心を打ち砕いた。
「そして、空。……この儀式が、今の形で始まったのは、お前が生まれてからです」
「え……?」
「お前は、この一族の中でも、飛び抜けて強い共感能力を持って生まれてきた。赤ん坊の頃、隣の家で夫婦喧嘩が始まると、お前は火がついたように泣き叫び、熱を出した。人の感情が、お前にとっては毒だったのです。だから私たちは、家族全員で役割を分かち合うことで、お前の心に流れ込む毒を、薄めてきた。この儀式は、お前一人を守るために、家族全員で続けてきたことなのです」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。僕が、原因だったのか。僕が、この奇妙な家族の元凶だったのか。僕が逃げ出したいと願っていたこの歪な檻は、僕を守るために、家族が自ら入ってくれた、愛情の揺り籠だったというのか。
第四章 僕が僕であるために
その夜、僕は一睡もできなかった。これまで抱えてきた不満や反発心が、罪悪感と感謝という、あまりにも巨大な感情の奔流に押し流されていく。僕が「普通の家族」を夢見る一方で、家族は僕のために「異常な家族」であり続けてくれた。父の孤独も、母の脆さも、僕が知ることのできたすべての感情は、僕の心を砕かないように、家族が代わりに砕いてくれていた欠片だったのかもしれない。
翌朝。アラームの音で目を覚ました僕は、しばらく天井を眺めていた。今日の僕の役割は、何だろうか。ゆっくりと体を起こすと、不思議と心は凪いでいた。混乱も、絶望も通り過ぎ、そこには静かな覚悟だけが残っていた。
リビングに降りると、いつものように、ちぐはぐな家族が食卓を囲んでいた。今日の「父親」はひかり、「母親」は健一、「娘」は美咲だった。そして僕は、「息子」だった。昨日と同じ、本来の僕の立場。しかし、その意味合いは、昨日とは全く違って見えた。
僕は自分の席につき、目の前の湯気の立つご飯と味噌汁を見つめた。父である健一が、母のように慣れない手つきでよそってくれたご飯。妹であるひかりが、父のようにどっしりと構えて見守る中で。
「いただきます」
僕は深く頭を下げ、箸を取った。そして、一口、ご飯を口に運ぶ。米の甘さが、涙になりそうなほど、全身に染み渡った。
僕は顔を上げ、家族の顔を一人ずつ見回した。父の顔をした「母親」。母の顔をした「娘」。妹の顔をした「父親」。そして、彼らが守ろうとしてくれた、僕。
「今日の朝ごはん、美味しいね」
僕は、目の前に座るひかりに、まっすぐ視線を向けて言った。
「……『お父さん』」
ひかりは、一瞬、十歳の少女の顔で、きょとんと目を丸くした。だがすぐに、その瞳の奥に宿る「父親」の魂が、僕の言葉の意味を理解したようだった。彼女は何も言わず、ただ、深く、優しく、頷いた。その表情は、僕が知るどの父親よりも、威厳と愛情に満ちていた。
僕が家を出るという選択は、変わらないかもしれない。祖母の言う通り、それは茨の道だろう。でも、もう逃げるためじゃない。僕が僕のままで、誰かを愛せるようになるために、僕は旅立つのだ。この家族が教えてくれたように、役割という仮面がなくても、人の痛みを理解し、自分の心を守れる強さを手に入れるために。
この奇妙な儀式が、いつか終わる日は来るのだろうか。僕が本当の自分を見つけ、その宿命を乗り越えた時、僕たちは「普通の家族」に戻れるのかもしれない。あるいは、この入れ替わりの日々こそが、僕たち家族が選び取った、唯一無二の愛の形なのかもしれない。
答えはまだ、風の中だ。だが、僕はもう一人ではない。心の中に、父親がいて、母親がいて、妹がいる。どんな役割を演じようとも、僕たちは、紛れもなく家族なのだから。食卓に差し込む朝の光が、僕たちの少し変わった、けれど、かけがえのない家族の肖像を、優しく照らし出していた。