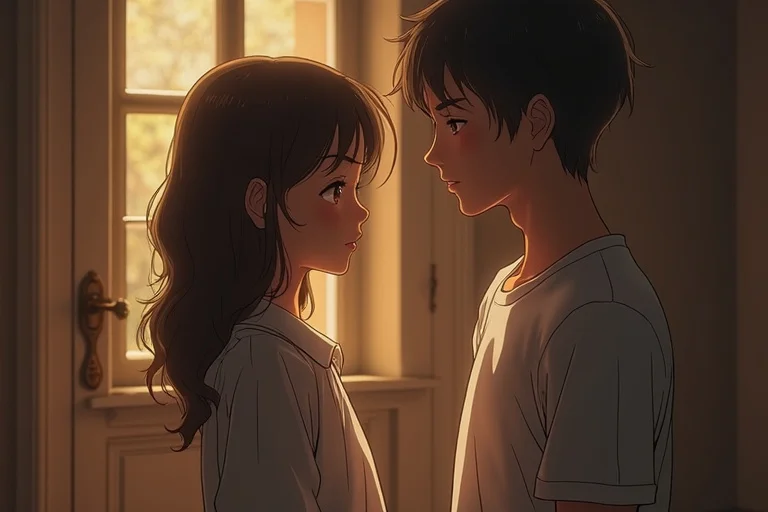第一章 軋む歯車
柏木湊(かしわぎ みなと)が、錆びついた実家の門をくぐったのは、実に五年ぶりのことだった。妹からの電話が、彼をこの場所に引き戻したのだ。「お父さん、少しおかしいの。たぶん、認知症が始まってる」。電話口で聞いた妹の声は、硬く、切実だった。
東京でグラフィックデザイナーとして多忙な日々を送る湊にとって、実家は過去を封じ込めた埃っぽい箱のような場所だった。特に、父・誠(まこと)とは、母・佳乃(よしの)が亡くなって以来、まともに口を利いた記憶すらない。無口で、頑固で、自分の世界に閉じこもる元時計職人の父。その存在 自体、湊にとっては息苦しさの象徴だった。
「ただいま」
誰もいないはずの玄関に向かって、呟きにも似た声を落とす。しんと静まり返った家の中は、母が生きていた頃のまま時が止まっているようで、カビと古い木の匂いが混じり合って鼻をついた。リビングのドアを開けた瞬間、湊は異様な光景に足を止めた。
部屋の中央に置かれたローテーブルの上で、父が猫背を丸め、一心不乱に何かをいじっている。カチリ、カチリ、と金属同士が触れ合う微かな音だけが、部屋の沈黙を支配していた。近づいてみると、それは古めかしい真鍮の置き時計だった。しかし、そのデザインは湊の記憶にあるどの時計とも一致しない。複雑な歯車が剥き出しになり、文字盤にはローマ数字でもアラビア数字でもない、奇妙な記号が刻まれている。
「父さん、何してるんだ」
湊の声に、誠はびくりと肩を震わせ、ゆっくりと顔を上げた。その目は虚ろで、焦点が合っていない。父は湊を一瞥すると、すぐに手元の時計に視線を戻した。
「……お前か」
「妹から聞いた。大丈夫なのか」
「何がだ」
「何がだ、じゃないだろ。その時計はなんだ?見たことないぞ」
湊の問いに、父は苛立ったように部品を置いた。
「お前には関係ない」
「関係なくないだろ。そんなガラクタいじってないで、少しは休めよ」
その瞬間、父の目が鋭い光を放った。
「ガラクタだと?……これは、ガラクタじゃない。佳乃との、約束の時計だ」
佳乃。母の名前が出たことに、湊は虚を突かれた。母が亡くなって十五年。父の口からその名を聞くことなど、ほとんどなかったはずだ。
「約束?なんのだよ」
だが、父はそれ以上何も答えず、再び時計の修理という名の分解作業に戻ってしまった。その背中は、湊の言葉を拒絶する分厚い壁のように見えた。狂気にも似た父の執着と、自分の知らない「約束」。軋む歯車のように噛み合わない父との会話に、湊は深い疲労と、胸の奥がざわつくような不穏な予感を感じていた。
第二章 錆びついた記憶
父の奇行の謎を解く鍵は、この家の中にあるはずだ。湊は、半ば義務感に駆られて、家の整理を始めた。父の工房として使われていた離れは、金属と油の匂いが染みつき、壁一面に様々な時計が掛けられていたが、あの奇妙な置き時計は見当たらない。
手掛かりを求めて母の遺品が残された部屋に入る。桐の箪笥を開けると、防虫剤の匂いと共に、母の好きだったラベンダーの香りがふわりと漂った。その一番下の引き出しの奥に、ひっそりと隠されるように置かれた数冊のノートを見つけた。それは、母がつけていた日記だった。
表紙をめくると、母の優美な筆跡が目に飛び込んできた。そこには、湊の知らない家族の姿が、色鮮やかに綴られていた。
『今日は湊と誠さんと三人で、裏山に秘密基地を作りました。湊が設計図を描いて、誠さんが一生懸命組み立てて。まるで小さな時計工房みたいで、とても楽しかった』
『湊が学校の工作で、小さな時計を作ってくれました。「これは家族の時間だよ」と言って、私にプレゼントしてくれた宝物。誠さんがそれに本物のムーブメントを入れてくれて、本当に動き出した時の湊の嬉しそうな顔!』
湊はページを繰る手を止めた。自分の記憶には、そんな出来事は一片たりとも存在しない。父と裏山で何かを作った記憶も、工作で時計を作った記憶も、全くなかった。自分が知っている父は、いつも工房にこもり、家族の輪から外れている存在だったはずだ。日記の中の父は、不器用ながらも家族を愛し、湊を温かく見守る、全くの別人だった。
混乱しながら最後のページまで読み進めると、湊の心臓を鷲掴みにするような一文があった。母が亡くなる数ヶ月前の日付だ。
『あの子が壊してしまったあの時計。誠さんは、今も諦めずに直し続けてくれています。「これは俺たちの時間そのものだから」と。どうか、あの時計が、いつか湊の失われた時間を繋ぎ、私たちの家族の時間を守ってくれますように』
あの時計。父が「佳乃との約束だ」と言っていた、あの時計のことだ。自分が、壊した?失われた時間?
頭の中で、錆びついていた記憶の歯車が、ぎしりと音を立てて無理やり回ろうとするような、鈍い痛みを感じた。自分の知る「家族」という物語が、根底から崩れ去っていくような感覚。湊は、日記を握りしめたまま、しばらくその場から動けなかった。
第三章 割れた文字盤
日記に導かれるように、湊は再び父の工房へと向かった。母の言葉が、父の行動の裏には自分の知らない何かがある、と告げていた。工房の隅に積まれた設計図の束。以前は気にも留めなかったその紙の山を、湊は一枚一枚、丁寧に確認し始めた。古びた壁掛け時計、腕時計、そして……あった。あの奇妙な置き時計の、精緻な設計図だ。
父の几帳面な線で描かれた歯車の数々。その設計図に、何か分厚いものが挟まっていることに気づく。そっと引き抜くと、それは茶色く変色した封筒だった。中から出てきたのは、一枚の古い診断書。発行された病院の名前に見覚えはない。
『患者氏名:柏木 湊』
自分の名前がそこにあることに、湊は息を呑んだ。
『診断名:外傷性健忘症(逆行性健忘および前向性健忘)』
日付は、湊が十歳になった年の夏。診断書に添えられた医師の所見には、衝撃的な事実が記されていた。
『交通事故による頭部強打。事故以前の数年間の記憶の大部分が欠落。また、新しい記憶の定着にも障害が見られる可能性あり。家族の粘り強いサポートが不可欠……』
血の気が引いていくのが分かった。指先が冷たくなり、呼吸が浅くなる。事故?自分は、幼い頃に記憶を失っていた?
脳裏に、断片的な映像がフラッシュバックする。ブレーキの軋む音。母の悲鳴。ガラスの割れる音。そして、自分の手の中にあったはずの何かが、粉々に砕け散る感覚。
――あの時計だ。
母の日記にあった、自分が作り、そして壊してしまったという「宝物」の時計。家族三人で作った、思い出の時計。
全てのピースが、恐ろしいほどの速度で繋がっていく。父が無口で頑固になったのは、事故で息子に大怪我をさせ、記憶まで失わせてしまった自責の念からだったのかもしれない。母が日記に日常を細かく書き留めていたのは、いつか自分が記憶を取り戻す日のために、失われた時間を記録するためだったのだ。
そして父が、狂ったように修理し続けていたあの時計。それは、湊が忘れてしまった「幸せな家族の時間」そのものだった。壊れたのは時計だけではない。あの事故で、湊の記憶の文字盤も、家族の時間も、粉々に砕け散ってしまったのだ。
「お前には関係ない」
父のあの言葉が、全く違う意味を持って胸に突き刺さる。あれは拒絶ではなかった。辛い記憶を思い出させたくない、これ以上息子を苦しめたくないという、父の不器用で、あまりにも切ない愛情表現だったのだ。父はたった一人で、認知症という病と闘いながら、湊が忘れてしまった家族の時間を、守ろうとし続けていた。
湊は、その場に崩れ落ちた。嗚咽が止まらない。自分が長年、一方的に父を断罪し、遠ざけてきたことへの、身を切るような後悔が全身を貫いた。色褪せていたはずの家族の記憶が、熱い涙とともに、鮮やかな色を取り戻していくようだった。
第四章 新しい針が動き出す
リビングに戻ると、父は変わらずテーブルに向かっていた。しかしその手は止まり、虚空を見つめている。その背中は、以前見た時よりもずっと小さく、寂しげに見えた。湊はゆっくりと父の隣に座った。カチリ、と古い床が鳴る。
「父さん」
声をかけると、父は驚いたようにこちらを見た。その焦点の合わない目に、一瞬だけ、確かな光が宿ったように見えた。
「……ごめん。ごめんなさい」
湊の口から、自分でも驚くほど素直な言葉がこぼれ落ちた。それは、何十年という歳月を経て、ようやくたどり着いた謝罪だった。
父の目が、大きく見開かれる。皺の刻まれた目尻に、みるみるうちに涙の膜が張っていく。言葉にはならなかったが、その表情が全てを物語っていた。「やっと、わかってくれたか」と。
湊は、テーブルの上に散らばった真鍮の歯車を一つ、手に取った。ひんやりとした金属の感触が、不思議と温かく感じられる。
「これ、手伝うよ。一緒に、直そう」
湊は父の手をそっと取った。認知症の影響か、少し震えているその手は、かつて時計を組み上げていた職人のそれとは思えないほど、か弱かった。しかし、湊が手を重ねると、父は力なく握り返してきた。
失われた記憶が、完全に戻ることはないのかもしれない。事故の前の、父や母と笑い合った日々を、ありありと思い出すことはできないだろう。だが、湊は確信していた。家族の愛は、記憶の中にだけ存在するのではない。今、この指先に伝わる父の温もり。父が守り続けてきたこの時計の部品一つ一つに込められた想い。それこそが、何よりも確かな真実なのだと。
父と息子は、それから言葉少なげに、時計の部品を組み立て始めた。湊が設計図を読み解き、父がおぼつかない手つきで部品をはめていく。それは、かつて裏山に秘密基地を作ったという、湊が忘れてしまった日々の再現のようでもあった。
時計は、まだ完全には動かない。どこかの歯車が、まだうまく噛み合っていないのだろう。それでも、二人が最後の部品を組み上げた時、カチリ、と小さな、しかし確かな音が響いた。秒針が、ほんの一瞬だけ、未来へと進んだ。
それは、止まっていた柏木家の時間が、再びゆっくりと動き出した、始まりの音だった。
数週間後、湊は東京の仕事部屋に、新しい設計図を広げていた。それは、真鍮の代わりに温かみのある木材を使い、奇妙な記号の代わりに、家族のイニシャルを刻んだ、新しい置き時計のデザインだった。色褪せたクロノスの隣で、新しい時間を刻むための時計。失われた過去を嘆くのではなく、これから生まれる未来を、この手で築いていくために。窓から差し込む光が、設計図の上に描かれた「新しい針」を、優しく照らしていた。