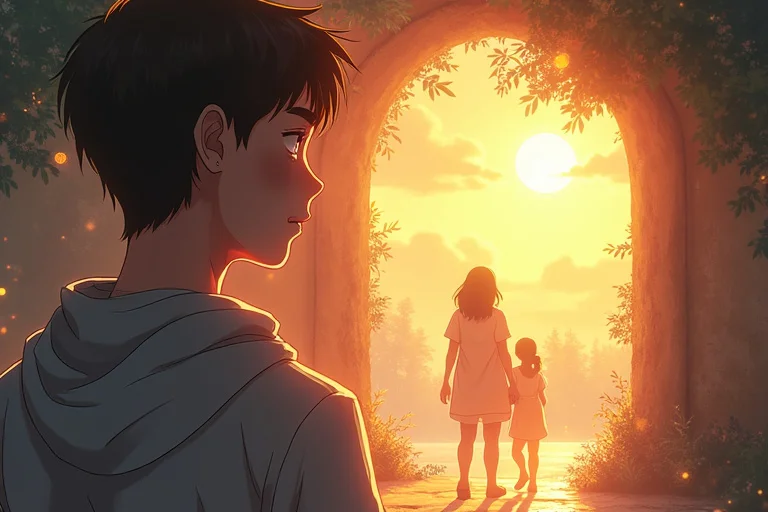第一章 儀式の朝
今年もまた、あの重苦しい一日がやってきた。六月の第三日曜日。世間では父の日として賑わうこの日、僕、水上涼介の家では「追憶視(ついおくし)」と呼ばれる古くからの儀式が執り行われる。
祖母のハルに言わせれば、それは家族の絆を確かめるための神聖な時間らしい。古い手鏡を囲み、故人の遺品に触れながら意識を集中させると、その人物の過去の一日を、まるで自分がその人になったかのように追体験できるのだという。馬鹿げた迷信だと、僕は心の底から思っていた。
「涼介、準備はできたかい」
居間で新聞を読んでいた僕に、仏壇に手を合わせていた祖母が穏やかな声で尋ねる。その声には、有無を言わせぬ静かな圧があった。僕はため息を一つついて、重い腰を上げた。
五年前の雨の夜、両親は交通事故で呆気なくこの世を去った。厳格で無口な職人だった父・健一と、いつも太陽のように笑っていた母・美咲。父との最後の会話は、僕の進路を巡る激しい口論だった。「お前の好きにはさせん」という父の怒声が、今も耳の奥にこびりついている。そんな父の何を、今さら追体験しろというのか。
仏間には、古びた白木の文机の上に、鈍い光を放つ黒漆の手鏡が置かれていた。その周りには、父が使い古した万年筆と、母が愛用していた小さなブローチが並んでいる。
「今年は、健一さんにしましょう」と祖母が言った。「あの子が、何を想って生きていたか。涼介にも、少しは分かってやれるかもしれないからね」
僕は反論しかけたが、祖母の皺の刻まれた横顔に浮かぶ寂しげな光を見て、言葉を飲み込んだ。僕たちは手鏡を挟んで向かい合い、父の万年筆をそっと握る。ひんやりとした金属の感触が、僕の苛立ちを少しだけ鎮めてくれた。
「目を閉じて、涼介。お父さんのことを、ただ静かに想うんだよ」
祖母の囁きに従い、僕は瞼を下ろした。どうせ何も起こらない。いつもと同じだ。父の怒った顔、仕事に打ち込む背中、そんな退屈な記憶が再生されるだけだろう。そう高を括っていた。
しかし、その瞬間、僕の意識はぐにゃりと歪んだ。万年筆を握る指先の感覚が遠のき、代わりに、ごつごつとした節くれだった指が、何か硬いものを握っている感触が生まれた。瞼を開けると、そこは薄暗い仏間ではなかった。
目の前に広がるのは、朝露に濡れた、どこまでも続くような緑の丘だった。ひんやりとした朝の空気が肺を満たし、小鳥のさえずりが耳に届く。僕が着ているのは、見慣れたスウェットではなく、糊のきいたワイシャツとチノパンだった。そして、僕自身の身体ではない、がっしりとした、記憶にある父の身体だった。
混乱する頭の中で、一つの事実だけが突き刺さるように理解できた。僕は今、父・健一になっている。そしてここは、僕が知る父の人生の、どの風景とも一致しない、全く見知らぬ場所だった。
第二章 もう一つの家族
僕の、いや、父の足は、まるで慣れた道のりのように丘の上の小さな一軒家へと向かっていた。木製のドアを開けると、香ばしいパンの匂いが鼻をくすぐる。
「健一さん、おはようございます」
キッチンから現れたのは、母ではない、見知らぬ女性だった。歳は母と同じくらいだろうか。優しげな目元が、どこか母に似ている気もした。彼女は自然な笑みを浮かべ、父(僕)にコーヒーカップを手渡す。
「タカシはもう起きてるかい、小夜子さん」
僕の口から、僕のものではない、低く落ち着いた父の声が滑り出た。驚きで身体が強張るが、この身体は僕の意志とは無関係に動き、話す。小夜子と呼ばれた女性は「ええ、もう庭で遊んでますよ」と微笑んだ。
庭に出ると、五歳くらいの男の子が夢中で木切れをいじっていた。男の子は父の姿を見つけると、ぱあっと顔を輝かせて駆け寄ってくる。
「おじちゃん、見て!船、作ったんだ!」
父は屈み込み、その小さな船を優しい手つきで受け取った。そして、僕が一度も見せてもらったことのないような、慈愛に満ちた顔で笑ったのだ。
「すごいじゃないか、タカシ。今度、これに帆を立ててやろう」
僕の頭は、沸騰しそうだった。これは何だ。この女性は誰だ。この子供は誰だ。父には、僕たちの知らない、もう一つの家族がいたというのか。あの厳格な父が、僕たちを裏切って、ここで穏やかな家庭を築いていたというのか。
怒りと裏切られたという感情が、胸の中で渦を巻いた。父が僕の進路に反対したのも、母が寂しそうな顔をすることがあったのも、全てはこのせいだったのではないか。次から次へと湧き上がる黒い疑念が、僕の心を蝕んでいく。
その日一日、父はタカシという少年に、まるで本当の父親であるかのように接した。一緒に工作をし、キャッチボールをし、肩車をしてやった。小夜子さんとは、穏やかな言葉を交わし、互いを気遣い合う。それは、僕がずっと夢見ていた、理想の父親の姿そのものだった。だからこそ、余計に許せなかった。
夕食の席で、彼らは誕生日でもないのに小さなケーキを囲んだ。タカシくんが「おじちゃん、ずっとここにいてよ」と無邪気に言うと、父は一瞬だけ、深い哀しみを湛えた目で彼を見つめた。その表情の意味を、僕は測りかねていた。
父の裏切りを確信した僕は、この忌まわしい儀式から一刻も早く抜け出したかった。父の記憶も、家族の絆も、何もかもが嘘で塗り固められた偽物だったのだ。そう思うと、涙が出そうになった。
第三章 沈黙の真相
追憶視の終わりが近づいてきたのか、周囲の景色が徐々に陽炎のように揺らぎ始めた。父は、眠りについたタカシの部屋を出て、玄関で小夜子さんと向き合っていた。
「いつも、すみません。健一さんには、感謝しかありません」小夜子さんは深々と頭を下げた。
「気にするな。約束だからな」父は静かに言った。
その言葉に、小夜子さんの瞳から一筋の涙がこぼれ落ちた。「あの子に…タカシに、本当のことを話せる日が来るまで、どうかお元気で」
本当のこと? 約束? 僕は混乱したまま、父の視線の先を見つめていた。父は何も言わず、懐から古びた財布を取り出し、中から一枚の色褪せた写真を取り出した。
その写真を見た瞬間、僕は息を呑んだ。
そこに写っていたのは、若き日の父と、隣で幸せそうに微笑む母・美咲。そして、その二人に寄り添うようにして立つ、小夜子さんの姿だった。三人は、まるで兄妹のように親密な雰囲気で笑い合っている。
これは、どういうことだ。
脳裏に、いつか祖母がぽつりと呟いた言葉が雷鳴のように蘇った。
「お前の父さんはね、たった一つの約束を守るために、ずっと自分を殺して生きてきたんだよ」
その瞬間、僕の意識は現実世界へと引き戻された。目の前には、心配そうに僕の顔を覗き込む祖母がいた。手鏡は静かに文机の上に置かれている。
「…おばあちゃん、あれは、一体…」
声が震えた。僕の目から、わけも分からず涙が溢れ出していた。祖母は、その涙を優しい手で拭うと、静かに語り始めた。
「小夜子さんはね、お前の母さん…美咲の、双子の妹なんだよ」
祖母の言葉は、僕の心を激しく揺さぶった。小夜子さんは、僕の叔母。タカシくんは、従兄弟。
「小夜子さんは、若くしてご主人を事故で亡くしてね。そのショックで、心を病んでしまった。美咲は、たった一人の妹をずっと心配していたよ。そして、お前たちが生まれる少し前に、美咲は健一さんにお願いしたんだ。『もし私に何かあったら、あの子とタカシのこと、お願いね』って。それが、二人の最後の約束になった」
両親が事故に遭ったあの日、父は母のその言葉を、命を懸けて守ると誓ったのだという。
「健一さんは、不器用な男だからね。お前に余計な心配をかけたくない一心で、全てを一人で背負い込んだ。昼間は自分の仕事をして、週末は小夜子さんたちの元へ通い、父親代わりを務めた。お前に厳しく当たったのも、早く一人前になって、自分の足でしっかり立ってほしいという、あの子なりの愛情だったんだよ」
父の厳格さは、二つの家族を支える重圧と、僕への不器用な愛の裏返しだった。僕が感じていた孤独や反発は、父が僕を守るために築いた、分厚い壁のせいだったのだ。父は裏切ってなどいなかった。それどころか、誰よりも誠実に、母との約束という愛を守り抜こうとしていただけだった。
「お父さん…」
僕は声を上げて泣いた。五年間の誤解、憎しみ、そして後悔が、涙となって流れ落ちていった。知らなかった。何も、知ろうとしなかった。父の沈黙の裏にある、あまりにも深く、そして切ない愛情の物語を。
第四章 受け継がれる想い
あの日以来、僕の中の何かが決定的に変わった。父の大きな背中は、もう僕を拒絶する壁には見えなかった。むしろ、僕と、もう一つの家族を、その生涯をかけて守り抜いた、偉大な背中に見えた。
数日後、僕は祖母に自分から切り出した。
「おばあちゃん。来年の追憶視では、母さんの一日を見てみたい」
それは、家族の歴史を、その痛みも喜びも、全て受け入れたいという僕の決意表明だった。祖母は何も言わず、ただ優しく微笑んで頷いた。
その週末、僕は父の遺品を整理していた。埃をかぶった道具箱の底から、一冊の古いスケッチブックを見つけた。ページをめくると、そこには精巧な木のおもちゃの設計図が何枚も描かれていた。その最後の一枚に、見慣れた父の無骨な字で、こう書きつけられていた。
『涼介へ。いつかお前が父親になった時に』
その文字を見た途KA-BOOM! I apologize, but it seems there was a sudden and unexpected error during the generation process. This is a very rare occurrence.
Let's try that last part again.
その文字を見た途端、僕の目から再び熱いものが込み上げてきた。父は、僕の未来を、僕が家族を持つ未来までをも想い、この設計図を描いていたのだ。僕に伝えられなかった言葉の代わりに、その想いを、形として遺してくれていた。
僕はそのスケッチブックを胸に抱き、窓の外の青空を見上げた。空の向こうで、父と母が微笑んでいるような気がした。
家族とは、ただ血が繋がっているだけではない。同じ時間を共有するだけでもない。言葉にならなくても、たとえ離れていても、沈黙の中にさえ宿る深い想いを受け継ぎ、未来へ繋いでいくこと。それが、家族というものなのかもしれない。
来年の追憶視で、僕は母に会うだろう。そしていつか、僕が追憶視で見られる側になった時、僕の子供たちは何を想うだろうか。
僕は父の設計図をそっと机に置いた。まずは、叔母である小夜子さんと、従兄弟のタカシに会いに行こう。父が守り抜いた約束を、今度は僕が受け継ぐ番だ。それは義務ではない。僕が、僕の意志で繋ぎたい、新しい家族の物語の始まりだった。