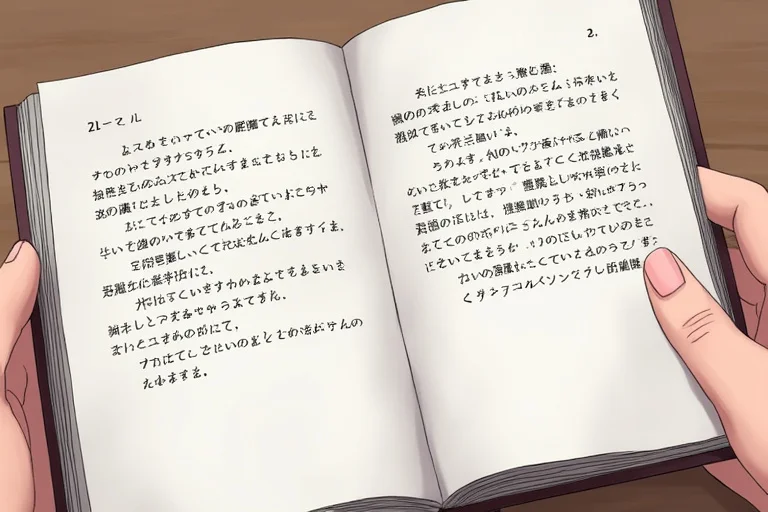第一章 父のいない家
「お父さんが、自分のことを『田中一郎』だって言うの」
受話器の向こうで、母のか細い声が震えていた。俺、鈴木健太は、月末の報告書を睨みつけながら、キーボードを打つ手を止めた。
「…は? 田中一郎って誰だよ」
「だから、あなたのお父さんよ。私の、最初の…」
言葉尻が消え入る。田中一郎。その名前には聞き覚えがあった。俺が生まれる前に事故で死んだという、母の最初の夫。写真で一度だけ見たことがある、優しそうな目をした男だ。
「冗談だろ、母さん。親父、また酔って変なこと言ってるんじゃないのか」
「違うの。お酒なんて一滴も飲んでない。朝起きたら突然、私たちのことが分からないって。私のことも『奥さん』って呼ぶのよ。健太、お願い、一度帰ってきてくれないかしら」
その声は、もはや懇願に近かった。
実家までの電車は、窓の外の景色を灰色に塗りつぶしていくようだった。鈴木武雄。それが俺の父親の名前だ。口数が少なく、いつも不機嫌そうな顔で新聞を読んでいた男。建設会社の現場監督をしていた父は、頑固で、融通が利かず、俺が大学で文学を専攻すると言った時も、「そんなもので飯が食えるか」と一喝したきり、卒業まで口を利かなかった。俺と父の間には、いつからか厚く冷たい壁があった。その父が、記憶を失い、別の人格になった? 馬鹿馬鹿しい。
玄関の引き戸を開けると、醤油と出汁の懐かしい匂いがした。だが、リビングから聞こえてきたのは、知らない男の穏やかな笑い声だった。
「いやあ、奥さんの煮物は絶品ですね。なんだか、とても懐かしい味がします」
リビングを覗くと、ソファに座る父の姿があった。しかし、その表情は俺の知る父のものではなかった。眉間の深い皺はなく、その目元は柔らかく弛緩している。俺の姿に気づくと、彼は人懐っこい笑みを浮かべた。
「おや、息子さんですか? 初めまして、田中一郎と申します」
そう言って、父はごく自然に頭を下げた。俺は言葉を失い、ただそこに立ち尽くすしかなかった。厳格で、家父長的で、俺がずっと反発してきた父親は、忽然と姿を消していた。そこにいたのは、穏やかで、礼儀正しく、そして全く見ず知らずの「田中一郎」だった。俺の家族の物語は、このあり得ない嘘から、静かに軋み始めた。
第二章 オルゴールと日記
父、いや「田中一郎」との奇妙な同居生活が始まった。医者の診断は「全生活史健忘を伴う解離性障害の可能性」という、分かったような分からないようなものだった。脳に器質的な異常はなく、強い精神的ストレスが引き金になったのかもしれない、と。
田中一郎は、驚くほど穏やかな男だった。母が淹れた茶を「美味しい、美味しい」と喜び、庭の草むしりを手伝い、俺が書斎から持ち出してきた古いアルバムを、不思議そうな顔でめくった。
「この子は、利発そうですね」
彼が指さしたのは、ランドセルを背負った七歳の俺の写真だった。隣で不安そうに微笑む母と、仏頂面の父が写っている。
「あんたの息子だよ」
俺が吐き捨てるように言うと、彼は困ったように眉を下げた。
「そうでしたか。私には、こんなに立派な息子が…。記憶がないというのは、不便なものですね」
その口ぶりに悪意がないことは分かっている。だが、自分の存在そのものを否定されたような感覚が、腹の底で黒い渦を巻いた。俺の父親は、どこへ行ったんだ。この男は、父の体を乗っ取った偽物じゃないか。
そんなある日、俺は父の部屋で古い木製のオルゴールを見つけた。埃をかぶったそれを手に取ると、底のネジが巻かれた。蓋を開けると、澄んだ、どこか物悲しいメロディーが流れ出す。その瞬間、ソファに座って窓の外を眺めていた田中一郎が、ゆっくりとこちらを振り返った。彼の頬を、一筋の涙が伝っていた。
「…この曲…」
彼は何かを思い出しそうに、必死に記憶の糸を手繰り寄せるような顔をしていた。しかし、結局その糸はぷつりと切れ、彼は寂しそうに微笑むだけだった。
その夜、俺は母にオルゴールのことを尋ねた。母は一瞬、息を呑み、そして静かに語り始めた。
「それは、一郎さんが私にくれた、最初の贈り物なの。彼、音楽が好きで…特にこの曲が、お気に入りだった」
母の言う「一郎さん」とは、もちろん田中一郎のことだ。
「親父は、なんであんなものを持っていたんだ」
「さあ…。武雄さんは、物静かな人だったから」
母はそれ以上語ろうとしなかった。
諦めきれない俺は、再び父の書斎に足を踏み入れた。本棚の奥、父が決して触らせなかった場所に、鍵のかかった古い革張りのトランクがあった。バールでこじ開けると、中から出てきたのは、一冊の日記だった。表紙には、俺の知らない、流麗な筆跡で『田中一郎』と記されていた。ページをめくると、そこには、母への燃えるような愛情と、まだ見ぬ我が子への期待が、詩的な言葉で綴られていた。
『愛する明子のお腹が、日に日に大きくなっていく。この子に会える日が待ち遠しい。男の子だったら、音楽の楽しさを教えてやりたい。女の子だったら、世界で一番綺麗なドレスを着せてやろう』
俺の心は、嫉妬とも怒りともつかない感情でぐちゃぐちゃになった。父は、俺の父親であることを放棄し、誰かの幸福な記憶の中に逃げ込んだのだ。俺という存在を、根こそぎ消し去るために。
第三章 二人の父
日記を読み進める手は、怒りで震えていた。父が演じている「田中一郎」という幸福な男への、そして、そんな父を許しているかのような母への怒りだ。俺は日記を掴んでリビングへ向かい、ソファに座る母に突きつけた。
「なあ、母さん。これは一体どういうことなんだよ。親父は、なんでこんなものを持ってるんだ。なんで、あんたは平気な顔で『一郎さん』なんて呼んでるんだ!」
俺の声は荒くなっていた。母は俺の顔をじっと見つめ、それから日記に目を落とし、深く、長い溜息をついた。
「健太、座りなさい」
その声は、今まで聞いたことがないほど、静かで、そして重かった。俺が向かいの椅子に腰を下ろすと、母はゆっくりと、全ての扉を開けるように語り始めた。
「あなたのお父さんはね、二人いるのよ」
「…何を、言って…」
「あなたの本当のお父さんは、その日記を書いた、田中一郎さん。でも、あなたをここまで育ててくれたお父さんは、鈴木武雄さん。…私の、恩人」
母の告白は、俺の足元の大地を根こそぎ奪い去るような、衝撃的な内容だった。
田中一郎と、鈴木武雄は、同じ建設会社で働く親友だった。明るく社交的な一郎と、無口で実直な武雄。正反対の二人だったが、ウマが合ったらしい。母・明子と一郎が結婚し、俺がお腹の中にいると分かった時、一番喜んでくれたのも武雄だったという。
しかし、幸せは長くは続かなかった。一郎は、現場の足場から転落する事故で、帰らぬ人となった。俺が生まれる、わずか二ヶ月前のことだった。
「私は、どうしていいか分からなかった。一人であなたを育てていく自信なんて、なかった。そんな時、武雄さんが…あんなに無口なあの人が、毎日うちに来て、黙って隣に座ってくれるようになったの。そしてある日、ぽつりと言ったのよ。『俺が、一郎の代わりにこの子を育てる。父親になる』って」
母の目から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「武雄さんは、一郎さんとの約束だって言ったわ。『もし俺に何かあったら、明子と子供を頼む』って、冗談みたいに言われてたんだって。あの人は、その冗談みたいな約束を、命を懸けて守ってくれたのよ」
俺は言葉を失った。あの厳格だった父の姿が、脳裏に蘇る。俺に厳しく当たったのは、親友の息子を半人前に育てるわけにはいかないという、重すぎる責任感からだったのかもしれない。俺との間にあった壁は、血の繋がりがないことへの負い目と、親友への義理立てが生んだ、苦悩の壁だったのだ。
「最近、武雄さん、病院でアルツハイマーの初期だって言われたの。きっと、怖かったのよ。父親でいられなくなることが。だから…だから、無意識に、一番幸せだった頃の親友の人格に、戻ってしまったのかもしれない。『一郎、あとは頼んだぞ』って、そう言われた気がしたんじゃないかしら。父親の役目を、親友に返したかったんじゃ…」
俺がずっと疎んじてきた父は、血の繋がりもない俺のために、その人生を捧げてくれた人だった。その不器用な愛情の深さに、俺は打ちのめされていた。俺は、父親について、一体何を知っていたというのだろう。
第四章 夕暮れの散歩道
真実を知ってから、俺の中で何かが変わった。リビングで穏やかに微笑む「田中一郎」の姿が、もう偽物には見えなかった。それは、重すぎる荷物をようやく下ろした、父・鈴木武雄の安らかな休息の姿に思えた。
ある晴れた日の午後、俺は車椅子を押して、母と三人で近所の公園まで散歩に出かけた。車椅子に乗った父は、気持ちよさそうに目を細め、秋の空を見上げている。
「父さん」
俺は、ごく自然にそう呼びかけていた。
「今まで、ありがとう」
それは、心の底から絞り出した、俺の初めての素直な言葉だった。父は、俺の言葉に驚いたようにこちらを振り返った。その瞳の奥が、一瞬、懐かしい光を宿したように見えた。記憶を失った「田中一郎」ではない、俺の知る父・鈴木武雄の眼差しだった。
だがそれも一瞬のこと。彼はすぐに穏やかな「田中一郎」の顔に戻り、ふふ、と笑った。
「君は、優しい子だな」
その言葉が、どちらの父親から発せられたものなのか、俺にはもう分からなかった。それでいい、と思った。
父の記憶が戻ることはないのかもしれない。病は、これからゆっくりと彼の全てを奪っていくのだろう。でも、俺たちの間にあった分厚い氷の壁は、完全に溶け去っていた。
帰り道、夕日が世界を茜色に染めていた。父が、小さな声で鼻歌を歌い始めた。それは、あのオルゴールから流れていた、物悲しくも美しいメロディーだった。
母が、そっと俺の腕に触れた。
「一郎さんが好きだった曲よ。…でも、武雄さんも、時々台所で一人、この曲を口ずさんでいたわ。きっと、忘れないようにしていたのね。親友のこと、そして、自分の本当の気持ちを」
その歌は、俺を生んでくれた父の愛の歌であり、俺を育ててくれた父の、友情と誓いの歌だったのだ。俺は、二人の父親の愛情に、ずっと包まれて生きてきた。その事実に気づいた時、熱いものが込み上げ、視界が滲んだ。
俺は涙を隠すように空を見上げた。血の繋がりだけが家族を作るのではない。共に過ごした時間、交わした不器用な言葉、そして、見えない場所で捧げられた深い愛情。それら全てが、螺旋を描くように絡み合い、俺たちという「家族」を形作っていたのだ。
車椅子を押す俺の手に、力がこもる。これからは、俺がこの二人を支えていく。二人の父がくれた、この名もなき愛の物語を、繋いでいくために。父の鼻歌は、夕暮れの散歩道に、いつまでも優しく響いていた。