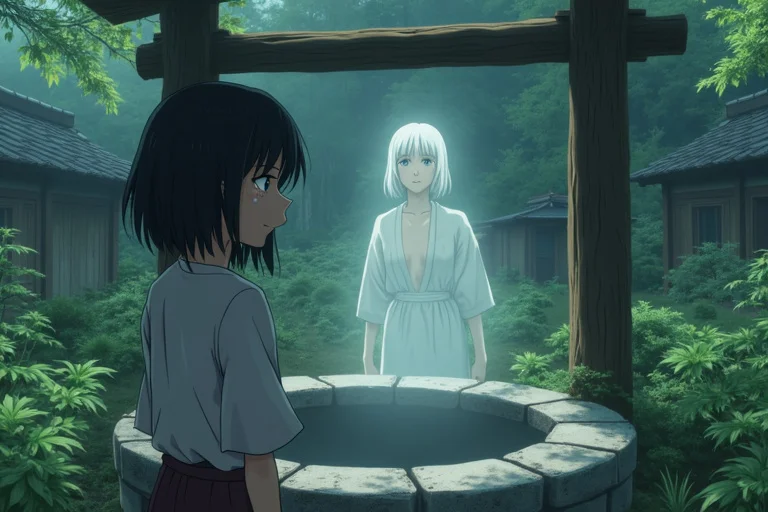第一章 色褪せる残像
微かな雨音で目が覚めた。窓の外は、夜明け前の薄墨色の空が広がっている。また、あの夢を見ていた。妹の陽菜が、泣きながら玄関の扉を開け、二度と振り返らずに去っていく夢。彼女の背中に触れようと手を伸ばした瞬間、指先が冷たいガラスに触れたような感覚と共に、意識が浮上した。
僕は、湊。ごく普通の大学生だ。ただ一つ、普通でない点を挙げるなら、家族に触れるたびに、彼らが共有する未来の断片を夢として見てしまうこと。そして、その夢が現実になるたび、僕の頭の中から、家族との過去の記憶が一つ、また一つと消えていく。
ゆっくりと身を起こし、パジャマの胸元をわずかに開く。そこからは、僕と家族とを結ぶ数本の『未来を紡ぐ糸』が生えていた。かつては真珠のような光沢を放っていたはずのそれは、今や色褪せた灰色の絹糸のように弱々しく、指で弾けば切れてしまいそうなほどに細くなっていた。特に、陽菜へと繋がる糸は、今朝また一段と透明度を増している。
リビングに下りると、香ばしいトーストの匂いが鼻をくすぐった。母さんがエプロン姿でキッチンに立ち、父さんは新聞を広げている。
「おはよう、湊」
母さんの声はいつも通り優しい。けれど、その声を聞いても、僕の胸には何の感情も湧き上がってこなかった。母さんが僕のために作ってくれた、幼い頃の好物は何だっただろうか。思い出そうとしても、頭の中には濃い霧がかかっているだけだ。
「ヒナはまだ寝てるのか」
父さんの低い声が響く。その声にも、昔のような威厳は感じられない。ただの音の連なりとして鼓膜を揺らすだけだった。
やがて、陽菜が不機嫌そうな顔でリビングに入ってきた。僕と目が合うと、気まずそうに逸らされる。僕たちは、いつからこんなにぎこちなくなってしまったのだろう。その答えを知っているはずの過去が、僕にはない。
首から提げたロケットペンダントの冷たさが、肌に染みた。銀製のそれは、代々受け継がれてきたもので、表面には家族の顔が精巧に彫られている。曽祖父、祖母、父、母、そして妹の陽菜。ただ、あるべきはずの僕の顔だけが、そこにはなかった。つるりとした空白のスペースが、まるで僕の存在そのものを否定しているかのようだった。
第二章 欠けた記憶のパズル
その日の夕食後、夢は現実となった。
「だから、私は東京の美大に行きたいって言ってるの!」
陽菜の叫び声が、食卓の空気を切り裂いた。
「馬鹿なことを言うな。地元の大学で十分だろう。お前にそんな才能があるとは思えん」
父さんの言葉は、刃物のように冷たかった。
売り言葉に買い言葉。口論はエスカレートし、ついに陽菜が椅子を蹴立てて叫んだ。
「もういい!こんな家、出て行ってやる!」
その言葉が放たれた瞬間、僕の頭を鋭い痛みが貫いた。
――陽菜が初めて自転車に乗れた日。何度も転んで擦りむいた膝をさすってやった時の、小さな手の温もり。
――二人でこっそり屋根裏に忍び込み、古い宝の地図を広げた時の、埃っぽい匂いと共犯者の笑み。
それらの記憶が、色鮮やかな砂絵が強風に吹かれて崩れ去るように、一瞬で消え失せた。目の前がぐらりと揺れ、僕はテーブルに手をついてかろうじて倒れるのを堪える。失われた記憶の代わりに流れ込んできたのは、陽菜の「現在」の痛みだった。彼女は家を出たいわけじゃない。ただ、誰かに自分の夢を信じてほしかっただけなのだ。その切実な叫びが、言葉を介さず僕の胸に突き刺さる。
「陽菜……」
声を絞り出したが、続く言葉が見つからなかった。慰めるための共通の思い出が、僕にはもうないのだから。陽菜は僕を一度だけ振り返ると、涙を浮かべたまま部屋に駆け込んでいった。残されたリビングには、重たい沈黙と、僕の胸でまた一段と細くなった糸の、か細い悲鳴だけが響いていた。
第三章 糸の囁き
家族の『糸』の劣化は、もう誰の目にも明らかだった。父と母の糸も、互いに弱々しく絡み合いながら、生命力を失ったように明滅している。このままでは、伝承の通り、僕たちの家族は社会の記録から、人々の記憶から消えてしまうかもしれない。
その恐怖に駆られ、僕は屋根裏部屋の探索を始めた。軋む階段を上り、ひやりとした空気が漂う薄暗い空間へ足を踏み入れる。古い家具に積もった埃の匂い。僕はいくつもの木箱を開け、ついに一冊の古びた日記帳を見つけ出した。それは、曾祖母のものだった。
インクが滲んだ美しい文字で、そこには『未来を紡ぐ糸』に関する記述があった。
『糸は絆であり、呪いでもある。定められた未来は、時に人を過去の記憶に縛り付ける鎖となる。真の絆とは、未来の約束ではなく、今この瞬間に生まれるもの』
ページをめくる指が震えた。さらに読み進めると、衝撃的な一文が目に飛び込んできた。
『我が一族には、時折、未来視と引き換えに過去を失う者が生まれる。その者は、古き鎖を断ち切り、家族を“解放”する役目を負う』
“解放”。その言葉が、僕の心に重くのしかかった。僕のこの能力は、呪いではなく、役目だというのか。ならば、僕が失ってきた数多の記憶は、家族を救うための代償だったというのだろうか。
第四章 最後の夢
僕は、決めた。この曖昧な恐怖の中で生き続けるのはもう終わりだ。たとえ最後の記憶を失うことになっても、家族を救うために、最も恐れていた選択をする。
その夜、僕はリビングに家族を集めた。父も、母も、自室に籠っていた陽菜も、僕のただならぬ様子を察して、黙ってソファに腰を下ろした。
「みんなに、話があるんだ」
僕は震える声で、自分の能力について、そして失われゆく記憶について、全てを打ち明けた。糸のこと、不吉な夢のこと、このままでは家族が消えてしまうかもしれないこと。誰もが言葉を失い、僕の胸元から伸びる色褪せた糸を呆然と見つめていた。
「お願いがある。みんなの手を、握らせてほしい」
沈黙が流れる。最初に動いたのは、陽菜だった。彼女はゆっくりと立ち上がり、僕の前に来ると、おずおずと手を差し出した。それに続くように、母が、そして父が、僕の手に自らの手を重ねた。
四人の手が一つになった瞬間、世界が白い光に包まれた。
視界に飛び込んできたのは、家族崩壊の最終楽章だった。誰もいなくなったがらんとした我が家。家具は埃をかぶり、壁にはひびが入っている。そして僕たちの胸から伸びた『糸』が、ぷつり、ぷつりと音を立てて切れ、光の粒子となって霧散していく。僕たちの名前が刻まれた表札の文字が薄れ、アルバムの写真から顔が消えていく。存在が希薄になる、その決定的な瞬間。
絶望的な光景。だが、その全てが消え去った後、完全な無が訪れたわけではなかった。何もなくなった荒野のような場所に、小さな、本当に小さな緑色の芽が、土を割って顔を出しているのが見えた。それは、か弱くも力強い、新しい始まりの光だった。
第五章 空白の肖像
夢から覚めた僕は、リビングの床に座り込んでいた。目の前には、父と母、そして陽菜がいる。知っている顔だ。だが、彼らと過ごした日々の温もり、交わした言葉の響き、共に泣き、笑った記憶の全てが、僕の中から完全に消え去っていた。頭の中は、静かで、がらんどうで、まるで生まれたての赤ん坊のようだった。
僕の胸で弱々しく明滅していた『糸』は、ほとんど見えなくなっていた。家族の糸も同じだった。僕たちは、もう過去にも未来にも繋がれていない。
不思議と、絶望はなかった。記憶というフィルターを失った僕の目には、初めて見るかのように、彼らの「今」の姿が鮮明に映っていた。将来への不安と希望を瞳に宿す妹。夫と子供たちを案ずる母の、目元の深い皺。家族を支える重圧に、わずかに肩を落とす父。彼らは、僕が「思い出」の中に閉じ込めていた偶像ではなく、今を必死に生きる、一人の人間だった。
僕は首からロケットペンダントを外した。自分の顔がなかった、あの空白のスペース。そこに映り込むのは、不安げに僕を見つめる三人の顔。
僕は、ゆっくりと微笑んだ。まるで初めて会う人に挨拶するように、真っ直ぐに彼らの目を見て言った。
「はじめまして」
第六章 新しい糸を紡ぐ
その一言に、家族は息を呑んだ。しかし、僕の澄み切った瞳の中に、過去への執着も未来への不安もない、ただ純粋な「現在」だけが映っているのを見て、何かを悟ったようだった。父が、母が、陽菜が、僕という記憶のアンカーを失ったことで、彼ら自身もまた、「親」や「妹」という過去から続く役割から解放されたのだ。
最初に口を開いたのは、父だった。
「……俺は、聡。お前の父さんだ。本当は、もっとお前たちと話がしたかった」
次に母が、涙を堪えながら続けた。
「遥よ。あなたの母。あなたの好きなものは、これから一緒に見つけていきましょうね」
そして陽菜が、僕の隣に座り、震える声で言った。
「私は陽菜。……お兄ちゃんの、妹。私、絵を描くのが好きなの。今度、私の絵を見てくれる?」
それは、思い出話ではなかった。未来の約束でもなかった。ただ、今の自分を語り、相手を知ろうとする、純粋な対話だった。僕たちの間には、もう『未来を紡ぐ糸』は存在しない。その代わりに、目には見えない、もっと温かく、しなやかで、自由な何かが、ゆっくりと生まれ始めていた。それは、過去に縛られず、定められた未来にも囚われない、今この瞬間を共有することから生まれる、新しい形の「絆」だった。
もう一度、ロケットペンダントを開く。かつて色褪せた未来を映し出した底は、今は鏡のように磨かれ、僕たち四人の、少しぎこちないけれど、確かな希望を宿した笑顔を鮮やかに映し出していた。空白だったはずのスペースに、初めて僕の顔が、家族と共にあった。
僕たちは、多くの記憶を失った。しかし、これから始まる無数の「今日」を、真っ白なキャンバスに描くように、共に創造していけるのだ。夜明けの光が差し込むリビングで、僕たちの新しい物語が、静かに始まった。