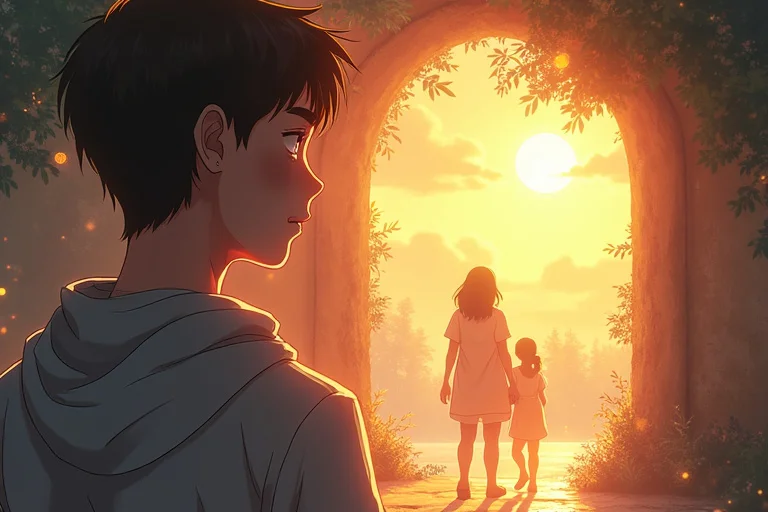第一章 失われる色彩
僕の左手が、世界から消え始めたのは、妹のミオが笑わなくなった日のことだった。
この街、セレスタは「家族の絆エネルギー」で満ちている。街灯の柔らかな光も、市場に並ぶ果実の瑞々しさも、全ては家族が互いを思いやる心から生まれるエネルギーによって支えられていた。人々は笑顔を交わし、感謝を口にすることで世界を輝かせていた。それが、当たり前の日常だった。
「お兄ちゃん、もう、いいの」
食卓で、ミオがぽつりと呟いた。その瞳からは、子供らしい無邪気な光が消え、まるで古びたガラス玉のように虚ろだった。父が冗談を言っても、母が好物を作っても、彼女の唇は固く結ばれたまま。その瞬間、僕の左手の小指の先が、すっと淡い光に溶けていくのを確かに感じた。冷たい風が通り抜けるような、奇妙な喪失感。
翌日には薬指が、その次の日には左手全体が、まるで水彩画を滲ませたように輪郭を失っていった。触れているはずのカップの熱を感じない。握ったはずのペンの重みがない。そして何より恐ろしいのは、母が僕の左手に気づかず、その空間に皿を置こうとしたことだった。僕の左手は、世界から認識されなくなりつつあった。
街の輝きも、呼応するように翳り始めていた。街灯は頼りなく瞬き、作物の育ちは鈍くなった。人々の顔からも笑顔が消え、互いを疑うような視線が交錯する。世界中から「家族の笑顔」が急速に失われているのだと、誰もが肌で感じていた。
不安に駆られた僕は、祖父の遺品が収められた屋根裏部屋の古い木箱を開けた。その中に、埃をかぶった一つの砂時計が眠っていた。「共鳴する砂時計」と祖父が呼んでいたものだ。手に取ると、ひんやりとした黒曜石の感触が伝わってくる。だが、くびれの部分で、琥珀色の砂は一粒たりとも動かず、まるで時間が凍りついたように静止していた。
第二章 停止した時間
家を出る決意をしたのは、自分の左腕が肩の近くまで透明になった朝だった。このままでは、ミオを、家族を、そして自分自身をも失ってしまう。僕は静止した砂時計をカバンにしまい、夜明け前の冷たい空気の中へと踏み出した。
活気を失った街は、まるで色褪せた写真のようだった。かつては笑い声とパンの焼ける香ばしい匂いに満ちていた大通りも、今は乾いた風が砂埃を巻き上げるばかり。すれ違う人々は皆、俯き、自分の家族のことで精一杯なのだろう、他人のことなど気にも留めない。絆エネルギーの低下は、人々の心から余裕を奪っていた。
そんな灰色の街の路地裏で、僕は一人の少女と出会った。名をリナと名乗った彼女は、汚れたローブを纏い、獣のように鋭い目で僕を警戒していた。彼女は家族を流行り病で亡くし、たった一人で生きてきたという。
「家族なんて、脆いものよ。信じたって、いつかはいなくなる」
リナは吐き捨てるように言った。僕が自分の腕が透明になっている理由を話しても、彼女は鼻で笑うだけだった。
「そんなもので消えるなら、とっくに消えてた方がマシだったかもね」
その夜、僕たちは廃墟となった建物で火を囲んだ。リナが分け与えてくれた硬いパンを齧りながら、僕は透明になった自分の腕を見つめる。存在が希薄になっていく感覚は、絶え間ない恐怖となって心を蝕んでいた。このままではいけない。何か、何かを変えなければ。その焦りだけが、僕を突き動かしていた。
第三章 共鳴の兆し
旅を続ける中で、僕たちは寂れた村に立ち寄った。そこで出会った老婆が、古い伝説を語ってくれた。
「昔々、わしらの祖先よりもっと昔。この世界で最初に体が透明になった男がおったそうな」
老婆は皺だらけの手で、暖炉の火をかき混ぜながら続けた。
「その男は、誰よりも家族を愛していた。じゃが、ある時、その家族に裏切られ、全てを奪われた。絶望した男は、家族という温かい繋がりそのものを憎むようになり、世界から絆を消し去ろうとした…」
その男は「初代」と呼ばれ、世界のどこかで今も生きているのだという。
その夜、リナが熱を出した。小さな体は火のように熱く、苦しげな息を繰り返している。僕は彼女のそばにつき、濡らした布で額を冷やし続けた。薬草を探しに夜の森を駆け、拙い手つきで煎じて飲ませる。
「…なんで…」
朦朧とした意識の中で、リナが呟いた。
「なんで、見ず知らずの私に、そこまでするの…?」
「君が、一人で苦しんでいるからだ」
僕がそう答えると、リナは驚いたように目を見開き、そして静かに涙を流した。それは、彼女が僕の前で初めて見せた、弱さの欠片だった。
夜が明け、リナの熱が少し引いた頃、僕はふとカバンの中の砂時計に目をやった。
信じられない光景だった。
完全に静止していたはずの砂が、たった一粒だけ、ぽつり、と音もなく下のガラスに移っていたのだ。
血の繋がりはない。家族でもない。それでも、リナを思いやる僕の心が、リナが僕に心を開いた一瞬が、凍りついた時間を、ほんの少しだけ動かしたのだった。
第四章 ゼロの独白
僕たちの前に「初代」が現れたのは、世界の絆エネルギーを制御する中央タワーの最上階だった。男は自らを「ゼロ」と名乗った。彼は若々しくも見え、老人のようにも見えた。その体は完全な透明ではなく、まるで揺らめく陽炎のように存在が不確かだった。
「来たか、新たな消えゆく者よ」
ゼロの声は、感情というものが一切抜け落ちていた。彼はタワーのシステムを掌握し、世界中から僅かに残った絆エネルギーを吸い上げ、自らの力に変えていたのだ。
「無駄なことを。家族などという幻想にいつまでしがみつく?」
ゼロは語り始めた。かつて彼が、どれほど家族を愛し、信じていたか。しかし、些細な誤解から、彼は家族に「裏切り者」の烙印を押され、家を追われた。助けを求めても、誰も彼を信じなかった。愛が深かった分、絶望もまた深かった。
「絆とは、互いを縛り付ける呪いだ。期待し、裏切られ、傷つけ合うためのシステムに過ぎん。ならば、私が全てを終わらせる。全ての人間が、他者に依存しない『個』として完結する世界こそが、真の救済なのだ」
ゼロが手をかざすと、凄まじいエネルギーの奔流が僕を襲った。体が胸のあたりまで一気に透明になり、立っていることすらままならない。意識が、遠のいていく。
第五章 砂時計が落ちる時
僕が倒れそうになったその時、リナが僕の前に立ちはだかった。
「ふざけないで!」
彼女の震える声が、静寂を切り裂いた。
「この人は、血も繋がらない、ただの通りすがりの私を助けてくれた!命がけで看病してくれた!それが絆じゃないっていうの!?」
リナの叫びに呼応するように、僕のカバンから溢れ出した光の中で、砂時計が激しく震えた。止まっていた砂が、堰を切ったように、サラサラと音を立てて流れ始める。それは、僕とリナとの間に生まれた絆。旅の途中で出会った人々との、ささやかな心の交流。それら全てが、凍てついた時間を溶かしていく。
僕はゼロの瞳の奥にある、深い、深い孤独を見た。彼は敵じゃない。誰にも理解されなかった、たった一人の子供だ。
僕は、残った力で立ち上がった。
「あなたの痛みは、分かってもらえなかった孤独だ。愛した分だけ、信じてもらえなかったことが辛かったんだ」
僕は彼を倒すのではなく、その絶望を受け止めようと決めた。
「でも、家族は血だけじゃない。あなたのその絶望ごと、俺が受け止める。俺が、あなたの家族になる」
透明になった腕を、僕はゆっくりと伸ばした。物理的な温もりはない。しかし、僕の魂が、彼の凍てついた魂に触れようとしていた。見えない腕で、僕はゼロの孤独を、そっと抱きしめた。
第六章 新しい世界の法則
僕の思いがゼロに届いた瞬間、砂時計の砂が、全て落ち切った。
タワーの頂点から放たれたのは、破壊のエネルギーではなかった。世界を包み込むような、どこまでも温かく、優しい光の奔流だった。それは血縁という枠を超えた、「思いやりの絆エネルギー」。ゼロの足元から、枯れていたはずの蔦が芽吹き、花を咲かせる。彼の頬を、何十年ぶりかの涙が伝った。
気がつくと、僕の体の透明化は止まっていた。しかし、完全に元に戻ることはなかった。透明になった左腕や胸の一部は、そのままだった。だが、それはもはや喪失の証ではなかった。その透明な部分を通して、僕は世界中の孤独な人々の心の声を、微かに感じ取れるようになっていた。それは、他者の痛みと繋がり、見えない絆を結ぶための、新しい能力だった。
ゼロは消えなかった。憎しみが癒された彼は、静かに微笑むと、光の中に溶け込み、世界を見守る存在となった。
街には、再び光が戻った。以前のような画一的な強い光ではない。様々な色の、多様な繋がりを認める、より優しく、柔らかな光だった。家の窓から、ミオの明るい笑い声が聞こえてきた。その笑顔は、もう僕の体を透明にすることはなかった。
第七章 見えない糸を紡ぐ者
僕とリナは、再び旅に出た。行き先は決まっていない。僕の透明な手が、か細い心の声を拾う方へ。
ある街では、些細なことで喧嘩した親子の間に立ち、互いの本当の気持ちを見えない糸で繋いだ。ある村では、孤独に震える老人のそばに座り、リナが淹れた温かいお茶を三人で飲んだ。
僕の体は、失ったのではない。得たのだ。血の繋がりだけが家族ではない。互いを思いやる心さえあれば、人は誰とでも家族になれる。僕の透明な体は、その新しい世界の法則の、生きる証となった。
空を見上げる。雲間から差す光が、僕の透明な左手を通り抜け、地面に柔らかな影を落とす。リナが隣で笑っている。その笑顔が、僕の心を温かいエネルギーで満たしていく。
世界はまだ、悲しみや孤独で満ちているかもしれない。
それでも、僕たちは歩き続ける。この世界に張り巡らされた、無数の見えない糸を、一つ一つ丁寧に紡いでいくために。