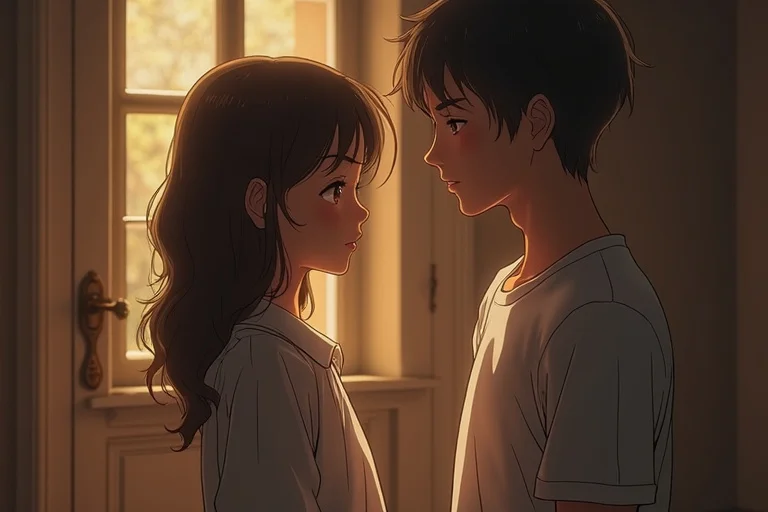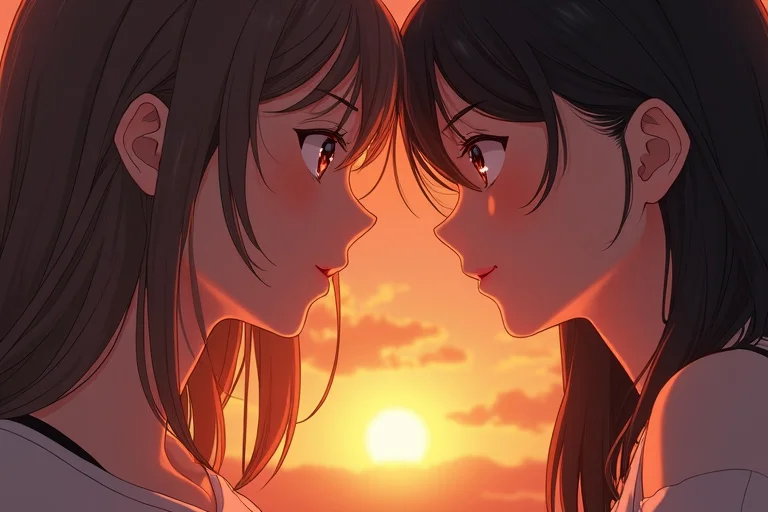第一章 硝子細工の食卓
夕暮れの満員電車は、情報の掃き溜めだ。
香坂遥は吊り革に指を食い込ませ、濁った空気を肺の半分だけで濾過する。右隣のサラリーマンからは、湿気たタバコと、胃壁を溶かすような焦燥感を含んだ脂汗の臭い。向かいの老婦人からは、防虫剤の樟脳と、孫に与える安い飴玉の甘ったるい香料が混じり合い、老いと愛着の気配となって漂ってくる。
言葉よりも雄弁な体臭の奔流。遥の鋭敏すぎる嗅覚にとって、他人の人生は吸い込むだけで脳を侵食する暴力的な粒子だ。
だが、最寄駅を降り、自宅のドアノブを回した瞬間、世界は唐突に回路を断たれる。
「お帰り、遥」
リビングから覗く母の笑顔は、左右対称に整いすぎていた。そこには夕飯の出汁の香りも、パート先で染みついた疲労の酸味も、あるいは息子を迎える母親特有の、日向のような温もりも存在しない。
ただ、新品のビニールクロスのような、無機質で冷ややかな「膜」の感触だけが、遥の嗅覚を拒絶するように張り詰めている。
「……ただいま」
遥は息を潜めて靴を脱ぐ。この家には生活臭がないのではない。父からも、母からも、妹からも、遥が本来感じるべき「家族の匂い」だけが、まるで外科手術で神経ごと切除されたかのように欠落しているのだ。
食卓には、色彩だけが鮮やかな料理が並ぶ。父がビールを注ぎ、妹が学校での些細な事件をさえずる。完璧な団欒の風景。しかし遥にとって、そこは真空のガラスケースの中に等しい。
「そういえば、これ。掃除してたら出てきたの」
母が目を細め、テーブルの上に白い欠片を置いた。
貝殻を繋ぎ合わせた、歪なブレスレットだ。
「懐かしいな。遥が十歳の時の夏休み、伊豆で作ったやつだ」
父が指先で愛おしそうにそれを撫でる。
「あの夏は本当に楽しかったわね。毎日海に潜って、夜は花火をして……この貝殻からは、まだあの時の潮風の匂いがするみたい」
妹も頷く。「ほんとだ。お日様の匂いもする」
遥は箸を置き、ブレスレットを手に取った。
指先に伝わるのは、石灰質の乾いた冷たさのみ。
鼻を近づける。深く、横隔膜が痛むほど吸い込む。
……何もしない。
潮騒も、夏の熱気も、家族が共有しているはずの記憶の残滓さえも。そこにあるのは、研磨されたガラス玉のような、つるりとした絶望的な「無臭」だけだった。
(まただ。僕だけが、その世界から締め出されている)
脳裏には、家族と同じ「楽しかった夏」の映像がある。青い海、入道雲、弾ける笑顔。だが、その記憶には匂いがない。誰かが描いた精巧な油絵を、分厚いアクリル板越しに眺めているような隔絶感。
遥はこみ上げる吐き気を嚥下し、口角を引き上げた。
「そうだね。懐かしい匂いだ」
嘘をついた瞬間、家族を包む「透明な膜」が、微かに、しかし確実に分厚くなったのを、遥の鼻だけが残酷に感じ取っていた。
第二章 腐臭と真空
違和感の正体を探るため、遥は週末を利用して、記憶の中にある伊豆の海岸へ足を運んだ。
海は、記憶の通りに青く凪いでいた。
観光客が纏う日焼け止めのココナッツ臭、焼きとうもろこしの焦げた醤油の匂い、そして生臭くも力強い潮風が、夏の熱気と共に押し寄せてくる。
ここは、匂いに満ちた世界だ。
遥はポケットから、例の貝殻を取り出した。
やはり、無臭だ。周囲の濃厚な磯の香りが、このブレスレットの周囲だけスッと避けて通るような、奇妙な真空地帯。
「おかしい……」
遥は記憶の地図を頼りに、家族と泊まったはずの民宿を目指して歩いた。
記憶の中では、ここで毎晩のようにスイカを食べ、縁側で花火をしたはずだ。その甘い煙の匂いさえ、脳裏には映像として焼き付いている。
だが、その場所へ辿り着いた瞬間、遥の足が止まった。
「……え?」
看板の文字を読むまでもない。遥の鼻が、脳よりも早く「異常」を検知して警鐘を鳴らしたからだ。
湿ったカビの胞子。床下の腐った木材。ネズミの糞尿。
それは数年で醸成されるものではない。十年以上、人の営みが絶えた廃屋特有の、濃密な死の気配。
蔦に覆われた建物を見上げながら、遥は眩暈を覚えた。
(僕たちが泊まったのは、十年前だぞ……?)
記憶の中の「鮮やかな夏」と、目の前の「朽ちた現実」。
その乖離が極限に達した時、脳の奥で、生々しい肉が裂けるような音がした。
美しい夏の映像に、強烈なノイズが走る。
鼻腔を突いたのは、潮風ではない。
もっと鋭利で、鼻の粘膜を焼き切るような化学物質の臭い。
ガソリンだ。
それも、古びた機械油と混じり合った、不快で危険な揮発臭。
遥の足は、意思とは無関係に動き出していた。
民宿の裏手、海へと続く細い坂道へ。記憶にはない道だ。だが、匂いが導いている。
甘く、そして嘔吐感を催すほどに人工的な「無臭の膜」の匂いが、その坂道の先から漂ってきている。その奥底から漏れ出しているのは、錆びた鉄と、焦げたゴム、そして消毒液のツンとする刺激臭。
坂を下りきった先は、ガードレールのない急カーブの崖道だった。
遥はその場に膝をついた。
アスファルトの裂け目に、誰かが手向けたであろう花束の痕跡があった。風化し、セロファンだけが残っている。
遥の嗅覚が、制御不能なフラッシュバックを引き起こす。
波の音ではない。金属がひしゃげる轟音と、鼓膜をつんざく悲鳴。
視界が暗転し、代わりに匂いが色彩を持って暴れ回る。
ガソリンの虹色の油膜。焼け焦げたタイヤの黒煙。そして、嗅いではいけない、鉄錆のような、生暖かい血の赤。
「う、ぐ……」
遥は胃液を吐き出した。
手首のブレスレットが、アスファルトの上でカチャリと虚しい音を立てる。
その瞬間、遥を世界から隔絶していた「無臭の膜」に亀裂が入った。
裂け目から溢れ出したのは、家族の絆などという美しいものではない。
もっとドロドロとした、肺が焼けるような、強烈な「後悔」と「恐怖」の汚臭だった。
第三章 空白の正体
帰宅した遥を待っていたのは、死のような静寂だった。
リビングの電気は消され、薄暗い部屋に、父と母、そして妹が座っている。
彼らはもう、笑っていなかった。
そして、あの無機質な「膜」も消え失せていた。
代わりに遥の鼻を襲ったのは、腐った果実がさらに発酵したような、濃厚な罪悪感の臭気だ。
「……全部、思い出したよ」
遥の声は震え、掠れていた。
「あの夏、僕たちは楽しく旅行なんてしてなかった。あの崖道で……」
母の肩が跳ねた。
「車が横転して、僕は……死にかけたんだね?」
言葉にした瞬間、記憶の空白が汚水のような勢いで埋まっていく。
集中治療室の冷たい空調。何十種類もの薬剤の臭い。電子音の不規則なリズム。
そして、ベッドの脇で泣き崩れる両親から発せられていた、汗と涙と、排泄物のような絶望が混じった、強烈な体臭。
医者の宣告。諦めの気配。
そのあまりの苦痛と恐怖に、彼らの精神は耐えきれなかったのだ。
『辛すぎる現実』を『空白』として処理し、その上に『楽しかった夏』という、どこかの絵本から切り取ったような偽の記憶を上書きした。
家族全員が、無意識のうちに共犯者となって。
遥が感じていた「無臭」は、彼らが必死に隠そうとした、血と膿の臭いを封じ込めるための蓋だった。
「ぁ……あぁ……」
母が崩れ落ちた。
言葉はない。ただ、喉の奥から絞り出される獣のような嗚咽だけが響く。
母の身体から、一気に汗が吹き出した。それは香水で誤魔化していたような整った香りではない。怯え、震え、自分を責めさいなむ、酸っぱく重苦しい人間の臭いだ。
父が顔を覆い、妹が母の背中にしがみついて泣き叫ぶ。
遥には見えた。彼らの毛穴という毛穴から立ち上る、どす黒い霧のような「トラウマ」の匂いを。
「ごめんなさい、ごめんなさい……遥、ごめんなさい……!」
母が床に額を擦り付け、錯乱したように繰り返す。
楽しかった夏などない。
あったのは、瀕死の息子を前にして、狂ってしまいそうになる心を必死で繋ぎ止めるための、あまりにも痛々しい妄想だけ。
遥は鼻を押さえた。
臭い。あまりにも臭くて、苦しい。
だが、それは紛れもなく、彼らが遥を失うまいとして足掻いた、愛の腐臭だった。
最終章 新しい呼吸
真実は、ナイフのように鋭く、そして鼻が曲がるほどに臭い。
だが、その痛みと悪臭こそが、遥がずっと求め続けていた「生きた手触り」だった。
遥は、床にうずくまる家族の前に歩み寄った。
彼らが纏っていた防護服のような「無臭の膜」は、もう完全に剥がれ落ちている。
そこにあるのは、後悔という名の苦い胆汁の臭いと、恐怖という名の冷たい鉄の臭い、そして涙の塩辛い匂いが混ざり合った、人間臭いカオスだ。
遥は、自分の手首にある白い貝殻のブレスレットを外した。
これは、偽の記憶の象徴だ。無臭の石ころだ。
だが、遥はそれを強く握りしめた。
貝殻の尖った端が掌に食い込み、痛みと共に、遥自身の匂いもそこに移っていく。
(変えるんじゃない。受け入れるんだ)
魔法などない。過去は書き換わらない。あの事故も、みんなが抱えた地獄のような恐怖も、消すことはできない。
遥は深く息を吸い込んだ。
家族が放つ、思わず顔を背けたくなるような痛々しい臭気を、全て自身の肺に取り込むように。
肺胞の一つ一つに、父の怯えを、母の懺悔を、妹の悲しみを染み渡らせる。
それは吐き気を催すほどに苦い。けれど、不思議と温かかった。
無機質な真空の中で窒息していた十年間より、この汚濁に塗れた空気の方が、遥かに息ができる。
「母さん」
遥はしゃがみ込み、震える母の手にブレスレットを握らせた。
「……臭うだろう」
母が涙で濡れた顔を上げ、おそるおそる手の中の貝殻に視線を落とす。
「僕たちの、本当の匂いだ」
母は震える手で、貝殻を鼻に近づけた。
そこに、かつての偽りの潮風はない。
遥の手汗と、母自身の涙と、そして床の埃の匂い。
泥臭く、生臭く、決して美しいとは言えない現実の匂い。
けれど母の瞳から、ボロボロと新たな涙が溢れ出した。
「……ええ。……ええ、そうね」
母がブレスレットを胸に抱きしめる。
「遥の……生きてる匂いがするわ」
妹が鼻をすすりながら、遥の袖を掴んだ。父も、充血した目で遥を見つめ、安堵の息を吐き出した。その呼気さえも、酒と疲労の匂いがしたが、もう遥は息を止めなかった。
遥は初めて、この家の空気を「美味しい」と感じた。
無菌室のような疎外感はもうない。
ここには、痛みがあり、過去があり、そして傷口を舐め合いながらも未来へと続く、血の通った匂いが充満している。
「ただいま」
遥が言うと、母はくしゃくしゃになった顔で、子供のように泣きながら頷いた。
「お帰りなさい、遥」
リビングを満たすのは、すっかり冷え切った煮物の匂いと、家族四人がそれぞれの傷と体臭を晒して寄り添う、複雑で、何よりも愛おしい「生」の匂いだった。
遥は大きく深呼吸をした。
その濃厚な香りを、二度と忘れないように、魂の深淵へと刻み込んだ。