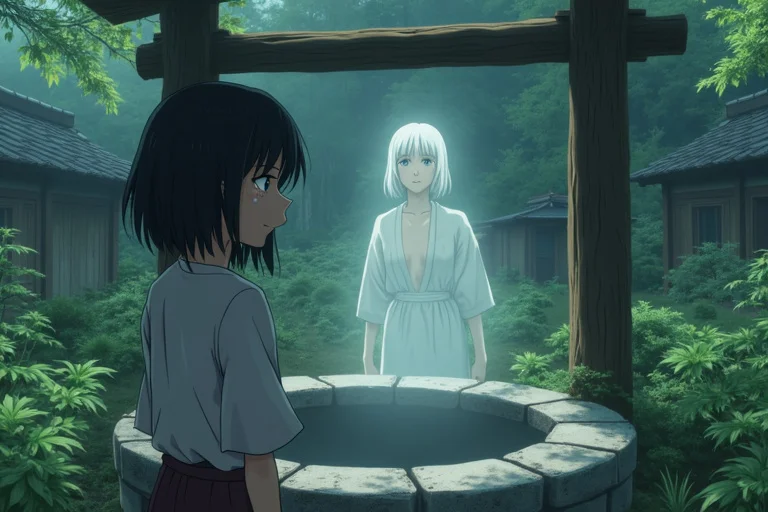第一章 影を纏う朝
床に落ちた自分の影が、まるで他人のように揺らめいて見える。毎月一度、満月の日に訪れるこの朝を、俺――宮沢涼介は心の底から疎ましく思っていた。我が家に代々伝わるという、馬鹿げた儀式。「影継ぎ」の日だ。
リビングに集まった家族四人。無口な父・雄一郎、穏やかな母・咲子、そして快活な高校生の妹・美咲。テーブルの中央には、先祖代々のものらしい古びた木箱が置かれている。中には、四つの小さな黒曜石。それぞれの石には、俺たちの名前が彫り込まれている。これを箱の中でかき混ぜ、見ずに一つ取り出す。引き当てた石に刻まれた人物の「影」を、日の出から次の日の出まで、一日だけ纏って過ごす。それが「影継ぎ」の全てだった。
「さあ、涼介からどうぞ」
母の咲子が、微笑みながら箱を差し出す。その声はいつもと変わらないが、彼女の足元に伸びる影は、普段のしなやかなそれとは違い、どこか無骨で、落ち着きがない。昨夜のうちに、父と母の間で影の交換は済んでいるのだろう。俺は舌打ちしたいのを堪え、無造作に手を入れた。ひんやりとした石の感触。指先に触れた一つをつまみ上げる。
最悪だ。石に刻まれていたのは「雄一郎」の三文字だった。
俺が最も引きたくなかった、父親の影。
俺が石をテーブルに置くと、父がゆっくりと立ち上がった。父の影が、まるで生き物のように床を滑り、俺の足元へと吸い寄せられる。同時に、俺自身の、どこか頼りなく伸びた影が剥がれ、父の方へと移動していく。奇妙な浮遊感とめまい。足元がぐらつき、世界が歪む。数秒後、視界が安定した時には、すべてが終わっていた。
俺の足元には、濃く、揺るぎない、まるで岩のような影が根を下ろしていた。父の影だ。
途端に、背筋に一本の鋼鉄が通されたかのような感覚に襲われる。猫背気味だった姿勢が、意思とは無関係にしゃんと伸びた。両肩に、ずしりとした重みがのしかかる。それは物理的な重さではない。長年かけて染み付いた、責任という名の見えない鎧。指先が微かに震え、何か硬いものを握りしめたい衝動に駆られた。新聞の、ざらついた紙の感触が恋しい。そんな、自分のものではないはずの感覚が、体の内側から湧き上がってくる。
「……行ってくる」
口から出たのは、自分でも驚くほど低く、抑揚のない声だった。まるで父が乗り移ったかのような声色に、向かいに座る美咲がくすくすと笑う。彼女は母の影を引いたらしく、いつもより少しおしとやかな仕草でコーヒーカップを傾けていた。そして、俺の影を纏った父は、ソファに深々と腰掛け、どこか遠い目をして窓の外を眺めている。その姿は、いつもよりずっと若く、頼りなげに見えた。
俺は玄関で革靴に足を入れる。紐を結ぶ指の動きが、驚くほど手際がいい。いつもはスニーカーしか履かないというのに。扉を開けると、朝の光が目に染みた。振り返らずに家を出る。父の影は、まるで俺が本当の雄一郎であるかのように、堂々とアスファルトの上にその輪郭を映し出していた。忌々しい一日が、また始まる。
第二章 父という名の枷
父の影は、重たい枷だった。大学の講義中も、俺の意識は常に背後にある気配――厳格で、一切の妥協を許さない父の視線のようなもの――に苛まれていた。友人が隣で冗談を言っても、うまく笑えない。口角を上げようとすると、頬の筋肉が強張るのだ。まるで、笑うことなど長年忘れてしまったかのように。
「涼介、今日どうした? なんか親父さんみたいだぞ」
昼休み、学食で友人の健太に言われ、俺は眉をひそめた。健太は俺の家の奇妙な儀式を知っている数少ない一人だ。
「見ての通りだよ。最悪のくじ運だ」
「あー、親父さんの影か。そりゃ災難だな」
.健太は同情的な目を向けながら、カツカレーを口に運んだ。俺は、まるで食欲がなかった。胃が何か重たいもので満たされているような、不快な満腹感。これも父の感覚なのだろうか。彼は毎朝、コーヒー一杯で会社へ向かう。
午後の講義をサボり、俺はキャンパスを抜け出した。普段ならゲームセンターにでも繰り出すところだが、足は自然と公園のベンチへ向かっていた。静かで、人通りの少ない場所。父も、仕事の合間にこうして一人で考え事をしているのかもしれない。そんな想像が、吐き気を催させた。
ベンチに座り、ぼんやりと空を眺める。父の影を纏っていると、世界が少し色褪せて見える気がした。目に映るすべてのものが、評価すべき対象、解決すべき問題として映る。木々の緑は光合成の効率を、遊ぶ子供たちの声は潜在的なリスクを、無意識に分析している自分がいた。創造性や衝動といった、俺を俺たらしめていたはずの感覚が、分厚い壁の向こうに追いやられている。
父は、こんな窮屈な世界で、毎日を生きているのか。
画家になりたい。漠然とだが、俺にはそんな夢があった。白いキャンバスを前に、心に浮かぶイメージを自由に描く。だが、父の影を纏った今、その夢はひどく陳腐で、非生産的な戯言に思えた。絵を描くことで、何が生み出される? 社会的な価値は? 安定した収入は? 次から次へと、冷徹な問いが頭をよぎる。
俺は父が嫌いだった。夢を語る俺を、いつも冷めた目で見ていたからだ。「現実を見ろ」と、一度だけ短く言われたことがある。その言葉が、ずっと胸に突き刺さっていた。お前に、俺の何がわかる。お前のように、退屈な人生を送るくらいなら死んだほうがましだ。そう、心の中で何度も叫んだ。
夕暮れが近づき、影が長く伸び始める。父の影もまた、地面に巨大なシルエットを描いていた。その影の先端が、まるで俺を操るかのように、自宅の方向を指し示している。俺はため息をつき、重い腰を上げた。この忌々しい儀式が、父への嫌悪感をさらに増幅させるだけだと、確信していた。
第三章 書斎の告白
家に帰ると、いつもと違う静けさが漂っていた。俺の影を纏った父は、俺の部屋でヘッドフォンをして音楽を聴いているらしい。かすかに漏れ聞こえるのは、俺が好きなインディーズバンドの、激しいギターリフだった。母の影を纏った美咲は、キッチンで鼻歌を歌いながら夕食の準備をしている。その手際は、驚くほど母にそっくりだった。誰もが、他人の人生を演じている。滑稽な茶番劇だ。
夕食を終え、自室に戻ろうとした俺の足が、ふと止まった。二階の廊下の突き当たり。固く閉ざされた、父の書斎の扉。普段は鍵がかかっていて、家族でさえ滅多に入ることのできない聖域だ。
なぜか、俺は無性にその中へ入りたくなった。いや、違う。俺の中の「父の影」が、その扉へ向かわせているのだ。ポケットを探ると、指先に冷たい金属の感触があった。書斎の鍵だ。父はいつも、このズボンのポケットに鍵を入れているのか。
まるで操り人形のように、俺は鍵を差し込み、扉を開けた。
部屋には、古い紙とインクの匂いが満ちていた。壁一面を埋め尽くす本棚。整然と並べられた法律や経済の専門書。その中に、一箇所だけ不自然な空洞があった。俺の目は、そこに吸い寄せられる。手を伸ばし、奥の壁板に触れると、そこが僅かに動いた。隠しスペースだ。
中には、一冊の古びたスケッチブックと、革張りの日記帳が収められていた。
好奇心に抗えず、俺は日記帳を手に取った。日付は、俺が生まれるよりもずっと前。そこには、俺がまったく知らない、父の姿があった。
ページをめくる指が震える。そこにあったのは、会社経営者・宮沢雄一郎ではない、一人の青年の、情熱と苦悩の記録だった。彼は、画家になることを夢見ていた。日記には、光の捉え方、色彩の調和についての考察が、熱っぽい言葉で綴られていた。スケッチブックには、息を呑むほど美しい風景画や、力強い人物のデッサンが何枚も描かれていた。それは、俺が目指すものより、遥かに高い次元にあった。
そして、俺は決定的なページを見つけてしまった。
『祖父の会社が危ない。長男である私が、夢を追っている場合ではないのかもしれない。咲子には申し訳ないが、絵筆を折る時が来たようだ』
その数ページ後、衝撃的な一文が目に飛び込んできた。
『息子が生まれた。涼介と名付けた。この子がいつか、私と同じように、親との間に壁を感じる日が来るかもしれない。言葉では、きっと何も伝わらないだろう。だから、我が家に新しい伝統を作ることにした。「影継ぎ」。月に一度、互いの影を交換する儀式だ。私の影を纏った涼介が、いつかこの書斎に辿り着いた時、私が背負った重みと、諦めた夢の痛みを、ほんの少しでも感じてくれるだろうか。これは、未来の家族へ宛てた、私の不器用な手紙だ』
日記が、手から滑り落ちた。
なんだ、これは。この馬鹿げた儀式は、先祖代々なんかじゃなかった。父が、俺のために…?
俺が感じていた父の影の重圧。それは、厳格さや退屈さの象徴などではなかった。それは、愛する家族のために自らの夢を断ち切り、たった一人で会社と人生の重責を背負うと決めた、一人の男の覚悟の重さだったのだ。俺が「枷」だと思っていたものは、父が俺たちを守るために纏い続けた「鎧」だった。
冷徹な現実主義者だと思っていた父が、こんなにもロマンチストで、不器用な愛情の持ち主だったなんて。涙が、頬を伝った。それは、俺自身の涙なのか、それとも、この影が記憶している、遠い日の父の涙なのか、分からなかった。
第四章 夜明けの輪郭
書斎を出て、俺は自分の部屋の扉を開けた。俺の影を纏った父が、ヘッドフォンを外し、こちらを見ていた。その目は、どこか不安げで、若々しい光を宿していた。まるで、悪戯が見つかった子供のような顔だ。
「……聴いてたのか。俺の好きなバンド」
俺が言うと、父は小さく頷いた。
「ああ。すごいな。こんな世界があるのか」
その声は、いつもより少し高く、軽やかだった。俺の影が、父にそうさせているのだ。
俺たちは、しばらく黙り込んでいた。だが、その沈黙は、以前のような気まずいものではなかった。互いの影を通して、言葉にならない何かを交換しているような、不思議な一体感があった。
やがて、窓の外が白み始めた。夜明けだ。影が元に戻る時が来た。
俺は父の前に立ち、父もソファから立ち上がった。互いの影が、するりと足元から離れ、本来の持ち主へと帰っていく。肩を押し潰していた重圧が消え、代わりに、忘れていた軽やかさが戻ってくる。父の背筋が、再びピンと伸び、いつもの厳格な表情が戻った。だが、その瞳の奥に、昨夜まではなかった温かい光が灯っているのを、俺は見逃さなかった。
「……涼介」
父が、俺の名前を呼んだ。
「そのスケッチブック、たまには使ったらどうだ」
それだけ言うと、父は部屋を出て行った。
俺は自分の机に目をやった。そこには、埃をかぶったまま、ずっと開かれることのなかったスケッチブックが置かれていた。父の言葉が、凍りついていた俺の心を、ゆっくりと溶かしていく。
「現実を見ろ」。あの言葉は、俺の夢を否定するものではなかったのだ。それは、夢を諦めた父が、自分自身に言い聞かせてきた言葉であり、そして、夢を追うことの厳しさを知るからこその、息子への不器用なエールだったのかもしれない。
俺はスケッチブックを手に取り、そっと開いた。真っ白なページが、無限の可能性となって俺の目に映る。
家族とは、血の繋がりや、交わす言葉の数だけで測れるものではない。時には、言葉にならない重みや、声にならない痛みを、そっと分かち合うことでしか繋がれない絆がある。我が家の奇妙な儀式は、そのための、父が遺した不器用で、そして、最大級の愛情表現だったのだ。
俺は鉛筆を握りしめた。まずは、父の肖像画を描こうと思った。俺が「影」を通して見た、鎧の下の、本当の父の姿を。キャンバスに向かう俺の背後に伸びる影は、もう頼りないだけのものではなかった。その輪郭には、父から受け継いだ、確かな強さが宿っているような気がした。