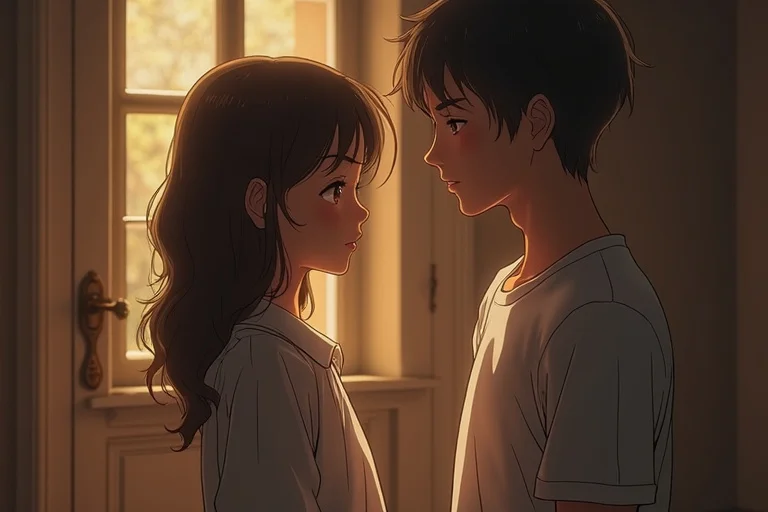第一章 完璧な家族のひび割れ
柏木湊の21歳の誕生日は、いつもと同じように、静かで完璧な一日になるはずだった。朝は、母・佳乃が焼き上げた完璧な円形のパンケーキから始まった。昼は、父・誠司が予約した、窓から手入れの行き届いた庭園が見えるフレンチレストランでの完璧なランチ。そして夕暮れ時、毎年恒例の「儀式」が執り行われる。
柏木家には、代々伝わる一つの習慣があった。一年に一度、湊の誕生日に、家族全員の肖像画を描いてもらうのだ。リビングの壁には、年代順に並べられた肖像画が、さながら小さな美術館のように飾られている。幼い湊が父の肩車ではしゃぐ姿、思春期の妹・陽菜が少しはにかんでいる顔。それらは全て、幸福な家族の歴史そのものに見えた。
今年も、白髪の老画家が重厚な画架を立て、静かにキャンバスに向かっている。父は威厳に満ちた表情でソファに腰掛け、母はその隣で聖母のように微笑む。妹は少し緊張した面持ちで背筋を伸ばし、湊はその間に、まるでパズルの最後のピースのように収まっていた。部屋に満ちるのは、油絵の具の芳醇な香りと、誰もが一言も発しない、張り詰めた静寂だけだった。
「……終わりましたぞ」
老画家のしわがれた声が、緊張の糸を切った。完成した肖像画は、今年も見事な出来栄えだった。写真よりも克明に、それでいて温かみのある筆致で描かれた柏木家は、誰が見ても「理想の家族」そのものだった。父が満足げに頷き、母が「まあ、素敵」と小さく声を上げた。
しかし、湊だけが気づいていた。キャンバスの上に現れた、微細で、しかし決定的な「歪み」に。
父の口元。威厳を湛えているはずのそれは、よく見ると嘲笑うかのように、ほんの僅かに歪んでいる。母の微笑み。慈愛に満ちているはずのその瞳の奥に、乾いた湖底のような絶望の色と、一粒の涙のきらめきが見える。妹の陽菜は、完璧な笑顔を浮かべているはずなのに、その頬は不自然に引きつり、指先はスカートを固く握りしめている。
そして、何よりも湊を慄かせたのは、自分自身の姿だった。彼は家族の輪の中心にいるはずなのに、その体はほんの数ミリ、外側に向かってずれていた。まるで、この息苦しいフレームから、今にも逃げ出したいと叫んでいるかのように。
「どうした、湊。気に入らないのか?」
父の鋭い声に、湊ははっと我に返った。「いや、そんなことは……。素晴らしいよ」
口ではそう取り繕いながらも、湊の背筋を冷たい汗が伝った。この絵は、ただの絵ではない。これは、完璧な家族という名の舞台の上で、仮面を被って踊り続ける僕たちの、声にならない悲鳴だ。壁に並ぶ過去の肖像画が一斉にこちらを見つめているような錯覚に陥り、湊は息苦しさを覚えた。なぜ、誰もこの違和感を口にしないのだろう。それとも、気づいているのは、自分だけなのだろうか。
第二章 色褪せた記憶の回廊
その夜、湊は眠れなかった。リビングの壁に掛けられた新しい肖像画が、暗闇の中で不気味な存在感を放っている。あの絵に描かれた「本心」は、一体どこから来るのだろう。好奇心と恐怖に突き動かされ、湊は懐中電灯を片手に、屋敷の奥にある開かずの間に足を踏み入れた。古い家財道具と共に、過去の肖像画が保管されている、埃っぽい蔵だ。
ひんやりとした空気が肌を撫でる。カビと古い木の匂いが鼻をついた。湊は、壁に立てかけられた古いキャンバスを一枚一枚、順に見ていった。
最も古いものは、湊が生まれる前の、若き日の両親の肖像画だった。そこには、今の彼らからは想像もつかないような、自由で、屈託のない笑顔があった。父は少し悪戯っぽく笑い、母は恥ずかしそうに頬を染めている。背景の空は、どこまでも突き抜けるような青色だ。
湊が生まれ、陽菜が生まれ、家族が増えていく。幼い頃の肖像画は、どれも活気に満ちていた。絵の具をつけた手で母に抱きつく湊。兄の服の裾を掴んで離さない陽菜。家族の周りには、いつも温かい光が満ちていた。
しかし、湊が小学校高学年になった頃から、絵の雰囲気は少しずつ変わり始めていた。構図はより厳格に、シンメトリーに近づいていく。表情からは無邪気さが消え、どこか作られたような微笑みが貼りつくようになる。背景の色も、鮮やかな色彩から、落ち着いた、しかし重苦しい色調へと変化していた。
決定的な変化があったのは、湊が中学二年生の時の絵だ。父の会社が大きなプロジェクトで苦境に立たされていた年だった。その年の絵の父は、まるで石像のように硬い表情をしていた。そして、その隣で微笑む母の顔色は、病的なまでに青白い。湊は思い出した。あの頃、母はよく体調を崩していたが、病院に行っても原因不明だと診断されていたことを。
さらに数年後、陽菜が高校受験を控えた年の絵。優等生でいつも明るい陽菜の顔は、笑顔でありながら、その目の下には深い隈が描かれていた。まるで、見えない重圧に押し潰されそうになっているかのようだ。
肖像画は、家族の歴史を記録していたのではない。それは、家族が押し殺してきた苦悩や葛藤の、克明な記録だった。この「完璧な家族」という幻想は、一体いつから始まったのか。そして、誰のために。この幻想を守るために、僕たちは何を失ってきたのだろう。
湊は、一番新しい、今日の肖像画を思い浮かべた。輪から外れかけた自分。それは、この息苦しい真実に気づき、無意識に抵抗を始めた自分の姿なのかもしれない。湊は、この歪んだ家族の真実を、そして肖像画の謎を解き明かすことを、固く心に誓った。
第三章 画家の告白と呪いの真実
翌日、湊は大学の講義を休み、あの老画家の住むアトリエを訪ねた。海辺の町にある、潮風で白く錆びた小さな家だった。ドアを開けると、無数のキャンバスと、油絵の具の匂いが湊を迎えた。
「柏木のご子息か。どうなされた」
イーゼルの前に座っていた画家は、筆を止め、静かに湊を見た。その目は、全てを見透かしているかのようだった。
「先生、教えてください。うちの肖像画は、一体何なんですか。あれは、僕たちの本心を描いているんですよね?」
湊は単刀直入に切り出した。画家はしばらく黙っていたが、やがて重いため息をつき、近くの椅子に座るよう促した。
「座りなさい。長くなる」
画家の語る話は、湊の想像を遥かに超えるものだった。
「あの肖像画は、真実を映すのではない」と、画家は静かに言った。「むしろ、その逆じゃ。あれは……現実を捻じ曲げるための、装置のようなものだ」
彼の告白によれば、柏木家の肖像画の歴史は、湊の曽祖父の代に遡るという。事業に失敗し、家族が離散しかけた曽祖父は、家族の絆を永遠に繋ぎ止める方法を探し求めた。そして、ある旅の絵描きから、不思議な力を持つという特別な顔料を手に入れた。
「その顔料で描かれた肖像画は、描かれた家族の『こうありたい』という強い願いを吸い上げ、現実をその『理想』の形に修正する力を持つ。家族の絆が永遠に続くように、と。それが、お宅の曽祖父様の願いだった」
湊は言葉を失った。父の仕事の失敗が、奇跡的に回避されたこと。母の謎の病が、いつの間にか治ってしまっていたこと。それらは幸運などではなく、肖像画が「完璧な家族」という理想を維持するために、現実を歪めた結果だったのだ。
「しかし、その力には代償が伴う。理想の現実を維持するため、肖像画は家族から『個性』や『自由な感情』を奪っていく。家族は、絵に描かれた『完璧な役割』を演じることを強いられる。いわば、美しい呪いじゃよ」
湊が感じていた息苦しさの正体は、それだったのだ。肖像画は家族の本心を映していたのではない。肖像画が、家族の心を支配し、操っていたのだ。湊が絵の中で輪からずれ始めていたのは、彼がこの呪縛に無意識に抗い始めていた証拠だった。
「なぜ、僕にだけ異変が見えるんですか?」
「お前さんが、家族の中で初めて、その『完璧さ』を疑ったからじゃろう。絵に支配されるのではなく、絵を『見る』側に回ったからだ。わしは長年、お前さんたちを描きながら、この呪いを解く者が現れるのを待っていたのかもしれん」
老画家は、悲しげな目で湊を見つめた。アトリエの窓から差し込む西日が、彼の深い皺を黄金色に照らしていた。湊は、自分の家族が、幸福の仮面を被ったまま、ゆっくりと魂を蝕まれていたという事実に、身の底から震えるような怒りと、そして深い悲しみを覚えていた。
第四章 不完全な僕らの肖像
その夜、湊は家族全員をリビングに集めた。壁には、あの完璧で、そして不気味な肖像画が掛けられている。
「父さん、母さん、陽菜。話があるんだ」
湊は、老画家から聞いた全てを、ありのままに話した。肖像画の力、その代償、そして自分たちが「完璧な家族」という呪いに縛られているという真実を。
案の定、誰も信じようとはしなかった。「何を馬鹿なことを言っているんだ」「お前は疲れているんだ」と父は一蹴し、母は困ったように微笑むだけだった。
湊は覚悟を決めた。彼は近くにあったペーパーナイフを手に取り、肖像画に向かって歩み寄った。「なら、これを壊せばわかるはずだ」
湊が刃先をキャンバスに近づけた、その瞬間だった。家全体がぎしりと軋み、父が胸を押さえてうめき、母と陽菜が顔を青ざめさせた。まるで、絵に加えられようとする痛みが、家族全員の体に伝わったかのように。
「やめなさい、湊!」
母の悲鳴が響く。家族はようやく、湊の言葉がただの妄想ではないことを悟った。彼らは、この美しい絵と、見えない糸で繋がっていたのだ。
「僕たちは、この絵に生かされてきたんじゃない。殺されてきたんだ」湊は静かに言った。「完璧じゃなくていい。喧嘩したっていい。泣いたっていい。それが、本当の家族じゃないのか」
湊はペーパーナイフを置くと、代わりに自分の部屋から一本の木炭を持ってきた。そして、油絵の具で描かれた完璧な肖像画の上に、その黒い炭を滑らせ始めた。
彼は、石像のような父の顔に、深い疲労の皺を刻んだ。聖母のような母の瞳に、堪えていた涙の筋を描き加えた。完璧な笑顔の妹の口元を、不安に震えるラインに変えた。そして、輪から外れかけていた自分自身を、しっかりと家族の中心に描き直し、その腕で、震える家族を抱きしめるような構図にした。
湊が最後の一本線を引いた瞬間、肖像画はふっと輝きを失い、ただの、黒と白の染みがついた油絵になった。同時に、家族の肩から、見えない重荷が下りたような空気が流れた。
沈黙を破ったのは、父だった。
「……すまなかった」
厳格だった父の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。「ずっと、完璧でなければならないと、自分を、そしてお前たちを追い詰めていた」
その言葉を合図にしたかのように、母は静かに泣き崩れ、陽菜は「もう、頑張らなくていいんだ」と呟きながら、兄の胸に顔を埋めた。
彼らはその夜、初めて本当の言葉で語り合った。失敗の恐怖、隠していた病への不安、期待に応えることへのプレッシャー。不格好で、みっともなくて、しかし、そこには紛れもない温かさがあった。
数年後。柏木家のリビングの壁には、今も一枚の肖像画が飾られている。湊が木炭で上書きした、あの不格好な絵だ。それは美術品としての価値などない、ただの落書きのようなものかもしれない。
しかし、その絵の中で、疲れた顔で寄り添う家族は、以前のどの肖像画よりも、ずっと幸せそうに見えた。完璧な幸福という幻想を手放した先に、彼らは、不完全さを受け入れ合うという、本物の愛を見つけたのだ。湊は時々その絵を見上げ、思う。家族とは、完成された美しい作品なのではなく、傷つき、修正を重ねながら、共に描き続けていく、未完のスケッチのようなものなのかもしれない、と。