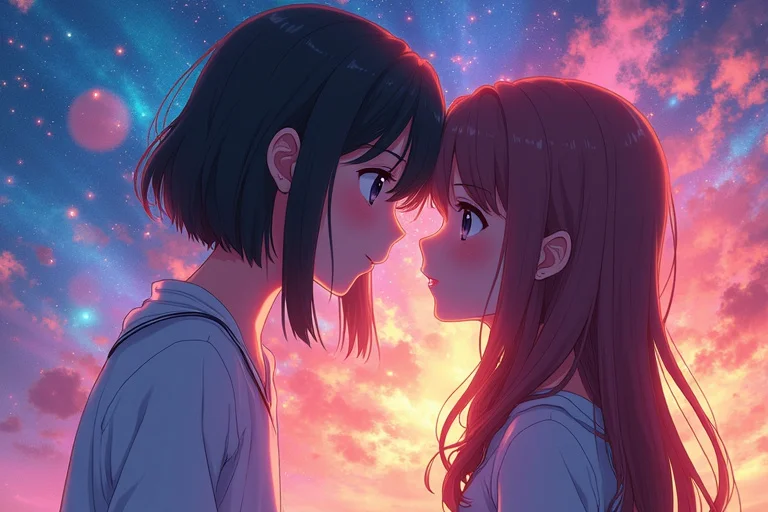第一章 開かずの箪笥
蝉の声が、アスファルトの熱気と共に脳髄を揺さぶる。父、正一の一周忌のために帰省した実家の空気は、俺が東京に置いてきたはずの、息苦しい記憶の澱を攪拌した。仏壇に手を合わせても、黒い額縁の中で無愛想に口を結ぶ父の顔は、生前と同じように何も語りかけてはこなかった。
「健太、ちょっといいかい」
法事が終わり、親戚たちが引き取った後の静まり返った居間で、母の美津子が遠慮がちに声をかけてきた。その手には、古びた雑巾が握られている。母の視線の先にあるのは、客間の隅で異様な存在感を放つ、黒光りする桐の箪笥だった。高さは俺の胸ほどもあり、華美な装飾はないが、がっしりとした重厚な作りは、いかにも頑固な職人だった父の仕事ぶりを彷彿とさせた。
「あそこの箪笥、お父さんが亡くなってからずっとそのままでね。あなた、どうにか処分してくれないかしら。私じゃ重くて動かせないし、何だか気味が悪くて」
父はこの箪笥を「わしの宝物だ」と言い、誰にも触らせなかった。俺が子供の頃、興味本位で引き出しに手をかけただけで、雷のような怒声が飛んできたものだ。中には何が入っているのか。父のへそくりか、あるいは誰にも言えない秘密でも隠してあるのか。父への反発心と、建築士としての妙な好奇心が頭をもたげた。
「わかったよ。どうせ古いだけだろ。壊して粗大ゴミに出せばいい」
俺は工具箱を引っ張り出し、無造作にバールを箪笥の隙間にねじ込もうとした。だが、ぴたりと組み合わさった木と木の間に、刃先が入る隙間さえない。まるで一枚岩のように、箪笥は俺の乱暴な試みを拒絶した。鍵穴はあるが、鍵は見当たらない。躍起になって全体を揺さぶってみるが、びくともしない。その時だった。
耳を澄ますと、箪笥の奥から、微かに音が聞こえる気がした。キシ、という木が軋むような音。そして、コロ、と何か小さな金属が転がるような、か細い響き。ひんやりとした木の表面に掌を当てると、まるでそれが呼吸しているかのような、不思議な錯覚に陥った。ただの古い家具ではない。この箪笥には、父が仕掛けた「何か」がある。俺の背筋を、冷たい汗が流れ落ちた。
第二章 埃の中の設計図
箪笥との格闘は、徒労に終わった。母は「無理しなくていいのよ」と心配そうに言うが、俺の中で何かが燻り始めていた。それは、父への長年の反発心とは違う、純粋な挑戦心のようなものだった。あの無口で、俺の選んだ道を一度も褒めなかった父が、最後に遺した謎。それを解き明かしたいという衝動に駆られたのだ。
鍵はどこにあるのか。考えられる場所は一つしかなかった。生前、父が聖域のように守っていた、離れの作業場だ。引き戸を開けると、むわりと木の香りと埃の匂いが鼻をついた。窓から差し込む西日が、宙を舞う無数の塵を金色に照らし出している。壁には使い込まれた鉋(かんな)や鑿(のみ)が整然と並び、床には木の端材が散らばっていた。ここで父は、来る日も来る日も木と向き合っていたのだ。俺が図面の上で線を引いている間、父は掌の感覚を頼りに、ミクロン単位の精度で木を削っていた。その事実に、今更ながら胸を突かれた。
作業台の引き出しを片っ端から開けていく。錆びた釘、古びたネジ、そして大量の設計図の束。そのどれもが、俺が学校で習った無機質な青焼きの図面とは違い、鉛筆で描かれた温かみのある線で構成されていた。その中に、ひときeyse異彩を放つ一冊の大学ノートを見つけた。表紙には何も書かれていない。
ページをめくると、そこに描かれていたのは、あの箪笥の内部構造らしき、極めて複雑な木組みの図だった。歯車のようなもの、連動する仕掛け板、そして意味不明な数字の羅列。「右三、上二、引く」「左一、下五、押す」。それは、まるで暗号文だった。ノートの最後のページに、掠れた文字でこう記されていた。
『悠人(はると)へ。父さんの、最高の仕事だ』
悠人? 誰だ、その名前は。俺の知る限り、親戚にそんな名前の者はいない。俺の心臓が、嫌な予感に脈打つのを感じた。このノートは、単なる設計図ではない。父が誰かに宛てた、メッセージそのものなのだ。
第三章 悠人への手紙
居間に戻り、俺はノートの暗号と箪笥を交互に見比べた。まるで難解なパズルを解くように、設計図に書かれた指示通り、箪笥の特定の場所を、特定の順番で押したり引いたりしていく。
「右三、上二、引く」
箪笥の右側面、上から三番目の木目を指で押し込むと、カチリ、と小さな音がして、木目がわずかに沈んだ。次に、天板の上から二番目の継ぎ目を引く。すると、今まで存在しなかったはずの場所に、小さな引き出しが音もなく姿を現した。鳥肌が立った。これは、ただの箪笥ではない。父の職人としての技術と魂が注ぎ込まれた、「からくり箪笥」だったのだ。
俺は息を殺し、次々と暗号を解読していった。引き出しが側面から現れ、底板がせり上がり、天板が開く。まるで魔法のように、箪笥はその秘密を少しずつ俺に開示していく。その度に、父の無骨な指先が、この木の一つ一つを撫で、組み立てていく光景が目に浮かぶようだった。
そして、ついに最後の仕掛けを解いた時。箪笥の中央、最も大きな扉が、重々しい音を立てて観音開きになった。中には、ポツンと一つ、古びたオルゴールが置かれていた。ゼンマイを巻くと、懐かしい童謡のメロディが流れ出す。俺が幼い頃、母がよく歌ってくれた歌だった。
だが、驚きはそれだけでは終わらなかった。オルゴールが置かれていた台座の底板に、指をかける僅かな窪みがあることに気づいた。そっとそれを持ち上げると、隠された空間が姿を現す。そこには、和紙の便箋で書かれた手紙の束が、大切に、大切にしまわれていた。
宛名は、すべて『天国の悠人へ』。
差出人は、すべて『父・正一より』。
震える手で、一番上の手紙を手に取った。日付は、俺が生まれた年のものだった。
『悠人へ。お前に、弟ができたぞ。健太という名前だ。お前と同じ、健康の健の字だ。あの日、お前をこの腕に抱くことすら叶わなかった父さんだが、今度こそ、この手でしっかりと守っていく。空の上から、弟の成長を見守っていてくれ』
ページをめくる手が止まらなくなった。そこには、俺の知らない家族の歴史が、父の無骨だが愛情に満ちた文字で綴られていた。悠人とは、俺が生まれる前に、生後間もなくして亡くなった、俺の兄の名前だったのだ。母は、俺に余計な哀しみを背負わせたくなくて、ずっと黙っていたという。
父は、誰にも言えなかった悲しみを、そして亡き長男への愛情を、このからくり箪笥に封じ込めていたのだ。健太が初めて立った日、初めて「父ちゃん」と呼んだ日、自転車に乗れるようになった日。反抗期で口も利かなくなった日。建築士になる、と宣言して家を飛び出した日。そのすべてが、悠人への報告として、克明に記されていた。
『悠人へ。健太が、家を出て行った。わしと同じものづくりの道だが、あいつはもっと大きな、たくさんの人が幸せになる家を造るらしい。わしは、あいつに何もしてやれん。口を開けば、つい憎まれ口ばかり叩いてしまう。だが、あいつが設計した家が建つ日を、誰よりも楽しみにしているのは、この父さんだということを、いつか分かってくれるだろうか』
手紙を持つ俺の手が、涙で濡れていた。無口、頑固、無理解。そう思っていた父の姿が、ガラガラと音を立てて崩れていく。父は、不器用なやり方で、俺を愛し、見守り、そして誇りに思ってくれていた。俺が父から逃げている間も、父はずっと、俺と、そして会えなかった兄と共に、家族として生きていたのだ。
第四章 家族の柱
流れ落ちる涙を、俺は拭おうともしなかった。それは後悔の涙であり、そして、遅すぎた感謝の涙だった。オルゴールの優しいメロディが、静まり返った部屋に響き渡り、まるで父が、そして兄が、俺の嗚咽を慰めてくれているかのようだった。
いつの間にか背後に立っていた母が、そっと俺の肩に手を置いた。「お父さん、不器用な人だったから」。母の声も震えていた。「あなたのことをどうやって褒めていいか、どう愛情を伝えたらいいか、きっと分からなかったのよ。でもね、いつもあなたの話ばかりしていたわ。あなたの造る家が見たいって、何度も」
俺は振り返り、初めて母の前で子供のように泣いた。父が遺したこの箪<h4>は、単なる古い家具ではなかった。言葉にできなかった愛情、伝えられなかった想い、そして、俺の知らない家族の歴史が刻み込まれた、タイムカプセルだったのだ。これは、父・正一の最高傑作だ。</h4>
「母さん、この箪笥、俺がもらっていいかな」
処分するなんて、とんでもない。これは俺が受け継がなくてはならない、家族の柱だ。俺と、会うことのなかった兄と、そして不器用な父を繋ぐ、たった一つの確かな証なのだから。
数日後、俺は引越し業者に頼んで、あの箪笥を東京の自分のマンションに運び込んだ。殺風景だったコンクリート打ちっぱなしの部屋に、黒光りする桐の箪笥は、不思議なほどの温かみと落ち着きをもたらした。窓から差し込む午後の光が、その美しい木目を黄金色に照らし出す。まるで、箪笥が呼吸し、微笑んでいるように見えた。
俺はスマートフォンを手に取り、実家の番号を呼び出す。数コールで、母の明るい声が聞こえた。
「もしもし、健太?」
「ああ、母さん。……あのさ」
言葉が詰まる。今まで、こんな風に改まって電話をすることなどなかった。だが、言わなければならない。父に言えなかった言葉を、今、伝えなければ。
「ありがとう。……いろいろと」
それは、母への感謝の言葉であり、天国の父に宛てた、三十年越しの返事だった。電話の向こうで、母が息を呑む気配がした。静寂の中に、窓の外の喧騒が遠く聞こえる。俺は、この箪笥に恥じないような、人の心を温かくする建物を、これから造っていこう。そう、心に固く誓った。