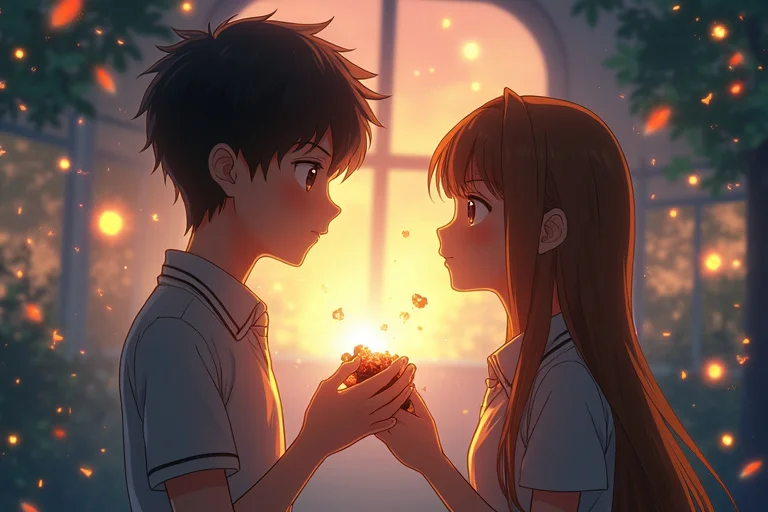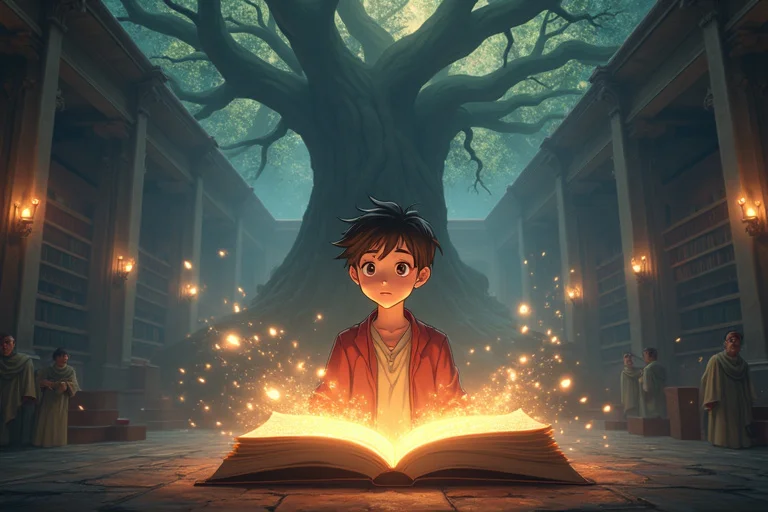第一章 五十年の時を超えた手紙
秋の気配が色づき始めた葉を通して、体育館の窓から差し込んでいた。創立百周年記念式典。壇上で語られる校長の退屈な言葉は、右の耳から左の耳へと、何の抵抗もなく通り過ぎていく。僕、水野翔太は、そんなありふれた日常の一コマが、永遠に変わってしまう瞬間の直前にいることなど、知る由もなかった。
式典のクライマックスは、五十年前の先輩たちが未来の僕たちのために埋めた、タイムカプセルの開封式だった。錆びついた金属の箱がこじ開けられると、生徒たちの間から期待の混じったどよめきが起こる。古びた文集、当時の生徒手帳、色褪せた写真。次々と取り出される品々に、歓声が上がった。
「――次に、個人宛の預かり品です。二年生、水野翔太くん」
司会の教師が読み上げた自分の名前に、心臓が跳ねた。僕? どうして。同姓同名の先輩がいたのだろうか。周囲の視線が突き刺さる中、僕は戸惑いながら壇上へ向かった。手渡されたのは、茶色く変色し、角が丸くなった一通の封筒。宛名には、インクが滲んだ拙い文字で、確かに『水野翔太様』と書かれていた。
自分の席に戻り、震える指で封を開ける。中には、一枚の手紙と、セピア色に焼けた写真が入っていた。写真は、夕暮れの屋上で撮られたものらしい。茜色の光を背に、知らない制服を着た少女が、はにかむように微笑んでいた。
そして、手紙。古紙特有の甘く乾いた匂いがした。
『未来の君へ。
元気にしていますか。五十年の時が経っても、君が笑っていますように。
どうか、あの日の約束を忘れないで。
また、屋上で。
月島 凛』
月島、凛。
その名前を、僕は知らない。同学年の名簿を隅から隅まで思い返しても、そんな名前の生徒はいなかった。そもそも、五十年前の人間が、どうして未来に生まれる僕の名前を知っている? そして、「あの日の約束」とは、一体何のことなのか。
手の中にある、あり得ないはずの手紙。ファインダーを覗くように、僕の日常のピントが、この瞬間、狂い始めた。それは、謎と切なさに満ちた、長い物語の始まりを告げるシャッター音のようだった。
第二章 存在しない少女の影
あの日以来、僕の頭の中は「月島凛」のことで一杯になった。彼女は誰なのか。この手紙は何かの間違いか、それとも手の込んだ悪戯か。僕はまず、自分のクラスから、そして同学年の名簿を片っ端から調べたが、やはり「月島凛」という生徒はどこにも存在しなかった。まるで、初めからこの世にいなかったかのように。
僕は写真部に所属している。といっても、人見知りで口下手な僕には、モデルを頼んでポートレートを撮るような勇気はない。いつも被写体は、誰もいない風景ばかりだ。校舎の窓枠が切り取る空、雨上がりのグラウンドにできた水たまり、誰も座らない中庭のベンチ。そこには誰もいない。だから傷つくこともない。僕が愛用しているのは、亡くなった祖父の形見である、古めかしいフィルムカメラ。デジカメのように撮り直しがきかない、その不自由さが妙に落ち着いた。
僕は、例の写真を現像し直して、自分の部屋の壁に貼った。夕陽を浴びて微笑む凛。その表情はどこか儚げで、見ていると胸の奥が締め付けられるようだった。彼女が誰なのか知りたい。その一心で、僕は放課後の図書室に通い、過去の卒業アルバムをめくった。しかし、五十年も前のアルバムに、彼女の姿はなかった。
調査が行き詰まり、途方に暮れていたある日のこと。僕は、壁の写真を眺めていて、ある小さな違和感に気づいた。写真の左隅。凛の肩の向こうに、ほんの少しだけ写り込んでいる何か。拡大鏡で覗き込んで、息を呑んだ。それは、カメラのストラップだった。革が擦り切れた、特徴的な模様のストラップ。――僕が今、祖父のカメラにつけているものと、全く同じだった。
ぞわりと背筋を何かが駆け上がった。これは偶然じゃない。この写真には、僕に繋がる何かが隠されている。
僕は、一つの噂を思い出した。この学校の歴史で、彼女の知らないことはないという、図書委員の三年生。校内の生き字引、変わり者で有名な、早乙女先輩。藁にもすがる思いで、僕は旧校舎の奥にある、古書の匂いが充満する図書準備室の扉を叩いた。
第三章 屋上のアリア
「五十年前のタイムカプセルから、君宛の手紙? しかも差出人は存在しない生徒……面白い」
早乙女先輩は、分厚い眼鏡の奥の瞳を好奇心に輝かせ、僕の話に聞き入っていた。彼女は、埃っぽい書庫の奥から、製本された古い学校新聞の束と、マイクロフィルムのケースをいくつも運び出してきた。カタカタと音を立てて回るフィルムリーダーの光が、先輩の理知的な横顔を照らし出す。
「あったわ」
静寂を破ったのは、先輩の低い声だった。画面に映し出されたのは、タイムカプセルが埋められた日の翌日の新聞記事。その小さな、本当に小さな囲み記事に、僕の心臓を凍らせる見出しが躍っていた。
『本校生徒、校舎屋上より転落死』
僕は息を詰めて、その本文に目を走らせた。被害者の名前は、月島凛。享年十六歳。写真部所属。
手紙の主は、五十年の時を生きることなく、この世を去った少女だったのだ。血の気が引いていくのが分かった。手足が冷たく、震えが止まらない。
「待って、まだ続きがある」
早乙女先輩が指さした記事の末尾には、こう書かれていた。
『現場には、同じく写真部の男子生徒一名が一緒にいた模様。事故のショックにより、男子生徒は当時の記憶が一部欠落していると証言しており、警察は事故と事件の両面で調査を……』
写真部。その言葉に、僕は祖父の顔を思い浮かべていた。祖父も、この高校の写真部だったと聞いている。まさか。そんな偶然があるはずがない。
僕は早乙女先輩に礼もそこそこに図書室を飛び出し、家へと走った。
自宅の物置の奥、祖父が遺した段ボール箱を開ける。黴と樟脳の匂いが鼻をついた。古いアルバム、使い古した現像道具。その中に、一冊の分厚い日記帳を見つけた。表紙には、祖父の名前『水野陽太』と記されている。僕の名前、翔太は、この祖父から一文字貰ったのだと、父から聞いたことがあった。
ページをめくる。そこには、僕の知らない祖父がいた。写真に情熱を燃やし、一人の少女に淡い恋心を抱く、十六歳の少年の姿が。そして、日記の中には、あの写真と同じ、凛と若き日の祖父が寄り添って笑う写真が何枚も挟まれていた。
日記は、事故の前日で途絶えていた。しかし、最後の一ページに、数十年後に書かれたであろう、震える文字が残されていた。
『凛、すまない。君との約束を、僕は果たせなかった。あの夕日を、君と一緒に撮るという約束を。君を失ったあの日から、僕の時間は止まってしまった。もう二度と、僕は人を撮れない。このカメラも、ファインダーも、君のいない世界を写すには、あまりに重すぎる』
全てのピースが、音を立ててはまった。
手紙は、凛が未来の祖父――陽太――に宛てて書いたものだったのだ。『翔太』と『陽太』。彼女が書いた拙い文字は、五十年の時を経て、孫である僕の元へ届いた。宛名を間違えたのではない。同じカメラを受け継ぎ、同じ風景を見ていた僕の元へ、運命が届けたのだ。
祖父が果たせなかった約束。凛が見たかった未来。五十年の時を超えた想いが、ずしりと僕の両肩にのしかかってきた。それは、もう僕だけの謎ではなく、僕が引き継ぐべき、切ない祈りそのものだった。
第四章 君のいた風景
真実を知った翌日、僕はカメラを手に、あの屋上へ向かった。錆びた金網の向こうには、街並みがオレンジ色に染まり始めている。凛が落ちた場所、祖父が全てを失った場所。冷たいコンクリートの上に立つと、風の音がまるで彼女のすすり泣きのように聞こえた。
今まで僕が撮ってきたのは、誰もいない、空っぽの風景だった。それは、傷つくことを恐れる僕自身の心の風景でもあった。だが、今は違う。このファインダーの向こうに、僕は写すべきものを見つけた。
僕はカメラを構えた。ファインダーが切り取る茜色の世界。そこには誰もいない。いるはずがない。けれど、僕には見えた気がした。夕陽の眩しさの中に、少しはにかんでこちらを見る、凛の笑顔が。隣で、優しく微笑む若き日の祖父の姿が。
カシャッ。
乾いたシャッター音が、秋風に溶けて消えた。涙が、頬を伝っていることに気づいた。
学園祭の写真コンテストに、僕はその一枚を応募した。タイトルは『プロローグ』。そこに写っているのは、夕暮れの誰もいない屋上だけだ。技術的に優れているわけでもない、何の変哲もない風景写真。案の定、その写真が賞を取ることはなかった。
それでも、僕にとっては、それでよかったのだ。
写真の横に置いた感想ノートには、たくさんの言葉が寄せられていた。
『なぜか、泣きそうになりました』
『この場所に、誰か大切な人がいたんじゃないかなって思いました』
『見ているだけで、胸が温かくなる不思議な写真ですね』
賞状よりも、トロフィーよりも、その言葉の一つひとつが、僕の心を満たしていった。人を撮れなかった僕が、初めて誰かの心を動かせた瞬間だった。
僕はこれからも、写真を撮り続けるだろう。祖父の古いカメラで、誰かの記憶や、見えない想いを写すために。
五十年の時を超えて僕の元に届いた手紙は、一つの物語を終わらせたのではなく、僕自身の人生の、長いプロローグを始めてくれたのだ。ファインダーを覗けば、世界は今も、切なく、そして美しく輝いている。凛が、そして祖父が見たかったであろう、この光の中で。