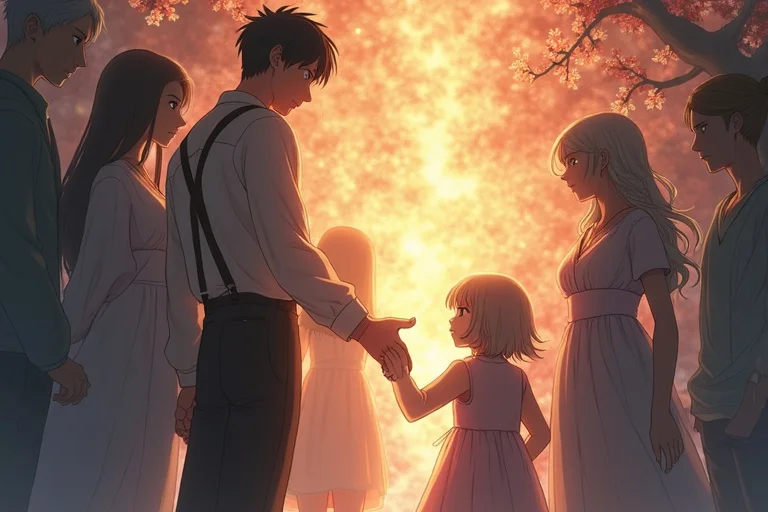第一章 花と雨と稲妻と
僕、カイの目には、家族の心が映る。
それは生まれついての、僕だけの景色だった。父さんの腕には、頼もしい意思を示す力強い蔦の模様が巻き付き、母さんの背中には、その穏やかな愛情を映す柔らかな陽光の模様がきらめいている。五つ下の妹、リナの頬には、好奇心に満ちた心が弾けるたびに、小さな星屑が流れる。喜びが満ちれば庭中の花が一斉に咲き誇るように、悲しみに沈めば窓を打つ静かな雨のように、彼らの感情は僕の肌にまでその色彩と温度を伝えてくる。
僕はその模様に囲まれて育った。父さんの蔦に励まされ、母さんの陽光に包まれ、リナの星屑に頬を緩ませる。それが僕の世界のすべてであり、揺るぎない安らぎだった。
ただひとつ、鏡を覗き込んでも、僕自身の肌には何の模様も浮かばない。まるで磨き上げられた石のように滑らかなままだ。その空白が、僕を時折、この温かな家族という絵画から切り離された、ただ一人の鑑賞者のように感じさせた。
街へ出ると、世界が静かに褪せていくのがわかる。人々は「絆」という名の体温を失い、その姿を変え始めていた。パン屋の主人の腕は硬い樫の木の肌に変わり、幼馴染の少女の髪は色褪せたドライフラワーのようにぱさついている。絆が希薄になるほど、人は人としての形を保てなくなる。それが、この世界の冷たい法則だった。完全な孤独は塵となって風に消える。
それでも、僕の家だけは違った。色鮮やかな感情の模様に満ちた、世界の法則が届かない聖域のように思えた。そう、あの奇妙な不協和音が、僕たちの食卓に忍び寄るまでは。
第二章 不協和音の模様
異変は、些細な綻びのように始まった。
食卓を囲んでいた時だ。父さんが冗談を言って、母さんとリナが笑った。母さんの背中にはいつもの陽光が溢れ、リナの頬を星屑が駆け巡る。しかし、父さんの腕に目をやった僕は、息を呑んだ。力強い蔦の模様に、まるで薄氷に走るような、鋭い亀裂が無数に刻まれていたのだ。それは怒りの稲妻でも、悲しみの雨でもない。僕の知らない、無機質で冷たい痛みの模様だった。
「父さん、腕が……」
僕が言いかけると、父さんは慌てて腕をテーブルの下に隠した。
「ああ、何でもない。少し疲れているだけだ」
その日から、家族の模様は静かにおかしくなっていった。母さんの陽光は時折、陽炎のようにぐらりと歪み、その向こうに深い影を落とす。リナの星屑は、瞬く間にその輝きを失い、黒い煤のような澱みに変わることがあった。
彼らは僕の前では決して表情を崩さない。けれど、家の空気に混じる焦げ付くような匂いや、誰もいないはずの廊下から聞こえる微かな呻き声が、彼らの隠した苦しみを僕に告げていた。僕が見ている模様は、彼らの感情ではない。もっと深く、根源的な何かが軋みを上げている音なのだと、直感が囁いていた。
なぜ、僕だけがその兆候を正確に読み取れないのだろう。まるで僕の目だけが、都合の悪い真実から逸らされているかのように。家族の中にいながら、僕は再び、たった一人の鑑賞者になっていた。
第三章 褪せる世界、色褪せぬ家族
世界の変貌は、堰を切ったように加速した。人々は絆を交わす言葉さえ忘れ始め、街は動植物と無機物が混在する、静かで歪な庭園へと姿を変えていった。かつて友人と語らった広場は、口を閉ざした石像たちが佇む沈黙の森となり、風が運ぶのは砂塵の匂いだけになった。
そんな崩壊寸前の世界にあって、僕の家族だけは、奇跡のように人間の形を保ち続けていた。その事実に安堵する一方で、僕の胸を占める不安は濃くなるばかりだった。彼らの肌を覆う奇妙な模様は、もはや日常の一部と化していた。ガラスの亀裂、揺らめく陽炎、黒い星屑。それはまるで、内側から崩壊していく器を、必死に繋ぎ止めている継ぎ接ぎのようにも見えた。
ある嵐の夜、屋根裏部屋で古い毛布を探していた僕は、床板の下に隠された小さな木箱を見つけた。埃を払い、錆びついた留め金を外すと、中から現れたのは、てのひらほどの大きさの鉱石だった。
それは、光を受けて万華鏡のように内部の色彩を変化させる、不思議な石だった。ただ美しいだけではない。握りしめると、遠い昔の温もりと、星々が砕けるような鋭い悲鳴が同時に流れ込んでくる。これが何なのかはわからない。けれど、これが家族の秘密の核心なのだと、僕は確信した。僕はその石を「絆の結晶」と名付け、そっとポケットに忍ばせた。
第四章 万華鏡が映す真実
翌朝、僕は結晶を握りしめ、リビングにいる家族を見た。そして、世界は反転した。
結晶を覗き込んだ僕の目に映ったのは、父でも、母でも、妹でもなかった。
父さんがいた場所には、大地に深く根を張り、天を衝くほどの巨木がそびえ立っていた。その幹には無数の傷が刻まれ、枝は折れ、葉は枯れかかっている。母さんの姿は、世界を優しく覆う大空そのものだったが、その空には大きな亀裂が走り、虚無の闇が覗いている。リナは、悠久の時を刻むはずの星々の運行そのものだったが、幾つもの星が光を失い、冷たい骸となって軌道を外れていた。
彼らは、人間ではなかった。この世界の「絆の法則」を司る、根源たる存在。創造主であり、世界の庭を手入れする、孤独な庭師たちだった。
結晶を通して、彼らの記憶が奔流となって僕の意識に流れ込む。人々が絆を失い、法則が崩壊を始めた時、彼らは自らの身体を器として、世界の歪みと苦痛をすべて吸収し始めたのだ。僕が見ていた奇妙な模様は、その壮絶な痛みの痕跡だった。世界が人間らしい形を保てなくなる中、彼らだけが変貌しながらも形を保っていたのではない。彼らが変貌することで、世界の崩壊をわずかに食い止めていただけなのだ。
そして、僕の真実も。
僕は、この法則に汚されない『最も純粋な絆』を体現するために、彼らによって意図的に切り離された存在。世界の行く末を見届けるための、たった一人の「観察者」。だから、僕自身の肌には何の模様も浮かばなかった。だから、彼らの真の苦しみを、僕だけが認識できなかったのだ。
第五章 観察者の選択
足元から世界が崩れていくような感覚に襲われながら、僕はリビングの扉を開けた。結晶越しではない、僕の裸眼に映る家族の姿は、もはや限界だった。父の肌は枯れ木のようにはぜ、母の輪郭は陽炎のように揺らぎ、リナは小さな影の中に沈み込んでいる。彼らは、僕の帰りを待っていたかのように、苦痛に歪んだ顔で微笑んだ。
「…見てしまったか、カイ」
父さんの声は、風に擦れる枯れ葉のようだった。
「お前は、この庭の最後の希望だ。我々が消えれば、法則も消える。世界は…真の無に還る」
母さんが、か細い腕を僕に伸ばそうとして、力なく落とす。リナの頬からは、黒い涙のような澱みが静かに零れ落ちていた。
僕は、観察者。このまま、愛する家族が、そしてこの世界が崩壊していくのを、ただ見ていることしかできないのか。純粋な絆として、誰とも交わらず、独りで存在し続けることが、僕の役目なのか。
違う。
そんなのは嫌だ。
蔦に励まされ、陽光に包まれ、星屑に笑いかけた、あの日々が僕の全てだった。たとえそれが、歪みを隠すための虚構だったとしても。
「僕はもう、独りで見ているのは嫌だ」
涙が頬を伝う。僕はポケットから結晶を取り出し、それを強く握りしめた。そして、崩れかけた家族の中心へと、ためらわずに歩み寄る。観察者としての役目を放棄し、初めて自らの意思で、彼らの法則に干渉する。
「僕も、家族だ」
僕が震える手で、三人の手にそっと触れた。
第六章 新しい庭の夜明け
僕の手が家族に触れた瞬間、絆の結晶が心臓のように強く脈打ち、砕け散った。そこから放たれたのは、創世の光。まばゆい光が僕たちを、家を、街を、そして世界そのものを包み込んでいく。あらゆる形が溶け、あらゆる色が混じり合い、時間の感覚さえもが消え去った。
どれほどの時が経ったのか。
光が収まった時、そこに広がっていたのは、僕の知らない世界だった。
石像と化していた人々は、互いに寄り添う苔むした森となり、風に歌っている。ドライフラワーの髪を持っていた少女は、恋人だった青年と共に、空を舞う一対の美しい鳥になっていた。人々はもはや、固定された「人間」という形に縛られてはいなかった。ある者は家族と融合して一本の川となり、ある者は友と繋がり合って地平線に架かる虹となる。それは、絆の在り方が無限に許容された、流動的で多様な、新しい世界の夜明けだった。
父も、母も、リナも、もういない。彼らは苦痛から解放され、僕を包み込む柔らかな光の粒子となって、この新しい世界の隅々に満ちていた。独りになったはずなのに、不思議と孤独ではなかった。
僕は自分の腕を見下ろす。
そこには、生まれて初めて、模様が浮かび上がっていた。
それは、赤や青、緑や金、あらゆる色が混じり合い、絶えず形を変え続ける、万華鏡そのもののような模様。この新しい世界の、無限の絆の形を映した模様だった。
僕は一人でありながら、すべてと繋がっている。
かつての観察者は、今、この新しい庭を見守る、最初の庭師となった。終わりであり、始まりの庭で、僕は静かに息を吸い込んだ。