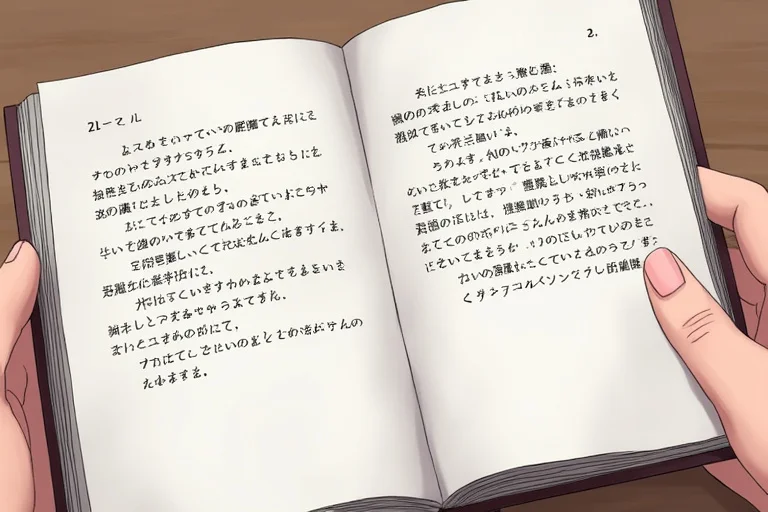第一章 失われた色彩
私の家族は、少しだけ特別だった。私たちは、感情の色を共有していたのだ。
父が仕事で成功した日の夕食は、食卓全体が誇らしげな黄金色に輝いた。母が丹精込めて育てた庭のバラが咲いた朝は、窓から差し込む光が生命力あふれる若草色に染まった。弟とくだらないことで笑い転げた休日は、部屋中が弾けるような空色の粒子で満たされた。私はその色が大好きだった。それは、目には見えないけれど確かに存在する、家族という絆の証明そのものだったからだ。
しかし、その色彩は、ある日を境にぷつりと消えた。
きっかけが何だったのか、今となっては思い出せない。気づいた時には、私たちの家は音を失った映画のように、完全なモノクロームの世界に変わっていた。食卓に並ぶ色とりどりの料理も、ただの濃淡の集合体にしか見えない。父の深い愛情を表していた温かなオレンジ色は消え、母の優しさを象徴していた柔らかな緑色も失われた。弟の好奇心旺盛な水色も、今はくすんだ灰色に沈んでいる。
「今日のハンバーグ、おいしいね」
母が、張り付けたような笑顔で言う。その言葉からは、かつて感じられたはずの明るいピンク色の響きが少しも立ち上ってこない。
「ああ」
父は新聞から目を離さずに短く応える。彼の周りは、何を考えているのか分からない、底なしのインクのような黒に塗りつぶされている。
弟のハルは、ヘッドフォンで耳を塞ぎ、ただ黙々とフォークを動かしているだけだ。彼の世界は、拒絶を示す硬質な鉛色で閉ざされている。
私、ユキだけが、この異常事態に気づいていた。いや、もしかしたら皆気づいているのかもしれない。けれど、誰もそのことには触れようとしない。まるで、色が見えていたこと自体が、私一人の幻覚だったかのように。
「誰かが嘘をついているんだ」
私は確信していた。この色の喪失は、家族の誰かが本当の感情を隠し、偽りの仮面を被っているせいだ。そうでなければ、こんなにも世界が色褪せてしまうはずがない。父の無関心? 母の空元気? それとも弟の反抗心? 犯人は誰だ。私は、失われた色彩を取り戻すため、密かに家族という名の容疑者たちを観察し始めた。このモノクロームの食卓に、もう一度、あの温かい色を取り戻す。それが、この家に生まれた私の、たった一つの使命のように思えた。
第二章 色の残滓と疑念
色彩を探す日々が始まった。それは、乾いた川底で、かつて水が流れていた痕跡を必死で探すような、虚しくも切実な作業だった。
古いアルバムを引っ張り出すと、そこには色鮮やかな記憶が溢れていた。七五三の日、金色の光に包まれてはにかむ私。海ではしゃぐ家族の周りには、きらきらと輝く青と白の飛沫が舞っている。写真の中の私たちは、間違いなく幸福の色を放っていた。ページをめくる指先が、微かに震える。この温もりは、幻なんかじゃなかった。
私は探偵のように、家の中を歩き回った。父の書斎に足を踏み入れる。埃っぽい本の匂いと、微かなインクの香り。父が長年愛用している万年筆のそばに、ほんの一瞬、燃えるようなオレンジ色の残光が見えた気がした。だが、目を凝らした時にはもう、それは冷たい灰色の闇に吸い込まれていた。
母が庭で花の手入れをしている時もそうだ。彼女が萎れたアジサイの花びらにそっと触れた瞬間、その指先から慈しむような淡い緑色が滲み出すのが見えた。しかし、私が「お母さん」と声をかけると、その色は蜘蛛の子を散らすように消え去り、母はいつもの作り笑いを私に向けるだけだった。
疑念は、私の中で黒い染みのように広がっていく。一番怪しいのは、弟のハルだ。彼は最近、自分の部屋に閉じこもってばかりいる。何を聞いても「別に」「関係ない」としか言わない。彼の閉ざされたドアの向こうには、どんな色の感情が渦巻いているのだろう。ある夜、私はこっそりと彼の部屋に忍び込んだ。乱雑に散らかった机の上に見慣れない手紙が置いてあるのを見つけ、手を伸ばした瞬間、背後でドアが開いた。
「何してんだよ」
ハルの声は、氷のように冷たかった。彼の瞳は、かつてないほど濃い、拒絶の鉛色をしていた。
「別に、何も……」
「人の部屋、勝手に入るなよ。気持ち悪い」
突き放すような言葉が、鋭いナイフのように私の胸に突き刺さる。私たちは激しく口論になり、その日以来、ハルは私と一切口を利かなくなった。
母にも問い詰めた。「最近、何か隠してない? 家族みんな、おかしいよ」と。母は一瞬だけ悲しそうに顔を歪め、すぐにいつもの笑顔に戻って言った。「考えすぎよ、ユキ。詮索するのはやめてちょうだい」。その言葉は、優しさの皮を被った拒絶だった。
家族の間にできた溝は、日に日に深くなっていく。色彩を取り戻そうとすればするほど、私たちはバラバラになっていくようだった。モノクロームの世界は、静かに、だが着実に、私たちの心を蝕んでいた。もう、あの温かい食卓に戻ることはできないのかもしれない。そんな絶望が、私の心を重く支配し始めていた。
第三章 モノクロームの真実
その夜、夕食の席で、ついに溜め込んでいたものが爆発した。きっかけは、私の「どうして誰も本当のことを言わないの!」という叫びだった。
「何の話だ」と父が低く言い、母は泣きそうな顔で俯いた。ハルは「また始まったよ」と吐き捨てるように言った。
「みんな嘘つきだ! この家はもう、偽物だ!」
感情のままに叫び、私は椅子を蹴立てて家を飛び出した。冷たい夜の雨が、容赦なく私の体を叩く。涙なのか雨なのか分からない液体が頬を伝い、滲んだ視界の中で、街のネオンサインが意味のない光の塊としてぼんやりと揺れていた。
当てもなく彷徨ううちに、私は古びた一軒の写真館の前に立っていた。ショーウィンドウに飾られたセピア色の家族写真。そうだ、ここは、私がまだ幼い頃、家族写真を撮った場所だ。ガラス戸の向こうに明かりが灯っているのが見え、私は吸い寄せられるようにドアノブに手をかけた。
中から現れたのは、白髪の優しい目をした老人だった。彼は私の顔を見るなり、驚いたように目を見開いた。
「おお、君は……確か、ユキちゃん、だったかな。大きくなったねえ」
写真館の主人は、雨に濡れた私を温かく迎え入れ、熱いココアを差し出してくれた。彼は私の家族のことをよく覚えていた。
「君のお父さんとお母さんはね、本当に君を大切にしていたよ。特に……そう、君を『家族』として迎えた日、あの日のことは忘れられない。写真館の中が、まるで光そのものになったみたいに、眩しく輝いていたんだ」
「……家族として、迎えた日?」
聞き慣れない言葉に、私は首を傾げた。主人は少し言い淀んだ後、店の奥から一枚の古い写真を持ってきた。
そこに写っていたのは、私よりもずっと若い父と母、二人だけだった。寄り添う二人は、幸せそうでありながら、どこか寂しげな影を宿しているように見えた。
「君がこの家に来る前の、お二人だよ」
主人は静かに語り始めた。私の両親が、長い間子供に恵まれなかったこと。そして、ある日、生まれたばかりの私を養子として迎えることを決めたこと。写真館の主人が言った「君を家族として迎えた日」とは、その日のことだったのだ。
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。私は、養子だった。血の繋がりがない、本当の家族ではなかった。
その瞬間、パズルのピースが恐ろしい音を立ててはまっていくのが分かった。
世界から色が失われたのは、いつからだっただろう。それは、私が思春期を迎え、「自分とは何者か」という漠然とした不安を抱き始めた時期と、ぴったり重なっていた。家族が嘘をついていたわけじゃない。私自身の心の奥底で、無意識のうちに芽生えていた「私は本当にこの家族の一員なのだろうか」という疑念。そのアイデンティティの揺らぎが、共感覚のトリガーである「家族であるという絶対的な確信」を蝕み、私の世界から色を奪っていたのだ。
父の無口さも、母の過剰な明るさも、ハルの反抗的な態度も、すべては違っていた。彼らは、私が傷つかないように、この真実から私を守ろうとして、不器用な愛情表現をしていたに過ぎなかったのだ。私が「偽物」だと思っていたのは、家族ではなく、私自身の、家族に対する不確かな心だった。雨音だけが響く写真館の中で、私はただ、呆然と立ち尽くしていた。
第四章 名もなき色
雨の中を、私は夢遊病者のように歩いて家に帰った。玄関のドアを開けると、リビングの明かりの下、心配しきった顔の父と母、そしてハルが私を待っていた。彼らの周りは、相変わらず色のない、深い灰色に包まれている。
「ユキ……」
母が震える声で私の名前を呼んだ。
私は、写真館で聞いた話を、途切れ途切れに話した。自分が養子だったこと、それを知ったこと。私の言葉を聞きながら、父は深く目を閉じ、母は静かに涙を流し始めた。
沈黙の後、父がゆっくりと口を開いた。
「ずっと、言わなければと思っていた。だが、いつ言えばいいのか、どう伝えれば君を傷つけずに済むのか、分からなかったんだ。すまない……」
「あなたを愛していない日なんて、一日もなかったわ」と母が泣きじゃくりながら言った。「血が繋がっているとか、いないとか、そんなこと、私たちにとっては一度も問題じゃなかった。あなたは、私たちの、たった一人の大事な娘よ」
隣に立っていたハルが、ぼそりと言った。
「……俺、姉ちゃんがいなくなるんじゃないかって、怖かったんだ。最近、ずっと変だったから。どう接していいか分からなくて……だから、つい……」
彼らの言葉は、飾りのない、ありのままの感情だった。不器用で、ぎこちなくて、でも、紛れもない真実の言葉だった。私が抱えていた孤独感の正体を知った。血の繋がりという「証拠」がないことへの、無意識の不安。その不安を、家族のせいにして、私は一人で苦しんでいたのだ。
必死に私を守ろうとしてくれた家族の姿に、胸の奥から、今までに感じたことのない温かい感情が込み上げてきた。それは、単純な喜びでも、安堵でもない。後悔と、感謝と、切なさと、そして確かな愛情が複雑に混ざり合った、深い深い感情だった。
その瞬間、世界に、ふわりと色が戻り始めた。
しかし、それは以前のような単純な金色やオレンジ色ではなかった。父の深い後悔を表す藍色、母の変わらぬ愛情を示す深紅、ハルの安堵と照れ臭さが混じった若葉色、そして私の涙から生まれたであろう透明な光。それら全ての色が、まるで水彩絵の具のように溶け合い、混じり合い、私たちの周りを優しく包み込んでいた。
それは、名前をつけることのできない、複雑で、どこまでも美しい「名もなき色」だった。血の繋がりを超え、嘘や過ちを乗り越え、それでもなお、共にいようと願う心だけが紡ぎ出すことのできる、私たちだけの家族の色だった。
食卓に、再び四人で座る。まだ少しぎこちない空気は残っているけれど、モノクロームの世界はどこにもなかった。テーブルの上には、あの名もなき色が、オーロラのように静かに揺らめいている。完璧な色でなくてもいい。この不確かで、複雑で、それでも確かにここに存在する温かい光こそが、私たちの「家族」の本当の姿なのだ。私は、その美しい光を、ただ静かに見つめていた。