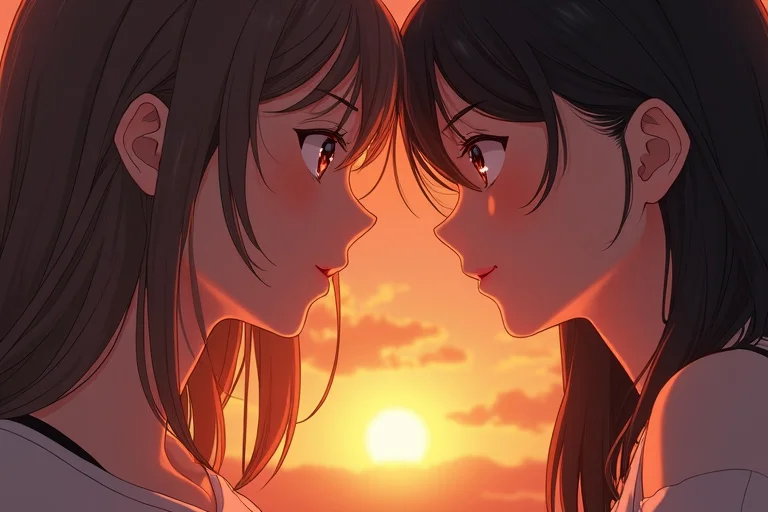第一章 軋む過去
「一度、帰ってきてくれないか。お父さんの調子が、あまり良くないの」
受話器の向こうから聞こえる母の声は、いつになく細く、張り詰めていた。俺、広瀬陽太は、都心のアパートで無感動にその言葉を受け止めていた。父さん、か。頑固で、無口で、俺が大学進学を機に家を出てからというもの、まともに話した記憶すらない。その父が、病気? にわかには信じがたかった。あの人は、まるで家の太い大黒柱のように、揺らぐことなどない存在だと思っていたからだ。
週末、重い腰を上げて乗り込んだ電車は、見慣れた景色を窓の外へ猛スピードで流していく。高層ビル群が低層の住宅街に変わり、やがて緑の匂いが濃くなってくる。最寄り駅に降り立つと、湿った土と植物の匂いが鼻腔をくすぐり、それが実家の匂いなのだと不意に思い出した。
坂道を上り、角を曲がると、古びた木造二階建ての我が家が見えてくる。陽太が生まれるずっと前から、広瀬家を雨風から守ってきたその家は、くすんだ焦げ茶色の壁と、少し傾いだ瓦屋根で、時の流れを全身に刻みつけていた。
玄関の引き戸を開けると、ギィ、と耳慣れた音がする。そして、家の奥から漂ってくる、古い木と埃の混じった懐かしい匂い。
「陽太、おかえり」
エプロン姿の母が、ぱたぱたとスリッパを鳴らして出迎えてくれた。その顔には、隠しきれない疲労の色が浮かんでいる。
「父さんは?」
「二階の寝室よ。今は眠っているわ」
荷物を置き、手を洗ってから二階へ向かう。階段が、俺の体重にみしり、と悲鳴を上げた。昔からこの家はよく鳴った。夜中にトイレに起きれば、床板が軋み、風が吹けば窓がカタカタと震える。それが当たり前の日常だった。
父の寝室の襖をそっと開ける。そこに横たわる父の姿は、俺の記憶にあるものとはまるで別人だった。大地に根を張る大木のような頑健さは影を潜め、まるで冬の枯れ木のように細く、小さくなっている。穏やかな寝息だけが、彼がまだここにいることを示していた。
その時、ふと壁に視線が吸い寄せられた。薄暗い部屋の壁紙に、水が滲んだような、不気味な黒い染みが広がっている。まるで巨大な影が、壁の内側から浮かび上がろうとしているかのようだ。見ているだけで、背筋がぞくりと冷たくなる。
「……あの染み、何?」
階下で母に尋ねると、母は一瞬、視線を泳がせた。
「さあ……家が古いから、雨漏りでもしたのかしらね」
その答えは、明らかに何かをはぐらかしていた。
その夜、異変はさらに明確になった。深夜、トイレに起きて廊下を歩いていると、誰もいないはずの子供部屋から、くすくすという笑い声が聞こえたのだ。幼い頃の俺と、今は嫁いで家を出た姉の声。あまりの生々しさに、心臓が跳ね上がる。慌てて部屋を覗き込むが、そこには月明かりに照らされた埃っぽい空気が漂っているだけだった。
気のせいか。疲れているんだ。そう自分に言い聞かせようとしても、一度芽生えた疑念は消えない。この家で、何かが起きている。それは、父の衰弱と、決して無関係ではない。そんな確信にも似た予感が、俺の胸の中で冷たく渦巻いていた。
第二章 壁に滲む面影
実家での生活は、奇妙な現象との同居だった。二階から聞こえる過去の笑い声は一度きりではなかった。ある時は、台所でトントンと小気味よく包丁がまな板を叩く音がした。それは、料理好きだった祖母がまだ元気だった頃の音によく似ていた。またある時は、玄関で「ただいま」という、若々しい父の声が響いた。まるで、家そのものが、過去の記憶を無差別に再生しているかのようだった。
俺は、非科学的なものを信じる性質ではなかった。だが、五感に直接訴えかけてくるこれらの現象を、気のせいや幻聴で片付けるには、あまりにも現実味を帯びすぎていた。
父の容態は、良くも悪くもならず、ただ静かに眠り続けている時間が長くなっていった。しかし、父の部屋の壁に広がっていた黒い染みは、日を追うごとにその形を複雑に変えていった。それはもはや単なる染みではなかった。目を凝らせば、そこに輪郭が見える気がした。七五三で紋付袴を着た幼い俺と、その手を取る若い父。縁側で日向ぼっこをする祖父母。家族旅行で撮った集合写真のシルエット。壁は、まるで古いアルバムのページのように、広瀬家の歴史を曖昧に映し出していた。
「母さん、やっぱりこの家、おかしいよ。壁の染みも、聞こえてくる音も……」
耐えきれず、再び母に詰め寄った。母は、茶碗を洗いながら、その手を止めずに静かに言った。
「陽太。あなたは、この家が生きていると言ったら、信じる?」
「……は?」
予想外の言葉に、俺は間抜けな声を出した。
「この家はね、私たち家族と一緒に、歳をとってきたの。嬉しいことも、悲しいことも、全部この壁や柱が覚えていてくれる。だから時々、昔を懐かしんで、音を立てたりするのよ。ただ、それだけ」
母の横顔は穏やかだったが、その瞳の奥には、諦めにも似た深い感情が宿っていた。それは、真実のほんの一部だけを切り取って見せられたような、もどかしい感覚を俺に残した。
俺は家のことを調べ始めた。屋根裏に上り、床下を覗き、古い図面を引っ張り出した。そこで奇妙なことに気づく。この家の設計図には、本来あるべきはずの基礎の部分に、まるで木の根のように複雑に絡み合った、奇妙な構造体が描かれていたのだ。そして、家の中心、父の寝室の真下にあたる場所には、同心円状の模様が記されていた。まるで、そこが全ての起点であるかのように。
ある日の午後、父の部屋の掃除をしていると、枕元から、ふわりと甘い香りが漂ってきた。金木犀のようでもあり、熟した果実のようでもある、どこか懐かしくて、心を落ち着かせる香りだった。香りの源を探すと、それは父の身体そのものから発せられているようだった。衰弱しているはずの父の肌は、不思議と艶があり、安らかな表情で眠っている。
その瞬間、バラバラだったピースが一つに繋がるような、恐ろしい直感が俺の背筋を駆け抜けた。この家。父の衰弱。壁の染み。過去の音。そして、この甘い香り。これらは全て、一つの大きな流れの中で起きているのではないか。そして、その中心にいるのは、紛れもなく父なのだ。俺は、家族が守ってきた巨大な秘密の、その輪郭に触れようとしていた。
第三章 最後の家賃
その夜は、嵐だった。激しい雨が屋根を打ち、風が家の隙間を縫って不気味な笛の音を立てる。夜中の二時頃だっただろうか。突如、家全体が地響きのように、ごとり、と大きく揺れた。同時に、全ての明かりが消え、世界が完全な闇に包まれた。
停電か。俺はスマートフォンのライトをつけ、階段を駆け上がった。胸騒ぎが止まらない。父の部屋だ。何かが起きる。いや、もう起きてしまったのかもしれない。
襖を開けた瞬間、俺は息を呑んだ。部屋の中は暗闇ではなかった。横たわる父の身体が、まるで内側から発光しているかのように、淡い、金色の光を放っていたのだ。その光は、ゆっくりと明滅し、鼓動と同期しているかのように見えた。そして、信じられない光景が目の前で繰り広げられた。
父の身体から、無数の光の粒子が、きらきらと舞い上がり始めた。それはまるで、真夏の夜の蛍の群れのようだった。粒子は、ゆっくりと上昇し、部屋の壁へ、床へ、そして天井へと、吸い込まれていく。光が吸い込まれた壁の一部は、一瞬だけ鮮やかな色彩を取り戻し、そこに満面の笑みを浮かべた家族の姿を幻のように映し出した。
「……陽太」
背後から、母の静かな声がした。いつの間に来たのか、母はロウソクを手に、穏やかな表情でその光景を見つめていた。
「見てしまったのね。これが、広瀬家に代々伝わる、最後の儀式よ」
母の口から語られた真実は、俺のちっぽけな常識を粉々に打ち砕いた。
この家は、生きていた。母が言った通りに。しかし、それは比喩などではなかった。この家は、広瀬家の血と記憶を糧とする、一つの生命体なのだ。先祖がこの土地に根を下ろした時、土地の精霊と契約を交わし、家族を守護する代わりに、その記憶と生命力の一部を「家賃」として家自身に捧げることを約束したのだという。
日々の暮らしの中で生まれる小さな喜びや悲しみは、家にとっての滋養となる。家族が幸せであるほど、家は強固になり、災厄から家族を守る。そして、一族の誰かがその生涯を終える時、その人物が持つ全ての記憶と生命力を、最後の、そして最大の「家賃」として家へ捧げる。そうすることで、その魂は消滅するのではなく、家の一部となり、永遠に家族を見守り続ける存在となるのだ。
「お父さんは、自分の死期を悟っていたの。だから、私たちに別れを告げるように、自分の人生の全てを、この家に明け渡しているのよ」
壁に滲んでいた染みは、父の膨大な記憶が溢れ出した痕跡だった。聞こえていた過去の音は、父の記憶の断片が、家という媒体を通して漏れ聞こえてきたものだったのだ。そして、父の身体から漂っていた甘い香りは、凝縮された生命そのものの香りだった。
俺は、言葉を失って立ち尽くす。目の前で起きていることは、死ではない。それは、父という一個人が、「家」というより大きな生命の流れに還っていく、荘厳な融合の儀式だった。冷徹な現実主義者だった俺の世界は、音を立てて崩れ、そして再構築されていく。家族とは、血の繋がりだけではない。この家そのものが、俺たちの記憶を抱き、命を繋ぐ、巨大な揺りかごだったのだ。
光の粒子が、最後のきらめきを放ちながら壁に吸い込まれていく。それに伴い、父の身体を包んでいた光は次第に弱まり、やがて完全に消えた。部屋には、嵐の音とロウソクの揺れる炎だけが残された。父は、まるで全ての役目を終えたかのように、ただ静かで、安らかな顔をしていた。
第四章 ただいま、我が家
父が「家」に還った翌朝、嵐は嘘のように過ぎ去り、空は突き抜けるような青色をしていた。家全体が、不思議な静けさと、そして温かみに満ちていることに、俺は気づいた。あれほど鳴り響いていた家鳴りはぴたりと止み、床を踏んでも、もう不気味な音はしない。まるで、満腹になった赤ん坊が、満足して眠りについたかのようだった。
父の寝室だった部屋に入ると、壁の染みは跡形もなく消えていた。その代わり、朝日が窓から差し込むと、光が当たった壁の一部分に、虹色の光の模様がうっすらと浮かび上がった。それはただの光の屈折かもしれない。けれど俺には、それが「ありがとう」と微笑む父の顔のように見えた。
葬儀は、ごく近しい親族だけでささやかに行った。参列者は皆、父が安らかな顔で旅立ったことを慰めにしていたが、その本当の意味を知っているのは、俺と母だけだった。俺たちは、父の亡骸を弔うと同時に、家となった父の新たな誕生を祝っていたのかもしれない。
東京のアパートに戻る日、俺は荷造りをしながら、ずっと考えていた。あの冷たくて狭い、コンクリートの箱のような部屋のことを。そこに「家族」はいない。思い出も、温もりも、根付くことはない。
玄関で、母が俺を見送ってくれた。
「陽太。いつでも帰ってきていいのよ。ここは、あなたの家なんだから」
母の言葉が、すとんと胸に落ちた。そうだ。ここは、俺の家だ。父がいて、祖父母がいて、これから生まれてくるかもしれない俺の子供たちの記憶も受け入れてくれる、俺たちの家なんだ。
「……母さん、俺、戻ってくるよ。あのアパート、引き払って、ここに戻ってくる」
俺の言葉に、母は一瞬だけ驚いたように目を見開き、そして、ふわりと花が咲くように笑った。その笑顔は、俺が今まで見た中で、一番美しかった。
数週間後、俺は全ての荷物をまとめ、再び実家の引き戸を開けた。
「ただいま」
その声は、自分でも驚くほど自然に出た。すると、俺の言葉に応えるかのように、家の奥の大黒柱が、ぽん、と乾いた優しい音を立てた。それはもう、老朽化した家の軋む音ではない。温かい血の通った、家族からの「おかえり」という返事だった。
俺はゆっくりと家の中に入り、その大黒柱にそっと手を触れた。ひんやりとした木の感触の下に、確かに感じた。ごく微かな、温かい脈動を。それは、この家で生きてきた全ての家族の鼓動であり、そして、俺を迎え入れてくれた父の鼓動でもあった。
「ただいま、父さん」
俺は、もう一度、今度は柱に向かって呟いた。風が窓を優しく揺らし、家全体が心地よい静けさで俺を包み込む。俺はもう、どこにも行く必要はない。俺の居場所は、家族の記憶が棲む、この家なのだから。見えないけれど、確かにここにいる家族と共に、俺は新しい日々を生きていく。そう、心に誓った。