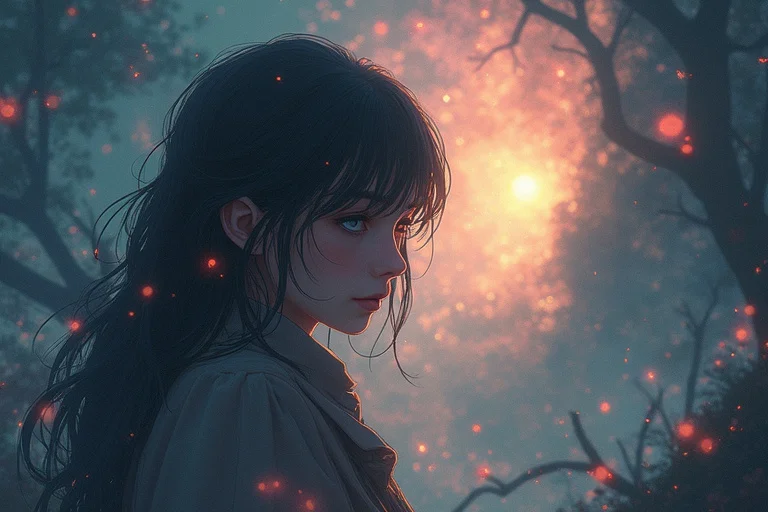第一章 静寂の万華鏡
埃っぽい匂いが、記憶の底にある何かを静かに揺り起こしていた。祖母が亡くなって三ヶ月。俺、水野湊(みずの みなと)は、誰も住まなくなったその家の遺品整理に一人で来ていた。蝉の声すら遠い、午後の気だるい光が差し込む和室で、桐箪笥の引き出しを一つずつ開けていく。着物、古い写真、価値の分からない置物。その一番奥に、それはあった。黒檀の筒に螺鈿細工が施された、古風な万華鏡。
子供の頃、祖母の膝の上でよくこれを覗き込んだものだ。くるりと回すたびに、色ガラスの破片が生まれ変わり、二度と同じ模様を見せることはない。「世界はね、湊。こうやって、ほんの少し見方を変えるだけで、いくらでも美しくなるんだよ」。耳元で囁く、優しかった祖母の声が蘇る。懐かしさに駆られ、俺は万華鏡の接眼レンズにそっと目を当てた。
その瞬間、世界が反転した。
色ガラスの幾何学模様ではない。目の前に広がったのは、息を呑むほど鮮やかな、見知らぬ風景だった。視界いっぱいの瑠璃色の空、地面にはエメラルドグリーンの苔が絨毯のように広がり、金糸のような光の粒子が舞っている。だが、何かがおかしい。風が木々を揺らし、花びらが宙を舞っているのに、音が、一切ないのだ。葉擦れの音も、鳥のさえずりも、自分の足音すらも。まるで最高級のノイズキャンセリングヘッドホンを装着したかのような、完璧な静寂が世界を支配していた。
混乱し、万華鏡から目を離そうとした。だが、離れない。それどころか、俺の身体はぐにゃりと歪む感覚と共に、風景の中へと吸い込まれていった。最後の意識に残ったのは、手から滑り落ちた万華鏡が畳の上で立てた、乾いた音だけだった。
気がつくと、俺は本当にあの風景の中に立っていた。足元の苔は羽毛のように柔らかく、吸い込んだ空気は澄み切って、ほのかに金木犀の香りがした。しかし、静寂は変わらない。自分の心臓の鼓動すら聞こえない、圧迫感のある無音の世界。ここはどこだ? 夢か? だとしたら、あまりにリアルすぎる。俺は声を張り上げようとしたが、喉から漏れ出たのは声にならない吐息だけだった。この世界では、音そのものが存在を許されていないようだった。
第二章 色彩の追憶
音のない世界での時間は、奇妙なほど穏やかに流れた。俺はあてもなく歩き続けた。不安よりも、どこか懐かしいという不思議な感覚が心を占めていたからだ。小高い丘を越えると、眼下に小さな集落が見えた。茅葺屋根の家々が並び、その間を人々がゆっくりと行き交っている。彼らは皆、穏やかな表情をしていた。
俺は勇気を出して、井戸端で立ち話をしているらしい二人の女性に近づいた。彼女たちは俺に気づくと、にこりと微笑んだ。口が動き、何かを語りかけてくる。しかし、声は聞こえない。身振り手振りで「どこから来たのか」と問われているようだった。俺が自分の状況を説明しようとしても、やはり声は出ない。言葉というコミュニケーションツールを奪われたもどかしさが、胸を締め付けた。
だが、彼らとの意思疎通が全く不可能というわけではなかった。彼らは俺の表情を読み、身振りを汲み取り、驚くほど正確に意図を理解してくれた。そして、この世界のことを教えてくれた。ここは「彩ノ国(さいのくに)」。言葉の代わりに、心で通じ合う民が暮らす、永遠に穏やかな場所なのだと。
日々を過ごすうち、俺はこの世界の風景が、祖母との思い出の断片で構成されていることに気づき始めた。集落の外れに咲き誇るコスモス畑は、幼い頃に祖母と手をつないで歩いた河川敷の景色そのものだった。集落の長老らしき老人が見せてくれた古い絵巻には、祖母が寝物語に聞かせてくれた龍の伝説が描かれていた。そして、人々が飲む茶は、祖母がいつも淹れてくれた、少し甘めのほうじ茶の味がした。
ここは、祖母の記憶が作り出した世界なのではないか。
その仮説は、ある種の安らぎを俺に与えた。大好きな祖母が愛した風景の中で、彼女の優しさに包まれているような感覚。音がないことも、晩年、耳が遠くなっていた祖母の世界を追体験しているようで、腑に落ちた。ならば、俺がここにいる意味は何だろう。どうすれば、元の世界に帰れるのだろう。
長老は、身振りで世界の中心にある「音の泉」を目指せと教えてくれた。そこに行けば、全ての問いの答えが見つかるだろう、と。俺は頷き、集落を後にした。懐かしくも奇妙なこの世界からの脱出を願いながらも、心のどこかでは、このままここにいたいと願う自分がいることに、まだ気づいていなかった。
第三章 音なき真実
光の粒子が道しるべのように舞う中を、俺はひたすら歩いた。やがて、巨大なクスノキがそびえ立つ、ひときら明るい場所にたどり着いた。木の根元には、水晶のように透き通った水が湧き出る泉があった。これが「音の泉」だろう。しかし、水面は鏡のように静まり返り、せせらぎの音一つ立てていなかった。
泉のほとりに、一人の女性が佇んでいた。白いワンピースを着た、長い黒髪の女性。彼女がゆっくりと振り向いた瞬間、俺は息を呑んだ。それは、古い写真でしか見たことのない、若き日の祖母の姿だった。
『よく来たね、湊』
驚いたことに、彼女の声ははっきりと俺の頭の中に響いた。それは紛れもなく、優しかった祖母の声だった。
「ばあちゃん……? どうして……それに、ここは一体……」
俺が心の中で問いかけると、彼女は悲しげに微笑んだ。
『ここは、私が作った世界だよ。耳が聞こえなくなってから、心の中だけで描き続けた、私の大事な思い出の世界。音のない、穏やかで美しい世界』
「やっぱり……。じゃあ、俺はどうしてここに?」
俺の問いに、祖母はしばらく黙っていた。そして、告げられた言葉は、俺の足元を根こそぎ崩壊させるような、残酷な真実だった。
『湊。お前は今、死にかけているんだよ』
――死にかけている?
理解が追いつかない。祖母は続けた。
『お前は、私の家からの帰り道、交差点で事故に遭ったんだ。今、病院のベッドの上で、生死の境を彷徨っている。ここは、お前の魂が迷い込んだ、生と死の狭間の世界。あまりに逝くのが早すぎるお前を、少しでも慰めたくてね。私の魂が、お前をここに呼び寄せたんだよ』
全身から血の気が引いていくのが分かった。あの家の、埃っぽい匂い。畳に落ちた万華鏡の乾いた音。あれが、俺の最後の記憶……? 意識を失う直前の、現実の記憶だったのか。この世界の穏やかさは、死へ向かう魂を鎮めるための、優しすぎる罠だったのだ。
『この世界は、痛みも、苦しみも、悲しみもない。私と一緒に、ここで永遠に過ごすこともできる』
祖母がそっと手を差し伸べる。その手は温かく、抗いがたい引力があった。音のない安寧。愛する祖母との永遠の時間。それは、抗うにはあまりに甘美な誘惑だった。俺の価値観が、生きるという当たり前の前提が、根底から揺らいでいた。
第四章 残響の選択
俺は、差し伸べられた祖母の手に触れることができなかった。この穏やかな世界は、確かに心地良い。だが、本当にそれでいいのか?
脳裏に、現実世界の光景がフラッシュバックする。心配そうな両親の顔。くだらないことで笑い合った友人たちの声。まだ果たせていない約束。これから出会うはずだった人々。これから奏でるはずだった、俺自身の人生の音。それらすべてを、ここで手放してしまうのか?
「……嫌だ」
声にならない声で、俺は呟いた。心の中で、叫んでいた。
「俺は、帰りたい。痛くても、苦しくても、俺の世界に帰って、生きたいんだ」
俺の決意を感じ取ったのか、祖母は寂しそうに、しかし誇らしげに微笑んだ。
『そうかい。……それでこそ、私の孫だ』
彼女の姿が、徐々に透き通っていく。
『一つだけ、覚えておいで。何かを失っても、世界は決して美しさを失わない。見方を変えれば、そこには新しい音が聞こえてくるはずだから』
それは、かつて万華鏡を覗きながら聞いた言葉と重なった。祖母の姿が完全に消える瞬間、彼女は最後に口を動かした。音は聞こえない。だが、俺にははっきりと分かった。
――ありがとう。
その言葉と共に、世界が白い光に包まれた。完璧な静寂が破れ、キーンという鋭い耳鳴りと、自分の心臓が激しく脈打つ音が、頭の中に叩きつけられる。意識が、急速に浮上していく。
次に目を開けた時、俺の目に映ったのは、真っ白な病院の天井だった。
「湊! 気がついたか!」
父の焦った声。母の泣き声。ピッ、ピッ、と単調に鳴り響く生命維持装置の電子音。
生々しい「音」が溢れる世界に、俺は帰ってきたのだ。
事故の影響で、俺は左耳の聴力を完全に失っていた。だが、不思議と絶望はなかった。右耳から流れ込んでくるざわめきの一つ一つが、生きている証として愛おしく感じられた。
退院の日、病室の窓辺には、あの螺鈿細工の万華鏡が置かれていた。母が事故現場から拾ってきてくれたらしい。俺はそれを手に取った。ひんやりとした黒檀の感触が、あの世界の静けさを思い出させた。
俺はもう、それを覗き込むことはしないだろう。
ただ、窓から差し込む光に万華鏡をかざした。筒の中で、色ガラスがキラリと輝く。音もなく、ただ静かに。
失った聴覚の代わりに、俺は新しい音を手に入れた。それは、風の気配や、人の心の温かさ、そして何より、生きているという確かな実感が生み出す、内なる残響だった。
ありがとう、ばあちゃん。俺は心の中で呟き、一歩、新しい日常へと踏み出した。片耳で聞く世界は、以前よりもずっと豊かで、美しい音に満ちていた。