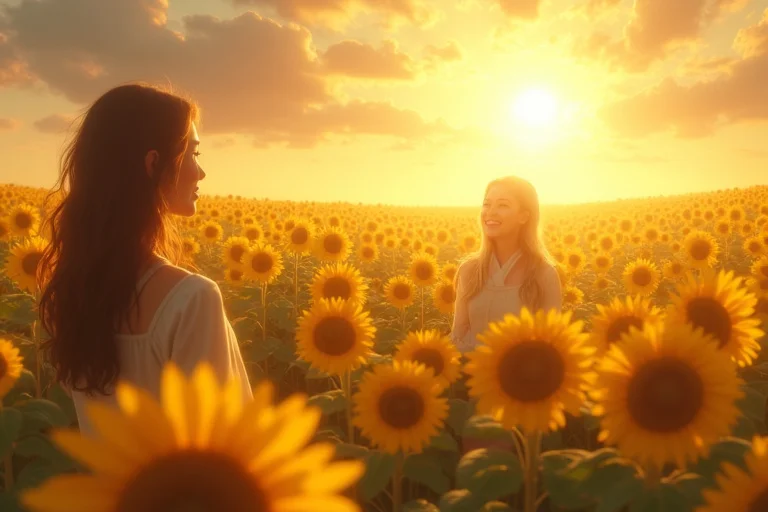第一章 嘘つきに降る雨
私の名前は水野雫(みずのしずく)。そして私には、秘密がある。他人が嘘をつくと、その人の周りにだけ、雨が降るのが見えるのだ。
それは呪いのような能力だった。幼い頃、友達だと思っていた子が、私の悪口を言っていないと嘘をついた時、彼女の頭上から灰色の霧雨が降り注ぐのを見たのが最初だった。以来、私の世界は偽りの湿気に満ちていた。愛を囁く恋人の口元からは甘い香りの小雨が、取引先の営業マンの額からは打算的な土砂降りが、テレビの中の政治家の演説からは、画面が滲むほどの大雨が見えた。人々は、息をするように嘘をつき、そのたびに私の心は冷たく湿っていく。だから私は、人と深く関わることをやめた。静寂と真実だけが詰まった図書館の司書という仕事は、そんな私にとって完璧なシェルターだった。
その日も、私はカウンターの奥で、返却された本にスタンプを押していた。古い紙の乾いた匂いと、インクのかすかな香り。ここには嘘の湿気はない。そう思っていた矢先、入り口のベルが鳴り、一人の青年が入ってきた。
彼を見た瞬間、私は息を呑んだ。彼の周りだけ、絶えず、しとしとと雨が降っていたからだ。
それは私が今まで見たどんな「嘘の雨」とも違っていた。攻撃的でもなく、狡猾でもない。ただひたすらに静かで、透明な雨粒が、彼の肩や髪を濡らし続けている。彼は太陽をそのまま名前にしたような男だった。晴山陽向(はるやまひなた)。屈託のない笑顔を浮かべ、誰にでも朗らかに挨拶をする。図書館の常連であるお年寄りや子供たちも、彼が来るとぱっと顔を輝かせた。
しかし、私の目には、その太陽のような彼の全身が、常に悲しい雨に打たれているようにしか見えなかった。彼は一体、どれほど巨大で、連続的な嘘を吐き続けているのだろうか。彼の存在そのものが、嘘で塗り固められているとでもいうのか。私はカウンターの陰から、本の背表紙をなぞる彼の指先と、それを濡らす見えない雨を、警戒心と、そしてほんの少しの好奇心を持って見つめ続けていた。
第二章 晴れ間のない男
晴山陽向が図書館に通い始めて、一ヶ月が過ぎた。彼は週に三度、決まった曜日にやってきては、児童書のコーナーで熱心に何かを探していた。彼の周りに降り続く雨は、一向に止む気配がない。
私は彼を観察し続けた。彼はいつも笑顔だった。他の利用者に本の場所を尋ねられれば親切に教え、子供が泣き出せば、面白い顔をしてあやしていた。そのどれもが、心からの行動に見える。なのに、雨は降っている。彼の優しさも、親切も、笑顔も、すべてが嘘だというのだろうか。私の能力が狂ったのかもしれないと、初めて思った。
ある日の閉館間際、児童書のコーナーを整理していると、彼が話しかけてきた。
「あの、すみません。ずっと探している本があるんですが」
彼の声は、彼の笑顔と同じように、からりと明るい。だが、彼の足元には、小さな水たまりができているように見えた。
「どのようなご本ですか?」
私は事務的に尋ねた。これ以上、彼に関わるべきではない。心が警鐘を鳴らしていた。
「『星を釣る少年』という絵本です。妹が大好きだった本で……もう絶版になっているみたいなんですけど」
彼の言葉に、私は手を止めた。彼の笑顔が一瞬、揺らいだように見えた。そして、雨足がほんの少しだけ強まる。妹、という言葉に、彼の嘘が関係しているのかもしれない。
「お調べしますので、少々お待ちください」
私はカウンターに戻り、PCで蔵書を検索した。該当する本は、この図書館にはなかった。その事実を告げると、彼は「そうですか……」と、あからさまに肩を落とした。その瞬間、彼の周りの雨が、ほんの少しだけ弱まった気がした。
「残念です。でも、ありがとうございました」
彼はそう言って、またいつもの太陽のような笑顔を浮かべた。途端に、雨は元の強さに戻る。
私は混乱していた。がっかりした表情を見せた時、雨は弱まった。笑顔を取り繕った時、雨は強まった。まるで、彼の「本心」が見えた時に雨が止み、「嘘」で塗り固めた時に雨が降るかのようだ。そんな馬鹿なことがあるだろうか。私の能力は「嘘」に反応するはずだ。
帰り支度をする彼の背中を見送りながら、私は言いようのない苛立ちと、胸の奥がちくりと痛むような奇妙な感覚に襲われていた。彼の降らせる雨は、私の心を静かに、だが確実に侵食し始めていた。彼の嘘の正体を暴きたいという衝動と、彼の本当の顔が見てみたいという願いが、私の中でせめぎ合っていた。
第三章 嵐の夜の告白
その夜、街は猛烈な嵐に見舞われた。閉館時間を過ぎ、最後の利用者が帰ったのを確認した直後だった。ごう、と地鳴りのような風が唸り、図書館の窓ガラスが激しく震える。次の瞬間、世界は完全な闇に包まれた。停電だった。
「きゃっ!」
まだ館内に残っていた数人の利用者の悲鳴が上がる。私も思わず息を呑んだ。非常灯すら点かない。完全な暗闇と、外で荒れ狂う嵐の音だけが、空間を支配していた。その時だった。
「皆さん、落ち着いてください! 大丈夫です!」
暗闇に響いたのは、晴山陽向の声だった。彼はまだ帰っていなかったのだ。
「壁際を伝って、私の声がする方へ来てください。出口まで誘導します」
彼の声には、不思議な説得力があった。人々は彼の指示に従い、ゆっくりと移動を始める。私はカウンターの陰で、その様子を窺っていた。雷光が窓を白く染めるたび、一瞬だけ彼のシルエットが浮かび上がる。人々を励まし、幼い子の頭を撫でる彼の姿。
その時、私は信じられない光景を目にした。雷が光る一瞬、確かに見えたのだ。必死に人々を導く彼の周りだけ、あの忌まわしい雨が、一粒も降っていなかった。彼が「大丈夫」と、人々を安心させるために声を張り上げるその瞬間だけ、彼の周りはからりと乾いていたのだ。
嘘だ。ありえない。人々を安心させるための「大丈夫」は、一種の嘘のはずだ。なのに、なぜ雨が降らない? 私の能力は、私の世界は、根底から覆されようとしていた。
全ての利用者を無事に避難させ、最後に残ったのは私と彼だけだった。嵐は少しずつ勢いを弱め始めていた。暗闇の中、彼が私の方へ歩いてくる気配がする。
「水野さん、怪我はありませんか?」
彼の声は少し疲れていた。私は震える声で、ずっと胸に燻っていた疑問をぶつけた。
「晴山さん……あなた、一体何者なんですか」
「え?」
「あなたの周りには、いつも雨が降っている。私にはそれが見えるんです。あなたが嘘をついているからだと思ってた。でも、今、あなたは嘘をついていたはずなのに、雨は降っていなかった。……どうして?」
暗闇が、彼の表情を隠す。長い沈黙の後、彼はぽつり、と呟いた。
「……見えていたんですね。あなたにも」
その声は、いつもの太陽のような明るさとは程遠い、深く、静かなものだった。
「僕の周りには、いつも雨が降っているんです。子供の頃からずっと。理由なんてわからない。でも、一つだけ分かっていることがある」
彼は一呼吸置いて、続けた。
「僕が、本当の気持ちを口にすると、雨が止むんです」
雷鳴よりも激しい衝撃が、私の全身を貫いた。
私が「嘘見の雨」だと思っていたものは、違ったのだ。
「妹は、一年前に事故で死にました」と彼は言った。「僕は、まだ悲しい。毎日、胸が張り裂けそうなくらい、悲しい。寂しい。でも、そんな顔、誰にも見せられないから、ずっと笑ってた。大丈夫だって、自分にも周りにも嘘をついてきた。僕が嘘をついている間、雨は降り続ける。僕の悲しみが、そうさせてるみたいに」
嵐の夜、人々を助けたいと必死に行動した時、彼は「大丈夫」と嘘をついたのではない。心の底から、人々を助けたいという「本心」で動いていた。だから、その一瞬だけ、彼の悲しみの雨は止んだのだ。
私が「嘘」だと思っていた雨は、彼の「悲しみ」そのものだった。私が持っていた能力は、嘘を暴くための呪いではなかった。他人の心の強い感情が、私には雨として見えていただけなのだ。嘘は強い感情を伴うことが多いから、私はずっと勘違いをしていた。
「あなたの周りに降る雨は、嘘の雨じゃなかった。……あなたの、心の雨だったんですね」
暗闇の中で、私は彼の頬を濡らす、見えない雨粒の正体を、ようやく理解した。
第四章 二人だけの虹
嵐が過ぎ去った翌朝、空は嘘のように晴れ渡っていた。図書館の窓から差し込む光が、空気中の塵をきらきらと輝かせている。私は、一睡もせずに夜を明かした。世界が、昨日までとは全く違って見えていた。
昼過ぎ、晴山陽向が図書館にやってきた。彼の周りには、やはり静かな雨が降っている。しかし、その雨はもう私にとって、忌まわしいものではなかった。それは彼の心の風景であり、彼が懸命に生きている証のように思えた。
「昨日は、すみませんでした。変なことばかり話して」
彼は少し気まずそうに言った。いつもの笑顔は、そこにはなかった。
「ううん」と私は首を振る。「私の方こそ、ごめんなさい。ずっとあなたのことを、嘘つきだって誤解してた」
私はカウンターから出て、彼の前に立った。そして、自分の秘密を打ち明けた。私が「感情の雨」を見る能力を持っていること。そのせいで人間不信になり、世界を信じられなくなっていたこと。
彼は驚いたように目を見開いた後、ふっと息を漏らすように笑った。それは、初めて見る、彼の本当の笑顔のような気がした。
「そっか。じゃあ、僕たちは似た者同士ですね。世界から、少しだけはみ出した」
「そう、かもしれない」
私たちは、互いの秘密を共有したことで、ようやく本当の意味で向き合えた。彼の悲しみの雨は、私だけが理解できる、彼からのメッセージだった。私の能力は、人を断罪するためのものではなく、彼の痛みを受け止めるためにあったのかもしれない。
「『星を釣る少年』、見つかりました」
私は一冊の絵本を差し出した。昨夜、彼が帰った後、徹夜で全国の古書店ネットワークを検索して、一冊だけ見つけ出したものだった。
彼は震える手でそれを受け取ると、表紙を優しく撫でた。彼の目から、本物の涙が一筋、こぼれ落ちる。その瞬間、彼の周りに降り注いでいた雨が、すっと止んだ。まるで、乾いた大地に水が染み込むように、彼の悲しみが静かに涙へと変わっていく。
雨が止んだ彼の周りには、柔らかな光が満ちていた。私は、その光景のあまりの美しさに、言葉を失った。
それから、私たちは時々、一緒に時間を過ごすようになった。彼の周りには、まだ雨が降っている日が多い。悲しみは、そう簡単には消えない。でも、それでいいと私は思うようになった。無理に晴れ間を作る必要はない。雨が降るなら、一緒に傘をさせばいい。時には、二人でその雨に濡れるのも悪くない。
ある日の帰り道、夕立が通り過ぎた後の空に、大きな虹がかかった。
「きれいだね」と彼が言う。彼の周りには、穏やかな小雨が降っていた。
「ええ、とても」
私は彼の隣で、その虹を見上げた。私の目には、二つの虹が見えていた。空にかかる七色の虹と、彼の心の雨が生み出す、私だけに見える透明な虹。
私の能力は、もう呪いではない。世界は嘘で満ちているかもしれないけれど、その雨の向こう側には、こんなにも美しい虹がかかることがある。私は、彼の心の雨と共に生きていくことを選んだ。冷たく湿っていた私の世界に、確かな温もりと色彩が戻り始めていた。