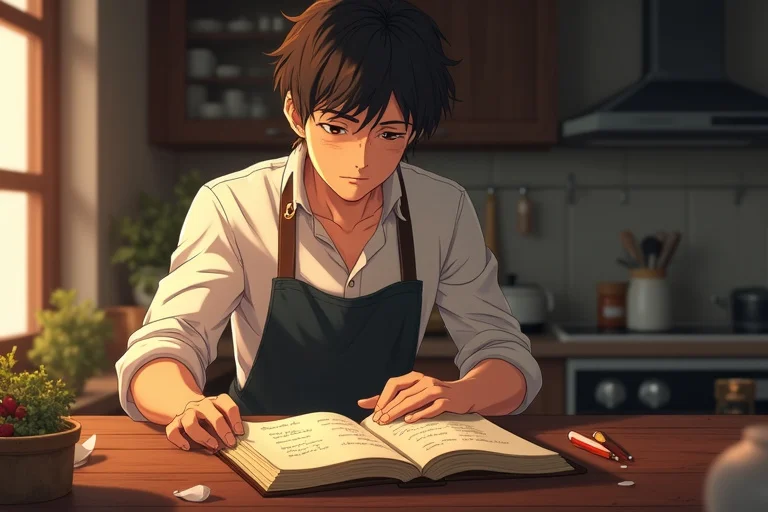第一章 一本針の時計
佐伯健太の日常は、限りなく無駄を削ぎ落とした、効率的な設計図の上にあった。三十四歳、独身。都心のシステム開発会社に勤める彼は、仕事も私生活も、最短距離で目的を達成することだけを信条としていた。感情という不確定要素は、彼の人生のバグでしかなかった。
そんな健太の整然とした日常に、ノイズが混じり始めたのは、隣の102号室に老人が越してきた三ヶ月前のことだ。高橋正治と名乗ったその老人は、柔和な笑顔とは裏腹に、健太の理解を超えた行動を繰り返した。
その最たるものが、ベランダでの奇行だった。高橋さんは毎日、陽が傾き始める午後三時になると、決まってベランダに椅子を出し、古びた置き時計を一心不乱にいじり始めるのだ。錆びついた真鍮の枠、黄ばんだ文字盤。そして何より奇妙なのは、その時計には長針も短針もなく、ただ一本、秒針だけが寂しげに取り残されていることだった。もちろん、その秒針が動くのを健太は一度も見たことがない。
「非効率の極みだ」。健太は自室の窓からその光景を眺めるたび、冷めた溜息を吐いた。壊れた時計を、しかも針が一本しかないものを、毎日毎日飽きもせずに磨いたり、分解しようとしたりしている。その時間があれば、もっと有意義なことができるだろうに。
ある日の夕暮れ、健太がコンビニの袋を提げてアパートの廊下を歩いていると、ちょうどベランダから部屋に戻ろうとしていた高橋さんと鉢合わせた。皺の刻まれた顔に、人の好い笑みが浮かぶ。
「佐伯さん、お帰りなさい」
「……どうも」
会釈だけして通り過ぎようとした健太を、高橋さんが引き止めた。
「あの、佐伯さん。ちょっと耳を澄ましてみてくれんかね」
高橋さんは、大切そうに抱えた一本針の時計を健太の耳元に近づけた。健太は眉をひそめる。当然、何も聞こえやしない。ただ、古びた金属と油の匂いが微かに鼻を掠めただけだ。
「……何も聞こえませんが」
「そうかい。そうだよなあ」
高橋さんは少し寂しそうに笑うと、「わしには、時々聞こえるんじゃよ。カチ、カチ、と……とても懐かしい音がな」と言って、自分の部屋へと消えていった。
健太は、その言葉の意味が分からなかった。老人の戯言か、あるいは認知の歪みか。いずれにせよ、自分には関係のないことだ。彼はそう結論づけ、自分の部屋の分厚いドアを閉めた。しかし、その日から、健太の耳の奥で、存在しないはずの時計の音が、幻聴のように微かに鳴り響き始めたのだった。
第二章 聞こえない音色
健太は高橋さんを避けるようになった。だが、老人はまるで健太の心の壁を見透かすかのように、巧みに関わりの糸を投げかけてきた。ある時は、健太が深夜残業で疲れ果てて帰宅すると、ドアノブに手作りの梅干しが入った小瓶が掛けられていたり。またある時は、健太が子供の頃に好きだったというマイナーな特撮ヒーローの話を、どこから聞きつけたのか嬉々として語りかけてきたりした。
「迷惑だ」と切り捨てられないのは、高橋さんの差し出すものが、不思議と健太の心の隙間にすっぽりと収まったからだ。梅干しは、亡き母がよく作ってくれた味にそっくりだった。特撮ヒーローの話は、父親が蒸発する前、最後に一緒に観た映画の記憶を蘇らせた。
健太の父親は、彼が中学二年生の時に、多額の借金を残して姿を消した。以来、健太にとって父親は、家族を裏切った無責任な男の象徴であり、彼が人間関係に深い壁を築く原因となった最大のトラウマだった。
ある雨の日、健太は高熱を出して会社を休んだ。意識が朦朧とする中、インターホンが鳴る。重い体を無理やり起こしてドアを開けると、そこには心配そうな顔をした高橋さんが立っていた。その手には、湯気の立つ土鍋が抱えられていた。
「顔色が悪いと聞いてな。大家さんから。おかゆ、食べられるかね」
その温かい匂いに、健太の心のダムが少しだけ、軋む音がした。
招き入れた部屋で、高橋さんは手際よく粥をよそいながら、ぽつりと語り始めた。
「わしの妻もな、体が弱くて、よくこうして粥を作ってやったもんじゃよ」
「……奥さん、いらっしゃったんですね」
「ああ。十年前に先立たれたがな。時間の流れが、人より少しだけゆっくりな人だった」
高橋さんは遠い目をして、ベランダに置かれた一本針の時計に視線を送った。
「あの時計は、妻の形見なんじゃ。あいつはいつも言ってた。『時間は長さじゃない、深さよ』ってな。だから、針は一本でいいんじゃ。たくさんの時を刻むより、一つの時を深く感じられれば、それで」
その言葉は、効率と速度だけを追い求めてきた健太の胸に、小さな棘のように突き刺さった。一本の針。それは、失われた時間への執着ではなく、たった一つの大切な時間を慈しむための象徴なのかもしれない。
健太は、自分が今まで「無意味」と断じていた行為の裏側に、深い愛情と哲学があることを知り、言葉を失った。冷たい部屋に、粥の湯気と、二人の間の穏やかな沈黙だけが満ちていた。
第三章 嵐の夜の日記
季節が移り、木枯らしが吹き荒れるようになったある夜、健太の日常は本当の意味で覆された。その夜は、窓ガラスを叩きつけるような激しい嵐だった。ふと、隣室が妙に静かなことに気づく。いつもなら、この時間にはテレビの音が微かに漏れ聞こえてくるはずなのに。嫌な予感が胸をよぎり、健太はためらいながらも102号室のドアをノックした。返事はない。何度か呼びかけても応答がなく、健太は大家に連絡し、マスターキーでドアを開けてもらった。
目に飛び込んできたのは、床に倒れ込んでいる高橋さんの姿だった。傍らには、あの古時計が転がっている。健太は我を忘れて駆け寄り、震える手で119番通報した。
病院の冷たい廊下で、健太は呆然と手術室のランプを見つめていた。脳梗塞。一命は取り留めたものの、意識が戻るかは分からないと医師は告げた。身寄りのない高橋さんのため、健太は大家に頼まれ、部屋の貴重品を整理することになった。
がらんとした部屋は、老人の生きた証で満ちていた。その一角、古びた文机の引き出しの奥から、健太は一冊の日記帳を見つけ出した。表紙には「高橋正治」と、几帳面な文字が記されている。ためらいながらもページをめくった健太は、そこに綴られていた信じがたい事実に、全身の血が凍りつくのを感じた。
『九月十五日。友、佐伯との約束の日。あいつは全ての荷物を一人で背負い、家族の前から姿を消した。「息子を頼む。あいつが一人で立てるようになるまで、遠くからでいい、見守ってやってくれ」。そう言って、自分の腕時計をわしに託した。あいつの時間の象徴だ』
佐伯。それは健太の父親の姓だった。日記を読み進めるにつれ、健太が知る由もなかった真実が、怒濤のように押し寄せてきた。父親は、事業の失敗で背負った借金を家族に負わせまいと、たった一人で姿を消し、その後の人生の全てを返済に捧げていたのだ。高橋さんは、その父親の唯一の親友であり、息子である健太を見守るという約束を、二十年近くもの間、ずっと果たし続けてくれていたのだ。
「無責任に家族を捨てた男」。健太がずっと憎み、軽蔑してきた父親の像が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。父は逃げたのではなかった。守るために、自らを犠牲にしたのだ。
日記の最後のページに、あの時計のことが書かれていた。
『あいつは言った。「俺が全部片付けたら、またお前と酒を飲む。その時まで、俺の時間を止めておいてくれ」と。だからわしは、あいつの時計から長針と短針を抜き、秒針だけを残した。いつかまた、あいつの時間が動き出す日を夢見て。健太君、君にはこの時計の音が聞こえるかね。これは、君の父さんが君を想う、心の音なんだよ』
「ああ……」
健太の口から、声にならない声が漏れた。高橋さんが言っていた「聞こえる音」の正体。それは物理的な音などではなかった。友との固い約束。息子への深い愛情。その全てが凝縮された、魂の響きだったのだ。健太は日記を握りしめたまま、その場に崩れ落ち、声を殺して泣いた。嵐の音に混じって、二十年間止まっていた涙が、堰を切ったように溢れ出した。
第四章 父のいる時間
高橋さんの意識は、数日後に奇跡的に戻った。しかし、病状は芳しくなく、残された時間は僅かだと告げられた。健太は毎日、仕事が終わると病院へ向かった。もはや、そこに非効率という言葉は存在しなかった。
ある晴れた午後、健太は高橋さんの許可を得て、あの一本針の時計を病室に持ち込んだ。そして、かつて高橋さんがしていたように、柔らかな布でその真鍮の枠をそっと磨き始めた。
「佐伯さん……」
ベッドの上から、高橋さんがかすれた声で呼びかける。
「わしは、親友との約束を、最後まで守れんかもしれんな」
「いいえ」
健太は顔を上げ、穏やかに微笑んだ。
「約束は、僕が引き継ぎます。だから、安心してください」
その言葉に、高橋さんの目に涙が光った。
健太は、時計を磨きながら、父のことを思った。会いたい。一言、謝りたい。そして、ありがとうと伝えたい。だが、父の居場所は分からない。それでも、この時計を磨いていると、不思議と父が隣にいるような気がした。止まった秒針が、父と自分、そして高橋さんを繋ぐ、確かな絆のように思えた。
数週間後、高橋さんは眠るように静かに息を引き取った。健太は一人、がらんとした病室で、窓の外に広がる空を見つめていた。悲しいはずなのに、心は不思議なほど温かかった。
アパートに戻った健太は、高橋さんの形見となった一本針の時計を、自室の机の一番よく見える場所に置いた。それはもう、ただの古時計ではない。父の愛、友の誠実さ、そして健太自身がこれから紡いでいくべき時間の、道標だった。
目を閉じると、聞こえる気がした。
カチ、カチ、と。
それは時計の音ではない。健太の心臓の鼓動であり、父の想いであり、高橋さんの優しさだった。止まっていた健太の時間が、今、確かに動き出した音だった。
翌朝、健太はアパートの廊下で、新しく隣に越してきたらしい若い夫婦と顔を合わせた。以前の彼なら、軽く会釈して通り過ぎただろう。しかし、健太は立ち止まり、柔らかな笑みを浮かべて言った。
「おはようございます。隣の佐伯です。よろしくお願いします」
その声は、驚くほど自然に、そして温かく響いた。健太の日常は、もう効率的な設計図の上にはない。不確定で、時に非効率で、けれど人間らしい温もりに満ちた、新しい時間が始まろうとしていた。空はどこまでも青く、澄み渡っていた。