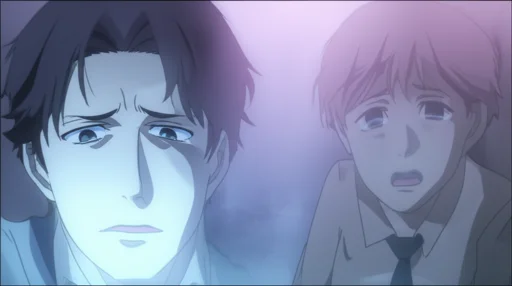第一章 壁の先の不協和音
水野響がそのアパートに決めたのは、完璧なまでの静寂が約束されていたからだ。築浅の鉄筋コンクリートマンションで、最上階の角部屋。隣室とは厚い壁で隔てられ、窓は二重サッシ。音響デザイナーという職業柄、音に過敏な彼にとって、それは理想的な城のはずだった。
引っ越して最初の数日は、その静けさに満ち足りていた。都会の喧騒から切り離された無音の空間は、思考をクリアにし、仕事の精度を上げてくれる。響はヘッドフォンの中で緻密な音の世界を構築し、外せば完全な静寂が待っているという環境に、ようやく安住の地を見つけたとさえ思った。
異変が起きたのは、一週間が過ぎた頃の深夜だった。
集中力が途切れ、ヘッドフォンを外した瞬間、それは聞こえた。
――ト、トン……トトン……。
壁の向こう、空き家のはずの隣室からだ。何かを軽く叩くような、不規則な音。響は眉をひそめた。ネズミか、あるいは建材の軋む音か。彼はさして気にも留めず、再び仕事に戻った。
しかし、その日から「音」は毎夜のように響の耳を訪れるようになった。それは次第に輪郭を帯び、単なる物音ではないことを主張し始めた。子どものすすり泣きのような、か細い声。途切れ途切れに聞こえる、意味をなさない鼻歌。それはまるで、壁一枚を隔てたすぐそこで、迷子の子供がしゃがみ込んでいるかのような、寄る辺のない寂しさを纏っていた。
響は管理会社に何度も問い合わせた。「隣は現在も空室です。間違いありません」。その一点張りに、響の苛立ちは募った。ならばこの音はなんだ。幻聴か? 過労で神経が参っているのか?
恐怖は、やがて彼の日常を侵食し始めた。日中でも、ふとした静寂の中にあの声の残響を探してしまう。完璧だったはずの城には亀裂が入り、そこから得体の知れない不安がじわりと染み出してくる。響はいつしか、無音を恐れるようになっていた。彼は孤独を愛していたはずなのに、その孤独が牙を剥き、すぐ隣に潜む「何か」の存在を際立たせる。
眠れない夜、響は冷たい壁にそっと耳を当てた。コンクリートのひんやりとした感触が、彼の熱っぽいこめかみを冷やす。
――……ご……んね……。
ノイズに混じって、確かに聞こえた。それは謝罪の言葉のようだった。何に対しての? 誰に対しての? 問いかけようにも、声の主は壁の向こうにいる。その事実は、響の心を底知れぬ沼へと引きずり込んでいった。
第二章 失われた残響
壁の向こうの声は、響にとって恐怖の対象であると同時に、奇妙な執着の対象にもなっていた。彼はプロ用の高感度マイクを壁際に設置し、その音を録音し始めた。音響デザイナーとしての本能が、正体不明の音源を分析したいという衝動に駆り立てたのだ。
ヘッドフォン越しに聞こえてくる「音」は、生で聞くよりも遥かに鮮明だった。すすり泣きの合間に、微かな息遣いや、衣擦れのような音まで拾っている。まるで、マイクのすぐ向こう側で、小さな存在が身じろぎしているかのようだ。響は録音したデータを波形編集ソフトで解析した。ノイズを除去し、特定の周波数帯を増幅させる。すると、今まで聞き取れなかった断片が浮かび上がってきた。
「……にい……ちゃん……」
「……さむ……いよ……」
「……ごめん……ね……」
それは、紛れもなく幼い子どもの声だった。そして、その声に含まれる哀切な響きに、響は胸を締め付けられるような感覚を覚えた。恐怖よりも先に、どうしようもない悲しみが込み上げてくる。なぜだろう。見ず知らずの、それどころかこの世の者かも定からない存在の声に、自分の心の深い部分が共鳴している。
その頃から、響の脳裏に、忘れていたはずの風景が断片的に蘇るようになった。
夏の終わりの、生ぬるい風。けたたましく鳴り響く遊園地の音楽。小さな手を握った時の、柔らかくて汗ばんだ感触。そして、不意にその手を振り払ってしまった時の、一瞬の罪悪感。
それは誰の記憶だ? 誰の手だった? 靄のかかった思考の海をいくら探っても、答えは見つからない。ただ、そのフラッシュバックが起こるたびに、壁の声に対する感情が、恐怖から憐憫へと少しずつ変化していくのを、響は自覚していた。
彼はアパートの周辺で聞き込みを始めた。古くから住んでいるという老婆は、響の部屋を指差し、顔を曇らせた。
「ああ、あそこの部屋ねぇ……。もう十年以上も前になるかねぇ。小さな男の子がいたご家庭だったけど……不幸な事故があってね。それ以来、どうも落ち着かないって話だよ」
老婆はそれ以上を語ろうとはしなかったが、響の中でバラバラだったピースが、おぼろげな形を結び始めようとしていた。事故。小さな男の子。そして、壁の向こうから聞こえる声。
その夜、響は録音した音声データを繰り返し聴いていた。何度も、何度も。すると、あることに気づく。すすり泣きや言葉の合間に、微かに聞こえるメロディ。それは、彼が幼い頃、母親がよく歌ってくれた子守唄の旋律だった。なぜ、壁の向こうの「子ども」が、この歌を知っている?
響の心臓が、嫌な予感と、そしてどこか懐かしいような期待感で、大きく波打ち始めた。
第三章 奏(かなで)の告白
答えに近づいているという確信が、響を焦らせた。彼は壁の構造を調べるため、リフォーム業者に連絡を取った。しかし、業者が来る前日の夜、異変はクライマックスを迎える。
壁からの音が、これまでとは比較にならないほど大きくなったのだ。それはもう、すすり泣きではなかった。何かを必死に訴えかけるような、切羽詰まった叫び声だった。壁を内側から叩く音が、ドン、ドン、と鈍く響き、部屋全体が震えるように感じられた。
「やめろ……! もうやめてくれ!」
響は耳を塞いで叫んだ。しかし、音は彼の頭蓋に直接響いてくる。パニックに陥った彼の脳裏で、今まで靄に閉ざされていた記憶の扉が、軋みを立ててこじ開けられた。
――遊園地の帰り道。夕暮れの公園。双子の弟と遊んだ、最後のかくれんぼ。
そうだ。俺には、双子の弟がいた。名前は、奏(かなで)。いつも俺の後ろをついてくる、少し気の弱い、だけど優しい弟。
『もういいかい?』
『まあだだよ!』
響の呼びかけに、奏の楽しそうな声が返ってくる。それが最後だった。響は鬼で、奏は隠れる側だった。いくら探しても奏は見つからず、痺れを切らした響は、先に家に帰ってしまったのだ。両親も、奏は友達の家にでも寄ったのだろうと、最初は気にしていなかった。
その夜、大きな地震があった。
全ての記憶が、濁流のように響の意識に流れ込んできた。あの部屋は、かつて自分たちが住んでいた家だった。そして、奏が隠れていた場所は、壁の向こう側にある、今はもう使われていない造り付けのクローゼットの中だったのだ。地震で扉の建て付けが歪み、中から開かなくなった。誰も、奏がそこにいるとは知らずに……。
両親は奏の失踪に心を病み、響もまた、弟を置き去りにした罪悪感と、凄惨な結末を目の当たりにしたショックで、その記憶に蓋をした。一家は逃げるようにその土地を離れ、奏の存在は家族の中で触れてはならないタブーとなった。そして響は、弟の記憶そのものを、心の奥底に封印してしまったのだ。
壁の向こうの声は、幽霊の呪いなどではなかった。
それは、兄に「見つけて」ほしかった弟の、最後の声だったのだ。
「にいちゃん」という呼びかけ。「さむいよ」という訴え。そして、「ごめんね」という謝罪。それは、かくれんぼを中断させてしまったことへの謝罪であり、兄を長年苦しませてしまったことへの、優しい弟からの謝罪だった。
「……かなで……」
響の口から、何十年ぶりに弟の名前が漏れた。涙が視界を滲ませる。
「奏ッ! ごめん……! 俺が、俺があの時……見つけてやれなくて……! ずっと忘れてて、ごめん……!」
彼は壁に両手をつき、額を押し付け、嗚咽した。壁を叩く音も、叫び声も、ピタリと止んだ。
しん、と静まり返った部屋に、響の泣き声だけが響く。
すると、冷たかったはずの壁から、ふわりと温かい空気が流れてきたような気がした。そして、彼の耳元で、はっきりと、しかし優しい声が響いた。
――みつけてくれて、ありがとう、にいちゃん。
それは紛れもなく、記憶の中のままの、幼い弟の声だった。
第四章 優しい木霊(こだま)
夜が明けた時、響の心は嵐が過ぎ去った後の空のように、静かに澄み渡っていた。瞼は腫れ上がっていたが、長年彼の肩にのしかかっていた重荷は、嘘のように消え去っていた。壁の向こうからは、もう何の音も聞こえない。奏の魂は、ようやく安らぎの場所を見つけたのだろう。
響は震える手でスマートフォンを手に取り、実家に電話をかけた。電話口に出た母親の懐かしい声に、彼は一瞬言葉を詰まらせた。
「母さん……俺、思い出したんだ。奏のこと」
受話器の向こうで、母が息を呑むのが分かった。響は泣きながら、全てを話した。この部屋で起きていること、取り戻した記憶、そして、奏との最後の対話を。電話の向こうから、父の嗚咽と、母の「ごめんなさい」という声が聞こえてきた。誰も悪くない。誰もが傷つき、互いを思いやるあまり、最も大切な記憶に蓋をしてしまっていただけなのだ。何十年も止まっていた家族の時間が、その日、ようやく再び動き始めた。
リフォーム業者の予約はキャンセルした。響はこの部屋を出ていくつもりはなかった。ここはもう、ただの仕事場ではない。弟の魂が最後に留まっていた、かけがえのない場所なのだから。
それからというもの、響の作る音は変わった。以前の彼の音は、どこか冷たく、完璧さを求めるあまり人間的な温かみに欠けていた。しかし今の彼の音には、深みと、そして聴く者の心に寄り添うような優しさが宿っていた。それはまるで、彼の内面的な変化が、そのまま作品に投影されているかのようだった。
壁の音は、もう二度と聞こえることはなかった。
けれど、響には聞こえていた。窓を開け、部屋に新しい風を入れる時。風鈴の音に混じって、奏の楽しそうな笑い声が聞こえる気がする。集中して仕事をしている時、ふと背後から「にいちゃん、がんばって」と囁く、優しい木霊(こだま)が聞こえる気がする。
それは幻聴かもしれない。あるいは、そうであってほしいという彼の願いが生み出した幻想かもしれない。
だが、響にとってはどうでもいいことだった。
かつて恐怖の対象だった「音」は、今では彼を支え、孤独を癒す、世界で最も優しい響きとなっていた。
彼はもう、一人ではなかった。壁の向こうではなく、すぐ隣に、心の中に、愛する弟の存在を感じながら、明日を生きていく。完璧な静寂よりも、遥かに温かい響きに包まれて。