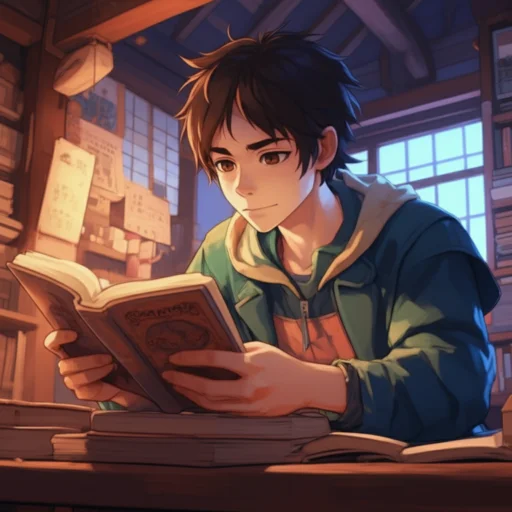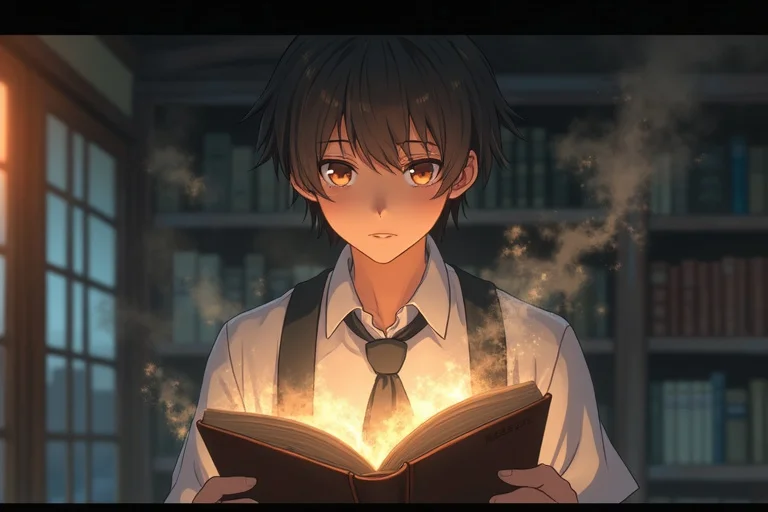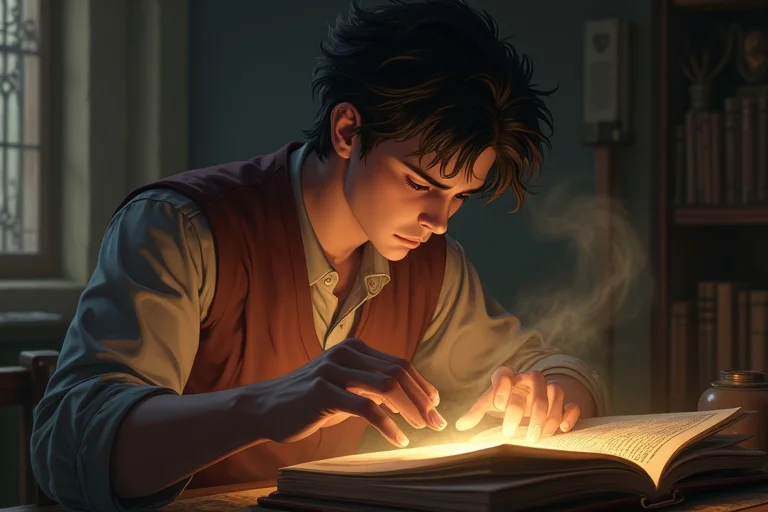第一章 埃の中の邂逅
柏木湊(かしわぎみなと)は、東京の喧騒から逃れるようにして、鈍行列車の窓に額を押し付けていた。流れていく景色は、高層ビルから低い家並みへ、そして青々とした田園へと姿を変えていく。祖母が死んだ。その報せは、スマートフォンの画面に無機質なテキストとして表示されただけだったが、湊を十年ぶりに故郷へと引き戻すには十分な力を持っていた。
三十歳になった湊の日常は、コードとモニターに埋め尽くされていた。システムエンジニアとして、それなりの評価と収入を得てはいるが、心は乾いたスポンジのように、何も吸収しようとしなかった。感動も、怒りも、深い喜びも、まるで他人事のように通り過ぎていく。そんな無気力な日々を送る彼にとって、祖母の死ですら、処理すべきタスクの一つに過ぎないように感じられた。
葬儀が終わり、親戚たちが慌ただしく帰っていく中、湊は一人、古びた母屋の縁側に座っていた。蝉の声が、むせ返るような夏の湿気とともに降り注ぐ。遺品整理という、最も厄介なタスクが残されていた。
「湊、蔵の方、見てきてくれないか。もう何十年も開けてないけど、何か残ってるかもしれん」
母の言葉に、湊は気乗りしないまま立ち上がった。
ぎい、と重い音を立てて開いた蔵の扉から、黴と埃の混じった、時間の匂いが溢れ出した。ひんやりとした暗闇に目が慣れると、そこは忘れ去られたモノたちの墓場だった。壊れた農具、古い着物、欠けた瀬戸物。ガラクタの山をかき分けて奥へ進んだ時、湊の足が何かにこつんと当たった。見ると、埃をかぶった桐の小箱が、まるで彼を待っていたかのように鎮座していた。
蓋を開けると、樟脳の匂いとともに、中から革張りの古びた手帳が現れた。そして、その下に一枚のモノクロ写真。セピア色に変色した写真には、凛々しい学帽をかぶった青年が写っていた。その切れ長の目、すっと通った鼻筋。湊は息を呑んだ。鏡を見ているかのように、自分と瓜二つの顔がそこにあったのだ。
「誰だ、これ……」
手帳を手に取る。ざらりとした革の感触が、指先に奇妙な熱を伝えた。表紙には、金文字のかすれた跡で『柏木 朔(さく)』と記されていた。聞いたことのない名前だった。パラリとページをめくると、そこには流麗な万年筆の文字がびっしりと並んでいた。
『大正十二年四月一日。桜舞う。今日から、私の新しい日々が始まる』
それは、湊の知らない過去からの、あまりにも鮮やかな第一声だった。乾ききっていたはずの湊の心に、小さなさざ波が立った。
第二章 色彩の日々
東京へ戻る新幹線の中、湊は我を忘れて曾祖父――柏木朔の日記を読み耽っていた。母に尋ねると、朔は湊の父方の祖父の兄にあたる人物で、若くして病で亡くなったと聞かされている、とのことだった。それ以上のことは、誰も知らなかった。
日記の中の朔は、湊とは正反対の人間だった。画家を志し、美術学校に通う彼の日常は、情熱と色彩に満ち溢れていた。
『……教授は私の絵を「形は良いが魂がない」と評した。悔しい。だが、的を射ている。私の目にはまだ、世界の本当の色が見えていないのかもしれない。キャンバスの上で、光そのものを掴みたいのだ』
『友人である和泉と、夜通し芸術を語り合った。彼の描く力強い線は、私にはないものだ。嫉妬と尊敬が入り混じる。この感情こそが、私を前に進ませるのだろう』
湊は、朔の言葉の端々から、むせ返るような絵の具の匂いや、ざらついたキャンバスの感触、友と酌み交わす安酒の味まで感じられるような気がした。自分が生きる灰色の世界とはまるで違う、極彩色の世界がそこには広がっていた。
そして、日記には頻繁に一人の女性の名前が登場するようになった。「小夜(さよ)」という名だった。彼女は、朔がスケッチによく訪れていた公園の近くにある和菓子屋の娘らしかった。
『……今日も彼女は、椿の花のようにそこにいた。黒髪に挿した銀のかんざしが、午後の光を浴びてきらりと光る。声をかける勇気もなく、ただ遠くから彼女の横顔をスケッチするばかりだ。私の絵の中の彼女は、微笑みかけてくれるというのに』
朔の淡く、不器用な恋心。その瑞々しい描写に、湊はいつしか自分のことのように胸を高鳴らせていた。恋愛も、人間関係も、どこかシミュレーションのようにこなしてきた自分にとって、朔の純粋な想いは眩しすぎた。
歴史とは、年号と事件の無味乾燥な羅列だと思っていた。だが、違った。そこには、自分と同じように悩み、笑い、恋をする、血の通った人間が生きていたのだ。自分とそっくりな顔をした曾祖父の人生を追体験するうちに、湊の心には、今まで感じたことのない温かい感情がゆっくりと染み渡っていくのだった。彼は、もっと朔のことを知りたいと、強く思うようになっていた。
第三章 無名の絵の具
日記のページをめくる指が、次第に重くなっていく。昭和の時代に入り、朔の世界を覆っていた鮮やかな色彩に、少しずつ黒いインクが滲み始めるように、不穏な言葉が増えていった。日中戦争の勃発。街を行進する軍靴の音。赤紙――召集令状。
『……和泉にも、赤紙が来た。彼は持病の喘息が悪化しており、誰が見ても兵役に耐えられる体ではない。だが、お国のためにと、彼は青白い顔で笑う。彼の家は、彼が一人息子なのだ。もし和泉がいなくなれば、彼の描くあの力強い線も、未来永劫失われてしまう』
湊の心臓が、嫌な音を立てて脈打った。読み進めるのが怖い。だが、ページから目を離すことができなかった。そして、昭和十三年の秋。運命の記述に、湊は突き当たった。
『柏木朔は、今日、死ぬことにした』
息が止まった。何を言っているんだ、この人は。病死したのではなかったのか。震える指でページを送り、湊は信じがたい真実を知ることになる。
『私の元にも、令状が届いた。だが、私の命は、和泉の命に比べれば軽い。私には両親も健在で、弟もいる。家を継ぐ心配はない。絵の才能なら、和泉の方が遥かにある。彼が生き残り、絵を描き続けることこそが、この国の未来にとっての宝ではないか。小夜さんのいるこの美しい国を、守りたい。そのために、私が彼の身代わりになる』
朔は、和泉と示し合わせ、役場の徴兵係に手を回し、自分の健康診断書と和泉のそれをすり替えたのだ。そして、彼は「和泉」として戦地へ赴き、戸籍上は「柏木朔」が病死したことにする、という計画を立てた。全ては、病弱な友人と、その才能、そして彼の家族を守るためだった。
『小夜さん、さようなら。あなたが好きでしたと、ついぞ言えませんでした。だが、私のこの命が、あなたの微笑む未来に繋がるのなら、悔いはない。私の名前は歴史から消えるだろう。それでいい。私は、未来という大きな絵を完成させるための、名もなき絵の具の一つになろう』
湊は、スマートフォンの明かりを頼りに、そのページを何度も何度も読み返した。涙が、古びた紙の上に落ち、インクを滲ませた。これが、真実。教科書には決して載らない、一人の人間の、あまりにも気高く、そしてあまりにも悲しい決断。自分のルーツだと思っていたものは、根底から覆された。自分のこの命が、ただの偶然ではなく、曾祖父の壮絶な自己犠牲と、名もなき願いの上に成り立っているという事実が、重く、しかし確かな手触りをもって湊の全身を貫いた。
第四章 未来へのバトン
日記は、そこで終わってはいなかった。最後に、薄い紙に書かれた手紙が挟まれていた。おそらくは検閲を逃れるために、誰かが密かに持ち帰ったものだろう。それは、大陸のどこかの戦地から、友である和泉に宛てた、朔の最後の手紙だった。
『和泉、元気でいるか。こっちは、まあ、なんとかやっている。空の色は、日本で見たどの青よりも深く、物悲しい。星が、驚くほど近くに見える夜がある。そんな夜は、お前のことや、小夜さんのことを思い出す。俺はもう、絵筆を握ることはないだろう。この手は、人を傷つけることしかできなくなった。だから、頼む。俺の分まで、描いてくれ。俺が見たかったこの空を、俺が守りたかった人々の笑顔を、お前のキャンバスに描き続けてくれ。もしこの手紙がお前の元に届くのなら、私はもうこの世にいないだろう。だが、それでいいのだ。私の命は、未来に繋がる一つの絵の具なのだから』
手紙を読み終えた時、湊の頬を、熱い雫が止めどなく伝っていた。それは、悲しみだけの涙ではなかった。感謝と、畏敬と、そして今まで感じたことのないほどの、生きていることへの確かな実感から来る涙だった。無気力だった自分の空っぽの器が、曾祖父の想いで満たされていくようだった。
東京に戻った湊の見る世界は、一変していた。満員電車の雑踏も、無機質なオフィスビルも、ただの風景ではなくなっていた。すれ違う名もなき人々一人一人に、自分には知り得ない壮絶な過去や、誰かからの願いが繋がっているのかもしれない。そう思うと、世界は驚くほど豊かで、尊いものに感じられた。
湊は仕事を辞めなかった。ただ、向き合い方が変わった。彼が書く一行一行のコードが、巡り巡って誰かの生活を支え、未来を作る一片になるのかもしれない。それは、曾祖父が願った「未来の絵」を彩る、小さな一点になるのかもしれない。そう思うと、乾いていた心に静かな情熱が湧き上がってきた。
ある週末、湊は画材店に立ち寄っていた。そして、一冊のスケッチブックと、数本の鉛筆を買った。絵を描くためではない。ただ、何かを遺したい、繋げたいという、抑えきれない衝動に駆られたのだ。
彼は、公園のベンチに座り、スケッチブックの真っ白なページを開いた。
そこに何を描くのか、彼自身にもまだ分からなかった。
だが、それでよかった。
柏木朔から受け取った、名もなき絵の具という名のバトン。それを手に、柏木湊の人生が、今、静かに、しかし確かに走り始めた。歴史とは過去の記録ではない。今を生きる我々の内に脈々と流れ、未来へと繋がっていく、壮大な物語そのものなのだ。
湊は鉛筆を握りしめ、深く息を吸った。その目は、かつての曾祖父のように、世界の本当の色を探していた。