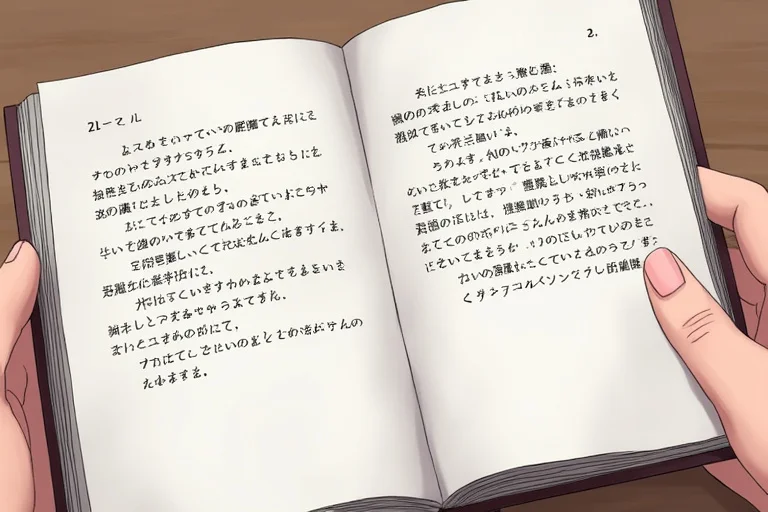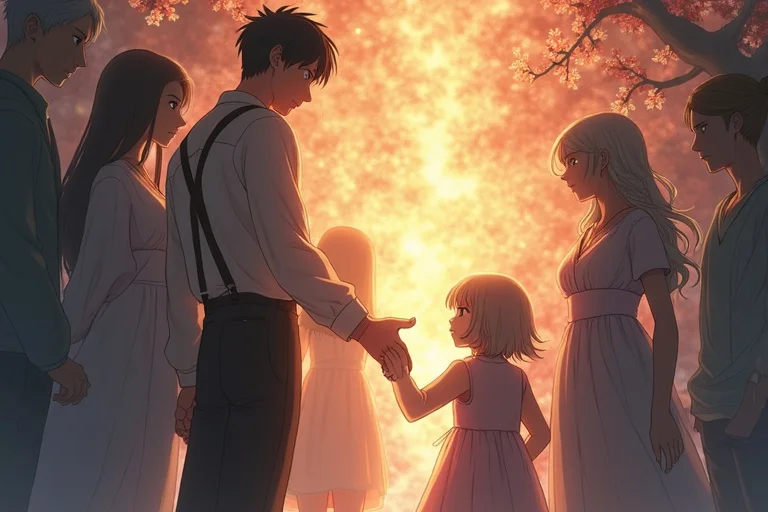第一章 無色の食卓
水島湊(みなと)にとって、家族との夕食は常に一種の苦行だった。食卓に並ぶのは、母・春子が腕によりをかけた色とりどりの料理。湯気を立てる肉じゃがの琥珀色、ほうれん草のおひたしの深い緑、トマトの鮮やかな赤。だが、湊の目には、それ以上に厄介な色彩が映っていた。
湊には、人の感情がオーラのような「色」として見える。この特異な体質は、物心ついた頃からのものだった。母の機嫌が良い日は食卓全体が暖かなオレンジ色に包まれ、妹の莉子(りこ)が学校で嫌なことがあった日は、彼女の席の周だけが澱んだ藍色に沈む。それは、言葉よりもずっと雄弁に、人の内面を暴露してしまう呪いのような力だった。
「湊、就職と一人暮らし、本当におめでとう。お父さん、何か言ってあげて」
春子の声は、喜びと一抹の寂しさが混じった、柔らかな藤色をしていた。湊は箸を置き、正面に座る父・陽一に視線を向けた。
陽一は、いつもそうだ。彼の周りには、何の色もなかった。無色透明。それは無関心とも、虚無とも違う、ただただ「何もない」という感覚を湊に与える。感情の色彩が渦巻くこの家で、父の存在だけが、ぽっかりと空いた穴のように異質だった。
「そうか。もうそんな歳か。頑張れよ」
陽一は抑揚のない声でそう言うと、湯呑みの茶をすすった。言葉に込められた感情を読み取ろうと、湊は目を凝らす。だが、やはり何も見えない。応援の黄色も、期待の金色も、心配の薄青色さえも。
この能力のせいで、湊は他人の本音と建前の乖離にうんざりしてきた。友人の励ましの言葉の裏に透ける嫉妬の濁った緑色。恋人の「愛してる」という囁きに混じる、不安の揺らめく灰色。世界は嘘と欺瞞の色で満ちていた。だからこそ、父の「無色」は湊を苛立たせた。嘘の色すらない。それは、息子が家を出ていくという一大事にさえ、心が一切動いていない証拠に思えた。
「これ、餞別だ」
食事が終わると、陽一は無言で小さな箱を差し出した。中には、黒檀の軸を持つクラシックな万年筆が収まっていた。
「……ありがとう」
湊がそれを受け取った、その瞬間だった。
チクリ、と指先に熱を感じたかと思うと、視界の端で、燃え盛る炎のような深紅の色が一瞬だけ閃いた。あまりに鮮烈で、目の奥が焼けるような赤。だが、それは幻のようにすぐに消え失せ、後にはいつもの無色透明な父がいるだけだった。
湊は心臓が跳ねるのを感じた。今の色は、間違いなく父から発せられたものだ。あれは一体、何だったのか。怒り? それとも……。
問い質そうと口を開きかけたが、父はすでに背を向け、書斎へと消えていくところだった。その背中からは、やはり何の色も読み取れなかった。残されたのは、手のひらの万年筆の冷たい感触と、脳裏に焼き付いた深紅の残像だけだった。
第二章 灰色の日々と万年筆の赤
新しい生活は、湊が期待したほどの解放感をもたらしてはくれなかった。都会の喧騒は、無数の感情の色が混じり合った濁流となって湊に襲いかかった。満員電車では、人々のストレスが放つどす黒い紫と、焦燥の汚れた黄色が空気を重くする。職場のオフィスは、上辺だけの賞賛が放つ薄っぺらい桃色と、嫉妬や不満の陰鬱な色がそこかしこで渦を巻いていた。
湊は、感情の色から逃れるように、ヘッドフォンで耳を塞ぎ、人との関わりを最小限に留めて日々を過ごした。実家から離れても、あの呪わしい能力は彼を蝕み続ける。誰も信じられず、心の底から安らげる場所はどこにもなかった。
たまに実家に電話をかけると、母はいつも「お父さんは元気にしているわよ」と明るい声で言った。その声の周りには、湊を安心させようとする優しい若草色が漂っていた。だが、その奥にかすかな憂いの影、薄墨色が見えるのを、湊は見逃さなかった。
ある週末、湊は久しぶりに実家へ帰った。リビングのソファで新聞を広げる父の姿は、半年前と何も変わらない。無色透明。湊は、あの夜に見た深紅の色のことを思い出していた。あれ以来、父から色を感じることは一度もなかった。あれはやはり、自分の見間違いだったのだろうか。
「兄ちゃん、考えすぎだよ」
夕食後、ベランダで涼んでいると、妹の莉子が隣にやってきた。彼女の周りには、兄を気遣う穏やかな水色が揺れている。
「お父さん、昔から不器用なだけだって。言葉とか、態度で示すのが苦手な人なんだよ」
「色が見えないお前には分からないさ。感情がないんだ、あの人には。俺が出ていく時でさえ、何も感じてなかった」
吐き捨てるように言うと、莉子の水色が少しだけ曇った。
「色が見えるお兄ちゃんには分からないかもしれないけど」と彼女は静かに反論した。「見えなくても、伝わるものだってあるんだよ。お父さんが毎朝、兄ちゃんの住んでる方角の空を見てるの、知らないでしょ」
その言葉は、湊の胸に小さな棘のように刺さった。だが、彼はそれを認めたくなかった。自分を長年苦しめてきたこの能力が、父の本質を見誤っているはずがない。そう信じたかった。
自室に戻り、机の引き出しから父に貰った万年筆を取り出す。滑らかな黒檀の軸を指でなぞる。あの夜の、焼けるような深紅。あれがもし、一瞬だけ漏れ出た父の本心だったとしたら。それは一体、どんな意味を持つ感情だったのだろう。湊は答えの出ない問いを胸に抱いたまま、万年筆を強く握りしめた。冷たい金属の感触だけが、現実感を伝えていた。
第三章 父のモノクローム
その電話が鳴ったのは、けたたましい雨が窓を叩く、火曜日の夜だった。
「湊……お父さんが、倒れたの」
母の声は、かつてないほど濃く、深い悲しみの紫色に染まりきっていた。湊は受話器を握りしめ、言葉を失った。
病院の白い廊下を、湊は夢遊病者のように歩いた。ガラスの向こう、集中治療室のベッドに横たわる父の姿が見える。様々な医療機器に繋がれ、穏やかな寝息を立てているように見えた。そして、その周りは――やはり、無色透明だった。生命の危機に瀕してさえ、この人は何の色も示さないのか。湊の胸に、怒りとも悲しみともつかない、冷たい感情が広がった。
待合室の硬い椅子で、母が静かに語り始めた。その言葉は、湊が信じてきた世界のすべてを、根底から覆すものだった。
「あなたいつも、お父さんのことが分からないって言ってたわね。無理もないわ。あなt……ううん、誰にも、あの人の本当の色は見えないんだから」
春子の周りを漂う深い紫が、後悔の念を示すように微かに揺らめいた。
「お父さんね、若い頃に事故に遭って……頭を強く打ったの。幸い命に別状はなかったんだけど、後遺症が残ってしまった。……色の、ほとんどが見えなくなってしまったのよ」
色が見えない? 湊は絶句した。
「それだけじゃないわ。私たち水島家のこの力はね、代々こう言い伝えられてるの。『自らの心が豊かであればあるほど、他人の感情の色もまた、鮮やかに見える』って。感受性のアンテナみたいなものなのよ」
母は、湊の目をまっすぐに見つめた。
「お父さんは、色覚を失ったことで、感情の起伏そのものを、少しずつ失っていったの。喜びも、悲しみも、怒りも……かつて見ていた鮮やかな『色』として感じることができなくなってしまった。世界が白黒になったのと一緒に、心まで、ゆっくりと色褪せていってしまったの」
だから、見えなかったのだ。父に感情が「なかった」のではない。湊の能力では捉えきれないほど、その感情の色が「淡く」なってしまっていたのだ。父は、モノクロームの世界で、色を失っていく自分の心と、たった一人で闘っていた。家族を愛したい、喜びを分かち合いたい。そう願いながらも、心が思うように色づかないことに、どれほど苦しんできたのだろう。
「じゃあ……あの万年筆の……」
湊の声は震えていた。
「ええ」と母は頷いた。「あなたが出ていくあの日、お父さん、自分のことみたいに喜んでた。『あいつの未来は、どんなに鮮やかな色をしてるだろうな』って、何度も言ってたわ。あの子の門出を、心から祝ってやりたいんだって」
あの深紅の色。それは、無関心などでは断じてなかった。色褪せた心の中から、父が息子への愛情と誇りを、ありったけの力で絞り出して見せた、魂の色だったのだ。自分の無力さに打ちひしがれながらも、必死で想いを伝えようとした、一瞬の奇跡。
湊は崩れるようにその場に膝をついた。自分がなんて愚かだったのか。疎ましく思っていたこの力は、他人の心を映すだけでなく、自分の心の豊かさを測る鏡でもあったのだ。父の静かな絶望に気づけなかったのは、父の心が無色だったからではない。父の苦しみを想像する力が、自分に欠けていたからだ。父の「無色透明」は、空虚の色ではなかった。それは、失われた色彩を取り戻そうともがき続けた、静かで、あまりにも壮絶な闘いの色だったのだ。
第四章 心で見る色
意識を取り戻した父は、まだ言葉をはっきりと話せる状態ではなかった。湊は毎日、仕事帰りに病室を訪れた。以前のような苛立ちは、もうなかった。ただ、父のそばにいたかった。
ベッドの傍らに座り、湊は痩せた父の手を握った。骨張った、節くれだった手。その手の周りには、やはり何の色も見えない。だが、湊はもう色を探そうとはしなかった。代わりに、自分の掌に伝わる、父の微かな温かさに集中した。時折、ピクリと動く指の力。穏やかに上下する胸。規則正しい寝息。
色が見えなくても、ここに父はいる。生きている。その事実が、何よりも確かな手触りをもって、湊の心に伝わってきた。
「父さん」
湊は、父に貰った万年筆で、日々の出来事をノートに綴り、それを読み聞かせた。新しいプロジェクトのこと、莉子の大学での活躍、母が作った夕食のメニュー。父はただ黙って聞いているだけだったが、湊が話し終えると、彼の指が感謝を示すように、弱々しく握り返してくるのが分かった。
湊の世界は、少しずつ変わり始めていた。職場で、同僚の疲れた顔の奥にある、家族を思う愛情の淡いピンク色が見えるようになった。満員電車で舌打ちする男の背後に、仕事のプレッシャーを示す暗い紫色だけでなく、それを乗り越えようとする意志の、細くとも確かな白い光が見えるようになった。
能力は呪いではなかった。それは、言葉や表情の裏にある、複雑で、矛盾に満ちた、それでも懸命に生きる人々の心の機微を、深く理解するための天啓だったのかもしれない。父が教えてくれたのだ。本当に大切なのは、見える色の種類や鮮やかさではない。その色の奥にある、声にならない想いを汲み取ろうとする、心そのものなのだと。
数ヶ月後、退院した父を連れて、湊は車を走らせた。向かったのは、子供の頃に家族でよく訪れた海だった。
車椅子を押して、砂浜の際まで行く。太陽がゆっくりと水平線に沈み、空と海を燃えるような橙色に染め上げていた。
「……きれいだな」
父が、かすれた声で呟いた。その横顔を、湊はそっと見つめる。
その時、湊は見た。
父の肩のあたりに、ほんのりと、ごくごく淡い光が灯るのを。それは、目の前の夕日と同じ、温かい橙色をしていた。瞬きをすれば消えてしまいそうなほど儚い光。幻かもしれない。夕日の残光が、そう見せているだけかもしれない。
だが、湊は確かに感じていた。それは父の心に灯った、純粋な「感動」の色なのだと。
湊は、何も言わずに微笑んだ。見えても、見えなくても、もうどちらでもよかった。父の心が、今この瞬間、自分と同じ色を感じている。その事実だけで、胸の奥がじんわりと温かくなる。
僕たちは、色を超えて繋がっている。家族とは、見えるものではなく、感じるものなのだ。
橙色の光が世界を包む中、湊は父の隣で、ただ静かに、変わりゆく空の色を見つめ続けていた。