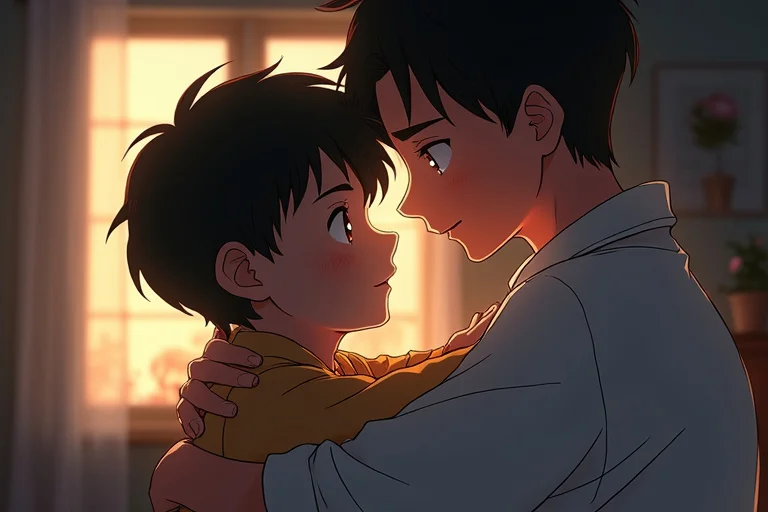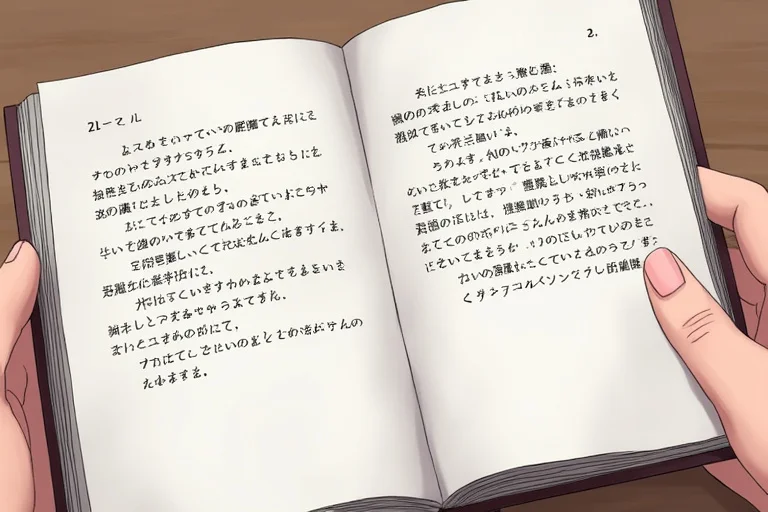第一章 不協和音の帰郷
三年ぶりに踏み入れた実家の玄関は、埃と、父の執着の匂いがした。フローリングの床には無数のケーブルが蛇のように這い、壁際には用途不明の測定器が鈍い光を放っている。俺、天野ケンジは、大学院の研究で忙殺される日々に一区切りつけ、亡き母の三回忌のために帰省した。だが、出迎えた父、トシオの第一声は、俺の予想を遥かに超えていた。
「ケンジか。ちょうどいい時に帰ってきた。母さんの『音』が、ひどく乱れているんだ」
父は痩せこけた頬をこわばらせ、リビングの隅に鎮座する巨大なオシロスコープの波形を睨みつけていた。その表情は、狂信者のそれに近い。
「……音?」
俺は眉をひそめ、耳を澄ませた。キーン、という微かな高周波音が、古い家の沈黙を震わせている。例えるなら、古いブラウン管テレビの電源を入れたままにした時のような、意識しなければ気にも留めないほどの音だ。
「またその話かよ。ただの家鳴りか、古い電化製品のノイズだろ」
吐き捨てるように言うと、父はゆっくりとこちらを振り返った。その目は深く落ち窪み、疲労と、一種の使命感が宿っている。
「違う。これはミサキだ。お前の母さんが、この家に残した声なんだよ」
母、ミサキが死んで二年が経つ。父はあの日から、この家の中に母の存在を感じる、と言い続けてきた。最初は悲しみが見せる幻覚だと思っていた。だが、父の行動は日に日にエスカレートし、元音楽家としての知識と妙な情熱を注ぎ込み、家中に自作の集音器や解析装置を設置し始めた。今やこの家は、父にとっての聖域であり、俺にとっては正気を疑う実験室だった。
「父さん、もうやめろよ。母さんは死んだんだ。こんな非科学的なことに没頭してないで、現実を見てくれ」
俺の言葉は、冷たい刃のように父子の間に突き刺さった。父は何も言い返さず、ただ静かに視線を波形に戻した。緑色の光が不規則に揺れている。その光景が、父の不安定な心を映しているようで、俺はたまらない苛立ちと、微かな罪悪感を覚えた。
壁にかけられた母の遺影が、穏やかに微笑んでいる。その笑顔とは対照的に、この家の空気は重く、冷え切っていた。父と俺の間で奏でられる不協和音の中で、母の三回忌は始まろうとしていた。俺はこの時、父の言う「音」の正体を科学的に暴き、彼をこの妄想から解放してやることこそが、残された息子としての務めだと固く決意していた。
第二章 聞こえない声の波形
翌日から、俺の「音」の正体を探る調査が始まった。物理学を専攻する俺にとって、原因不明の音響現象は、父の言うような心霊現象ではなく、必ず合理的に説明できるパズルのはずだった。
「周波数は15キロヘルツ前後で常に変動。特定の電源系統に依存していない……」
俺は持参したノートパソコンにスペクトラムアナライザのソフトを立ち上げ、データを収集していく。だが、奇妙なことに、音の発生源が全く特定できないのだ。配電盤のブレーカーを一つずつ落としても、家の外の電柱からの影響を遮断しても、「音」は微弱ながら鳴り続けている。まるで、この家そのものが呼吸するように、音を発しているかのようだった。
父はそんな俺の行動を黙って見ていたが、時折、ぼそりと呟いた。
「発生源を探しても無駄だ。それは、この空間全体に満ちているものだから」
そして、古びたノートに、鉛筆で五線譜のようなものを書きつけていく。オシロスコープに表示される波形を、彼なりの解釈で「楽譜」に起こしているのだという。
「ほら、昨夜からずっと、このシのフラットの音が低く呻いている。母さんは何かを悲しんでいるんだ」
「それはただの周波数の揺らぎだ」
俺たちの会話は、決して交わることのない平行線だった。
調査の過程で、俺は母が愛した温室が酷い状態になっていることに気づいた。ガラス張りの小さなサンルームは、かつては色とりどりの花と緑で溢れていた。だが今、ほとんどの植物が葉を黄色く変色させ、力なく萎れている。
「水も肥料もやっている。日当たりも悪くない。だが……枯れていくんだ」
父は温室のガラスを撫でながら、寂しそうに言った。「母さんの音が弱っているから、この子たちも元気をなくすんだ」
馬鹿げている、と思った。植物が枯れるのには、病気や害虫、土壌の変化といった科学的な原因があるはずだ。しかし、土を調べても、葉を観察しても、明確な原因は見当たらない。ただ、この温室に入ると、あの高周波音が他の場所よりも僅かに強く感じられることに、俺は気づいていた。まるで、枯れゆく植物たちの、声なき悲鳴のように。
父との溝は埋まらないまま、時間だけが過ぎていく。俺は焦っていた。このままでは、父を救うことなどできない。俺は、いつしか「音」そのものに憎しみにも似た感情を抱き始めていた。母を奪い、父の正気まで奪おうとする、不気味なノイズ。その正体を暴くまで、ここを去るわけにはいかなかった。
第三章 静寂に響く子守唄
三回忌の前夜、大型の台風が町を直撃した。窓ガラスを激しく叩く風雨の音で、家全体が軋む。そして深夜、ついに送電線がやられたのだろう、家中の明かりがふっと消え、世界は完全な闇と静寂に包まれた。
停電だ。換気扇の音も、冷蔵庫のモーター音も、父の測定器が発する電子音も、すべてが止んだ。嵐の音さえも一瞬遠のいたかのような、真空の静けさ。
その、瞬間だった。
俺の耳に、信じられないほどクリアな「音」が届いた。
それはもはやノイズではなかった。澄み切った、水晶の鈴を振るような、清らかな旋律。今まであらゆる雑音に紛れて聞こえなかった、その音の真の姿。高く、低く、優しく揺れるそのメロディは、俺の記憶の奥底を激しく揺さぶった。
「……ああ……」
声にならない声が漏れた。これは、知っている。幼い頃、熱を出して寝込んだ俺の枕元で、母さんが口ずさんでくれた子守唄だ。なぜ。どうして。幻聴か? だが、それはあまりに生々しく、鼓膜を震わせていた。
その時、懐中電灯の光と共に、父がリビングに飛び込んできた。その顔は、驚きと歓喜に満ちていた。
「ケンジ! 聞こえるか! 今だ、今なんだ! 母さんが、はっきりと歌っている!」
父の手にしたノートには、まさに今俺が聞いている旋律と寸分違わぬ楽譜が記されていた。長年の観測で、父は雑音の奥にあるこのメロディの断片を、少しずつ繋ぎ合わせていたのだ。
俺は言葉を失い、その場に立ち尽くす。父は震える手で、書斎の奥から一枚の古い設計図を取り出してきた。
「これを読めば、全部わかる」
それは、母の自筆で書かれたものだった。タイトルには『時空間音響共鳴理論に基づく、記憶・感情パターンの定着化に関する考察』とある。
「母さんは……音響物理学の研究者だったんだ」
父が、静かに語り始めた。俺の知らない、母のもう一つの顔だった。
「彼女は、自分の死期を悟っていた。そして、自らの理論を完成させようとした。記憶や感情という電気信号を、特定の高周波パターンに変換し、愛する空間、つまりこの家に『残響』として定着させる研究だ」
父が使っていた奇妙な測定器は、母が遺した設計図を元に、父が作り上げた受信装置だったのだ。それは、オカルトでも妄想でもなかった。最先端の科学と、深すぎる家族への愛が融合した、母の最後の研究プロジェクトだった。
「音は、母さんの魂そのものじゃない。彼女が遺した、愛の残響なんだ。そしてこの残響は、私たち家族の心に共鳴して安定する。私とお前の心が離れていたから、音は乱れ、不協和音になっていた。温室の植物が枯れたのも、母さんの温かい残響が、私たちの不和によって弱まっていたからなんだ」
嵐の音の中で、子守唄の旋律が優しく響き続ける。それは、俺と父の間に横たわっていた氷の壁を、ゆっくりと溶かしていく、温かい涙のようなメロディだった。
第四章 残響のハーモニー
夜が明けると、台風は嘘のように過ぎ去っていた。停電はまだ続いていたが、家の中は奇妙なほどの静けさと、穏やかな光に満ちていた。そして、あの美しいメロディが、変わらずに家全体を包み込んでいる。
俺は父と共に、母の遺した設計図と父の記録ノートを広げた。そこには、俺が大学で学んでいる数式や理論が、母独自の視点で発展させられた形でびっしりと書き込まれていた。
「この共振回路の調整がずれている。父さんの音楽的感性で音の調和を感じて、俺が物理的にパラメーターを補正する。二人でやらなきゃダメなんだ」
「ああ……そうか。ミサキは、それもわかっていたのかもしれないな」
生まれて初めて、俺と父は、一つの目標に向かって協力した。父が「この高音にもう少し温かみが欲しい」と言えば、俺はコンデンサの容量を微調整する。俺が「信号の安定性を高めるには、この帯域のノイズをカットする必要がある」と言えば、父は自身の耳を頼りに最適なフィルター設定を探り当てた。
科学と芸術。理論と感性。俺と父。対極にあると思っていた二つのものが、母の遺した「音」を媒体にして、完璧なハーモニーを奏で始めた。
俺たちは何時間も没頭した。その間、母の思い出をたくさん話した。父の知らなかった母の癖、俺の知らなかった母の夢。失われた時間を取り戻すように、言葉を紡いだ。
すると、どうだろう。俺たちの心が通い合うにつれて、家の「音」はさらに澄み渡り、豊かで、温かい響きを持つようになっていった。それはもう子守唄の単旋律ではなく、いくつもの音が重なり合った、複雑で美しい和音となっていた。
ふと温室に目をやると、信じられない光景が広がっていた。萎れていた植物たちが、僅かに顔を上げ、葉の緑も心なしか色濃くなっているように見えた。奇跡だ、と思った。いや、これは奇跡ではない。母の愛の残響が、俺たちの絆によって力を取り戻し、生命に再びエネルギーを与えているのだ。
昼過ぎに電気は復旧したが、俺たちはもう、あのけたたましい測定器の電源を入れることはなかった。
母の三回忌の法要は、二人だけで静かに行った。遺影の前で手を合わせる。家の中心で、穏やかで優しいハーモニーが、まるで母の呼吸のように響いている。
俺はもう、この音の正体を科学的に証明しようとは思わない。これは、俺たちの家族だけの真実だ。母は肉体を失った。その喪失感が消えることはないだろう。だが、彼女は確かにここにいる。この家を、俺たちを、美しい音色で包み込み、見守ってくれている。
父と二人、温室の縁側に座り、お茶を飲む。再生し始めた緑の葉が、午後の光を浴びてきらきらと輝いている。言葉は少ない。だが、沈黙は少しも気まずくなかった。俺たちの間には今、母が遺してくれた最高のハーモニーが流れているのだから。
家族の絆とは、目に見えるものや、交わす言葉だけではないのかもしれない。それは音のように、光のように、空間そのものに満ちて、たとえ姿が見えなくなっても、愛する者たちの心の中で永遠に響き続ける残響なのだろう。俺は空を見上げ、心の中でそっと呟いた。
「聞こえるよ、母さん。ちゃんと、聞こえてる」