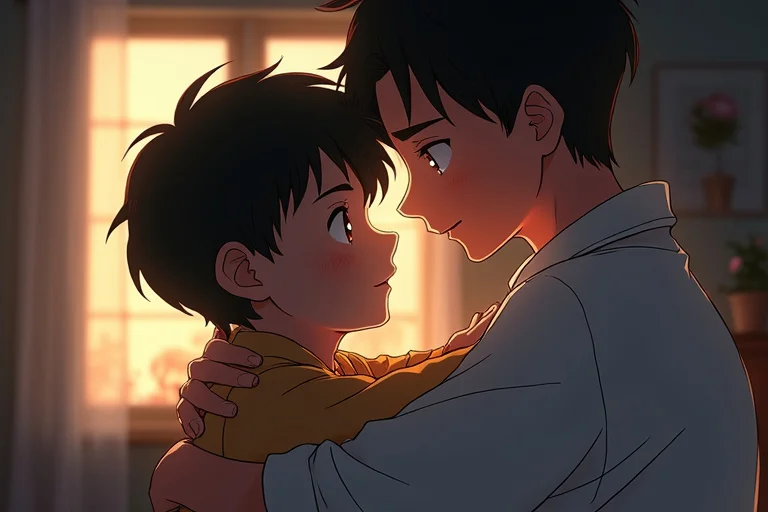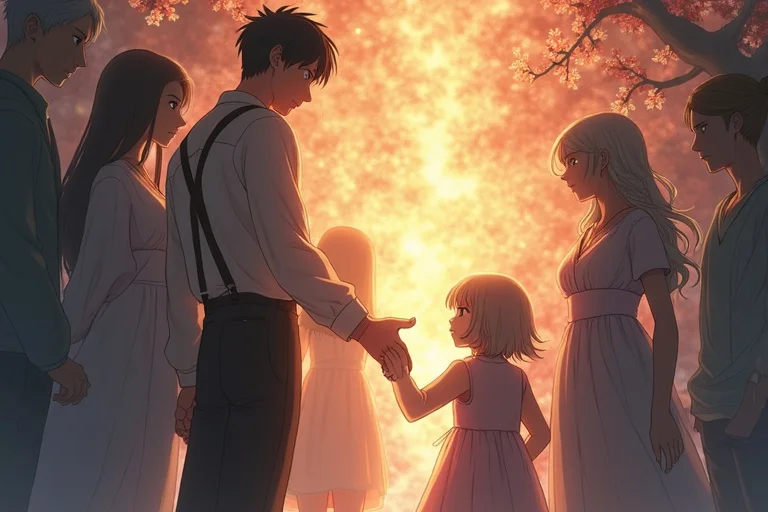第一章 枯れゆく季節
朝の光がリビングに差し込む。俺、片山涼介が淹れたコーヒーの香りが、トーストの焼ける匂いと混じり合う、いつもの朝。しかし、その日常の風景の中で、一つだけ、致命的に調和を欠いたものが存在した。リビングの隅に置かれた、我が家の「家族樹」だ。
「家族樹」は、この地域に住む家族が代々受け継ぐ、不思議な植物だ。家族の絆を養分として育ち、その繁茂は家庭円満の証とされている。我が家の樹は、結婚した時に妻の美咲が実家から株分けしてもらったもので、娘の陽菜が生まれてからは、天に届くかのように勢いよく枝を伸ばし、艶やかな深緑の葉を茂らせていた。それは俺の誇りであり、仕事の疲れを癒してくれる、静かな家族の一員だった。
だが、ここ一ヶ月ほどだろうか。その誇りに、明らかな翳りが見え始めていた。
「また葉が落ちてる…」
俺はマグカップを片手に、床に散らばる数枚の黄色い葉を忌々しげに見つめた。それは自然な新陳代謝ではなかった。枝は覇気を失って垂れ下がり、かつて光沢を放っていた葉は、まるで魂が抜けたように色褪せている。美咲に任せきりだった水やりや手入れを、俺も手伝うようになった。ネットで調べた高価な液体肥料も試した。だが、樹の衰弱は止まらない。
「パパ、おはよう」
背後から、小学三年生の陽菜の声がした。振り返ると、陽菜は食卓の椅子に座り、俺ではなく、枯れゆく樹をじっと見つめていた。その小さな瞳に浮かぶ憂いを、俺は見逃すことができなかった。
「陽菜、おはよう。大丈夫だ、パパがきっと元気にしてやるからな」
俺が力強くそう言うと、陽菜はこくりと頷いたが、その表情は晴れなかった。
キッチンに立つ美咲は、何も言わない。彼女は樹の変化に気づいていないはずがない。むしろ、俺よりも先に、その微細な兆候を感じ取っていたに違いない。だが、彼女はその話題を巧みに避けていた。俺たちが樹について話そうとすると、彼女は決まって窓の外へ視線を移し、天気の話を始めるのだ。
食卓を囲む三人。カトラリーの音だけが響く。かつては陽菜の学校での出来事で賑やかだったこの時間が、今は息苦しい沈黙に支配されている。俺は仕事の忙しさを理由に、家族と向き合うことから逃げていたのかもしれない。この枯れゆく樹は、そんな俺たち家族の、見えない亀裂を可視化した姿そのものだった。俺は焦っていた。このままでは、葉がすべて落ちるように、俺たちの何かも、取り返しがつかないほど失われてしまう。そんな恐怖が、じわりと胸を侵食し始めていた。
第二章 偽りの陽光
「家族樹」の衰弱を食い止めるため、俺は行動を開始した。原因は、コミュニケーション不足。家族と過ごす時間が足りないせいだ。そう結論づけた俺は、まず手っ取り早い解決策に飛びついた。
「今度の週末、温泉旅行に行かないか?前から行きたがってた、あの露天風呂がある旅館、予約取れそうだぞ」
夕食の席で、俺は努めて明るい声で提案した。陽菜の顔がぱっと輝くのを期待して。しかし、陽菜は美咲の顔をちらりと窺うだけだった。
「…ごめんなさい、涼介さん。その日は陽菜のピアノの発表会が近いから、レッスンを休ませるわけにはいかないの」
美咲は、申し訳なさそうに、しかしきっぱりと断った。その返事は正論で、俺は反論の言葉を見つけられなかった。
ならばと、俺は早く帰宅する日を増やした。これまでなら部下と飲んでいた時間も、まっすぐ家に帰り、陽菜の宿題を見てやろうとした。だが、陽菜は「もう終わったから」とノートを閉ざし、美咲は「夕飯の支度があるから」とキッチンに籠ってしまう。俺の居場所は、リビングのソファの上だけだった。手持ち無沙汰に眺めるテレビの音だけが、空虚に響く。
俺はまるで、家に差し込む「偽りの陽光」のようだった。そこに光はあるのに、何の温かみももたらさない。俺の努力は空回りし、家族の心には届いていない。その証拠に、「家族樹」はさらに弱々しくなっていた。葉は次々と落ち、床を掃くのが俺の日課になった。枝はまるで助けを求めるように、力なくしなっている。その姿は、家族に受け入れてもらえない俺自身の姿と重なって見えた。
ある夜、俺は一人、リビングで酒を飲んでいた。美咲と陽菜はもう寝室だ。静寂の中、ふと樹に目をやると、月明かりに照らされた細い枝が、微かに震えているように見えた。俺は吸い寄せられるように近づき、乾いた土に触れた。ひんやりとして、生命の熱を感じない。
「どうしてなんだ…」
呟きは誰にも届かない。俺は、何を見誤っているのだろう。ただ家族を愛している。幸せにしたい。その気持ちに嘘はないはずなのに、なぜ絆は枯れていくのか。俺は、問題の根源が、もっと深く、俺の知らない場所にあることを、予感し始めていた。
第三章 夜の庭師
その夜は、奇妙なほど静かだった。俺は寝付けず、書斎でぼんやりと本を読んでいた。時計の針が深夜一時を回った頃、廊下から微かな物音が聞こえた。泥棒か、と一瞬身構えたが、それはもっと繊細で、か細い音だった。
俺は息を殺して書斎のドアを少しだけ開け、廊下を覗き込んだ。月の光が差し込む薄闇の中、陽菜の部屋のドアがわずかに開いており、そこから一条の光が漏れていた。そして、小さな囁き声が聞こえる。
「…ごめんね。今日も、パパとママ、あんまりお話しなかったんだ。だから、これ、あげるね…」
陽菜の声だ。誰と話しているんだ?
好奇心と心配が入り混じった感情に突き動かされ、俺はそっと陽菜の部屋に近づいた。ドアの隙間から中を窺うと、信じられない光景が目に飛び込んできた。
陽菜はベッドの脇にしゃがみ込み、小さなテラコッタの鉢植えに顔を寄せていた。その鉢に植えられているのは、名も知らぬ小さな観葉植物だったが、それはリビングの「家族樹」とは対照的に、驚くほど生命力に満ち溢れていた。瑞々しい緑の葉を茂らせ、月明かりを浴びてきらきらと輝いている。陽菜は、その葉をそっと撫でながら、一日の出来事を、自分の寂しい気持ちを、その小さな植物に注ぎ込むように語りかけていたのだ。まるで、それが彼女の本当の「家族樹」であるかのように。
俺は息を呑んだ。陽菜が育てていた、彼女だけの秘密の庭。その時、雷に打たれたような衝撃が全身を貫いた。
「家族樹」は、家族の「幸せ」だけを吸い上げて育つのではなかった。それは、家族が共有する「一つの心」そのものを映し出す鏡だったのだ。
俺が仕事に心を奪われ、美咲が孤独を抱え、陽菜が寂しさを募らせるうちに、俺たちの心は知らず知らずのうちに離散していた。共有されるべき感情の置き場を失った心は、それぞれが個別の拠り所を求め始めていたのだ。陽菜にとって、それがこの小さな鉢植えだった。
ふと、寝室の方を見ると、美咲の部屋の窓辺にも、小さな鉢植えが置かれているのが見えた。ベランダで彼女が密かに育てていた、小さなハーブの鉢だ。彼女もまた、自分の心の置き場を、別に作っていたのだ。
愕然とした。陽菜にも、美咲にも、それぞれの「樹」があった。では、俺は? 俺の心は、どこにあったのだろう。行き場を失い、誰にも打ち明けられず、ただ枯れていくだけの、リビングのあの大きな樹。あれこそが、孤立した俺の心の姿そのものではなかったか。
俺は、家族という一つの器に、全員の心を無理やり押し込もうとしていた。だが、心はそんなに単純なものではない。俺は家族の心を一つにしようとするあまり、それぞれの心を殺していたのだ。その事実に気づいた瞬間、足元から崩れ落ちるような感覚に襲われた。
第四章 三つの鉢植え
翌日の夜、俺は美咲と陽菜をリビングに呼んだ。二人は、俺の真剣な表情に戸惑っているようだった。俺は、枯れかけた「家族樹」の前に立った。
「すまなかった」
俺は深々と頭を下げた。
「俺は、この樹を元気にすることばかり考えて、お前たちの心を全く見ていなかった。仕事にかまけて、寂しい思いをさせていたことにも気づかなかった。俺は、家族を一つの形に押し込めようとしていたんだ」
俺は、昨夜見た光景を正直に話した。陽菜が、そして美咲が、それぞれに自分の心の拠り所となる植物を育てていたこと。そして、この大きな「家族樹」が、行き場を失った俺自身の心の象徴であることに気づいたことを。
陽菜は驚いたように目を見開き、やがてぽろぽろと涙をこぼし始めた。美咲も、固く結んでいた唇を震わせ、静かに涙を流した。
「あなただけじゃないわ…」と美咲が言った。「私も、あなたにどう気持ちを伝えたらいいか分からなくなっていた。だから、あのハーブに話しかけるしかなかったの…」
「パパ、いつもお仕事大変だから、わがまま言っちゃいけないって…」
陽菜がしゃくりあげながら言う。
俺たちは、お互いを思いやるあまり、本当の心を隠し、見えない壁を作ってしまっていた。俺は涙を流す二人を、そっと抱きしめた。温かかった。久しぶりに感じる、家族の温もりだった。
数日後、俺は園芸店で、小さなテラコッタの鉢と、一株の苗を買ってきた。ポトスという、丈夫な観葉植物だ。
その夜、俺たちはリビングの大きな「家族樹」の周りに、それぞれの鉢植えを並べた。陽菜の生命力溢れる緑。美咲が育てた、控えめながらも良い香りを放つハーブ。そして、俺が今日買ってきたばかりの、まだ小さなポトスの苗。
三つの、大きさも形も違う鉢植え。
「家族って、一つの大きな樹になることじゃないのかもしれないな」
俺は呟いた。
「それぞれが自分の樹をしっかり育てて、でも、こうして隣にいて、寄り添って。時には水を分け合ったり、光を譲り合ったり。そういうことなのかもしれない」
美咲と陽菜は、黙って頷いた。リビングの大きな樹が、すぐに息を吹き返すことはないだろう。失われた信頼を取り戻すには、時間がかかる。俺たちの関係も、これからゆっくりと育てていかなければならない。
だが、三つの小さな鉢植えが寄り添う光景は、不思議なほどの安らぎと希望を与えてくれた。それは、俺たちの新しい家族の形だった。
それから一週間が経った朝。俺が「家族樹」に水をやっていると、あることに気づいた。枯れ木同然だった太い幹の、その根元。乾いた土を割って、ほんの数ミリ、小さな緑色の芽が顔を出していた。
それは、あまりにも小さく、か弱い芽だった。しかし、そこには確かな生命の息吹があった。俺はそっとそれに触れる。冷たい土の中から生まれた、温かい希望。俺は振り返り、キッチンに立つ美咲と、学校へ行く準備をする陽菜に微笑みかけた。俺たちの季節は、まだ始まったばかりだ。