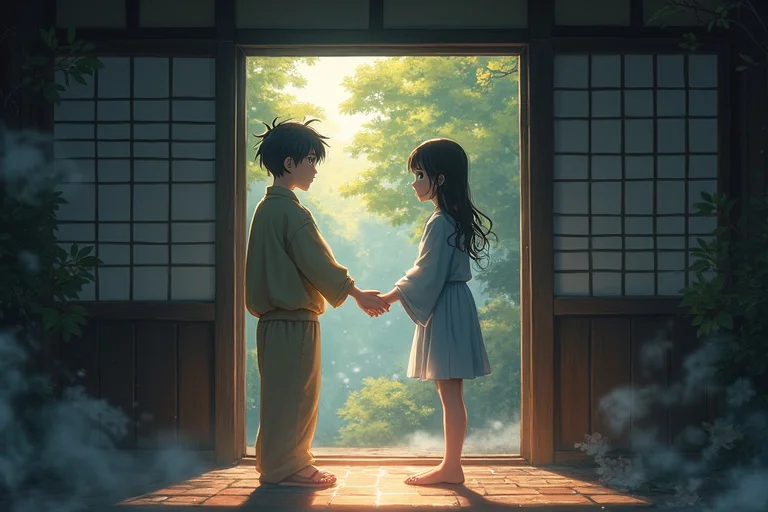第一章 色なき街の観察者
僕、湊(ミナト)の目には、世界が光の糸で織られたタペストリーのように映る。人々が家族と結ぶ絆は、色とりどりのオーラとなってその身を包むのだ。雨上がりの交差点、傘の下で寄り添う親子からは、太陽のような黄金色の太い光が伸び、互いを温かく繋ぎとめている。カフェの窓際で口論する姉妹の間には、チリチリと火花を散らす真紅の線が張り詰め、やがてどちらかが溜息をつくと、儚く揺らいで藍色に変わる。
僕は古書店の片隅で、インクと古い紙の匂いに包まれながら、窓の外を行き交う光の束をただ眺めている。僕には、その光がない。両親や妹を想う気持ちが胸にないわけではない。むしろ、人一倍強いとさえ思う。だが、僕の身体のどこにも、その感情が具現化することはない。声は色褪せた書物のように平坦で、瞳は磨かれていないガラス玉のように無個性だ。僕から伸びる家族への光は、まるで霧の中の蜘蛛の糸のように、か細く、曖昧に揺れているだけだった。
近頃、街には奇妙な人々が増え始めていた。彼らは僕と同じ「空白」の人間だ。昨日まで鮮やかな光を放っていたはずの人が、ふとした瞬間にすべての色を失い、まるで操り人形の糸が切れたかのように、茫然と立ち尽くす。人々は彼らを「無縁者(むえんもの)」と呼んだ。家族への情動の一切を失い、共有されていたはずの身体的特徴も消え、ただの個として世界に放り出された人々。
その虚ろな瞳を見るたび、僕は背筋に冷たいものを感じた。あの空白は、僕が世界に広げている病なのだろうか。僕という存在そのものが、この世界の美しい絆を、根元から断ち切っているのではないだろうか。
第二章 共鳴せぬ鏡
「無縁者」の噂は、古書のページに積もる埃のように、静かに、しかし確実に街を覆っていった。その原因を探るうち、僕は郷土史家である時枝(トキエダ)という老人の名に行き着いた。彼は、この現象を古代からの伝承と結びつけて研究している唯一の人物だった。
時枝氏の書斎は、本の森だった。床から天井まで伸びる書架が迷路のように入り組み、空気に溶け込んだ古い紙の匂いが、時間の流れを曖昧にさせる。彼は僕を見ると、皺の刻まれた目元を和らげた。
「君が、湊君か。君のような若者が、私の与太話に興味を持つとは珍しい」
彼の指先が、微かに琥珀色の光を帯びていた。亡き妻への追憶が、肌の温もりとして具現化しているのだと、僕にはわかった。
書斎の奥、ビロードの布が掛けられた場所に、それはあった。「共鳴の鏡」だ。黒曜石のように磨かれたその鏡は、人の姿だけでなく、その者が家族へ抱く最も強い感情の色を、オーラのように映し出すという。
時枝氏が鏡の前に立つと、彼の姿の周りに、夕焼けのような淡い緋色が滲んだ。妻への尽きせぬ愛情の色だ。
「さあ、君も」
促されるまま、僕は鏡と対峙した。そこに映るのは、色のない瞳と、感情の読めない表情をした、見慣れた自分の姿だけ。鏡面はシンと静まり返り、何の光も、何の色も映し出すことはなかった。まるで、僕の魂がそこには存在しないとでも言うように。
「……やはり、な」時枝氏が呟く声が、やけに遠く聞こえた。鏡の冷たさが、肌を突き刺すようだった。
第三章 蝕まれる絆
「お兄ちゃん、最近疲れてる?」
妹の遥(ハルカ)が、古書店に顔を出した。彼女は僕とは正反対だ。両親への感謝と愛情が、その瞳を蜂蜜のような美しい琥珀色に染め上げ、その輝きは両親の瞳にも共有されている。彼女が笑うと、店の中の空気がぱっと華やぐ気がした。
彼女は僕の隣に座り、楽しそうに大学での出来事を話してくれた。だが、僕は気づいてしまう。彼女の瞳の琥珀色が、僕と一緒にいる間、ほんの少しだけ、その輝きを曇らせる瞬間があることに。
「ねえ、お兄ちゃん」
不意に、彼女の声のトーンが落ちた。
「最近、時々ね……お兄ちゃんと話していると、パパやママとの繋がりが、少しだけ遠くに感じるの。胸のあたりが、すうっと寒くなるような……変だよね?」
その言葉は、僕の心臓を鷲掴みにした。
やはり、僕のせいだ。僕のこの「空白」が、大切な妹の絆さえも蝕んでいる。僕が傍にいるだけで、世界から色が失われていく。
その夜、テレビのニュースは深刻な面持ちで「無縁者」の増加を報じていた。彼らは社会から孤立し、生きる意味を見失っていく。その映像に映る虚ろな群衆と、鏡に映った自分の姿が、寸分違わず重なった。
第四章 均衡の古文書
僕は自室に閉じこもった。誰とも会わなければ、誰の絆も傷つけずに済む。僕という存在が、最初からなければよかったのだ。壁に立てかけた鏡には、相変わらず色なき僕が映っている。僕はその鏡に布をかけ、世界から自分を消し去ろうとした。部屋の空気は淀み、息をすることさえ苦しい。僕が吐き出す息が、この部屋の色を奪っていく気がした。
その時、静かにドアがノックされた。時枝氏だった。息を切らせた彼は、羊皮紙の巻物のような、古びた一冊の書物を抱えていた。
「見つけたぞ、湊君。君の『空白』の、本当の意味かもしれない」
彼が広げた古文書には、虫食いの穴だらけのページに、かすれたインクでこう記されていた。
『絆は人を強くする。されど、過剰なる結びつきは個を溶かし、世界を一つの色に染め、停滞させる。故に世界は、時折「空白」を生み出す。それは何色にも染まらぬ器。溢れ出す感情を受け止め、個が個であるための余白を守り、世界の均衡を保つための楔である』
時枝氏は、興奮を隠せない様子で僕に語った。
「君は、世界を壊しているのではない。逆だ! 家族という絆が強くなりすぎ、人々が『家族』という役割の中に個人の自我を埋没させてしまう……そんな世界の窒息を防ぐための、安全装置なのだ。君という『空白』が、過剰な感情の奔流を受け止める緩衝材として機能しているんだ」
彼の言葉が、雷のように僕の身体を貫いた。
「では、『無縁者』たちは……?」
「彼らは、絆にがんじがらめになり、個を失いかけていた人々だったのかもしれない。君という『空白』に触れることで、一度その結びつきがリセットされた。それは喪失ではない。新たな関係を、自分自身の足で築き直すための……更地なんだよ」
第五章 透明な光の誕生
緩衝材。安全装置。楔。
僕の「欠落」は、欠落ではなかった。それは、世界が多様なままであるために必要な「役割」だった。
僕は震える足で立ち上がり、鏡にかけた布を剥がした。そこに映る自分は、もうただの「空白」ではなかった。誰かの絆を羨むのでもなく、自分の無個性を嘆くのでもない。この身体は、あらゆる家族の形を、そこに属する一人ひとりの自我を、静かに肯定するためにある。特定の誰かに向けた強烈な感情ではない。だが、それは世界に存在する無数の絆そのものへ向けた、限りなく普遍的で、静かな愛情だった。
僕が、僕自身のその役割を、心の底から受け入れた、その瞬間。
鏡の中の僕の胸の中心から、ふわりと、柔らかな光が灯った。
それは、何色でもなかった。赤でも青でも、黄金色でもない。しかし、あらゆる光の色をその内に秘めているかのような、純粋な「透明な光」だった。それは声の艶でも、瞳の色でもない。僕の存在そのものから滲み出る、生命の輝きそのものだった。
僕から伸びていたか細いオーラもまた、確かな輪郭を持つ透明な光の帯へと変わっていた。それはプリズムのように、僕が少し動くだけで、その内側に七色の虹をきらめかせる。
窓の外に広がる街の景色は、何も変わらない。色とりどりのオーラが交差し、中には光を失った「無縁者」も歩いている。だが、僕にはもう、それが欠落には見えなかった。すべてが、この世界を織りなす、多様な糸の一本一本に見えた。
「お兄ちゃん!」
駆け込んできた遥が、僕の姿を見て息を呑む。
「……なに、それ……?すごく……すごく、綺麗……」
彼女の琥珀色の瞳が、僕の放つ透明な光を映して、これまでにないほど深く、美しく輝いていた。
僕は初めて、自分の身体に宿ったこの具現化に、静かな誇りを感じていた。これは誰かと共有するための絆ではない。この世界そのものと結ぶ、僕だけの、普遍的な絆の証なのだ。僕というカンバスは、空白なのではない。これから描かれる、あらゆる色の未来を受け入れるために、ただ透明に広がっているだけだったのだ。