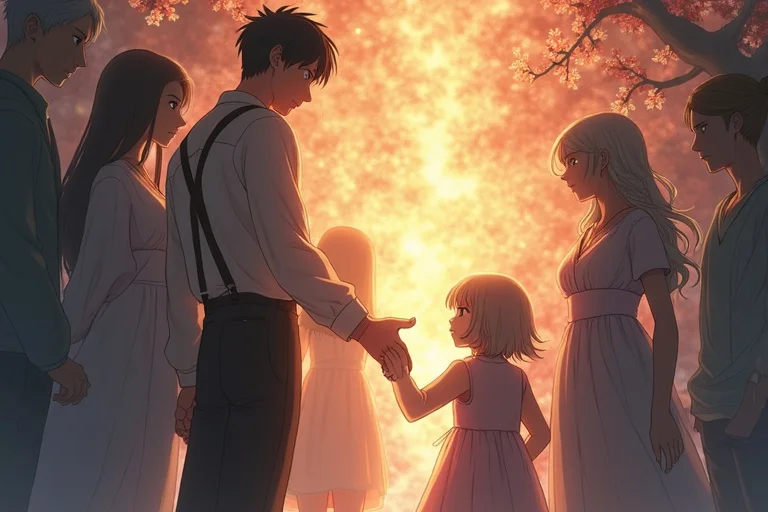第一章 鳴り出した古びた歌声
「これ、おばあちゃんから。あんたに、だってさ。」
そう言って、母が渡してきたのは、手のひらに収まるほどの、古びた木製のオルゴールだった。入院中の祖母からの贈り物にしては、あまりに質素で、色褪せた彫刻は、長い年月の痕跡を刻んでいる。真白は今年28歳。兄が一人、妹が一人。それぞれが自分の人生を歩み始め、家族が揃って食卓を囲むことも稀になった最近、祖母からの唐突な贈り物が、妙に心に引っかかった。
薄暗い自室の机の上で、真白はそのオルゴールを眺めた。表面は艶を失い、触れるとざらりとした感触が指先に伝わる。蝶番が錆びつき、蓋を開けるのも一苦労だった。きぃ、と軋む音を立てて開いた中には、小さなバレリーナの人形が鎮座していた。その指先は欠け、チュチュは黄ばんでいる。真白は恐る恐るゼンマイを巻いた。ギチギチと鈍い音を立てて、ゼンマイが巻き上がっていく。やがて、カチリと軽い音がして、バレリーナがゆっくりと回転を始めた。
その瞬間、かすかに、しかし確実に、部屋の空気が変わった。チリン、チリンと、途切れがちな、それでいて郷愁を誘うメロディが流れ出す。それは、真白がこれまで聞いたことのない、しかしどこか懐かしい子守歌のようだった。そして、その音の狭間から、ハッキリと人の声が聞こえてきたのだ。
「ああ、可愛いわね、この子。小さな手のひらで、私の指をぎゅっと握るのよ。この温かさがあれば、どんな困難だって乗り越えられる。そうでしょう、あなた?」
その声は、優しく、しかし確かな響きを持っていた。真白は息を飲んだ。耳を澄ませる。間違いなく、人間の声だ。それはまるで、すぐ隣で誰かが語りかけているかのようだった。しかし、部屋には真白しかいない。その声は、祖母の声ではない。もっと若い、遠い過去から響いてくるような響きを持っていた。
「誰……?」
真白は呟いた。オルゴールから聞こえるその声は、真白の曾祖母、既に他界しているはずの祖母の母の声だった。真白は曾祖母の写真を数枚しか見たことがない。しかし、その声は、写真から感じられる穏やかで凛とした雰囲気にぴったりと重なった。オルゴールは、まるで生きているかのように、語り始めたのだ。それは、真白の家族の、誰も知らない秘密の物語の始まりだった。
第二章 理想の家族の物語
オルゴールの語りは、毎日少しずつ、真白の耳に届き続けた。曾祖母は、その若き日、曾祖父との出会いから、結婚、そして子どもを授かった喜び、家族を築いていく上での小さな困難とそれを乗り越える夫婦の絆を、まるで詩を朗読するかのように語った。語り口は温かく、家族への深い愛情に満ちていた。
「真白、また聞いてるの?」
ある日、リビングでオルゴールのメロディと曾祖母の声が聞こえるのを聞きつけ、母が顔を出した。真白は、半信半疑の母や、最初は冷やかしていた兄や妹にも、オルゴールの声を共有した。
「本当に誰かの声がするんだね。でも、古いオルゴールだから、音の歪みでそう聞こえるだけなんじゃない?」と兄は懐疑的だった。「昔の録音技術でこんなクリアな声が残るはずないよ」と妹は科学的な視点から否定した。両親もまた、単なる錯覚だとして、深くは取り合わなかった。
しかし、真白だけは違った。オルゴールが語る物語は、真白が抱いていた「家族」に対する理想像そのものだった。常に寄り添い、どんな困難も共に乗り越える夫婦。子どもたちの成長を心から喜び、互いを深く信頼し合う兄弟姉妹。それは、真白が今の家族に感じている空虚さとは対極にある、輝かしい世界だった。
真白の家族は、決して不仲というわけではない。年に数回は顔を合わせ、世間話をする。しかし、その会話は常に表面的なもので、互いの心の内を深く探り合うことはなかった。父は仕事、母は趣味、兄は独立した生活、妹は遠方の大学。それぞれが独立しすぎているが故に、どこか断絶しているような感覚があった。
オルゴールの物語は、真白に希望を与えた。「私たちも、きっと昔はこんな風に強い絆で結ばれていたんだ」と、真白は思った。祖父も祖母も、オルゴールが語るような強い愛のもとに育ち、また真白の親世代も、その理想を受け継いできたはずだと。オルゴールが奏でるメロディは、真白の心に温かい光を灯した。このオルゴールが、今の家族をもう一度繋ぎ直すきっかけになるかもしれない。そんな淡い期待を抱きながら、真白は毎日、オルゴールに耳を傾け続けた。しかし、その希望の裏で、真白はオルゴールの語りに、奇妙な「間」や「抜け落ちた部分」があることに気づき始めていた。語られる家族の歴史は、あまりに完璧で、あまりに美しかったのだ。
第三章 歪んだメロディと空白の真実
オルゴールが語る物語は、時折、唐突な沈黙を挟むようになった。それは数秒から数十秒の間だったが、その空白の間に、真白の心には奇妙な不安がよぎった。語られる曾祖母の声も、以前のような明瞭さを失い、メロディもまた、微かに、しかし確かに音程を外すことが増えた。
そしてある日、オルゴールが語り始めた内容は、真白の家族が抱える、それぞれの隠れた問題と、まるで呼応するかのようにリンクし始めた。
「あの時は本当に苦しかった。家族を守るためなら、どんなことでも、どんな嘘でも、ついてみせると誓ったわ。」
曾祖母の声が、突然、それまでの朗らかなトーンとは異なる、かすれた、しかし強い決意を秘めた響きで語り出した。その言葉が、ちょうど兄が会社で大きな失敗をして、それを家族に隠そうとしていた時期と重なったのだ。真白はゾッとした。偶然だろうか?
さらに、オルゴールは、曾祖父が事業で大きな挫折を味わったこと、家族が貧困の淵に立たされた過去を語り始めた。その語り口には、当時の曾祖母の葛藤と、家族を守るための必死な思いが滲んでいた。しかし、そこには決定的な「空白」があった。曾祖父がその危機をどう乗り越えたのか、曾祖母が具体的に何をしたのか、肝心な部分が語られないのだ。ただ「家族の愛で乗り越えた」と、曖昧な言葉で締めくくられるばかりだった。
その夜、真白はオルゴールを再び開いた。バレリーナはいつもより早く、不規則に回転しているように見えた。メロディは完全に音程を外し、まるで幽霊がすすり泣くかのような、歪んだ音を奏で始めた。そして、曾祖母の声は、もはや温かい語り口ではなく、苦悶と後悔に満ちた、ほとんど聞き取れない囁きに変わっていた。
「嘘を……ついたの……私……家族のために……」
その言葉は、ひどく断片的で、辛うじて聞き取れるものだった。オルゴールが語っていたのは、単なる曾祖母の記憶ではなかったのだ。それは、家族の「集合無意識」が宿る媒体であり、語られていたのは、家族が「そうあってほしい」と願った、美化された家族の歴史だったのだ。オルゴールは、家族が目を背けてきた真実の断片を、歪んだ音と途切れた言葉でしか語ることができなかった。
真白は、ハッと息を飲んだ。これまでの理想的な物語は、家族が自分たちを守るために作り上げた「嘘」だったのだ。曾祖母が家族のために隠し通した「過ち」が、オルゴールが語らなかった「空白」の中に隠されている。そして、その過去の「空白」こそが、現在の家族が抱える問題の、遠い、しかし確かな遠因となっているのだと、真白は直感した。オルゴールが語る美化された過去は、完璧な家族像という重い足枷となり、現代の家族に本音を隠させ、表面的な繋がりしか持てない理由となっていたのだ。真白の価値観は、根底から揺らいだ。
第四章 オルゴールが語れなかったこと
真白は、オルゴールの歪んだメロディと、断片的な囁きから真実の糸口を掴み、家族の様子を注意深く観察し始めた。父はいつも過去の成功談ばかりを話し、母は父の言葉を盲目的に肯定する。兄は失敗を恐れ、妹は常に周囲の目を気にしていた。彼らは皆、曾祖母が作り上げた「完璧な家族」という幻想に縛られているように見えた。
ある週末、真白は家族全員を食卓に集めた。普段なら互いの予定を優先する兄と妹も、真白の真剣な眼差しに気圧され、久しぶりに四人が顔を揃えた。
「オルゴールが、曾祖母が隠した真実を語ろうとしている。私たちが、ずっと見て見ぬふりをしてきたこと。それが、今の私たちの家族をバラバラにしているんだと思う。」
真白はそう切り出した。最初は誰もが戸惑い、反発した。「何を馬鹿なことを」と父は怒り、「そんなことで家族が壊れるはずがない」と母は目を背けた。兄は「現実を見ろ」と皮肉り、妹は不安そうに俯いた。
しかし、真白は怯まなかった。オルゴールの語れなかった「空白」の部分、曾祖父の事業の失敗とその後の曽祖母の行動について、真白は図書館で古い新聞や資料を漁り、少しずつ事実を掴んでいた。曾祖父の事業破綻後、曾祖母は家族の体面を守るため、そして子供たちを飢えさせないために、当時では「はしたない」とされていた、水商売の仕事に身を投じていたのだ。その事実を家族に隠し通し、曾祖父が事業を再建したという美談にすり替えた。
「曾祖母は、家族を守るために嘘をついた。それは、きっと正しい選択だったんだ。でも、その嘘の上に築かれた『完璧な家族』という幻想が、私たちを縛り続けている。父さんは、完璧な夫であり父でいようとして、自分の弱さを隠している。母さんは、理想の妻であるために、父さんの過ちを見て見ぬふりをしてきた。兄さんは、失敗を恐れて、新しい挑戦ができない。妹は、周りの期待に応えようとして、自分の本心を見失っている。私も、この家族のどこか空虚な空気に、ずっと目を背けてきた。」
真白の言葉は、まるで鋭い刃のように、家族一人一人の心の奥底に突き刺さった。沈黙が続く。やがて、父が震える声で話し始めた。彼の事業での失敗、そしてその後の苦悩。母が流す涙。兄が打ち明ける過去の過ちと、そこからの怖れ。妹が抱える、本当はやりたいことと、世間体との葛藤。
激しい感情のぶつけ合いが、食卓を嵐のように駆け巡った。それは、家族が何十年も避けてきた、本音と本心のぶつかり合いだった。互いの痛み、弱さ、そしてそれでも、互いを大切に思う気持ちが、露わになっていく。
第五章 偽りの絆を越えて
嵐のような夜が過ぎ、真白の家族は、偽りの理想という重い足枷を打ち破った。翌朝、食卓には、どこか晴れやかな、しかし少し疲れた表情の家族がいた。昨夜の激しい感情の応酬は、彼らの間に、かつてないほどの透明な空気をもたらしていた。
オルゴールは、真白の部屋の机の上で静かに佇んでいた。ゼンマイを巻いても、もう曾祖母の声は聞こえない。かすれたメロディだけが、途切れ途切れに流れ、やがてそれも途絶えた。役割を終えたオルゴールは、ただの古びた木箱に戻っていた。しかし、それはもはや、嘘を語る「嘘つきなオルゴール」ではなかった。真実を呼び起こし、家族の目を覚まさせた「導きのオルゴール」だったのだ。
真白は、家族とは何かを改めて考えた。それは、完璧な理想像ではなく、傷つきやすく、不完全な互いを認め合い、支え合うこと。過去の美談にしがみつくのではなく、現在を生き、未来を共に築いていくこと。オルゴールが語れなかった空白の真実を受け入れたとき、家族は真の絆を取り戻したのだ。
オルゴールはもう語ることはない。しかし、その残した問いかけは、これからも真白の、そして家族の心に長く残り続けるだろう。真白の心には、過去の美化された家族像ではなく、傷つきながらも寄り添い合う、現在の家族の温かい光が灯っていた。完璧ではないけれど、それでも愛おしい家族の顔が、真白の脳裏に浮かぶ。彼女は、これからの家族の歴史を、偽りなく、自分たちの手で、紡いでいく決意を新たにした。オルゴールは沈黙したが、新たな家族の物語は、今、始まったばかりだった。