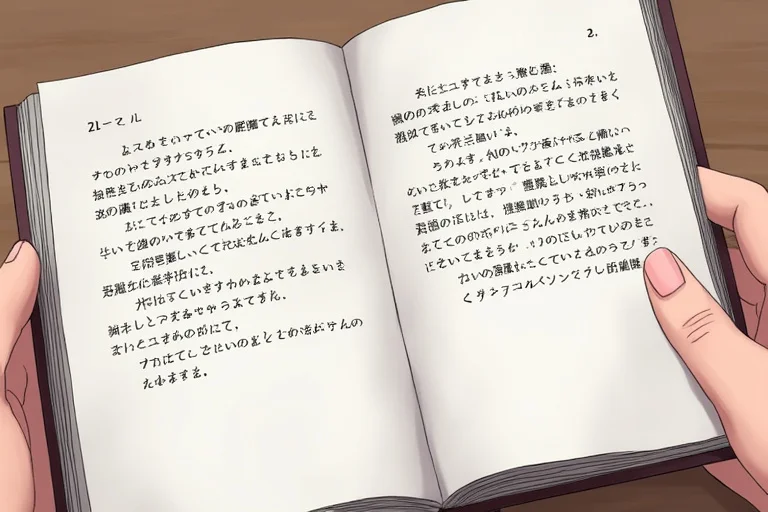第一章 木箱と亡き母の声
父、雄一郎が死んだのは、蝉の声がアスファルトの熱に溶けていくような、夏の盛りだった。病院の白い廊下で医師から告げられた言葉は、まるで現実感のない映画のセリフのように、俺、健太の耳を滑り落ちていった。あっけない、心筋梗塞だった。
物心ついた頃には、もう母はいなかった。写真でしか知らない、優しく微笑む母。そして、その隣で硬い表情を浮かべる、若き日の父。俺の家族は、その小さな写真立ての中の三人だったが、実態は、不器用な父と息子の、静かでぎこちない二人暮らしがすべてだった。
父との会話は、いつも途切れがちだった。食卓に並ぶのは、味のしない煮物と、スーパーの惣菜。父はテレビのニュースに視線を固定し、俺はただ黙々と箸を動かす。母の話をしようものなら、父は聞こえないふりをして席を立つか、「もういい」と短く遮るだけだった。その背中はいつも頑なで、俺との間に分厚い壁を築いているように見えた。俺は、父が母を失った悲しみを、俺にまで背負わせたくないのだと、そう勝手に解釈していた。
四十九日を過ぎ、父の遺品を整理していた時だ。押し入れの奥、古い布団の間に埋もれるようにして、その木箱は見つかった。桐だろうか、年月を経て飴色になった表面は滑らかで、ひんやりと冷たい。蓋を開けると、防虫剤の懐かしい匂いと共に、カセットテープがぎっしりと並んでいた。そして、一台のポータブルカセットプレーヤー。
テープのラベルには、すべて同じ、父の几帳面な文字で『健太へ』とだけ記され、日付が添えられていた。日付は、俺が生まれた年から、母が亡くなったとされる五歳の夏まで、びっしりと続いていた。これは何だ? 父が遺した、何かの記録か。俺はプレーヤーに一番古い日付のテープをセットし、再生ボタンを押し込んだ。
ジー、というノイズの後、聞こえてきた声に、俺は息を呑んだ。
「……健太、聞こえる? ママですよ」
女の声だった。柔らかく、少しだけ鼻にかかった、優しい声。写真の中の母が、そのまま語りかけてきたような錯覚に陥る。
「今日で、あなたが生まれて一週間。小さな手で、私の指をぎゅっと握ってくれました。天使みたいに、可愛い寝顔……」
それは、亡き母の声だった。しかし、何かがおかしい。声は美しいが、抑揚がなく、どこか平坦だ。まるで、目の前にある文章を淡々と読み上げているような、奇妙なぎこchnessさを孕んでいた。そして時折、かすかな咳払いや、紙が擦れるような乾いた音が、声の背後に聞こえる。まるで、誰かに監督されながら、無理に読まされているような……。その不自然な響きが、夏の終わりの湿った空気と相まって、俺の背筋を冷たく撫でた。
第二章 色褪せた日々の記録
俺は憑かれたように、テープを聴き続けた。一本、また一本と、テープを入れ替えるたびに、俺は母の声に導かれて、自分の知らない過去を追体験していった。
『健太、今日は初めて寝返りを打ちました。世界が少し、広がったね』
『離乳食の人参は嫌いみたい。べーって、顔中に塗りたくって、パパと二人で大笑いしました』
『公園の鳩を、一生懸命追いかけていましたね。あなたのその小さな背中が、いつか大きくなる日が、ママは楽しみで、少しだけ寂しいです』
語られるのは、愛情に満ちた母親の眼差しそのものだった。俺の記憶にはない、幼い日々の断片。父が決して語ることのなかった、家族三人の温かい時間。俺は、これまで感じていた父へのわだかまりが、少しずつ溶けていくのを感じていた。父は、ただ不器用だっただけなのだ。母との幸せな記憶を、一人で抱えるのが辛くて、だからこそ、こんな形で記録を残してくれたのではないか。
しかし、テープを聴き進めるほどに、冒頭で感じた違和感は、確信へと変わっていった。母の声は、最後まで感情の起伏が乏しい。嬉しいはずの出来事も、悲しいはずの予感も、同じトーンで語られる。まるで、感情という名の絵の具を持たない画家が、モノクロの線だけで世界を描いているようだった。
俺は、母は体が弱かったと聞かされている。もしかしたら、病床で声を振り絞って、この記録を遺してくれたのかもしれない。そう考えれば、この不自然さにも納得がいく。俺は自分にそう言い聞かせた。父が母の話題を避けたのも、このテープに込められた母の苦しみを思い出すのが辛かったからだ。きっと、そうだ。そうに違いない。
父との数少ない思い出が、脳裏をよぎる。小学校の運動会、他の父親たちがビデオカメラを回す中、父はただ黙って、ゴール地点で俺を待っていた。俺が転んで膝を擦りむいた時も、「立て」とぶっきらぼうに言うだけで、決して手を差し伸べはしなかった。だが、その夜、俺が眠った後、そっと枕元にやってきて、俺の膝に新しい絆創膏を貼り直してくれていたことを、俺は知っている。
父の愛情は、いつも見えにくい場所にあった。このテープも、きっとそういうものなのだ。父なりの、最大限の愛情表現。俺は木箱を抱きしめ、窓の外に広がる夕焼けを眺めた。空は、父が好きだった日本酒のように、深く、静かな茜色に染まっていた。
第三章 テープの向こうの真実
ついに、最後の一本にたどり着いた。ラベルの日付は、母が亡くなったとされる日の、三日前。俺はごくりと唾を飲み込み、震える指で再生ボタンを押した。
テープから流れる声は、これまでになく弱々しく、途切れがちだった。
『健太……もうすぐ、五歳のお誕生日ね。ママは、あなたに会えて……本当に、幸せでした。強く、優しい子に、なってね……。ずっと、空から見ていますから……』
いつものように、それは愛情深い言葉だった。だが、その直後だった。
ふっと、声が途切れる。数秒の沈黙。そして、今まで聞こえたことのない、小さな、しかしはっきりとした呟きが、テープに記録されていた。
「……もう、いいかしら、雄一郎さん」
その声に、全身の血が逆流するような衝撃が走った。なんだ? 今のは……。
混乱する俺の耳に、追い打ちをかけるように、決定的な声が響いた。
「……ああ、ありがとう。今日はここまでだ。よく頑張ってくれた」
それは、紛れもなく、父・雄一郎の声だった。俺が三十年間、聞き続けてきた、あの不器用で、ぶっきらぼうな父の声。
頭が真っ白になった。何が起こっている? これは、母の声ではなかったのか? 父が、誰か別の女性に、これを録音させていた? なぜ? 一体、何のために?
パニックに陥った俺は、半ば無意識に、もう一度父の書斎を掻き回した。机の引き出し、本棚の裏、ありとあらゆる場所を探す。そして、あの木箱の底板が、わずかに浮き上がっていることに気づいた。爪を引っかけてこじ開けると、そこには、黄ばんだ一通の封筒が隠されていた。宛名には、震えるような字で『健太へ』とある。
俺は封を開け、中の便箋を広げた。そこには、父の、最初で最後の手紙があった。
『健太へ。この手紙を読んでいるということは、お前はすべてを知ってしまったのだろう。許してくれ。
お前の母、美咲は、お前を産んで七日後に、この世を去った。生まれつき心臓が弱く、出産は命懸けだと、医者には止められていた。だが、美咲はお前を産むことを諦めなかった。「あの子に会いたい」と、そう言って笑った。
あいつが亡くなった時、俺は途方に暮れた。腕の中には、まだ小さな、お前がいる。俺のような不器用な男に、母親の愛情まで注ぐことなど、できるはずもなかった。お前に、母親の愛情を知らずに育ってほしくなかった。母親が、どれほどお前を愛し、会いたがっていたか、伝えたかった。
悩んだ末、俺は、美咲の遠い親戚で、声が少し似ている女性に、すべてを話して頼み込んだ。俺が書いた「美咲が生きていたら書いたであろう日記」を、読んでもらうことにしたんだ。彼女は、俺の馬鹿げた頼みを、静かに受け入れてくれた。
母さんの話を避けていたのは、この嘘が、いつかお前を深く傷つけるのではないかと、怖かったからだ。すまない。本当に、すまない。だが、これだけは信じてほしい。テープの中の言葉は、すべて、俺がお前の母さんならきっとこう言うだろうと、心から信じて書いた言葉だ。あれは、俺と、天国の美咲と、二人からの、お前への愛の言葉なんだ』
手紙は、涙の染みで、ところどころ滲んでいた。
第四章 父が残した愛の形
俺は、その場に崩れ落ちて嗚咽した。涙が、次から次へと溢れて止まらなかった。
壁だと思っていたものは、壁などではなかった。それは、父がたった一人で背負い続けた、途方もなく巨大で、歪で、しかしどこまでも純粋な愛情の塊だった。無口で、不愛想で、いつも背中を丸めていた父。その背中は、息子を傷つけまいと、巨大な嘘という重荷を隠すために、丸まっていたのだ。
しばらくして、俺は立ち上がり、おぼつかない足取りでカセットプレーヤーの前に戻った。そして、最初の一本を、もう一度、セットした。
『……健太、聞こえる? ママですよ』
今、この声は、全く違う響きを持って俺の心に届いた。
平坦で、感情のない声。その向こう側に、俺は父の姿を見た。緊張でこわばった顔で、録音に立ち会う父。紙をめくる乾いた音は、次のセリフを必死で考える父の焦り。小さな咳払いは、込み上げる感情を押し殺す、父の苦悩。
これは、「偽りの母の声」などではない。
これは、紛れもない、「父の愛の声」そのものだった。
父は、母の死という絶望の淵で、一つの物語を創造したのだ。息子、健太のための、世界でたった一つの物語を。不器用な父が、人生のすべてを賭けて紡いだ、壮大な愛の物語を。
俺は父の遺影に、そっと手を合わせた。写真の中の父は、やはり硬い表情で、こちらを見ている。
「親父、ありがとう」
声に出した言葉は、涙で震えていた。
「俺、ちゃんと受け取ったよ。あんたたちの、愛情を」
部屋には、カセットテープから流れる優しい声と、窓から差し込む柔らかい光だけが満ちていた。父が遺した「声の葉」は、これからも俺の人生に寄り添い続けるだろう。それは、偽りの記憶ではない。歪んだ形をしていようとも、間違いなく本物の、父と母がくれた、かけがえのない愛の形なのだから。俺はこれから、この声を胸に生きていく。そして、いつか自分に家族ができたなら、この不器用で、途方もない愛の物語を、きっと語って聞かせようと思った。