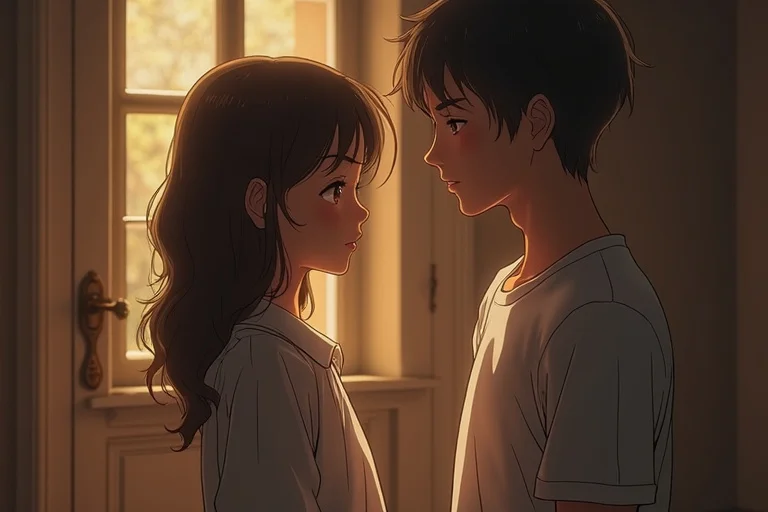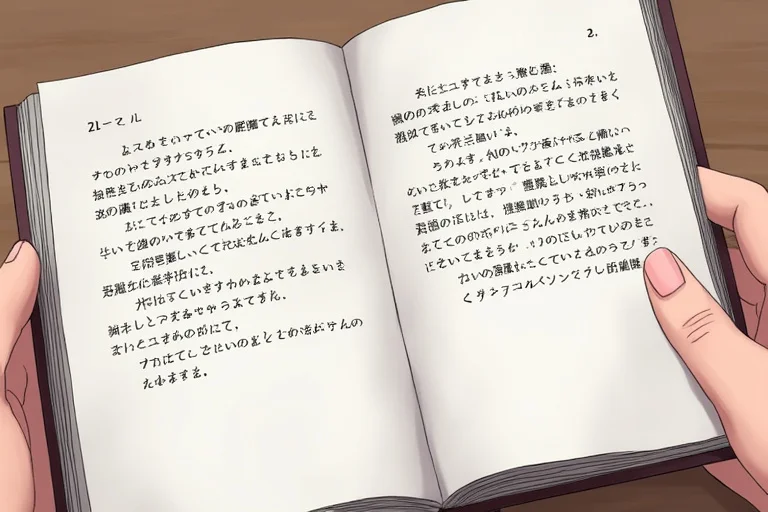第一章 色褪せるマンダラ
俺、結城慧(ゆうき けい)には、ささやかな秘密がある。人に触れると、その人物が持つ家族との関係性が、色と形で構成された幾何学模様として脳裏に浮かぶのだ。それは万華鏡のように、あるいは精緻なマンダラのように、その家族だけの宇宙を描き出す。
「ありがとうございました」
古物商を営む俺の店で、老婦人が古びた懐中時計を買い取ってくれた。代金を受け取る際に触れた指先から、温かな模様が流れ込んでくる。三世代の家族が織りなす、複雑で力強い黄金色の螺旋模様。見ているだけで胸が温かくなるような、強い絆の形だ。
だが最近、そんな鮮やかな模様に出会う機会がめっきり減った。今日訪れた客のほとんどは、単純な直線や、くすんだ灰色の円で構成された、ひどく希薄な模様しか持っていなかった。まるで、家族という概念そのものが世界から色を失っていくような、漠然とした不安が胸をよぎる。
店のシャッターを下ろし、軋む階段を上がって自宅へ戻る。夕食の準備をする妹の澪(みお)が、「おかえり」と振り返った。その笑顔に、俺は言いようのない違和感を覚える。妹に近づき、何気ないふりをしてその肩に手を置いた。
瞬間、息を呑んだ。
かつて俺たちの家族が描いていた模様は、太陽のように燃え盛る、複雑怪奇な黄金のマンダラだった。父と母、俺と澪、四つの点が強固な引力で結びつき、互いを照らし合っていた。だが今、俺の脳裏に映ったのは、その見る影もない姿だった。模様はところどころが欠け、輝きは弱々しい銀色にまで落ち込んでいる。中心にあったはずの引力は弱まり、全体がゆっくりと解けていく砂の城のようだった。
心臓が冷たい手で掴まれたような感覚。俺はリビングの隅に置かれた、祖父の形見である古い秤に目をやった。真鍮製のその秤は、ただの骨董品ではない。家族の「思い出の重さ」を測る、特別な秤だ。俺たち家族の思い出が重ければ重いほど、その針は大きく右に振れる。
その針が、今、ほとんどゼロを指していた。昨日よりも、さらに左に傾いている。まるで、俺たちの存在そのものが、この世界から少しずつ消えかけているかのように。
第二章 失われる重さ
世界は静かに、だが確実に変わりつつあった。テレビのニュースキャスターが、真顔で「専門家は、特定の人間関係における記憶の希薄化、いわゆる『家族健忘』の拡大に警鐘を鳴らしています」と語っていた。人々は隣にいる親や兄弟を、血の繋がっただけの「同居人」としか認識できなくなり始めていた。愛情も、憎しみも、感謝も、すべての感情が漂白されたように薄まっていく。
その波は、俺たちの家にも容赦なく押し寄せていた。
「お兄ちゃん」
ソファで本を読んでいた澪が、ふと顔を上げた。
「なんだ?」
「ううん、なんでもない。ただ…なんだか、お兄ちゃんのこと、すごく昔から知ってる気がするんだけど、どんな人だったか、あんまり思い出せないの」
彼女は困ったように眉を寄せ、自分の手のひらを見つめた。その言葉は、鋭い氷の破片となって俺の胸に突き刺さる。澪の記憶からも、「家族の重さ」が失われ始めているのだ。父も母も、最近は口数が減り、互いの視線が合うことさえ稀になった。家の中には、思い出の代わりに冷たい沈黙が満ちていく。
俺は再び、あの古い秤の前に立った。祖父が遺したこの秤だけが、失われつつあるものの正体を知っている気がした。秤にそっと手を触れる。家族四人がこの家に揃っている時、針は俺たちの思い出の総重量を示してきた。幼い頃の家族旅行、喧嘩して泣いた夜、誕生日を祝った食卓。その一つひとつが、物理的な重さとなってこの秤に記録されていたのだ。
そして、その針は今も、目に見えない速さでゼロへと向かっている。このままでは、俺たちは本当に互いを忘れ、世界からも忘れ去られてしまうだろう。
第三章 秤が示す場所
藁にもすがる思いで、俺は屋根裏部屋にしまい込んでいた祖父の日記を引っ張り出した。埃をかぶった革張りの表紙をめくると、独特のインクの匂いが鼻をつく。祖父もまた、俺と同じ能力を持っていたのかもしれない。日記には、俺が知覚する幾何学模様や、家族の重さに関する記述が散見された。
ページを読み進めるうち、ある一節に目が留まった。
『世界の家族は、一つの根源から分かたれた枝葉にすぎない。根が枯れれば、すべての枝葉は重さを失い、枯れ落ちる運命にある。もし根の在り処を知りたければ、秤に問え。根の重さを測る時、真の秤は北を指し示す』
俺は弾かれたようにリビングへ駆け戻り、秤を睨みつけた。目を凝らすと、確かに、重さを示す針が、まるで磁石のように、ごく微かに北の方向へと引かれているのが分かった。北。この現象の根源は、北にある。
「行くよ、お兄ちゃん」
旅の準備を始めた俺の背後から、澪の声がした。
「お前はここに…」
「嫌だ」澪は俺の言葉を遮り、強い意志を宿した瞳で俺を見つめた。「私も忘れたくないの。お兄ちゃんや、お父さん、お母さんと過ごした…その、温かかった何かを。それが何だったのか、思い出したいの」
彼女の手に触れる。色褪せた模様の中に、それでも消えずに残っている小さな光の点を見つけた。俺は黙って頷いた。二人でなら、まだ間に合うかもしれない。
第四章 最初の家族の聖域
秤が指し示す北の果て。俺と澪がたどり着いたのは、雪と氷に閉ざされた、時が止まったかのような古い聖堂だった。吹き付ける風が聖堂の壁に当たり、まるで誰かの嗚咽のような音を立てている。
重い扉を開けると、内部は驚くほど静かで、澄み切った空気に満たされていた。その中央に、巨大な天秤が鎮座していた。俺の家の秤とそっくりな意匠だが、その大きさは比較にならない。天秤は、この聖堂そのものが持つ荘厳な気配と共鳴しているようだった。
天秤の一方の皿には、内側から淡い光を放つ巨大な結晶体が乗っていた。もう一方の皿は、空っぽだ。俺たちが近づくと、家の秤がポケットの中で熱く振動し、巨大な天秤と呼応した。
何かに導かれるように、俺は光る結晶体にそっと手を伸ばした。
触れた瞬間、奔流のようなイメージと感情が、俺の意識を飲み込んだ。それは、途方もなく長い時間、この世界を見守り続けてきた存在の記憶だった。愛、喜び、悲しみ、怒り、そして赦し。この世界で最初に「家族」という概念を形成し、その絆の温かさを知った存在——「最初の家族」の記憶。
彼らは、自らの存在を世界の礎として捧げ、あらゆる家族の絆の「重さ」を、その身一つで支え続けてきたのだ。俺が今まで見てきた、人々の鮮やかな幾何学模様の源流は、すべてここにあった。
だが、永劫とも思える時間は、その偉大な存在すら摩耗させていた。彼らは世界の重さに耐えきれなくなり、自らの役目を終えることを選んだのだ。その存在を完全に世界へ解放し、静かに消滅する。それが、世界中で起きている「家族健忘」の真相だった。家族という概念そのものが、その源流と共に消え去ろうとしていた。
第五章 選択の天秤
『我らは消える。この重さが世界に還れば、人々は家族という名の鎖から解き放たれるだろう』
結晶体を通して、「最初の家族」の穏やかで、しかし諦観に満ちた意識が直接語りかけてくる。彼らにとって、それは救済のつもりなのだ。絆が生む苦しみやしがらみからの解放。
だが、俺は知っていた。その鎖こそが、人が人であるための温かい重りなのだと。俺が見てきたあの美しい幾何学模様、複雑に絡み合いながらも輝きを放つ絆の形こそが、この灰色になりかけた世界に必要なものだと。
「嫌だ」俺は声に出して言った。「その重荷が、愛おしいんだ」
俺は決断した。消滅を止めるのではない。この歪んだ天秤を、もう一度釣り合わせるのだ。
俺は覚悟を決め、空っぽの皿に手をかざした。そして、意識を集中させた。俺自身の家族の「思い出の重さ」を——失われかけ、それでもまだ確かに胸に残る、父と母、そして澪との日々の記憶を。ささやかだが、俺にとっては世界の全てであるその重みを、皿の上に乗せた。
「重さは、一つの場所が背負うものじゃない。世界中の家族で、分かち合うものなんだ!」
俺の行動に呼応するように、隣にいた澪も、祈るように皿に手をかざした。すると、奇跡が起きた。俺たちの小さな重さが呼び水となり、どこからともなく無数の光の粒が現れ、空の皿へと降り注ぎ始めた。それは、世界中の人々が、無意識のうちに捧げた自分たちの家族の思い出の重さだった。忘れかけていた温かい記憶の欠片が、世界を救うために集まってきていた。
第六章 新しい幾何学
巨大な天秤が、ギシリと音を立ててゆっくりと傾き始める。光の結晶体が乗った皿が持ち上がり、俺たちが重さを注いだ皿が沈んでいく。やがて、二つの皿は完全に水平になり、ぴたりと静止した。
その瞬間、巨大な結晶体はまばゆい光を放ったかと思うと、音もなく砕け散り、無数の小さな光の粒子となって聖堂の天窓から世界中へと飛び立っていった。世界の礎であった「最初の家族」は、その役目を終え、その重さをすべての家族へと公平に分配したのだ。
家に帰った俺は、澪の手にそっと触れた。
脳裏に浮かんだのは、かつてのような太陽のマンダラではなかった。代わりに、小さく、繊細な銀色の光を放つ、雪の結晶にも似た模様がそこにあった。それはもはや、世界で唯一の特別な輝きではない。しかし、他のどんな模様とも違う、俺たち家族だけの、新しくて確かな絆の形だった。世界の無数の家族の模様の中に、俺たちの模様もまた、ささやかに、だが誇り高く存在している。
リビングの隅にある古い秤の針は、もう二度と、あの特別な重さを示すことはないだろう。だが、その針は静かに、そして正確に、家族四人がこれから紡いでいく日々の、ささやかな思い出の重さを刻み続けている。
俺はその針の穏やかな動きを、言いようのない愛おしさを込めて、ただ静かに見つめていた。