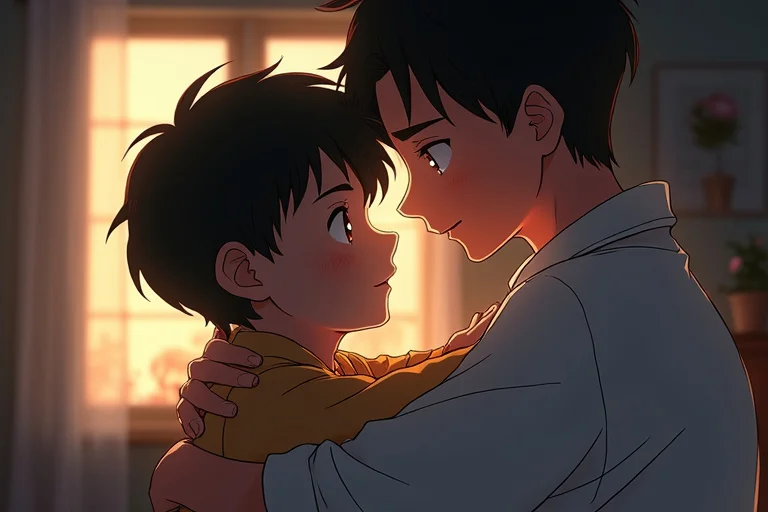第一章 同期の朝
毎晩、午前二時きっかりに、僕たちの意識は家の中心へと引き寄せられる。それは抗うことのできない潮流のようだ。頭蓋の内側に冷たい液体が流れ込み、他人の思考の断片や感情の色彩が、自分のものと混じり合っていく。父の仕事の疲労、母の些細な喜び、妹の友だちとの小さな諍い。家族四人分の記憶が、巨大なサーバーにアップロードされ、そして再分配される。これが、僕、相沢海斗(あいざわかいと)の家族が「家族」であるための、絶対的な儀式――『同期』だ。
今夜の僕は、必死に抵抗していた。脳裏に焼き付いて離れない、一つの光景。放課後の教室、西日に照らされた窓辺で、隣のクラスの佐伯さんが笑った顔。風に揺れる髪、少し潤んだ瞳、僕に向けられた、はにかむような微笑み。それは僕だけの宝物のはずだった。誰にも汚されたくない、自分だけの聖域。
「隠れろ、隠れろ、隠れろ……」
心の中で呪文のように唱える。思考のいちばん深い場所に、その記憶を沈めようと試みる。だが、無駄な努力だとわかっていた。僕たちの家の中央、リビングの吹き抜けに鎮座する『コア』と呼ばれる乳白色の水晶体は、完璧な精度で僕たちのすべてを吸い上げていく。
意識が遠のき、やがて完全な無に帰す。そして再び目覚めるのは、朝の光が瞼を射抜く頃だ。
翌朝、食卓に漂う空気は、バターが溶けるトーストの香ばしさとは裏腹に、重く、そしてひどく気まずかった。父は新聞から目を上げず、母は不自然なほど陽気にサラダを混ぜている。五歳の妹、美羽(みう)だけが、僕の顔をじっと見つめていた。
「お兄ちゃん、佐伯さんって、だあれ?」
無邪気な声が、静寂をナイフのように切り裂いた。母の混ぜる手が止まり、父がわざとらしく咳払いをする。僕の頬に、じわりと熱が集まるのがわかった。昨夜、僕が必死に守ろうとした宝物は、今や家族全員の共有物となっていた。僕の淡い恋心は、家族会議の議題にでもなるかのように、食卓の真ん中に無防備に晒されている。
「海斗。学生の本分は勉強だ」
父が、新聞の向こうから重々しく言った。その声には、昨夜の僕が感じた胸の高鳴りに対する、冷ややかな評価が滲んでいた。
「あなた、そんな言い方……。海斗ももう高校生なんだから」
母がかばうように言うが、その声色にも、佐伯さんの笑顔を見たときの微かなときめきが混じっている。気持ちが悪い。僕の感情が、他人の声を通して再生されている。
これが僕たちの家族の形。嘘も隠し事もない、すべてがガラス張りの関係。人々はそれを理想だと言うかもしれない。だが、十七歳の僕にとって、それは息の詰まる牢獄以外の何物でもなかった。自分だけの秘密を持つことが許されない世界で、僕はどうやって「自分」になればいいのだろう。トーストをかじると、バターの風味と一緒に、父の苦々しさと母の戸惑い、そして妹の純粋な好奇心の味がした。自分の舌が、もはや自分のものではないような気がした。
第二章 孤独な反響
『コア』を破壊したい、と初めて思ったのは、その日の午後だった。僕たちの記憶を管理する、あの忌まわしい水晶体。父が著名な脳科学者であり、この同期システム『メモリア・リンク』の開発者であるという事実は、僕の反抗をより一層困難にしていた。父にとって、このシステムは家族の絆の象徴であり、彼の研究者としての誇りそのものだった。
「隠し事のない家族こそが、真の信頼で結ばれた理想の形だ」
父はいつものようにそう語った。その言葉が、僕の記憶の中から反響する。父自身の声で。
僕はシステムの抜け道を探し始めた。同期が始まる午前二時に、家の外に出ていればどうなるだろう。ある夜、僕は両親が寝静まったのを見計らって、そっと家を抜け出した。冷たい夜気が肌を刺す。午前二時。僕は近所の公園のベンチに座り、固唾をのんでその瞬間を待った。しかし、時間きっかりに、意識は容赦なく家の中の『コア』へと引きずり込まれた。物理的な距離は、何の意味もなさなかった。
翌朝の食卓は、言うまでもなく最悪だった。僕のささやかな反逆の記憶は、またしても家族全員に共有されていた。父の怒り、母の悲しみ。その感情が波のように押し寄せ、僕は自分の朝食の味さえ感じられなかった。
それから僕は、もっと別の方法を模索した。同期の時間に、強い光を見たり、大音量で音楽を聴いたり、敢えて複雑な計算問題を解いたりもした。どうにかして意識の表面にノイズを作り出し、核心にある記憶を守ろうとしたのだ。だが、『コア』はそんな小手先の抵抗をあざ笑うかのように、僕の思考の深層まで正確にスキャンしていった。
孤独だった。家族の中にいながら、僕は誰よりも孤独だった。僕が抱くシステムへの不満や反発心さえ、筒抜けなのだ。僕の「個」であろうとする闘いは、常に観客の前に晒されている一人芝居のようだった。
ある日、僕は父の書斎に忍び込んだ。『メモア・リンク』に関する資料を探すためだ。分厚いファイルの中に、システムの設計図や開発日誌を見つけた。そこには、僕の知らない専門用語と数式がびっしりと書き込まれていた。そして、ファイルの最後に挟まれていた一枚の古い写真に、僕は目を奪われた。
それは、七歳くらいの僕と、今よりずっと若々しい両親が写った写真だった。僕は、病院のベッドのような場所で、頭にたくさんの電極のようなものをつけて、それでも屈託なく笑っていた。父と母は、そんな僕を心配そうに、しかし愛情深く見つめている。その写真の裏には、父の震えるような文字で、こう記されていた。
『海斗の失われた記憶を、僕たちの愛で埋める。今日、プロジェクトが始まる』
失われた記憶? プロジェクト? 僕の頭は混乱した。僕に、失われた記憶なんてあっただろうか。僕の記憶は、物心ついた頃からずっと、家族全員の記憶と混じり合っていた。それ以前の、僕だけの記憶というものの存在を、僕は考えたことすらなかった。胸の中に、これまで感じたことのない種類の、冷たい疑念が湧き上がってきた。
第三章 砕かれたプリズム
その夜、僕は決行を決意した。父の書斎で見つけた設計図のコピーを握りしめ、リビングの吹き抜けへと向かった。心臓が早鐘のように鳴っている。この動悸さえ、あと数時間後には家族に伝わってしまう。だが、もうどうでもよかった。真実が知りたい。僕の知らない「僕」の過去が、このシステムに隠されているのなら、それをこじ開けるしかない。
午前一時五十分。僕は『コア』の前に立っていた。乳白色の水晶体は、心臓のようにゆっくりと、そして規則正しく明滅している。設計図によれば、緊急停止用の物理スイッチが、台座の裏にあるはずだ。
僕が台座に手をかけた、その時だった。
「海斗、何をしている」
背後から、氷のように冷たい父の声がした。振り向くと、そこには青ざめた顔の父と、不安げな母が立っていた。妹の美羽も、母のパジャマの裾を握りしめている。僕の決意は、やはり筒抜けだったのだ。
「やめさせてくれ! もうこんな生活はうんざりだ!」
僕は叫んだ。声が震える。
「これは僕のためじゃない! 父さんの自己満足だろ!」
「違う!」父が叫び返す。「お前にはわからない! これがお前を守る、唯一の方法だったんだ!」
僕たちは揉み合った。僕を止めようとする父の腕を、僕は必死で振り払う。その拍子に、僕の肘が『コア』の表面に強く叩きつけられた。
パリン、という硬質な音と共に、水晶体に亀裂が走った。明滅が不規則になり、激しく明暗を繰り返す。そして、次の瞬間。僕たちの頭の中に、轟音と共に膨大な情報がなだれ込んできた。それはいつもの同期とは全く違う、暴力的な奔流だった。アーカイブされていた、過去の記憶の洪水。
見えた。七歳の僕が、高い熱を出して倒れる光景。病院の白い天井。医師の深刻な顔。ウイルス性脳炎、そして重い記憶障害が残る可能性。僕の脳が、過去の出来事を記憶として定着させることができなくなってしまったという事実。
絶望する両親の姿。そして、脳科学者である父が、狂気的な情熱で一つのプロジェクトに没頭していく様が見えた。それが『メモリア・リンク』だった。
「可哀想に、海斗は昨日のことも覚えていられないんだ……」
泣き崩れる母の記憶。
「大丈夫だ。僕が海斗の記憶になる。僕たちの記憶を海斗に与え続ければ、あの子は社会から孤立せずに済む。僕たちが、海斗の世界そのものになるんだ」
そう誓う、父の悲痛な決意。
このシステムは、家族の絆を深めるための理想の装置などではなかった。それは、記憶を失った僕を救うための、あまりにも歪で、あまりにも献身的な、愛の枷だったのだ。僕が求めていた「個」や「プライバシー」は、父と母が、そして僕の記憶障害を知らずに育った妹でさえも、僕のために自ら投げ捨ててくれたものだった。
彼らは僕に記憶を与えるために、自分自身の「個」を犠牲にし続けてきた。僕が感じていた息苦しさの正体は、彼らの十年にも及ぶ、計り知れないほどの愛情と自己犠牲の重さだった。
洪水のようだった記憶の逆流が止む。僕たちは、リビングで呆然と立ち尽くしていた。砕けたプリズムのように散乱した真実の光が、僕たちの心を貫いていた。僕は、ただ、嗚咽を漏らすことしかできなかった。
第四章 はじまりの食卓
亀裂の入った『コア』は、沈黙していた。あの規則的な明滅は、もうない。僕たちを縛りつけていた鎖は、暴力的な形で断ち切られた。リビングに満ちていたのは、気まずさとは違う、深い静寂だった。
最初に口を開いたのは、父だった。いつも自信に満ち溢れていたその声は、今はか細く、震えていた。
「すまなかった、海斗」
父は僕の前に歩み寄り、深く頭を下げた。「お前を愛するあまり、お前を檻に閉じ込めてしまった。父親失格だ」
その言葉に、僕は首を横に振った。僕の頬を、涙が止めどなく流れていた。
「違うよ、父さん。僕のために……僕のために、そこまで……」
言葉が続かなかった。僕が疎ましく思っていたすべてが、僕への愛だった。僕が壊そうとしていた世界は、僕を守るためだけに作られた砦だった。母も静かに泣いていた。美羽だけが、何が起こったのかわからず、僕と父の顔を交互に見上げている。
僕は、ひび割れた『コア』に視線を向けた。そして、ゆっくりと口を開いた。
「父さん、母さん。もう、大丈夫だよ」
僕の声は、まだ震えていたけれど、そこには確かな意志があった。
「たとえ、明日には今日のことを忘れてしまうとしても。僕は、僕自身の力で生きていきたい。不完全なままでいい。それが、僕だから」
父は顔を上げ、驚いたように僕を見た。その瞳に、長年の罪悪感から解放されたような、安堵の光が宿るのが見えた。
「ありがとう、海斗」
その夜、僕たちは最後の『同期』をした。それは機械的なものではない。僕たちはリビングの床に輪になって座り、互いの手を握り合った。そして、言葉で、表情で、涙で、これまでの感謝と、後悔と、そして愛を伝え合った。それは、不完全で、曖昧で、でも何よりも温かい、本当の意味での心の同期だった。
翌朝、僕は鳥の声で目を覚ました。頭の中は、驚くほど静かだった。他人の感情のざわめきはない。あるのは、昨夜の出来事の鮮明な記憶と、少しだけ重い瞼だけだ。
食卓には、焼きたてのトーストとコーヒーの香りが満ちていた。昨日までと同じ光景。でも、何かが決定的に違っていた。
「おはよう」
僕が言うと、三人が一斉に「おはよう」と返した。その声には、僕の知らないそれぞれの夢の余韻が混じっているのかもしれない。
席について、トーストを一口かじる。サクッとした食感、広がる小麦の甘みとバターの塩気。それは、ただのトーストの味だった。父の苦々しさも、母の戸惑いも混じっていない、僕だけの味覚。それが、こんなにも豊かで、美味しいものだなんて知らなかった。
「今日のコーヒーは、少し濃いな」と父が言った。
「そう? 私はちょうどいいけど」と母が笑う。
「美羽は、イチゴジャムがいい!」
当たり前の、とりとめのない会話。共有されない、それぞれの感想。その一つ一つが、僕には奇跡のように輝いて見えた。
僕たちの家族は、完璧ではなくなった。これから僕は、忘れることと闘いながら生きていくのかもしれない。それでも、僕たちは初めて、本当の意味で向き合えたのだ。すべてを共有するのではなく、互いの不完全さを受け入れ、それぞれの違いを認め、それでもなお、ここにいる。
窓から差し込む朝の光が、テーブルの上で揺れている。僕は、日記帳を買おうと思った。忘れてしまわないように。この温かい光も、コーヒーの香りも、そして、目の前にいる、僕の愛する不完全な家族の笑顔も。僕だけの言葉で、一つ一つ、大切に紡いでいくために。僕たちの本当の物語は、このはじまりの食卓から、今、始まるのだ。