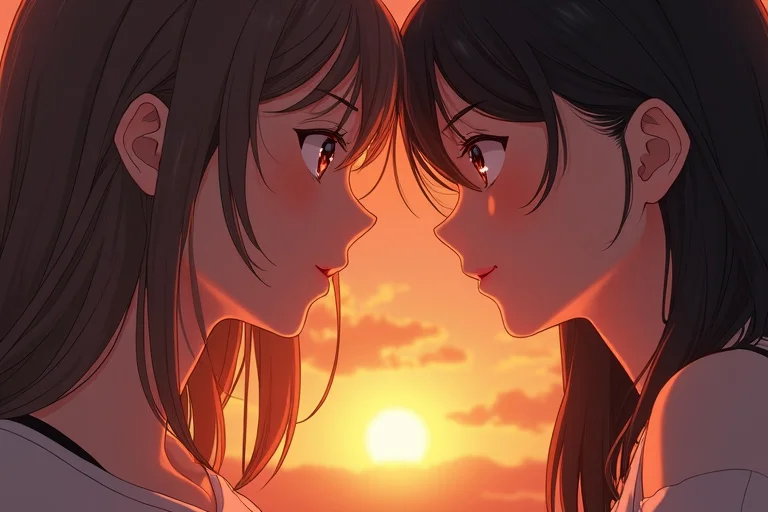第一章 閉ざされた扉と月光の誘い
ハルは、毎晩同じ夢を見る。それ自体は珍しいことではないかもしれない。だが、奇妙なのは、その夢が家族全員に「同期」しているとしか思えないことだった。夢の中で、ハルはいつも見慣れたリビングにいる。しかし、そこにはいつも見慣れない少女がいる。細い手足、風に揺れる栗色の髪、そして何よりも目を引くのが、満開の桜のようにぱっと明るい笑顔だ。その少女は、ハルを「ハル兄」と呼び、いつも楽しそうに何かを語りかけてくる。壁には、見たこともない家族写真。そこには、幼い頃の父と母、そしてハルの妹によく似た少女と、あの栗色の髪の少女が、まるで本物の家族のように肩を寄せ合って笑っていた。
「ねえ、ハル兄。この絵本、読んでくれる?」
少女が差し出す絵本には、鮮やかな花が描かれている。ハルはいつも、夢の中でその絵本を読み聞かせようとするのだが、言葉を発しようとすると、喉の奥から白い霧が吹き出し、少女の顔は遠のき、やがて視界は純白に塗りつぶされてしまう。そこで夢は途切れる。
「またあの夢か……」
目覚めたハルは、額に薄っすらと汗をかき、心臓がいつもより速く脈打っているのを感じる。時計は午前6時。窓の外はまだ薄闇に包まれている。同じ夢を見始めたのは、一ヶ月ほど前。最初は偶然だと思っていた。だが、毎晩続くその奇妙なリアリティに、ハルは内心で薄ら寒いものを感じ始めていた。
朝食の食卓はいつも通り、静寂に包まれていた。父は新聞の影に隠れ、母は黙って食パンを焼いている。妹のユウは、スマホの画面に釘付けだ。
「みんな、変な夢とか見ない?」ハルは不意に尋ねた。
父は新聞から目を離さず、「なんだ、急に。仕事の夢なら毎晩見てるぞ」とぶっきらぼうに答える。
母はハルの顔をじっと見つめ、「あら、ハル。何か悪い夢でも見たの?」と心配そうに言ったが、それ以上は何も聞かなかった。
ユウはスマホから目を離さず、「別にー。ティックトックの夢なら見るけど」と気のない返事。
ハルは肩を落とした。やはり、自分だけがこの異常な夢を見ているのだろうか。
しかし、夢は日を追うごとに鮮明さを増していった。少女の表情、声の響き、壁の家族写真の細部。現実と夢の境界が曖昧になり、ハルは次第に「あの少女は一体誰なのか」という問いに囚われていった。寝不足が続き、学校の授業中もぼんやりと過ごすことが増えた。現実の家族関係は、もはや修復不可能なほどに冷え切っているように感じられた。父とはほとんど口を利かず、母は何かを隠しているように見える。ユウとは共通の話題もなく、それぞれが自室に引きこもる時間が長かった。ハルは、この閉塞感に窒息しそうだった。
ある晩、ハルはまた夢の中で少女と出会った。彼女はいつものリビングではなく、見慣れない庭で遊んでいた。月明かりに照らされた庭には、見たことのない赤い花が咲き乱れている。少女は振り返り、ハルに笑顔を向ける。「ハル兄、この花、すごく綺麗でしょ? アヤって呼んでるんだ!」
その言葉を聞いた瞬間、ハルの脳裏に雷が落ちたような衝撃が走った。「アヤ?」彼は心の奥底で反芻した。この少女の名前は、アヤ……。
その日の夢はそこで途切れたが、ハルは確信した。この夢は、ただの夢ではない。そして、あの少女「アヤ」は、きっと家族の、忘れ去られた何かに関係しているのだと。
第二章 アルバムの中の影と心の軋み
翌朝、ハルはいつもより早く目を覚ました。アヤという名前が、まるで現実世界での鍵のように、彼の思考を支配していた。食卓の静寂は変わらない。ハルは普段行かない戸棚や、誰も開けることのない段ボール箱の中を探し始めた。何か手がかりはないか。家族が昔使っていたもの、古い写真、手紙……。
数時間後、埃をかぶった段ボールの底から、古びたアルバムを見つけた。表紙は褪せ、角は擦り切れている。きっと、もう何年も開かれていないのだろう。
ハルは自室に戻り、アルバムをゆっくりと開いた。ページをめくるごとに、彼の心臓は奇妙なリズムを刻み始めた。そこには、若い頃の両親が写っている。そして、まだ幼いユウの姿もあった。だが、何枚かの写真には、ユウの隣に、あの夢の中の少女によく似た子が、笑顔で写っていたのだ。栗色の髪、澄んだ瞳、そしてあの屈託のない笑顔。間違いなく、夢の中のアヤだ。彼女は両親に抱かれ、ユウと手をつなぎ、どこかの海辺で貝殻を拾っている。どの写真も、家族四人が心から楽しんでいる様子が伺えた。今の家族からは想像もできないほど、満ち足りた笑顔がそこにあった。
特にハルの目を引いたのは、真新しい一軒家の前で、家族全員が満面の笑みを浮かべている集合写真だった。その家は、ハルが今の家に引っ越す前に住んでいた、古い木造の家によく似ていた。写真の裏には、父の筆跡で「アヤ、五歳の誕生日。新しい家で!」と書かれている。
ハルは混乱した。自分には兄も姉もいないはずだ。アヤは一体誰なのか?なぜ、彼女の存在が家族の記憶から消え去っているように見えるのか?
その日の夕食後、ハルは意を決して、アルバムを食卓に置いた。
「ねえ、お父さん、お母さん。この子、誰?」
ハルは、アヤが写っているページを開いて見せた。
父は、テーブルに置かれたアルバムを見て、一瞬、顔色を変えた。母の手に持っていた箸が、カタリと音を立てて落ちた。ユウも、初めてスマホから目を離し、アルバムを凝視した。
「ハル……どこで、これを……」母の声は震えていた。
父は押し黙り、何か言いかけたが、すぐに口を閉ざした。まるで、その言葉を発することが、禁じられたかのように。
「この子、アヤって書いてある。僕のお姉ちゃんなの? なんで、誰も話してくれなかったの?」
ハルの問いに、両親は顔を合わせ、深い悲しみを湛えた目で互いを見つめ合った。しかし、誰も答えようとはしなかった。ただ、重苦しい沈黙が、夕食の食卓を支配した。その沈黙は、家族の間に横たわる、見えない深い溝を、より明確にした。
ハルは、この家族が抱える秘密が、単なる「忘れ去られた過去」ではなく、何かもっと深く、彼らの心を蝕むものであることを直感した。そして、この秘密が、今の家族をバラバラにしている原因なのではないか、とも。
第三章 忘れ去られた笑顔と記憶の断層
ハルは両親の沈黙を破ることができなかった。だが、アヤの存在は、彼の心の中でますます大きくなっていった。夢の中のアヤは、以前にも増してハルに何かを訴えかけてくるようになった。彼女の言葉は、まるで過去の記憶の断層から響く残響のようだった。
「ねえ、ハル兄、あのね、ユウがね、私の絵をね、破っちゃったの。でも、謝ってくれたから、もういいの」
「お母さんがね、私のためにね、お花の刺繍をしてくれたんだよ。見て、このドレス!」
断片的な記憶が、ハルの頭の中で、パズルのピースのようにゆっくりと組み合わされていく。それは、彼が生まれる前の家族の日常、アヤという少女が生きていた証だった。
数日後、ハルは学校の帰りに、写真に写っていた古い家を訪れた。もう他の家族が住んでいて、外観は少し変わっていたが、確かにあの家だ。家の前に立つと、妙な既視感に襲われた。まるで、自分がこの場所で生きていたかのように。
その夜、ハルが見た夢は、今までで一番鮮明だった。古い家の庭で、アヤが赤い花に水をやっている。
「ハル兄、見て!この花、もうすぐ咲くよ! お父さんがね、『アヤが元気でいてくれたら、この花もきっと強く咲くよ』って言ってくれたんだ」
アヤは嬉しそうにハルに話しかける。その瞬間、ハルの意識は、アヤの視点へと移った。彼女の小さな手で、ジョウロから水がこぼれる。隣には、優しい眼差しを向ける父と、微笑む母、そして無邪気に駆け回る幼いユウ。その光景は、あまりにも幸福で、そしてあまりにも儚かった。
「……ハル……」
夢の中で、遠くから母の声が聞こえた。アヤの視界は、ゆっくりと暗転していく。
「お父さん、お母さん、ユウ……みんな、ごめんね……」
その言葉が、ハルの心臓を抉った。
ハルは跳ね起きた。心臓が痛むほど鼓動している。目には、なぜか涙が溢れていた。
翌朝、ハルは決意を固め、もう一度、両親にアヤのことを尋ねた。
「アヤは、僕のお姉ちゃんなんだよね? なんで、みんな、アヤのこと、忘れようとしたの?」
ハルの強い問いかけに、ついに母が口を開いた。その声は、震えながらも、深い決意を秘めていた。
「ハル……、ごめんなさい。アヤは、あなたのお姉ちゃんだった。あなたが生まれる二年前に、病気で亡くなったの……」
母の言葉に、ハルの世界が音を立てて崩れ落ちた。
「私たちは、あまりにも悲しくて、アヤがいなくなった現実を受け入れられなかった。あまりにも辛すぎて、彼女の記憶を、心の奥底に封じ込めてしまったの。そうすれば、悲しみがなくなると思って……。あなたが生まれて、私たちは希望を見つけた。アヤの記憶をあなたに背負わせたくなくて、私たちは沈黙を選んだの……」
父は、沈黙したまま、ただ涙を流していた。ユウも、姉の存在を知り、困惑した表情で座っていた。
「転」の瞬間だった。ハルの価値観は根底から揺らいだ。自分が「アヤの代わり」として生まれたのだという事実。そして、家族が抱えていた、あまりにも深く、あまりにも重い悲しみ。それが、今の家族の間に深い溝を作っていたのだ。誰もがアヤを忘れようとし、その悲しみを独り抱え込んだ結果、家族は互いに心を閉ざしてしまった。ハルは、自分が抱いていた家族への不満や閉塞感が、この隠された悲しみからくるものだったのだと、初めて理解した。
第四章 記憶の旅路と心の解凍
真実を知ったハルは、最初は両親の行為に反発を覚えた。どうして、こんなにも大切な存在を、隠し通そうとしたのか。しかし、同時に、彼は両親の深い悲しみと、アヤを忘れようとした苦悩を、痛いほど理解した。もし自分が同じ立場だったら、耐えられただろうか。彼の心の中で、アヤの面影が、もはや単なる過去の残像ではなく、家族を再び繋ぐための「橋」として、光り輝き始めた。
ハルは、夢の中のアヤが教えてくれた、あの赤い花のことを思い出した。「アヤって呼んでるんだ!」その言葉に、ハルは光明を見出した。アヤが好きだった花。それは、彼女の存在を象徴するものだ。ハルは両親とユウに、「アヤが好きだった花を、みんなで探しに行こう」と提案した。それは、アルバムにあった、アヤが海辺で遊んでいた写真の場所だった。
最初は戸惑っていた両親とユウも、ハルの真剣な眼差しに、やがて頷いた。
家族は、アヤが写っていたアルバムの海辺へと向かった。潮風が肌を撫で、波の音が心を洗う。そこは、穏やかで美しい場所だった。ハルは、波打ち際で貝殻を拾うユウの姿を見て、夢の中のアヤと重なった。
その夜、彼らは海辺の宿に泊まった。そして、奇跡が起こった。家族全員が、同じ夢を見たのだ。
夢の中には、満開の赤い花が咲き乱れる庭があった。月明かりの下、アヤが、優しい笑顔で立っていた。
「お父さん、お母さん、ユウ……そして、ハル兄。みんな、ありがとう」
アヤの声は、そよ風のように優しく、しかし確かな響きを持っていた。
「私を、忘れないでくれて、ありがとう。でも、悲しまないで。未来を歩んで。そして、互いを愛して。それが、私が一番、願っていたことだから」
アヤは、一人ひとりの顔をゆっくりと見つめた。両親は、夢の中で涙を流し、アヤを抱きしめた。ユウは、初めて出会った姉の存在に、戸惑いながらも、その温かさに触れようと手を伸ばした。
そしてアヤは、ハルの目を真っ直ぐ見つめた。
「ハル兄、あなたが来てくれて、本当に嬉しかった。あなたがいるから、みんな、また笑えるようになったんだよ」
アヤの言葉は、ハルの心を温かく包み込んだ。彼は、自分が「アヤの代わり」ではなく、アヤが残していった家族の愛と希望を受け継ぎ、未来へと繋ぐ存在なのだと、悟った。
夢の中で、赤い花が風に揺れ、散り始めた。アヤは、その花びらとともに、ゆっくりと透明になっていく。
「さようなら。でも、ずっと一緒だよ」
彼女の最後の言葉は、ハルの心に深く刻み込まれた。
第五章 回廊の彼方、咲き誇る希望
目覚めると、部屋には朝日が差し込んでいた。家族全員の顔には、微かな涙の跡があったが、同時に、清々しいほどの安堵と、かすかな笑顔が浮かんでいた。彼らは、夢の中でアヤに再会し、そして、彼女の別れを受け入れたのだ。長年閉ざされていた心の扉が、ゆっくりと、しかし確実に開かれた瞬間だった。
ハルは、もはや現実主義者ではなかった。見えない絆、心の繋がり、そして記憶の持つ力を、彼はこの経験を通じて深く理解した。バラバラだった家族は、アヤという、かつて存在したかけがえのない生命の記憶を共有することで、再び一つになった。アヤは、彼らの心の中で、永遠に生き続ける。その存在は、もはや悲しみの源ではなく、家族の愛と絆の象徴となった。
家に帰ったハルは、家族全員で庭に赤い花を植えることを提案した。それは、夢の中でアヤが「アヤって呼んでる」と言った花に似た、小さな、しかし力強い花だった。土を耕し、種を蒔き、水をやる。その共同作業の中で、家族の間に、以前のような温かい会話と笑顔が戻っていった。父は仕事の話をするようになり、母は明るい歌を口ずさむようになった。ユウはスマホから目を離し、ハルと、植えた花のことについて話すようになった。
食卓には、賑やかな会話が戻った。アヤの思い出を語り合うこともあった。しかし、そこにはもう悲しみはなかった。アヤの記憶は、家族を繋ぐ美しい回廊となり、その回廊には、新たな希望の花が咲き誇っていた。ハルは、その花を見るたびに、アヤの存在と、家族の深い愛を思い出す。彼は、家族の過去、現在、そして未来を繋ぐ、大切な存在へと成長したのだ。
家族の生活は、以前とは全く違うものになった。アヤはもう夢に現れない。しかし、彼女のメッセージは、彼らの心に深く根を下ろし、揺るぎない絆を育んでいった。赤い花は、庭で風に揺れ、太陽の光を浴びて、力強く咲き続けている。それは、失われた命への追悼であり、同時に、再生と希望の証だった。家族は、記憶と共に、未来へと歩んでいく。その歩みは、決して一人ではない。過去の悲しみを乗り越え、互いを支え合う、温かい家族の絆に満ちていた。