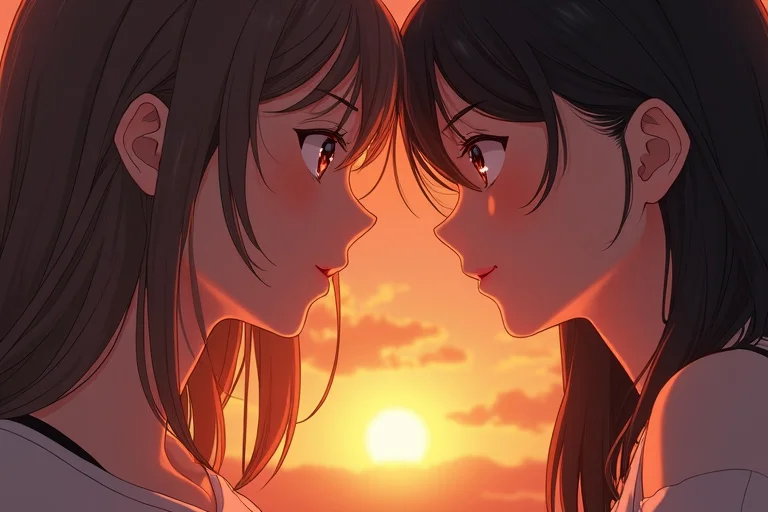第一章 褪せた写真と父の鍵
父、雄一郎が死んで、一年が経った。一周忌のために帰省した実家は、主を失ったことで目に見えて活気をなくしていた。埃の匂いが混じる線香の香りが、記憶の隅々にまで染み込んでくるようだ。母の聡子は、めっきり口数が減り、その背中は一周りも二周りも小さく見えた。
「健太、お父さんの書斎、そろそろ片付けないとね」
母の力ない声に促され、俺は重い腰を上げた。生前の父が唯一、誰にも踏み込ませなかった城。町工場を経営していた父は、仕事人間だった。無口で、頑固で、俺が物心ついた頃から、父とまともに会話をした記憶はほとんどない。その背中はいつも、俺たち家族ではなく、仕事の書類や図面に向いていた。俺が東京の大学へ進み、デザイナーとして自立したのも、そんな父への反発心があったからかもしれない。
書斎は、父の不在を最も色濃く感じさせる場所だった。使い込まれた万年筆、インクの染みついたデスクマット、びっしりと専門書が並ぶ本棚。すべてが、時が止まったかのようにそこにあった。俺はため息をつきながら、一番大きなデスクの引き出しを一つずつ開けていく。整理された請求書の束、古い通帳、そして、一番下の引き出しの奥に、それはあった。
カタン、と乾いた音がした。他の書類とは明らかに異質な、小さな桐の箱。そっと開けると、中には一本の古びた真鍮の鍵と、セピア色に変色した一枚の写真が入っていた。
写真には、見覚えのない風景が広がっていた。白い灯台を背景に、三人の男女が笑っている。一人は、間違いなく若い頃の父だ。俺の知らない、柔らかな表情をしている。そしてその隣には、俺の母ではない、見知らぬ美しい女性が寄り添っていた。彼女の腕には、幼い女の子が抱かれている。三人は、まるで本当の家族のように、幸せそうに微笑んでいた。
心臓が嫌な音を立てて脈打つ。これは、誰だ?
「母さん、これ…」
リビングに戻り、母に写真を見せた。母は一瞬、息を呑んだように見えたが、すぐにゆっくりと首を横に振った。
「さあ…知らないわ。お父さんの、古い友人かしらね」
その声は、あまりに平坦で、かえって何かを隠しているように聞こえた。父は、俺たちを裏切っていたのか? あの無口な背中の向こうには、別の家族との温かい時間があったというのか? 長年心の底に燻っていた父への不信感が、黒い煙となって再び立ち上り始めた。この鍵と写真が、父という人間の、俺の知らない扉を開けてしまうのではないかという予感が、胸をざわつかせた。
第二章 灯台の町と開かれた私書箱
父の裏切りを暴いてやりたいという衝動と、真実を知ることへの恐怖。二つの感情が、俺の中で渦を巻いていた。結局、好奇心と長年のわだかまりが勝った。俺は母に「少し古い友人に会ってくる」と嘘をつき、写真に写っていた灯台のある町へと車を走らせた。
インターネットで調べたその町は、実家から車で二時間ほどの、寂れた港町だった。潮の香りが、ひなびた商店街を吹き抜けていく。写真と同じ、白亜の灯台が、灰色の空に向かってすっくと立っていた。あの写真が撮られたのは、この場所に違いない。
問題は、あの古びた鍵だ。一体、何を開けるためのものなのか。俺は町の不動産屋や古い商店を訪ね歩いたが、誰も心当たりはないと言う。途方に暮れて、町の中心にある郵便局に立ち寄った時だった。壁際に並ぶ、年季の入った私書箱。そのうちの一つに、俺が持っている鍵とよく似た形の鍵穴があるのを見つけた。
まさか。震える手で鍵を差し込むと、吸い込まれるように収まり、カチリと軽い音を立てて回った。小さな金属の扉を開けると、そこには、厚い手紙の束が窮屈そうに詰め込まれていた。束ねられた手紙の一番上、差出人の欄には、インクが滲んだ美しい文字でこう書かれていた。
『佐伯美月』
写真の女性の名前だろうか。そして宛名は、父の名前――『倉田雄一郎様』。
俺はゴクリと唾を飲み込み、一番古い日付の手紙を手に取った。港が見える公園のベンチに腰掛け、封を切る。そこから溢れ出てきたのは、俺の想像を遥かに超える、父の人生の断片だった。
手紙は、父と美月という女性が、かつて深く愛し合った恋人同士であったことを物語っていた。しかし、家柄の違いや親の反対によって、二人は結ばれることなく別れた。父はその後、母と結婚し、俺が生まれた。美月も別の男性と家庭を持った。
手紙を読み進めるうちに、俺の心は怒りで満たされていった。やはり父は、結婚後もこの女性と関係を続けていたのだ。そして、決定的な一文が目に飛び込んできた。
『あなたと別れてから生まれたあの子、海(うみ)は、もう五歳になります。あなたにそっくりな、頑固なところもあるけれど、とても優しい子です』
写真に写っていた女の子。海。俺の、腹違いの妹。
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。父は、母と俺という家族がありながら、別の場所にもう一つの家族を持っていた。あの無愛想な顔の裏で、二重生活を送っていたのか。俺が感じていた疎外感は、気のせいではなかったのだ。父の心は、ここにはなかった。怒りと悲しみで、手紙を持つ手が震えた。許せない。絶対に、許せるはずがなかった。
第三章 沈黙の理由
怒りに任せて、手紙の束を破り捨ててしまおうかと思った。だが、何かが俺を押し留めた。これは、父が死ぬまで隠し通した秘密だ。その全てを見届けなければならない気がした。俺は、震える指で次の手紙の封を切った。
しかし、そこに綴られていた内容は、俺の浅はかな推測を根底から覆すものだった。
美月は、娘の海が幼い頃に夫を病で亡くしていた。そして数年後、彼女自身も、治る見込みのない重い病に侵されていることがわかった。手紙は、彼女の悲痛な叫びだった。
『雄一郎さん、お願いです。もし私に万が一のことがあったら、あの子を一人にしないで。施設になんて入れたくない。血の繋がったあなたに、あの子の未来を託すことしかできないのです』
手紙の束の中には、父からの返信の下書きと思われる便箋も数枚、挟まっていた。そこには、万年筆で書かれた、父の苦悩が滲んでいた。
『美月、無茶を言うな。私には妻も、息子もいる。君の願いを叶えることは、二人を裏切ることになる。私にはできない』
そうだ、それでいい。俺は心の中で毒づいた。だが、その数年後の日付の手紙には、父の決意が記されていた。それは、美月の病状が悪化し、いよいよ最期の時が近いことを知らせる手紙への返信だった。
『わかった。君との約束を、今度こそ守ろう。もしもの時は、私が必ず海ちゃんを引き取り、育てる。そのために、私は働かなければならない。どんなに格好悪くとも、家族に嫌われようとも、金がいる。君の娘と、私の家族、二つを守るために、私は馬車馬のように働く。だから、安心してくれ』
全身から血の気が引いていくのがわかった。
俺が「仕事ばかりで家庭を顧みない」と反発していた父の姿。それは、いつか来るかもしれない「もしもの時」に備え、血の繋がった娘を引き取るための、そして俺たち家族の生活水準を落とさないための、苦渋の決断だったのだ。父は、誰にも言えない秘密と責任をたった一人で背負い込み、二つの「家族」を守るために、その無口な背中を酷使し続けていた。俺の知らないところで、父はたった一人、とてつもない重圧と戦っていたのだ。
父が俺の進学を黙って許してくれたこと。母が新しいパートを始めたいと言った時、何も言わずに頷いたこと。その全てが、この秘密に繋がっていた。俺は、父の何を見てきたのだろう。あの大きな背中が、どれほど多くのものを背負っていたのか、想像すらしていなかった。
「親父…」
声にならない声が漏れた。怒りは消え、代わりに、どうしようもない罪悪感と、父への尊敬の念が、涙となって溢れ出してきた。港に停泊する船の汽笛が、まるで父の慟哭のように、長く、物悲しく響いていた。
第四章 見えない糸
俺は、手紙の束を抱きしめるようにして、実家に戻った。そして、リビングで呆然とテレビを見ていた母に、全てを話した。父と美月さんのこと、海ちゃんのこと、そして、父が一人で背負っていた覚悟のこと。
俺が話し終えると、母はしばらく黙っていたが、やがて静かに涙を流し始めた。そして、俺の予想もしなかった言葉を口にした。
「…知っていたわ」
「え…?」
「全部じゃないけれどね。あのお父さんが、あんなに必死に働くのには、何か大きな理由があるんだろうって。女の勘、かしらね。でも、聞けなかった。聞いたら、あの人の覚悟が揺らいでしまう気がして。だから、信じて待つことにしたの。あなたのお父さんは、決して私たちを裏切るような人じゃないって」
母は、父を信じていた。父の沈黙の意味を、その奥にある誠実さを、誰よりも理解していたのだ。俺は、自分の浅はかさが恥ずかしくて、顔を上げられなかった。俺たち夫婦は、二人で一つの家族だったのだ。
手紙の束を改めて見ると、一番上に、ごく最近の日付の封筒があった。それは、成長した海さんからの手紙だった。彼女は結局、美月さんの死後、遠い親戚に引き取られたらしかった。しかし、父は匿名で、ずっと彼女の成長を見守り、学費などの援助を続けていたのだという。
手紙には、こう綴られていた。
『顔も知らない倉田様。あなた様のおかげで、私は大学まで卒業し、素敵な人と出会い、結婚することができました。今、私のお腹には新しい命が宿っています。いつかお会いして、直接お礼を申し上げたいです。本当に、ありがとうございました』
同封されていた写真には、幸せそうに微笑む海さんと、その隣で優しく彼女を支える旦那さんの姿が写っていた。
俺は書斎に戻り、窓から夕焼けに染まる町を眺めた。父が守りたかったもの。それは、血の繋がりや形だけではない、「家族」という温かい繋がりそのものだったのだろう。
俺は、海さんに会いに行こうとは思わない。彼女には彼女の幸せな家庭がある。父が遠くから静かに見守ったように、俺もそうするべきだ。それが、父の遺志を継ぐことになる。
不器用で、無口で、でも誰よりも深く、人を愛した男。俺の父。
書斎の机に置かれた父の遺影が、夕日を浴びて、ほんの少しだけ、誇らしげに笑ったように見えた。
家族とは、なんだろう。一緒に食卓を囲むことか。血が繋がっていることか。違う。きっと、見えない場所で互いを想い、信じ、支え合う心の中にこそ、その本当の姿は宿るのだ。
俺は、父が残した真鍮の鍵を、そっと握りしめた。これはもう、秘密の扉を開けるための鍵ではない。父の大きな愛と、家族を繋ぐ、見えない糸の象徴なのだ。いつか俺も、誰かのために、こんなにも強く、優しい人間になれるだろうか。夕凪の静けさの中、俺は初めて、心から父の息子であることを誇りに思った。