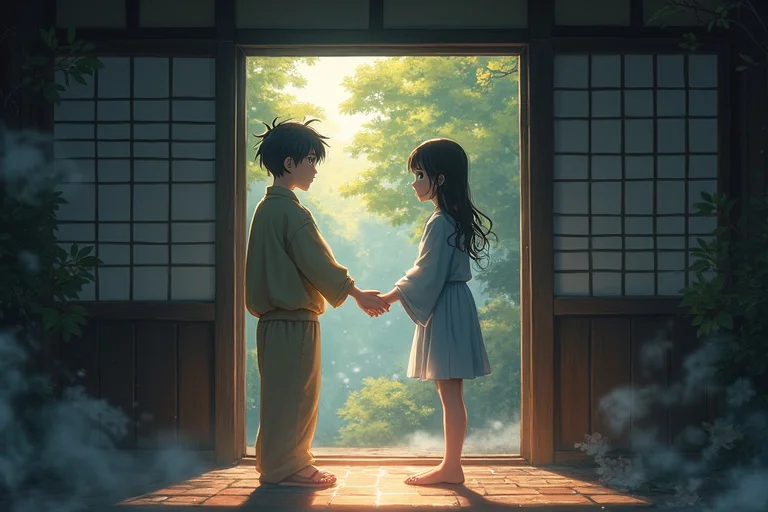第一章 漂流する哀しみ
朝の食卓に満ちていたのは、トーストの香ばしい匂いと、妹の他愛ないおしゃべり、そして父がめくる新聞の乾いた音だった。僕、相葉涼介にとって、それは見慣れた、少しだけ退屈な日常の風景のはずだった。だがその日、僕の心を満たしたのは、まったく別のものだった。
どくり、と心臓が大きく跳ねたかと思うと、唐突に、理由のわからない巨大な哀しみの塊が胸の奥からせり上がってきた。それはまるで、冷たい霧が肺腑に流れ込んでくるような感覚。目の前にいる家族の姿が、急速に色褪せて遠ざかっていく。
「……兄ちゃん? どうしたの、パン焦げちゃうよ」
訝しげに僕を覗き込む妹の遥の声が、水の中から聞こえるようにくぐもっている。僕は必死に首を横に振った。大丈夫だ、と伝えたいのに、喉が締め付けられて声が出ない。次の瞬間、熱い雫が眦からこぼれ落ち、テーブルに染みを作った。自分の涙なのに、まるで他人のもののように感じられた。
「涼介? おい、大丈夫か」
父の低い声。母の心配そうな眼差し。僕は慌てて手の甲で涙を拭い、「なんでもない。ちょっと、目にゴミが」と、我ながら稚拙な嘘をついた。
これが初めてではなかった。この築八十年を超える古い家に住み始めてから、時折、こんな風に正体不明の感情に襲われるようになった。ある時は、真夜中にふと目覚めると、誰かの焦燥感に駆られて部屋を歩き回り、またある時は、庭の金木犀を眺めているだけで、胸が張り裂けそうなほどの幸福感に満たされる。それは決して僕自身の感情ではない。まるで、この家の壁や柱に染み込んだ、過去の住人の「感情の残響」を、僕だけが受信してしまっているかのようだった。
家族に相談しても、「考えすぎだ」「思春期みたいなことを言うな」と一蹴されるだけ。僕のこの奇妙な感受性は、誰にも理解されなかった。
この家に漂う数多の感情の中でも、最も強く、頻繁に僕を捉えるのが、あの「哀しみ」だった。それは単なる悲嘆ではない。後悔と、取り返しのつかない喪失感、そして誰にも届かない叫びのような無力感が入り混じった、深く、暗い哀しみ。
僕は、その感情の主を特定していた。この家を建てた曽祖父、相葉宗一郎。彼は家族の話によれば、若くして病で亡くなったという。きっと、彼は多くの未練をこの家に残していったに違いない。その無念の情が、八十年という時を超えて亡霊のように家を彷徨い、僕に取り憑いているのだ。
「また、曽祖父さんか……」
僕はトーストをかじりながら、窓の外に広がる、手入れの行き届いていない庭を睨んだ。この家は、呪われている。そして僕は、その呪いの唯一の受信者なのだ。そう思うと、家族との食卓さえも、息苦しい牢獄のように感じられた。
第二章 屋根裏の航海者
曽祖父の呪縛から逃れたい一心で、僕は家の過去を探ることにした。いわば、幽霊退治のための情報収集だ。彼の無念を突き止め、何らかの方法で供養すれば、この奇妙な現象も終わるかもしれない。そう信じるしかなかった。
目的地は、屋根裏部屋。そこは、家の歴史が埃と共に堆積した、忘れられた聖域だった。ぎしり、と軋む梯子を登ると、黴と古い木の匂いが鼻をつく。斜めになった天井から差し込む一筋の光が、空気中を舞う無数の塵をきらきらと照らし出していた。
「うわ、すごいな……」
そこは、まさしく時の墓場だった。古い家具、用途のわからない農具、黄ばんだ着物が詰められた桐箪笥。僕はその中から、曽祖父の遺品と思われるものを探し始めた。妹の遥が「宝探しみたい!」と目を輝かせてついてきたが、すぐに埃に音を上げて階下へ戻っていった。
いくつかの木箱を開け、ようやく目的のものを見つけ出した。それは、分厚い革の表紙がついた、一冊の古い日記だった。表紙には、達筆な文字で『相葉宗一郎』と記されている。これだ。僕は高鳴る胸を抑えながら、その場で日記を読み始めた。
日記は、曽祖父がこの家を建てた頃から始まっていた。そこには、新しい家族の拠点を得た喜び、妻への深い愛情、そして生まれてくる子供への期待が、瑞々しい筆致で綴られていた。僕は彼の文章から、実直で、愛情深い人物像を思い浮かべた。
ページをめくるにつれて、僕は違和感を覚え始めた。家族から聞いていた「若くして病で亡くなった不幸な人」というイメージとは、あまりにもかけ離れていたからだ。彼の日記には、日々の些細な出来事が、慈しむような言葉で記されていた。娘(僕の祖母)が初めて歩いた日の感動。庭に植えた桜の木が花を咲かせた喜び。家族で囲む食卓の温かさ。どこをどう読んでも、不幸の影は見当たらない。
「おかしい……」
僕は呟いた。僕が感じている、あの深く暗い哀しみは、どこから来るというのだ? この日記の主が、あんな絶望を抱えていたとは到底思えなかった。
さらに読み進めると、彼の病状が悪化していく時期の記述にたどり着いた。だが、そこにあったのも、絶望ではなかった。
『我が命、長くはないと医者に告げられた。だが、悲しくはない。この腕で愛する妻を抱き、娘の成長を見守ることができた。この家で、数えきれぬほどの幸福な時間を過ごした。私がこの世を去った後も、この柱や壁が、我らの笑い声を記憶し、家族を守ってくれるだろう。思い残すことは、何もない』
そこにあったのは、死を目前にした人間の、穏やかで、満ち足りた感謝の言葉だった。僕の仮説は、根底から崩れ去った。僕を苛むあの哀しみは、曽祖父のものではなかった。では、一体誰の? 何の感情なのだ? 謎は解けるどころか、さらに深く、暗くなった。僕は埃っぽい屋根裏部屋で、途方に暮れるしかなかった。
第三章 未来からの谺(こだま)
曽祖父の日記を最後まで読み終えた時、僕はその最終ページに、追記のような形で書かれた短い一文を見つけた。それは、彼の死の数日前に記されたものだった。
『不思議なことがある。時折、この家は未来の声を運んでくるようだ。まだ生まれぬ者の喜びや、いつか訪れるであろう哀しみの欠片が、風のように心を通り過ぎていく。それはきっと、この家が家族と共に生き、呼吸している証なのだろう』
未来の声を運んでくる? どういう意味だ? 僕はその一文を何度も読み返した。非科学的で、詩的な比喩。そう片付けてしまうこともできた。だが、僕の身に起きている不可解な現象と、奇妙に符合する。
その時だった。
「きゃっ!」
階下の庭から、妹の遥の短い悲鳴が聞こえた。僕は弾かれたように窓に駆け寄った。庭では、遥が古井戸のそばにある大きな庭石によじ登ろうとして、足を滑らせていた。彼女の小さな体が、ぐらりと大きく傾ぐ。その下には、角の尖った石がいくつも転がっていた。
ぞわり、と全身の肌が粟立った。
まさか。
時間が、引き伸ばされたようにゆっくりと流れる。遥が落ちていくスローモーションの映像と、僕の脳裏に稲妻のように閃いた光景が、完璧に重なった。
――ああ、これだ。
僕がずっと感じてきた、あの感情。後悔と、取り返しのつかない喪失感。誰にも届かない叫び。それは、今まさに、この瞬間に起こるはずだった悲劇を目の当たりにした家族の――おそらくは僕自身の――「未来の感情」だったのだ。曽祖父が書き残した「未来の哀しみの欠片」とは、これのことだった。それは呪いなどではなく、未来からの警告。悲劇を回避するための、必死の谺(こだま)だった。
「遥!!」
僕は叫びながら、屋根裏部屋を飛び出した。梯子を転げ落ちるように駆け下り、廊下を疾走し、庭へ続くガラス戸に体当たりするようにして外へ出る。
間に合え!
遥の体が、ついにバランスを失って庭石から落下する。僕は地面を蹴り、倒れ込む彼女の体と地面の間に、滑り込むように身を投げ出した。ごん、と鈍い衝撃。僕の背中に、石の角が食い込む激痛が走った。だが、腕の中には、驚きと恐怖で目を見開いた遥の、温かく、柔らかな感触があった。
「……兄ちゃん?」
「……大丈夫か」
息を切らしながら尋ねる僕に、遥はこくこくと頷いた。怪我はないようだ。僕の背中は酷く痛んだが、そんなことはどうでもよかった。腕の中にある温かい命の重みが、何よりも雄弁に、僕が守りたかったものを教えてくれていた。
僕は遥を抱きしめたまま、空を仰いだ。古い家の屋根が、僕たちを見下ろしている。この家は、過去の記憶だけでなく、未来の感情さえも抱きしめて、僕たちに語りかけていたのだ。それは呪いではない。時を超えた、家族の愛そのものだった。僕が感じていた哀しみは、この出来事が起こった「もしも」の世界線からの、僕自身の絶望だったのだ。
第四章 愛しき時間の織物
あの日以来、僕の世界は一変した。いや、世界が変わったのではない。僕が世界を見る目が、そして家族を見る目が、根本から変わったのだ。
家に漂う「感情の残響」が消えることはなかった。だが、僕はもうそれを恐れたり、疎んだりすることはなくなった。それは、過去と未来の家族から僕へと送られる、声なき手紙のようなものだと理解したからだ。
ある晴れた午後、リビングでうたた寝をしていると、ふと、穏やかで温かい安らぎの感情が心を包んだ。僕は目を開ける。ソファの向かいでは、父が静かに本を読み、その隣で母が楽しそうに編み物をしている。その光景を見ているだけで、胸に満ちた安らぎが、きっと未来の僕がこの瞬間を思い出して感じるであろう、懐かしい幸福感なのだとわかった。
僕はシニカルな仮面を脱ぎ捨てた。父の仕事の話に真剣に耳を傾け、母の作る夕食を「美味しい」と素直に口にするようになった。遥とは、くだらないことで笑い合う時間が増えた。僕の変化に、家族は少し驚きながらも、明らかに喜んでいた。食卓の空気は、以前とは比べ物にならないほど、明るく、温かいものに変わっていった。
家の軋む音、壁の染み、少し傾いた柱。そのすべてが、僕には愛おしく思えた。この家は、僕たち家族の喜びも悲しみも、すべて記憶し、未来へと繋いでいく巨大な生命体なのだ。曽祖父が日記に記したように、この家は家族と共に呼吸している。
ある日の夕食後、僕は家族に、僕が体験してきたこと、そしてあの日、遥を助けることができた理由を、拙い言葉で打ち明けた。彼らは驚き、すぐには信じられないという顔をしていた。だが、僕の真剣な眼差しと、何よりも僕自身の変化が、その言葉に説得力を持たせていた。
父はしばらく黙り込んだ後、ふっと息を吐いて言った。
「そうか……。親父(僕の祖父)も、時々、妙なことを言っていたな。『この家は、俺たちが忘れたことを覚えていてくれる』って。そういうことだったのかもしれんな」
その夜、僕は自分の部屋で、窓の外に広がる星空を眺めていた。ふと、また新たな感情の波が寄せてくるのを感じた。それは、これまで感じたことのない、深く、静かで、満ち足りた「喜び」の感情だった。
これが誰の、いつの喜びなのかはわからない。僕自身の未来の喜びか、あるいは、まだ見ぬ僕の子供や孫の喜びなのかもしれない。
確かなことは、この家で、僕たち家族はこれからも時間を紡いでいくということだ。喜びも、そしておそらくは避けられない哀しみも、すべてを分かち合いながら。未来の哀しみの予兆を感じたなら、今度もきっと、全力でそれを回避するために走るだろう。未来の喜びの予感を感じたなら、その日が来るのを、今の幸せを噛み締めながら待つだろう。
僕は、夜空に浮かぶ月に向かって、静かに微笑んだ。感情の家系図は、僕という一点で過去と未来が交差し、これからも豊かに、複雑に、そしてどこまでも愛おしく織りなされていくのだ。