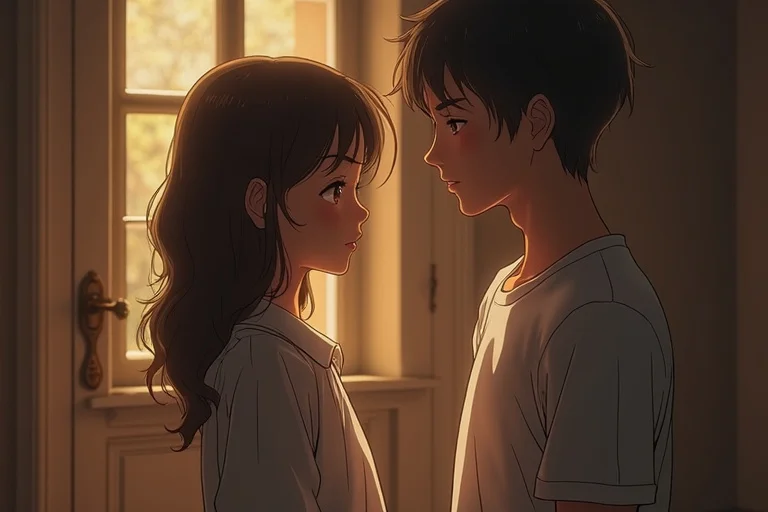第一章 涙を流す壁
コンクリートの匂いと排気ガスの粒子に慣れきった肺に、雨上がりの土と草いきれの混じった空気が満ちていく。水野咲は、三年ぶりに実家の門をくぐり、深く息を吸い込んだ。祖母の三回忌。それだけの理由がなければ、この家に戻ることはなかったかもしれない。
東京でのデザイナーの仕事は、咲の心を少しずつ、しかし確実に摩耗させていた。締め切りに追われ、無機質な人間関係に疲れ果て、アパートの部屋に帰れば、ただ沈黙が待っている。そんな日々のなかで、「家族」という言葉は、温かい記憶であると同時に、どこか遠い国の響きを伴うようになっていた。
「おかえり、咲」
玄関で出迎えてくれた父、健一は、最後に会った時よりも少し背が縮んだように見えた。母の陽子が亡くなって五年。父の口数はさらに減り、その肩には、咲には見えない重しがのしかかっているようだった。
「ただいま、お父さん」
ぎこちない挨拶を交わし、仏壇に手を合わせる。祖母の穏やかな遺影の隣で、母が優しく微笑んでいた。胸の奥が、ちくりと痛む。
家の中は、時が止まったかのようだった。磨き込まれた廊下、少し傾いた柱時計、居間のソファに掛けられた手編みのカバー。すべてが咲の記憶の中にある姿のままだ。だが、なぜだろう。家全体が、まるで微かに熱を帯びているような、妙な圧迫感があった。古い木造家屋特有のきしみや匂いとは違う、もっと生命的な気配。咲は自分の疲労のせいだろうと、その違和感を頭の隅に追いやった。
その夜、事件は起きた。
法事を終え、親戚たちが帰った後の静寂。咲は自室のベッドで寝付けずにいた。階下で柱時計が午前二時を打つ音を聞きながら、喉の渇きを覚えて身体を起こした。
そっと階段を降り、居間のドアを開ける。ひんやりとした夜気が肌を撫でた。月明かりが障子を通して、部屋をぼんやりと青白く照らしている。冷蔵庫へ向かおうとした咲の足が、ふと、止まった。
居間の壁。母がいつも座っていた安楽椅子の、ちょうど後ろのあたり。その壁紙に、いくつもの濡れた筋が、まるで涙の跡のように浮かび上がっていたのだ。
「水漏れ…?」
咲は壁に近づき、指先でそっと触れてみた。ひんやりと湿っている。しかし、天井にシミはないし、雨漏りの気配もない。壁の内側から、水が滲み出しているかのようだ。何より奇妙なのは、その濡れた筋が、ゆっくりと形を変え、あるものは消え、またあるものは新しく現れていることだった。まるで、目に見えない巨大な誰かが、壁の向こうで静かに嗚咽しているかのように。
それは、五年前、母の死を知らされた父が、この部屋で一人、声を殺して泣いていた姿と重なった。あの時、父はまさにあの安楽椅子に座り、壁に背を預けていた。
ぞくり、と背筋に悪寒が走る。咲は、自分が決して見てはならないものを見てしまったような感覚に襲われ、息を詰めて後ずさった。壁の涙は、月明かりの中で静かに流れ続けていた。それは、この家が発する、声なき慟哭のように思えてならなかった。
第二章 家の記憶、母の言葉
翌朝、咲は何事もなかったかのように振る舞った。昨夜の出来事は、きっと疲労が見せた幻覚だ。そう自分に言い聞かせ、父との無言の朝食を済ませた。しかし、一度芽生えた疑念は、家の些細な変化に咲の意識を向けさせた。
父と進路のことで激しく口論した高校時代を思い出し、胸が苦しくなった瞬間、足元の床板が「ミシリ」と不機嫌そうな音を立てて軋んだ。逆に、幼い頃、母に褒められたくて庭の草むしりを手伝った楽しい記憶を辿れば、陽の当たらないはずの廊下が、ふわりと一瞬だけ明るくなった気がした。
気のせいだ、と打ち消すたびに、家は新たなサインを送ってくる。父がため息をつくと部屋の空気が重くなり、咲が鼻歌を歌うと窓辺の観葉植物の葉がかすかに揺れる。まるで、この家が家族の一人ひとりの感情に共鳴し、呼応しているかのようだ。
「お父さん、この家、なんだかおかしくない?」
昼下がり、縁側で黙って庭を眺めている父に、咲は思い切って切り出した。
「壁が濡れていたり、床が急に鳴ったり…。なんだか、生きているみたいで」
父はゆっくりと咲に視線を向けたが、その目には何の感情も浮かんでいなかった。
「古い家だからな。あちこちガタがきてるんだ。お前も疲れてるんだろう。少し休め」
その声は、咲の問いを拒絶する壁のように、硬く、冷たかった。
これ以上話しても無駄だと悟った咲は、一人、屋根裏部屋へと向かった。そこは、家族の歴史が埃をかぶって眠る場所だ。開かずの箪笥や古いアルバム。その中に、母が遺した日記帳を数冊見つけた。
ページをめくると、懐かしい母の丸い文字が目に飛び込んでくる。日々の出来事、家族への想い、そして、この家に対する愛情。咲は、その中に奇妙な記述がいくつもあることに気づいた。
『今日は健一さんと喧嘩をしてしまった。家も怒っているのか、キッチンの水道の蛇口がずっとポタポタと涙をこぼしている。ごめんね、私たちの家』
『咲がコンクールで賞をもらった。家中が喜んでいるみたいに、日差しが隅々まで温かい。あなたも一緒に喜んでくれているのね。いつもありがとう』
母は、この家を単なる建物としてではなく、感情を分かち合う家族の一員として捉えていたのだ。日記の最後の方のページは、病状の悪化を記す苦しい言葉で埋め尽くされていた。そして、最後の一文はこう締めくくられていた。
『私が逝っても、この家がみんなを見守ってくれる。私の想いは、この柱に、壁に、屋根に遺していくから。だから、お願い。泣かないで』
咲は日記を閉じた。指先が震えている。昨夜の壁の涙は、幻覚ではなかった。あれは、母の死後、この家に遺された悲しみの記憶そのものだったのだ。父の悲しみ、そして家を出て行ってしまった自分への寂しさ。家は、家族の心を映す鏡となって、五年もの間、静かに涙を流し続けていた。
咲は、自分がこの家から、そして家族から、いかに目を背けて生きてきたかを痛感した。都会の孤独は、自ら選んだものではなく、この家との繋がりを断ち切った結果だったのかもしれない。
第三章 嵐の夜の告白
その夜、天気予報が告げていた通り、猛烈な嵐が町を襲った。風が唸りを上げ、窓ガラスを激しく叩く。雨粒は、まるで無数の礫となって屋根に打ち付けられた。家全体が、悲鳴を上げるように激しく揺れ、きしんでいた。
咲は、これがただの嵐ではないことを直感していた。家の揺れは、風のせいだけではない。内側から、まるで巨大な心臓が苦しげに脈打つような、不気味な振動が伝わってくる。壁の涙は、今や壁一面を覆い尽くす滝のようになり、床に水たまりを作っていた。
居間で呆然と立ち尽くす咲の隣で、父がぽつりと呟いた。
「…陽子の命日が、近いからな」
その声は、諦めと悲しみに濡れていた。咲が父の顔を見上げると、その皺の刻まれた目元に、光るものがあった。
「家が、苦しんでいるんだ」
父は、ついに重い口を開いた。それは、咲が今まで聞いたこともない、水野家に代々伝わる秘密の物語だった。
この家は、咲の曾祖父が、家族への愛を込めて建てた特別な家だった。単なる木と土の塊ではない。建てられたその瞬間から、家族の魂と共鳴し、感情を分かち合う「生きた存在」になったのだという。
嬉しいことがあれば、家は春の陽だまりのように温かくなる。喧嘩をすれば、冬の隙間風のように冷たくなる。家族の歴史と感情を、その身に刻み込み、記憶してきた。それが、この家の宿命だった。
「陽子は、誰よりもこの家のことを理解していた」と父は続けた。「あいつは、いつも家に話しかけていたよ。『家族を守ってね』ってな。そして…死ぬ直前、あいつは最後の力を振り絞って、この家に強い願いを託したんだ」
父の言葉が、嵐の音にかき消されそうになる。
「『私が死んでも、家族がバラバラにならないように、この家が見守ってほしい』…それが、陽子の最後の想いだった。だが、俺は…俺は、あいつを失った悲しみに沈むばかりで、お前とも向き合えなかった。お前は家を出て、家族の心は離れてしまった」
父の告白は、咲の胸を鋭く抉った。
「その結果、家は陽子の最後の願いと、俺たちの悲しみの間で引き裂かれることになった。陽子の『家族を守りたい』という温かい想いと、残された俺たちの冷たい悲しみがぶつかり合って…家は五年もの間、ずっと苦しみ続けていたんだ」
嵐の轟音は、家の苦しみが最高潮に達したことの現れだった。壁を伝う無数の涙は、母の悲しみであり、父の絶望であり、そして咲自身の孤独の象徴だった。
「このままでは、家は…この悲しみの重さに耐えきれず、死んでしまうかもしれん」
父が絞り出した言葉は、家の崩壊を意味していた。それは、家族の繋がりが完全に失われることの、最終宣告のように聞こえた。咲は、激しくきしむ柱を見つめ、自分たちが犯してきた過ちの大きさを、ただただ痛感するしかなかった。
第四章 ただいま、私たちの家
父の告白は、咲の心の奥底にあったダムを破壊した。堪えきれなくなった涙が、頬を伝って溢れ出す。それは、母を亡くした悲しみであり、父を一人にしてしまった後悔であり、そして、ずっと一人で苦しんでいたこの家への謝罪の涙だった。
「ごめんなさい…お父さん。ごめんなさい…」
咲は、子供のように声を上げて泣いた。
「私、怖かったの。東京で一人でいるのも、ここに戻って、お母さんがいない現実に直面するのも。だから、ずっと逃げてた。仕事のせいにして、忙しいフリをして、家族から目を背けてた。寂しかった。ずっと、ずっと寂しかった…!」
初めて聞く娘の弱音に、父の肩が震えた。父は無言で咲のそばに寄り、その不器用で節くれだった大きな手で、咲の頭をそっと撫でた。
「…俺もだ、咲。俺も、陽子がいなくなったこの家で、どうしてお前と向き合えばいいのか、分からなかったんだ。お前の顔を見ると、陽子を思い出して辛かった。寂しいのは、お前だけじゃなかった。すまなかった…」
父と娘は、初めて互いの胸の内にある悲しみと孤独を曝け出した。言葉にならない想いが、涙となって二人の間を流れていく。その瞬間、まるで奇跡のように、家の外で猛威を振るっていた嵐が、すうっと力を失っていくのが分かった。風の唸りが遠のき、窓を叩いていた雨音が、優しい子守唄のような響きに変わる。
そして、家を内側から揺さぶっていた不気味な振動と、絶え間ないきしみが、ぴたりと止んだ。
二人が顔を上げると、壁を滝のように流れていた涙の跡は跡形もなく消え、部屋の空気が、ふわりと温かさを取り戻していた。まるで、家が安堵のため息をつき、微笑んだかのように。
母の願いと、残された家族の悲しみの間で引き裂かれていた家は、父と娘の心が再び通い合ったことで、ようやく安らぎを取り戻したのだ。
その日を境に、咲は実家で暮らすことを決めた。幸い、デザイナーの仕事はリモートでも続けられる。コンクリートのジャングルで一人で戦うよりも、この「生きた家」と共に、父と共に、もう一度「家族」を築き直す方が、ずっと自分らしい生き方だと感じた。
数ヶ月が過ぎた、ある晴れた秋の日。咲は庭の片隅で、新しい花の苗を植えていた。土の匂いが心地よい。縁側では、父が穏やかな表情で、その様子を眺めている。二人の間に、以前のような気まずい沈黙はもうない。
ふと、咲は顔を上げて、家全体を見渡した。陽の光を浴びて輝く瓦屋根、年月を経て味わいを増した木の壁。それは、ただの建物ではなかった。自分たちを守り、共に笑い、共に泣いてくれる、かけがえのない家族の一員だ。
その時、二階の窓ガラスが、太陽の光をキラリと一度だけ強く反射した。それはまるで、母であり、祖母であり、そしてこの家そのものである巨大な存在からの、優しいウインクのように思えた。
「ただいま」
咲は、誰に言うでもなく、しかし確かな温もりを感じながら、そっと呟いた。心からの笑顔で家に微笑み返すと、応えるかのように、心地よい風が庭を吹き抜け、花の香りを運んできた。家族は三人だけじゃない。この家も、ずっと一緒に生きていく。その確信が、咲の心を温かく満たしていた。