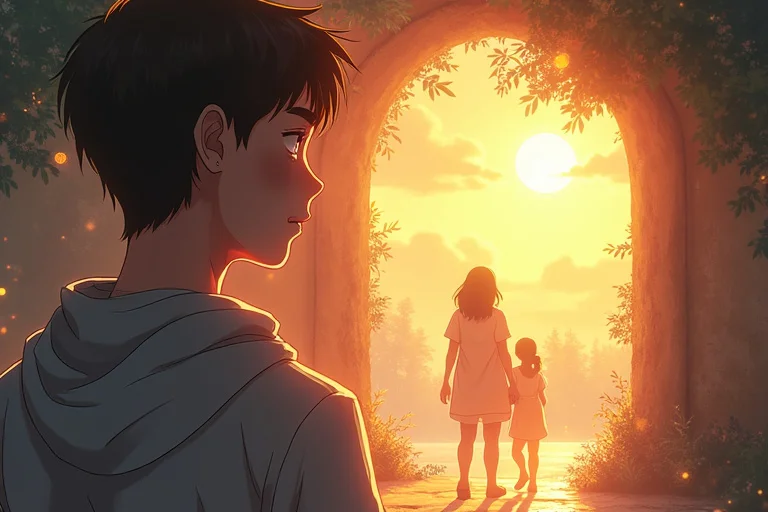第一章 硝子の残骸
僕の指先から伸びる、数本の透き通った糸。それは父さんへ、母さんへと繋がる『血縁の糸』だ。他の家族が持つような、温かい赤や穏やかな青といった色彩を、僕らの一族の糸は持たない。ただ、水晶のように無色透明な光を放っている。
リビングの床に散らばった硝子の蝶を、僕は静かに拾い集める。昨夜、書斎にこもっていた父さんがまた「具現化」させたものだ。それは、若き日の父さんが母さんにプロポーズした植物園で舞っていたという、オオゴマダラの標本。繊細な翅脈まで忠実に再現されたそれは、父さんの記憶そのものだった。
「湊、ありがとう」
背後からかかった母さんの声は、ひどく乾いていた。振り返ると、母さんの指から伸びる無色の糸が、父さんのそれと触れ合うか触れ合わないかの距離で、か細く震えているのが見えた。父さんの病が、二人の心を少しずつ蝕んでいる。美しいはずの記憶の結晶が、今では家族を繋ぐ糸をきつく締め上げる枷となっていた。
硝子の蝶を箱に収めながら、僕は窓の外に目をやる。この世界では、世代を重ねるごとに親から子へ受け継がれる『記憶の色』が薄まっていく。色が完全に消えれば、その家族は歴史から存在ごと消滅する。けれど、僕らの一族は違う。色のない、永遠に消えない糸を持つ代わりに、最も大切な記憶を物理的に吐き出すという呪いを抱えていた。この硝子の蝶のように、美しく、そして痛々しい残骸として。
第二章 糸巻きの囁き
どうすれば、この呪いを解けるのだろう。その答えを求めて、僕は三年前に亡くなった祖母の部屋に足を踏み入れた。祖母もまた、同じ病に苦しんでいたと聞く。白檀の香りが微かに残る箪笥の引き出しの奥に、それは眠っていた。使い古された、黒檀の糸巻き。
そっと手に取ると、指先から伸びる僕の無色の糸が、糸巻きに淡い光を灯した。まるで、乾いた大地が水を吸うように、僕の存在に共鳴している。糸巻きには、祖母のものだろうか、一本の細い無色の糸が巻き付いていた。その糸の断片に指を触れた瞬間、脳裏にノイズ混じりの映像が流れ込んできた。
若い頃の祖母が見える。彼女は誰かに向かって、必死に訴えていた。
『……この鎖を、いつか誰かが……。私たちの記憶は、呪いじゃない……』
声は途切れ途切れで、相手の顔も判然としない。けれど、その瞳に宿る強い光だけが、網膜に焼き付いて離れなかった。祖母は、この病の正体を知っていたのかもしれない。そして、それを呪いではなく、別の何かだと信じようとしていた。この糸巻きは、単なる遺品ではない。祖母が僕に残した、声なき道標なのだ。
第三章 褪せる世界の色
学校の帰り道、友人の亮介が嬉しそうに一枚の写真を見せてくれた。彼の曽祖父が若い頃のものだという。セピア色の写真の中で、彼は力強く微笑んでいた。
「でもさ、最近、じいちゃんが曽祖父さんのこと、あんまり思い出せないって言うんだ。写真を見ても、誰だっけって」
亮介の指から伸びる家族の糸は、鮮やかな茜色をしていた。だが、彼の祖父、そして父へと繋がるにつれて、その色は少しずつ淡くなっている。世界の法則――『記憶の色の薄まり』は、こうして静かに、しかし確実に人々の繋がりを過去から削り取っていく。彼らは忘れていくのだ。愛した家族の顔も、交わした言葉の温もりも。
その残酷な法則から唯一逃れているのが、僕らの一族だ。僕らは忘れない。忘れることができない。だからこそ、溢れ出した記憶が物理的な形を取り、僕らを内側から壊していく。どっちが幸せで、どっちが不幸なのだろう。答えの出ない問いが、鉛のように胸に沈んだ。僕らの『無色』は、この世界における異端であり、エラーそのものなのかもしれない。
第四章 具現化の連鎖
その夜、事件は起きた。甲高い音が響き、リビングへ駆けつけると、床一面に色とりどりのビー玉が転がっていた。呆然と立ち尽くす父さんの隣で、母さんが、わなわなと震えながら蹲っている。母さんの手から、まるで泉のようにビー玉が溢れ出していた。
「陽菜……!」
父さんの悲鳴に近い声。ついに、母さんにも病が発症したのだ。そのビー玉は、僕が幼い頃に失くして大泣きした、宝物だったはずだ。母さんにとって、僕を慰めたあの瞬間が、最も幸せな記憶の一つだったのだろう。しかし、その幸せの象徴が、今は激しい奔流となって家を埋め尽くしていく。
ガラスがぶつかり合う耳障りな音が、僕の思考を麻痺させる。父さんと母さんの糸が、危険なほど絡み合い、ちぎれそうにきしんでいた。このままでは、家族がバラバラになってしまう。記憶が、糸が、全てが消えてしまう。
僕はポケットから祖母の糸巻きを握りしめた。助けて、おばあちゃん。どうすればいい。心の叫びが、糸巻きに吸い込まれていく。
第五章 始まりの願い
糸巻きが、心臓のように熱く脈打ち始めた。僕の手の中で眩い光を放ち、祖母の糸が僕自身の糸と絡み合う。視界が真っ白に染まり、僕は時を遡る奔流に呑み込まれた。
辿り着いたのは、見たこともない太古の風景だった。そこには、僕らと同じ『無色の糸』を持つ、最初の一人の男がいた。彼の周りでは、家族たちの『記憶の色』が次々と消え、人々が愛する者の存在を忘れていく悲劇が起きていた。彼は、最後の家族が消えゆくその瞬間、天を仰いで強く願ったのだ。
――どうか、この温もりを、この繋がりを、永遠に忘れさせないでくれ。
その純粋で切実な願いが、世界の法則を歪めた。世界のシステムは、彼の願いを叶えるために、彼の血族を『記憶の色が薄まらない』特異点として設定した。しかし、容量を超えた記憶は、行き場を失い、物理世界へ漏れ出すしかなかった。それが『記憶の具現化』の正体。僕らの一族が背負ってきた病は、呪いなどではなく、世界で最初の、家族を失いたくないというたった一つの愛の願いが生んだ、巨大なシステムエラーだった。
そして、僕は知ってしまった。このエラーを修正する方法を。修正すれば、僕らの病は治る。だが代償として、世界中の人々から『家族』という繋がりと記憶がリセットされ、彼らはその概念を永遠に失うのだと。
第六章 空に紡ぐオーロラ
僕は、現実に戻っていた。床にはビー玉が転がり、両親は疲弊しきった顔で互いを支え合っている。僕の手には、二つの選択肢があった。僕ら家族の安寧か、この世界の全ての家族の記憶か。
脳裏に、亮介の笑顔が浮かぶ。街ですれ違う人々が、その指先から伸ばす色とりどりの糸が明滅する。あの温かい光を、僕が消してしまっていいはずがない。
僕は、決めた。このエラーを「解決しない」。この病を、僕らの一族が引き受けるべき、愛の証として受け入れる。
僕は両親の前に立ち、目を閉じて意識を集中させた。僕の無色の糸は、ただ視るだけの力ではなかった。それは、記憶を、願いを「編み直す」ための糸だったのだ。指先から伸びた無数の糸が、床のビー玉を、棚の上の硝子の蝶を、優しく掬い上げていく。
すると、物質だったはずの記憶の残骸が、光の粒子へと変わり、窓から空へと昇っていった。僕は夜空へ向かって、そっと手をかざす。
次の瞬間、漆黒のキャンバスに、壮大な光のカーテンが広がった。緑、紫、そして茜色。それは、父さんの記憶、母さんの記憶、そしてこの世界に生きる全ての家族の記憶の色が混じり合った、巨大なオーロラだった。
「まあ……」
母さんが、息を呑む。父さんも、言葉を失って空を見上げていた。二人の間の無色の糸は、以前よりもずっと強く、しなやかな輝きを取り戻していた。
僕ら家族の病は、これからも続くだろう。けれど、具現化された記憶はもう、僕らを苦しめる残骸ではない。世界中の人々が、ふと空を見上げるたびに、遠い誰かの、しかし確かに存在する家族の温もりを感じるための、永遠の道標となるのだ。
僕は、新たな『家族の記憶の紡ぎ手』となった。この無色の糸で、空に愛を紡ぎ続ける。それが、僕が見つけた答えだった。