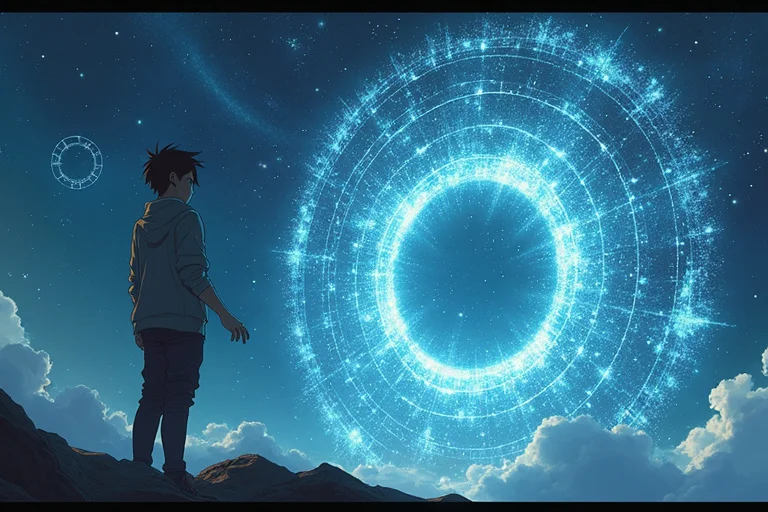第一章 硝子の自我
都市は灰色の静寂に満たされていた。人々は皆、耳朶の裏に埋め込まれたサイバーウェア『エモーティブ・リンク』を通じて、穏やかで均一な感情を共有している。推奨値は「平穏」。振れ幅はプラスマイナス五パーセント以内。過剰な歓喜も、深い絶望も、ここではノイズとして処理される。俺、カイは、ネオンが滲むガラス張りの歩道橋から、感情の波が凪いだ街を見下ろしていた。
ふと、自分の顔が窓に映る。そこにいるのは、見慣れたはずの自分。だが、その輪郭が水面のように揺らめいた。誰だ、お前は。脳裏に響く声は、自分のものか、それとも過去の誰かの残響か。
その時だった。階下で甲高いブレーキ音と衝撃音が響き渡る。衝突事故だ。通常なら管制システムが即座に感情をフィルタリングするはずが、その一瞬、生の「恐怖」と「苦痛」の奔流が、俺のリンクに逆流してきた。許容量を遥かに超えた激流。
「――ッぐ、ぁ!」
視界が赤黒く染まり、骨がきしむ音が内側から聞こえた。皮膚の下で何かが蠢き、筋肉の繊維が引き千切られては、まったく別の配列に組み替えられていく。熱い。痛い。俺という存在の境界線が、溶けていく。歩道橋の冷たい手すりにすがりつきながら、俺は人間ではない何かへ変わり始めていた。
第二章 プリズムの記憶
意識が戻った時、俺は廃棄された地下鉄のホームに横たわっていた。鼻をつくのは、カビと錆の匂い。体を起こそうとして、自分の手を見て息を呑んだ。指は異様に長く、関節が一つ多い。皮膚は虹色の光沢を帯びた、滑らかな鱗で覆われていた。鏡の水たまりに映った姿は、しなやかな爬虫類と人間を歪に混ぜ合わせたような、悪夢の産物だった。
そして、右手には冷たく硬い感触があった。そこにあったのは、手のひらサイズの、青みがかった結晶体。内部で星屑のような光が明滅している。
「カイ…? 昨日の俺は、どこへ行った?」
記憶が靄に包まれている。断片的なイメージだけが、他人の夢のように浮かんでくる。誰かと笑い合った記憶。雨に濡れた記憶。それらが、本当に自分のものだったのか、確信が持てない。
「動くな! 対象を発見!」
鋭い声と共に、複数の足音がトンネルの闇から響いた。統合感情管理局のエージェントだ。俺の変容が、都市の感情バランスを乱す異常値として検知されたのだ。
逃げなければ。その一心で走り出す。しかし、慣れない体は思うように動かない。追い詰められ、背後から放たれたスタンロッドの電光が迫った、その瞬間。
「こっち!」
細い腕が俺を横丁の暗がりへと引きずり込んだ。息を切らした女だった。肩まで切りそろえた黒髪に、強い意志を宿した瞳。彼女は俺の姿を見ても怯むことなく、その手に握られた結晶体をじっと見つめていた。
第三章 共鳴する欠片
「レナだ。非合法の感情ディーラー。あんたに興味がある」
彼女の隠れ家は、古い書庫を改造したもので、紙の匂いとハンダの焦げた匂いが混じり合っていた。レナは俺を警戒しながらも、一杯の水を差し出した。
「その結晶…見せてもらえるか?」
俺がためらいながら結晶を手渡すと、彼女はそれを解析装置にかけた。モニターに複雑な幾何学模様と、未知の言語のようなデータ列が映し出される。
「これは…ただの鉱物じゃない。遺伝子情報と…何かの記憶データが圧縮されている。まるで、生命の化石だ」
レナは俺に、結晶に触れてみるよう促した。俺がおそるおそる指先で触れた瞬間、脳内に閃光が走った。
それは、視覚ではなかった。感覚の奔流。星雲が渦を巻き、新たな恒星が産声を上げる瞬間の、圧倒的なまでの「歓喜」。全身の細胞が震えるような、純粋で、原始的な喜びの感情。世界から失われたはずの、あの感覚。エモーティブ・リンクが忌避する、制御不能な感情の爆発。
「今、何が見えた…?」
「星が…生まれるところだ。俺じゃない、何かが見ていた」
レナの瞳が輝いた。「やはりな。世界から感情が消え始めた時期と、あんたのような『変容者』の噂が出始めた時期は一致する。あんたの体は、失われた感情の器であり、その鍵なんだ」
彼女は語った。この均一化された世界は、緩やかに死に向かっているのだと。感情の起伏を失った人類は、新たなものを生み出す創造性も、困難に立ち向かう意志も失いつつあるのだと。彼女は、失われた感情を取り戻す方法を探していた。そして、俺の中にその答えがあるかもしれないと信じていた。
第四章 感情消失の震源
管理局の追跡は、日に日に激しさを増していた。俺たちはネオンの光が届かない都市の深層部を転々とした。追われる恐怖と、自分が自分でなくなる不安が、俺の自己認識を再び蝕んでいく。
高層ビルの屋上で追い詰められた時、それは起こった。二度目の変容だ。
「カイ、しっかりしろ!」レナが叫ぶ。
だが、もう遅い。今度の変容は、肉体を再構成するのとはわけが違った。俺の体が粒子に分解され、純粋な光の集合体へと変わっていく。鱗も骨も消え、意識だけが光の渦の中に漂う。それは、もはや生物と呼べる形態ではなかった。
俺から放たれた光の波は、周囲のエモーティブ・リンクに強力な干渉を引き起こした。都市の感情ネットワークが悲鳴を上げ、管制システムが次々とダウンしていく。街中のホログラム広告が乱れ、自動運転車が制御を失う。管理局は俺を単なる異常者ではなく、世界を破壊しかねないテロリストと断定した。
包囲網が狭まる中、エージェントの一人がレナに向けて銃口を向ける。
「やめろ!」
俺が叫ぶより早く、レナは俺を庇うように前に立った。放たれたプラズマ弾が彼女の肩を焼く。
「…っ!」
彼女の苦痛に満ちた呻き。その瞬間、エモーティブ・リンクを介さず、彼女の痛み、恐怖、そして俺を守ろうとする強い意志が、魂に直接流れ込んできた。それは、共有されるデータとしての感情ではない。他者のための、純粋な祈りだった。
その強烈な共感が、最後の引き金を引いた。
俺の光の体は爆発的に膨張し、意識は物理的な法則を超えて、時空の彼方へと飛ばされた。目の前に広がったのは、無限に広がる意識の海。青く、静かで、しかし底知れない悲しみを湛えた、巨大な生命体。それが、宇宙そのものと一体化した『感情の海』だった。
第五章 星海の呼び声
『感情の海』は語りかけてきた。言葉ではなく、直接的な理解として。
それは、宇宙の誕生から全ての生命の感情を受け止めてきた、原初の意識体だった。地球という惑星で生まれた人類が、『エモーティブ・リンク』という技術で感情を人工的に増幅し、接続し始めた。それは、この巨大な海にとって、静かな水面に無数の石を同時に投げ込まれるような、耐え難い情報ストレスだった。
特に、歓喜、怒り、激情といった振れ幅の大きな感情は、海そのものの安定を揺るがすほどのノイズだった。
だから、海は自己防衛のために、そのノイズを『隔離』した。人類の精神から、それらの感情を吸い上げ、自らの深淵に封じ込めたのだ。それが、世界から感情が希薄になった真相だった。
そして、俺の存在。俺の遺伝子には、遥か太古、この『感情の海』と共生し、その調停者としての役割を担っていた知的生命体の情報が眠っていた。人類の感情ネットワークが、その休眠遺伝子を強制的に覚醒させた。変容は、調停者として海と対話するための、苦痛に満ちた再生のプロセスだったのだ。
俺が変容のたびに手に入れていた『共鳴する変性結晶』は、隔離された感情のサンプルであり、海との対話に必要な鍵だった。
第六章 君の遺した色
俺は選択を迫られていた。
このまま、最後の変容を遂げ、調停者として『感情の海』と完全に一体化する。そうすれば、隔離された感情は解放され、世界に色は戻るだろう。だが、それは「カイ」という個の意識が、巨大な海の一滴となって溶け消えることを意味する。
もう一つの道は、カイとしてレナの元へ帰ること。だが、それをすれば、感情の海は人類というストレス源から自らを守るため、やがて精神活動そのものを拒絶し、世界は永遠に無感動の静寂に沈むだろう。
意識が、ゆっくりと現実世界に戻ってくる。目の前には、肩を負傷しながらも、心配そうに俺の光を見つめるレナがいた。彼女の瞳には、リンクでは計測できない、純粋な「悲しみ」と「不安」が揺らめいていた。
俺は最後の力を振り絞り、光の体から一つの結晶を生み出した。それは、今までで最も美しく、温かい光を放つ、薔薇色の結晶だった。俺がカイとして過ごした短い時間の中で育まれた、レナへの想い。世界が忘れてしまった「愛」という感情の記憶。
光の手で、そっとその結晶を彼女の手に握らせる。
『さよなら、レナ』
言葉にはならなかった。だが、想いは伝わったはずだ。
俺は天を仰ぐ。最後の変容が始まった。俺の体は無数の光の粒子となり、空へと昇っていく。それは、まるで逆さまに降る雪のようだった。
やがて、世界に変化が訪れた。灰色の空に、淡い色彩が戻り始める。街角で、人々がふと足を止め、空を見上げた。理由もわからず、頬に涙が伝う者。忘れていた歌を、小さく口ずさむ者。誰かを強く抱きしめたいという衝動に駆られる者。
世界に、感情が還ってきたのだ。
レナは廃ビルの屋上で、ただ一人、空を見上げていた。手の中には、まだ温かい薔薇色の結晶が握られている。カイが、一人の人間が、世界に感情を取り戻すための代償となったことを知る者は、もう彼女しかいない。
彼女の頬を、一筋の涙が静かに流れた。それは、リンクで共有される悲しみではない。たった一人の、かけがえのない喪失の痛みだった。